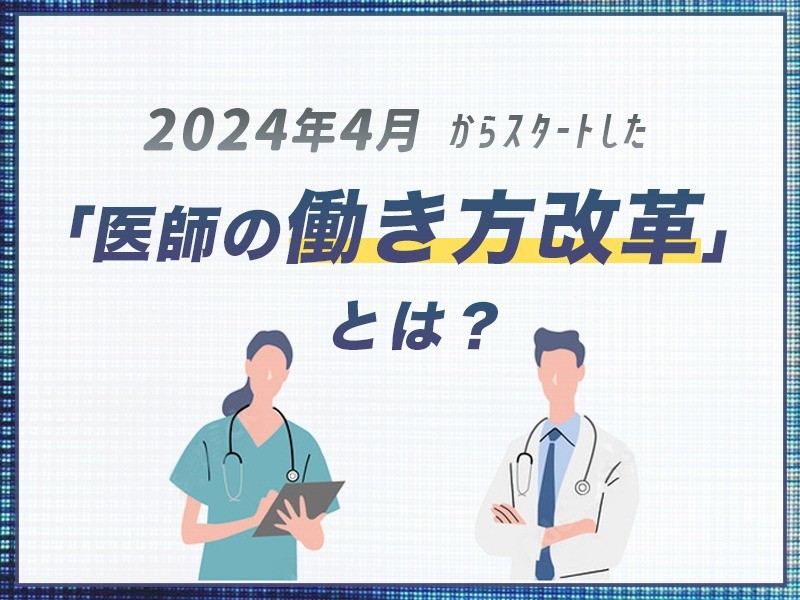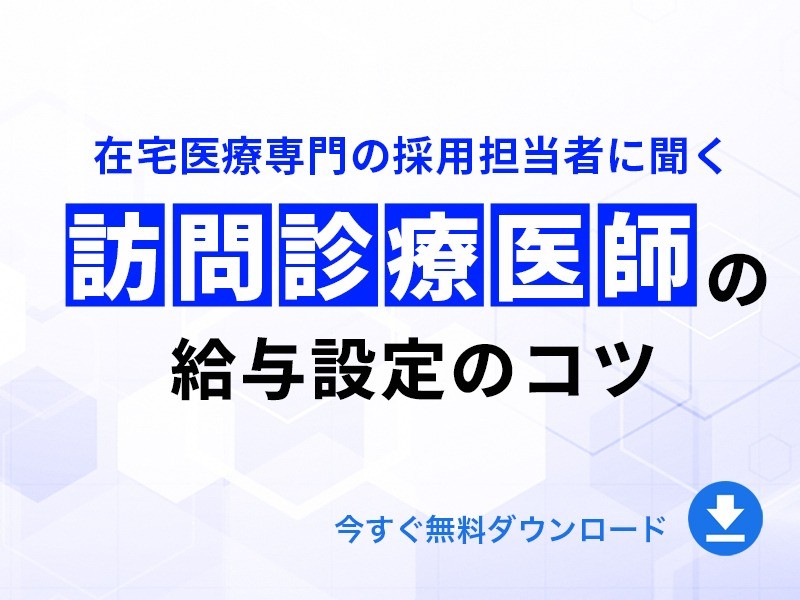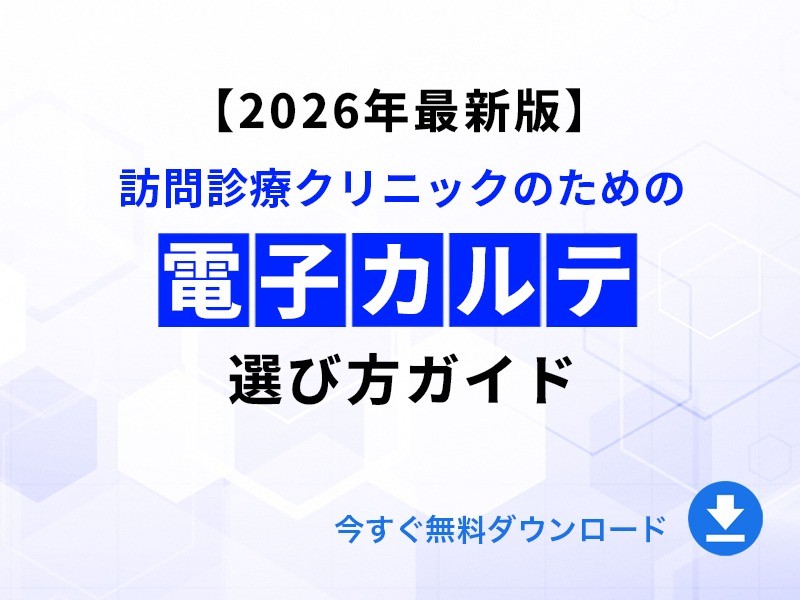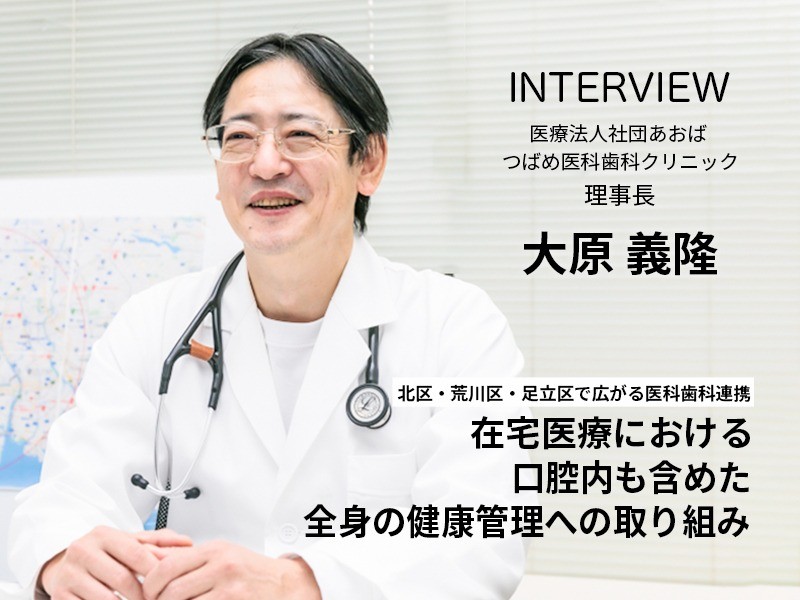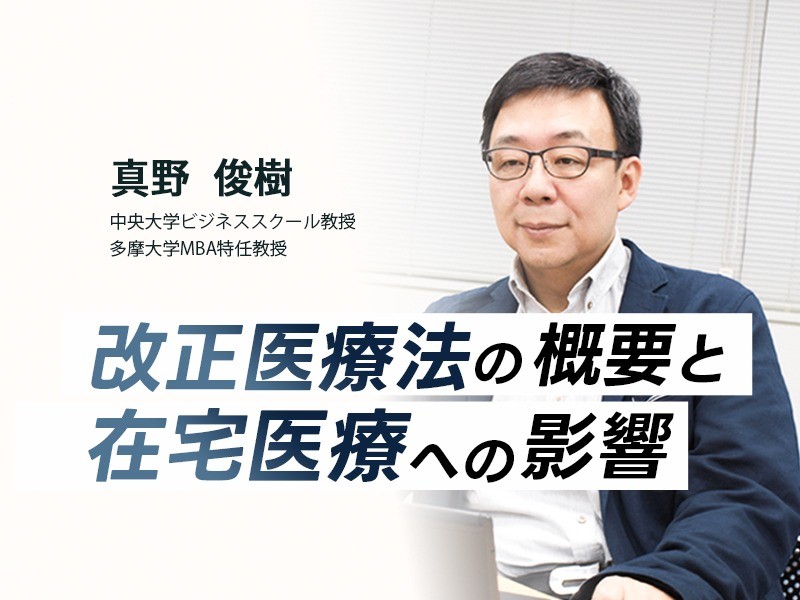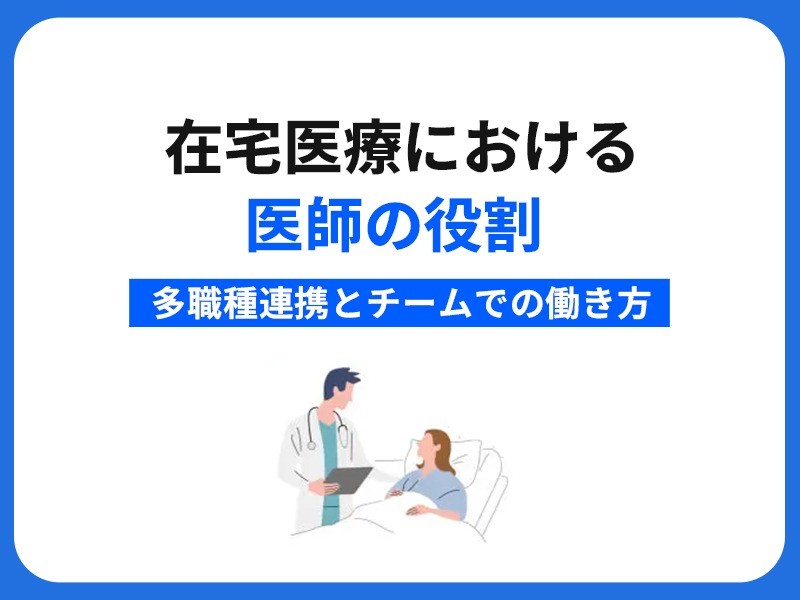医師の働き方改革の在宅医療への影響を読み解く|後編|求められるのは財務とオペレーションの適正化
- #在宅医療全般

医療法人おひさま会最高人材育成責任者の荒隆紀先生に聞く「医師の働き方改革」後編では、財務やオペレーションの重要性、在宅医療の集約化、役割分担などについてお話いただきました。より上流にある潜在的な医療ニーズにも対応すべきという荒先生に、在宅医療の今後の展望などを伺っています。
■あわせて読みたい
2024年4月からスタートした「医師の働き方改革」とは?
医師の働き方改革の在宅医療への影響を読み解く|前編|夜間対応や医師の確保で間接的な影響を懸念(医療法人おひさま会 荒 隆紀先生インタビュー)
医療法人おひさま会
荒 隆紀 先生
2012年新潟大学卒業。洛和会音羽病院で初期研修後、同病院呼吸器内科後期研修を経て、関西家庭医療学センター家庭医療学専門医コースを修了。家庭医療専門医へ。「医療をシンプルにデザインして、人々の生き方サポーターになる」を志とし、医療介護福祉領域の人材育成パートナーとなるべく起業。その他、関西で在宅医療を展開する医療法人おひさま会のCLO(Chief Learning Officer)として法人全体の人材育成/組織開発をしながら、新潟大学総合診療研修センターの非常勤講師として医学生教育にも従事している。著書:「京都ERポケットブック」(医学書院)、「在宅医療コアガイドブック」(中外医学社)
人や設備の集約化が必要に
働き方改革によって一人ひとりの医師が働ける時間が減る中で、盤石な組織を作るために必要なことは、財務とオペレーションです。在宅医療に対してもかかりつけ医としての機能が強く求められる時代の中で、24時間365日対応できる体制を整えるためには、やはりそれなりの医師数と医師を支えるスタッフ数を揃えることが必要になるからです。
特に、夜間の往診依頼が来たときにも、特定の医師だけに依存しなくても対応できるようなモデルを各法人が確立させていかなければなりません。そのためにはICTなどを活用しながら、さまざまに工夫することが重要になるでしょう。
他の施設や病院、訪問看護ステーションなどとも連携し、常に情報共有できている状況を作ることも大切です。そうでなければどうしても非効率な往診などが発生してしまうからです。非効率な往診などが発生しないようにするためには、他施設と連携してオペレーションを適正化していくことが必須になります。
同時に、人材を用意してICTなど必要な物に投資していくためには、それなりに財務面で安定していることも求められます。このように考えていくと、オペレーションと財務の両面で足腰が強い法人を作っていくことが求められるでしょう。
集約化や適正化、分業などがキーワードに
もちろん、小規模な在宅医療の医療機関の役割も重要です。たとえ少人数の患者を対象とするだけだとしても、在宅医療に取り組む意義は非常に大きいからです。しかし、地域において大規模な医療機関と小規模な医療機関との役割分担は、今後ますます進んでいくと考えられます。
病院がすでにそうなっているように、在宅医療においても今後は集約化や適正化、分業などがキーワードになると思います。大規模な法人と小規模な法人がどちらも同じような医療を行うのではなく、それぞれの役割の分業が今後5年、10年でさらに加速するのではないでしょうか。
医療はどうしてもそもそも公益性が高い事業ですから、休日・夜間であっても誰かが犠牲になって支えなければならないという側面があります。しかしそれをすべての医療機関で行ってしまうと地域全体が疲弊してしまうので、そうならないためにもある程度は集約化が必要になると思います。
実際に診療報酬でも、大規模な医療機関が小規模な医療機関を支援することに対する加算が設けられる方向になっています。コロナ禍で起きたことですが、1人で診療している医療機関の院長が体調不良になったとき、それによって地域医療が立ち行かなくなる事態が散見されました。
このようなことが再び起こらないように、地域で医療機関同士が支え合う、あるいは拠点となる在宅医療の医療機関が他の医療機関をカバーできる体制を整えるというのが今求められていることです。すでに地域ごとに在宅医療連携拠点となる医療機関が決定されつつあり、そうした医療機関は自分のところの患者だけではなく、地域全体をカバーする視点が求められています。
より上流にある潜在的な医療ニーズに対応すべき
また、これは個人的な意見ですが、医療は困ったときに患者を助けることが重要ですが、果たしてそれだけで良いのか? ということも合わせて考えるべきときに来ていると思います。もちろん、今目の前で苦しんでいる患者を救うことは極めて重要な役割です。それは当然のこととしてこれまで以上に取り組みつつ、より上流の部分にもっと関わっていくことが必要と感じています。
これを在宅医療と関連させて考えるならば、夜の往診に多く行けば行くほど素晴らしいのかどうか考えてみるべきでしょう。夜間に体調を崩して困っている人を助けることに加えて、その患者が夜に体調が悪くならないように、日中もっとできることはなかったのかということを振り返って改善する必要があります。
こうしてこそ初めてPDCAサイクルを回していることにつながりますし、患者や家族の困りごとに応えるプラスアルファの取り組みになるはずです。
これは非常にコストも時間もかかりますから、すぐには取り組むことが難しいかもしれません。しかし、本来は非常に重要なことであり、診療報酬の加算などもそうした取り組みに対してこそ手厚くすべきと個人的には考えます。
多様化する医師のキャリアに応え、質の高い医療を提供する
医師の働き方改革はずいぶん昔から議論されてきたことではありますが、まだまだ改革の道半ばという印象です。時間外労働の上限規制などだけではなく、もっとトータルで医療職の働く環境や働き方がウェルビーイング(Well-being)でなければ、患者に良い医療など提供できないからです。
働き方改革はまだまだ発展途上ですが、私たちはそうした中で今後も生き残れる医療法人でなければならないと感じています。そのためには、多様化する医師のキャリアやニーズに対応し、同時に患者に対しては24時間365日、質の高い医療を提供しつづける――そのような医療法人を今後も目指していくことが重要なのではないでしょうか。