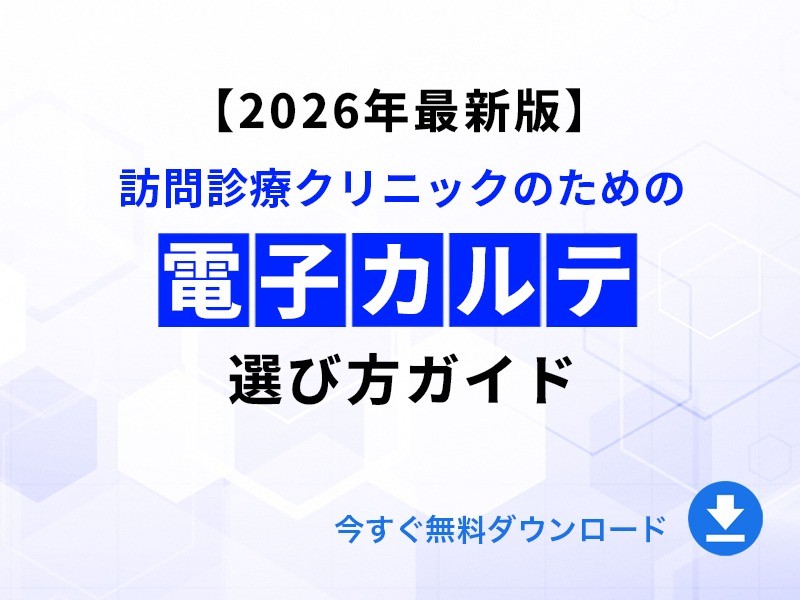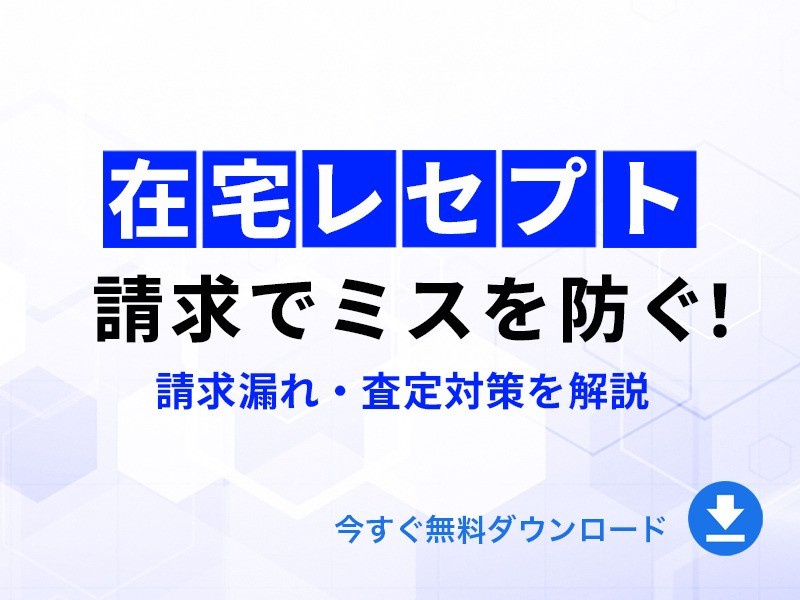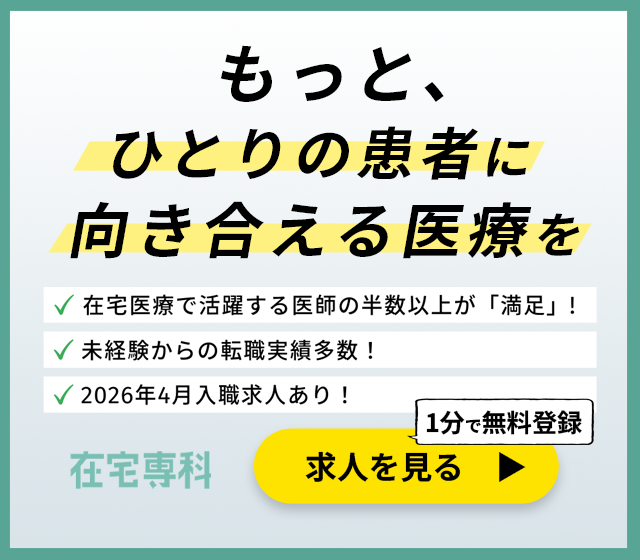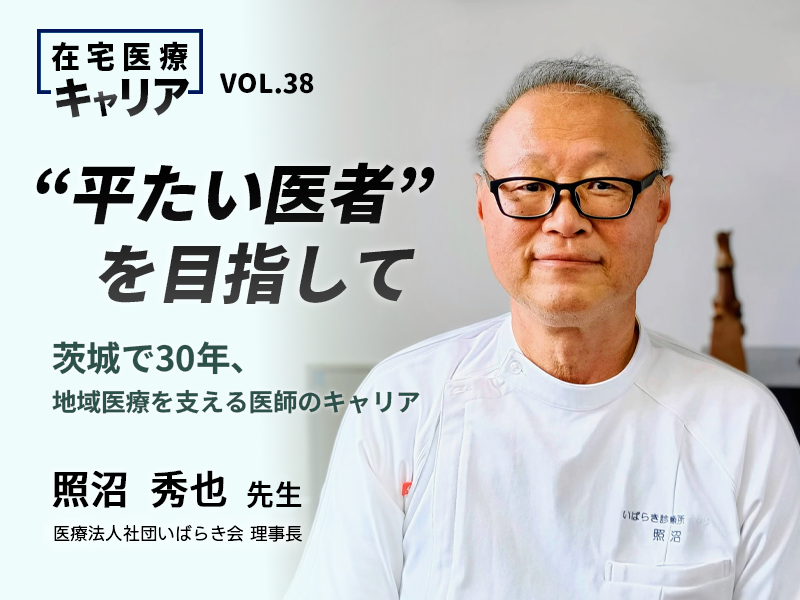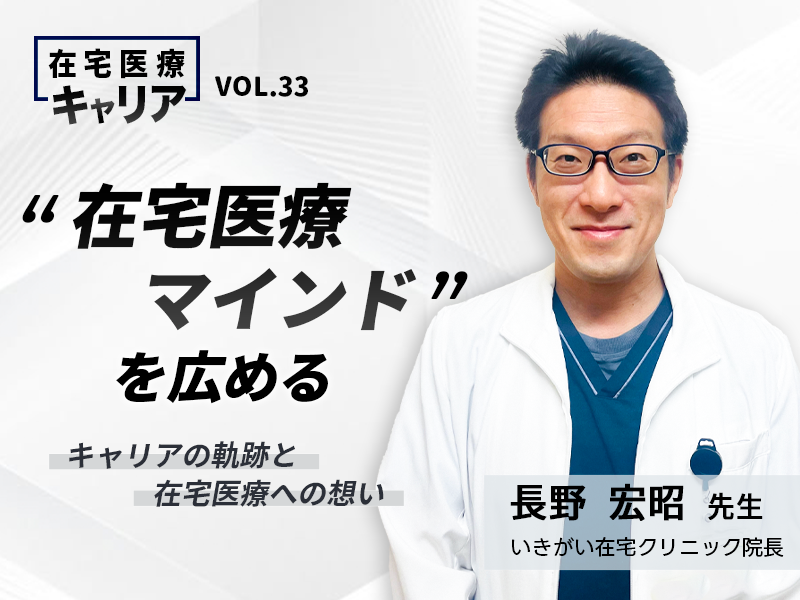
沖縄市を拠点に、在宅医療を通じて地域の暮らしを支える、いきがい在宅クリニック 院長 長野 宏昭先生。
本記事では、長野先生のこれまでのキャリア、在宅医療への想い、そしてこれからのビジョンについてお話を伺いました。
いきがい在宅クリニック 院長 長野 宏昭先生
1980年奈良県生まれ。岡山大学医学部卒業。中学生の時に大好きだった祖母を亡くし、いのちと向き合う現場での仕事を志す。
2012年に沖縄へ移住し沖縄県立中部病院へ就職。在宅医療、ホスピスマインドを学ぶ仲間達と出会い、2023年いきがい在宅クリニックを設立。
エンドオブライフ・ケア協会認定ファシリテーター・いのちの授業認定講師として子どもから大人まで幅広い層にマインドを紹介している。
マインドを軸に地域をデザインする試みとして、シェアハウス型ホスピス「いきがいの家」、苦しみを抱えた人の居場所「よりどころ」を建設。
琉球大学医学部非常勤講師として学生教育に力を入れ、答えのない心の問題について対話する学生サークル「ヨリドコロ」の外部顧問。
趣味でヴァイオリン・ヴィオラ演奏を嗜んでおり、病院や地域でのコンサートも毎年開催している。
資格:総合内科専門医、呼吸器内科専門医・指導医、がん治療認定医
日本在宅医療連合学会評議員 他
岡山、関西、そして沖縄で歩んだキャリア
──まずは先生のこれまでのキャリアについてお聞かせください。
岡山大学医学部をご卒業後、どのようなキャリアを歩まれてきたのでしょうか?
私は岡山大学を卒業後、大阪赤十字病院で初期研修を受け、呼吸器内科を専門に選びました。
大阪や神戸の総合病院にて、約8年間、多様な患者さんを診療し、医師としての土台を築いたと思います。
その後、たまたま沖縄県立中部病院で呼吸器内科の募集があるのを知りました。
中部病院は全国的にも有名な研修病院であり、学生や研修医の教育にも力を入れています。
「若い世代のために何かできれば」という思いもあり、沖縄への移住を決意しました。
──呼吸器内科医として勤務されていたとのことですが、在宅医療に携わるようになったきっかけについて教えてください。
もともと在宅医療への興味はありました。
ただ、本格的に在宅医療を行うようになったのは、沖縄県立中部病院での勤務がきっかけです。
呼吸器内科医として、肺がん患者さんの治療やお看取りを多く経験する中で、「家に帰りたい」「家で過ごしたい」という患者さんの切実な思いに触れる機会が何度もありました。その声に応えたいという思いが、在宅医療への関心をより深めていきました。
中部病院には高山 義浩先生をはじめとする在宅医療チームがあり、私も「ぜひ参加させてください」とお願いして、加えていただきました。
この経験が大きな転機となって、患者さんの生活や人生に寄り添うことの重要性をより実感し、在宅医療に強く関心を抱くようになりました。
急性期病院の中で担う、在宅医療の役割
――沖縄県立中部病院で「地域ケア科」を創設されたと伺いましたが、立ち上げの経緯について教えてください。
地域ケア科は、沖縄県立中部病院の中で在宅医療を担う部門ですが、当時はこうした取り組みを行う急性期病院は珍しかったと思います。
活動自体はボランティアのようなかたちでスタートしました。
たとえば、「お家に帰りたい」と希望する患者さんの退院を支援し、退院後には実際にご自宅を訪ねて、きちんと生活できているかを見守る。
このような取り組みから始まったのです。
その後、高山先生をはじめとする在宅医療を担う先生方とともに、これらの活動を正式な医療行為として認めてもらうための組織づくりに取り組みました。院長とも交渉を重ねた結果、「地域ケア科」という部門が新たに立ち上がりました。
――急性期病院の中で在宅医療を行うことには、どのような意義があったのでしょうか?
中部病院は救急の患者さんが非常に多く、救急部門も逼迫していました。
私たちが退院支援や在宅ケアを充実させることで、病院に戻ってくる患者さんの数が減るはずだと説明し、地域ケア科の必要性を理解してもらいました。
私は呼吸器内科の診療を続けながら、その傍らで在宅医療も担当していました。
ほかの先生方もプライマリ・ケア専門医や感染症の専門医など様々で、それぞれの専門性を活かしながら在宅医療に携わっていました。
人との縁が紡いだ「いきがい在宅クリニック」設立
――中部病院で在宅医療に携わり、そこから「いきがい在宅クリニック」を開業されたと伺いました。
開業にあたっては、どのような経緯や思いがあったのでしょうか?
中部病院に勤務していた頃は、呼吸器の業務が8割、在宅医療が2割ほどでした。
しかし在宅医療への関心が高まるにつれ、その割合を増やしたいと思うようになりました。
開業を決めるまではいくつかの段階があったのですが、特に地域の看取りの勉強会で同じ思いを持つ仲間に出会ったことが大きな転機になりました。
その中でも大きかったのは、看護師の親泊 朝光さんとの出会いです。
彼が訪問看護ステーションの立ち上げを目指していることを知り、病院へ通うことが難しい患者さんが地域にたくさんいる現実に心を動かされました。
そして自分もそうした人たちの力になりたいと強く思ったのです。
また、「いきがいクリエーション」という会社との出会いも大きなきっかけです。
社長の田村浩介さんの取り組みに感銘を受け、そこからさらに在宅医療の重要性を実感しました。
──2023年に開業されたとのことで、コロナ禍の影響などもあったのでしょうか?
はい。コロナ禍で呼吸器内科の医師として最前線に立ち、多くの人工呼吸器患者さんを診てきました。
多くの方が隔離され、家族に会えないまま亡くなっていく現実に心を痛めました。
患者さんたちの中には「お家に帰りたい」と願う声が多くあり、在宅医療の必要性を改めて痛感しました。
その後、親泊さんがいきがいクリエーションの副社長となり、「在宅ホスピス、シェアハウス型のホスピスを作りたい」という夢を語ってくれました。
そこで「やっぱり医師がそばにいて、いつでも訪問できる体制が必要だ」という話になり、自分がその役割を担うしかないと強く感じました。
最終的に開業を決意したのは、そのホスピス計画を聞いたときですね。
笑顔と音楽があふれる──シェアハウス型ホスピス「いきがいの家」
――先ほどのお話しにもあった「シェアハウス型在宅ホスピス」について、どのような場所か教えてください。
「いきがいクリエーション」の皆さんと一緒にシェアハウス型ホスピス「いきがいの家」を立ち上げました。
このホスピスは、共同生活を営む寄宿舎のような場所です。
主にがんの終末期の方が入居されていて、訪問看護師が24時間常駐し、医師も24時間365日いつでも対応できる体制をとっています。
建物は3階がクリニック、2階がホスピス、そして1階には「ヨリドコロ」という共有スペースになっています。
ヨリドコロは、患者さんやご家族、地域の方が集まって、コーヒーを飲んだり、お話をしたり、リラックスできる空間です。
勉強会やイベント、音楽コンサートなんかも開催していて、地域の人が集える場にもなっています。
――先生はヴァイオリンを弾かれるそうですね。患者さん方に向けて演奏される機会もあるとか。
大学時代、岡山大学のオーケストラに所属していたんですが、医学生時代は正直、勉強以上に音楽に熱中していました(笑)。
その時に磨いた技術と練習効率のおかげで、今も少しの練習時間でも演奏を楽しめています。
ホスピスの患者さんの前で演奏する機会もあるのですが、在宅医療を始めてから特に「音楽の力」を強く感じるようになりました。
耳に直接届く音の振動や、懐かしい曲を聴いたときにふっと昔の記憶がよみがえる瞬間。それが患者さんの表情や言葉に現れるんです。
ただ診療して薬を出すだけではない、音楽を通じて生まれる関係性や心の交流があると信じています。

“ゆいまーる”の心で地域を支える──未来に描くビジョン
――今後、いきがい在宅クリニックとして、どのようなビジョンを描いておられますか?
まずは、私自身が元気で在宅医療を続けられていること、そして今一緒に働いているスタッフの方や看護師さんたちが、無理なく、笑顔で働けていることが一番ですね。やはりスタッフが笑顔でいることが、利用者さんや地域の穏やかさにつながっていくと思っています。
あとは、いきがいクリエーションの皆さんとも話しているんですが、将来的には沖縄のどこかに、病気を予防するための研究施設のような、予防医学センターを作りたいと考えています。
特に支援したいのは、一人暮らしの方々です。
今後ますます増えていくことが予想されますが、社会とのつながりを持たずに暮らす人たちは、生活習慣病やアルコール依存などのリスクが高まるというデータもあります。
そんな中、「一人暮らし=寂しい」ではなく、「一人暮らし=かっこいい」と思えるような、そんな暮らしのモデルを提示できたらいいなと思っています。
そのためには、医療だけでなく、地域の人々が集まり、支え合えるような場を増やしていきたいと思っています。
沖縄には“ゆいまーる”という素晴らしい文化があります。困っている人を見て見ぬふりせずに自然と手を差し伸べる精神。
それを現代の暮らしや医療の中にうまく結びつけていけたら、きっと素敵な未来が築けるんじゃないかと思っています。
治すだけではなく、共に生きる──在宅医療のやりがい
――最後に、地域医療や在宅医療に関心を持つ医師や医学生に向けて、メッセージをいただけますか?
私は在宅医が増えてくれたら嬉しいという思いはありますが、それ以上に大切なのは、“在宅医療マインド”が広がっていくことだと感じています。
たとえ外科や救急の先生であっても、その人の生活や人生に関心を持って関わる姿勢は、取り入れられるはずです。
在宅医療は「医療」である以上、診断や処方、処置などはもちろん必要なことです。でも、本当に大事なのは、その人の生き方や価値観を尊重して、伴走していくことだと考えています。
正しい医療を追い求めるだけではなく、目の前の人の人生に興味を持って、その人の物語に寄り添っていくこと。
そして、たとえ病気が治らなくても、笑顔で過ごせたり、「生きていてよかった」と思ってもらえるような時間を支えられること。
私は、それこそが在宅医療のやりがいだと感じています。
そういった関わり方に魅力を感じてくれる方が、地域医療や在宅医療の仲間になってくれたら、とても嬉しく思います。