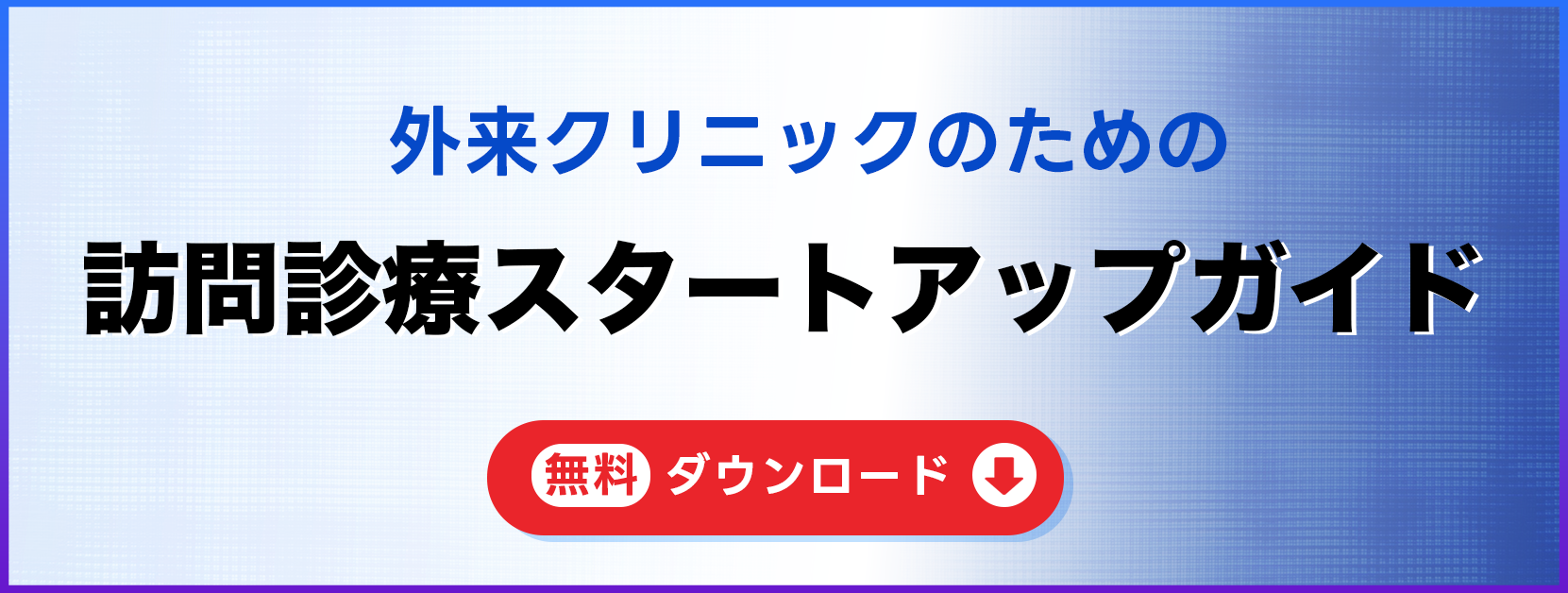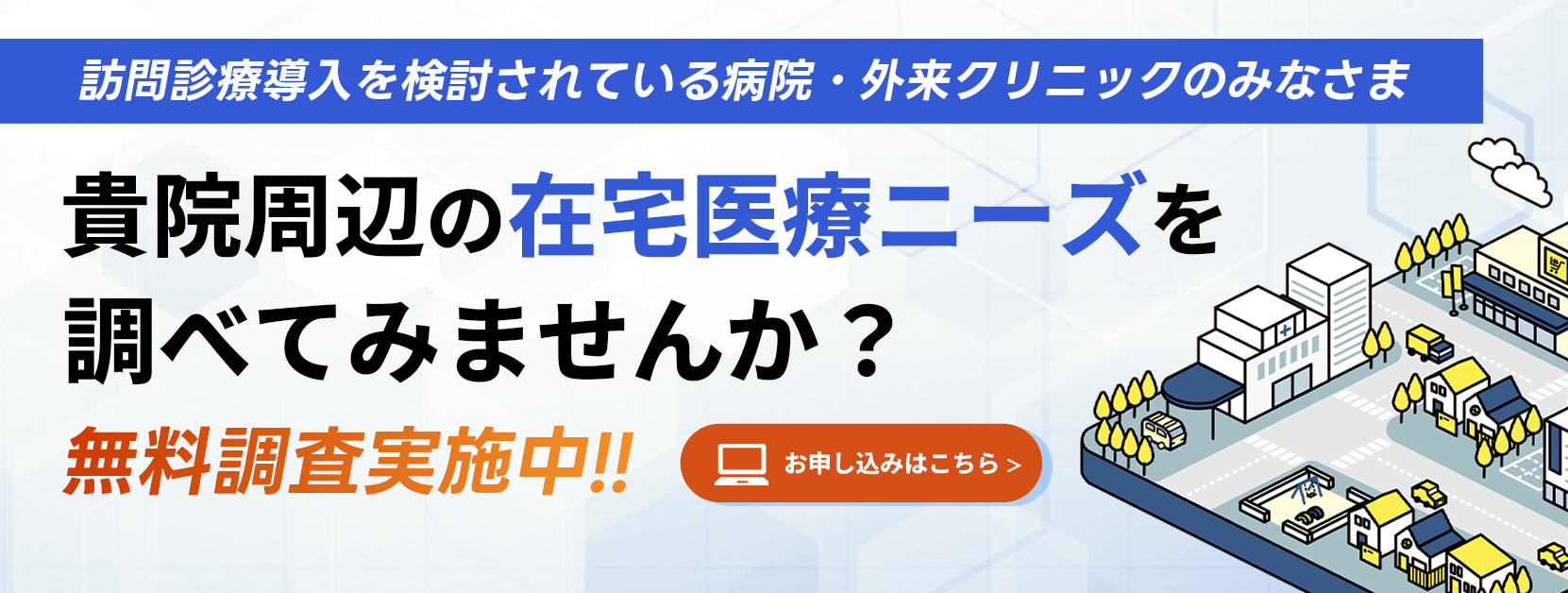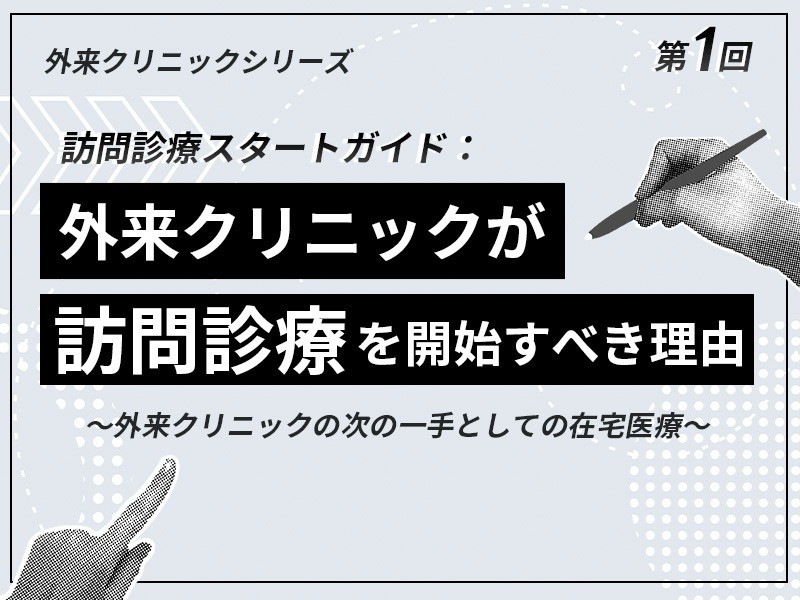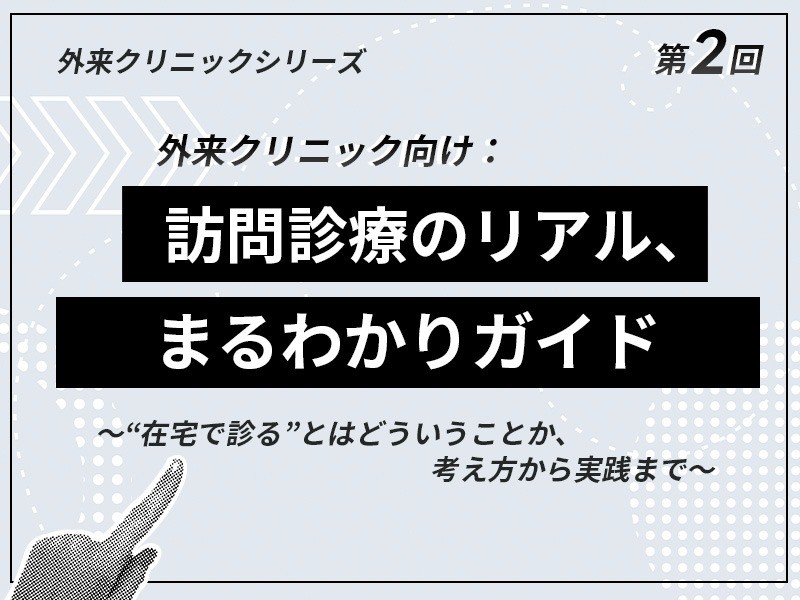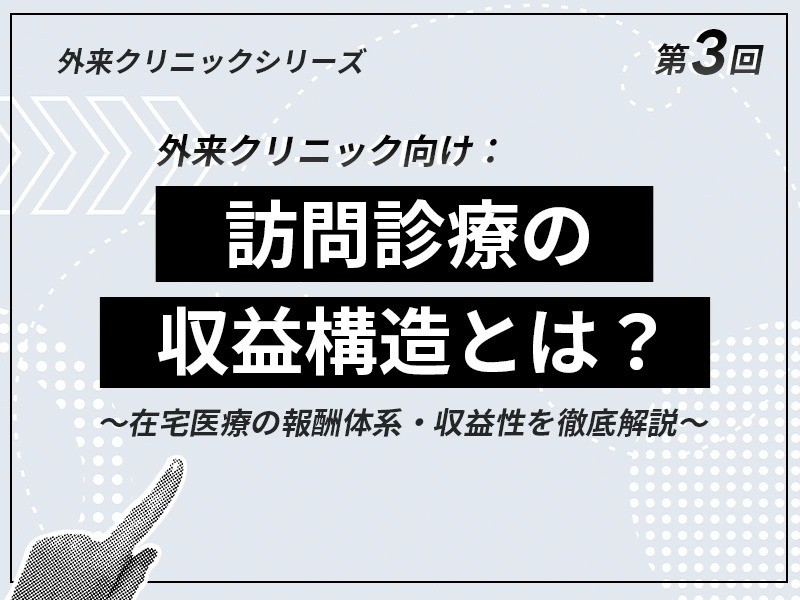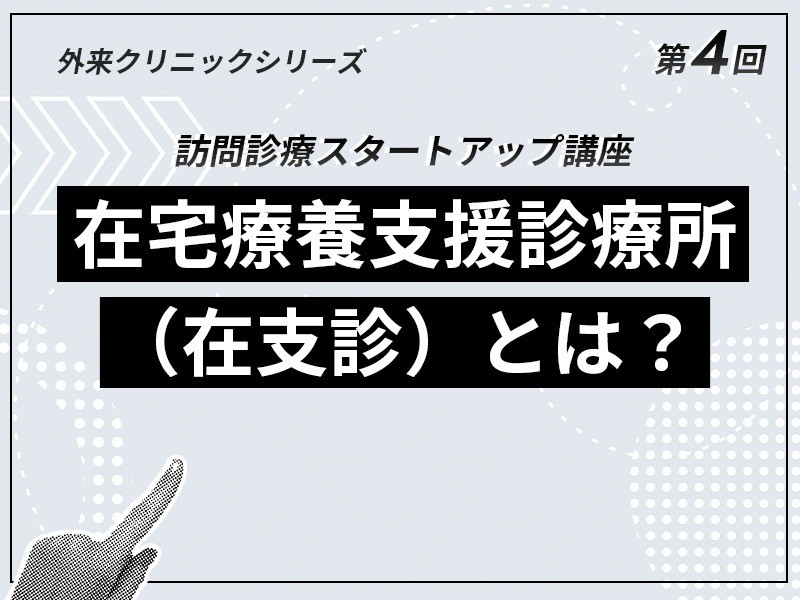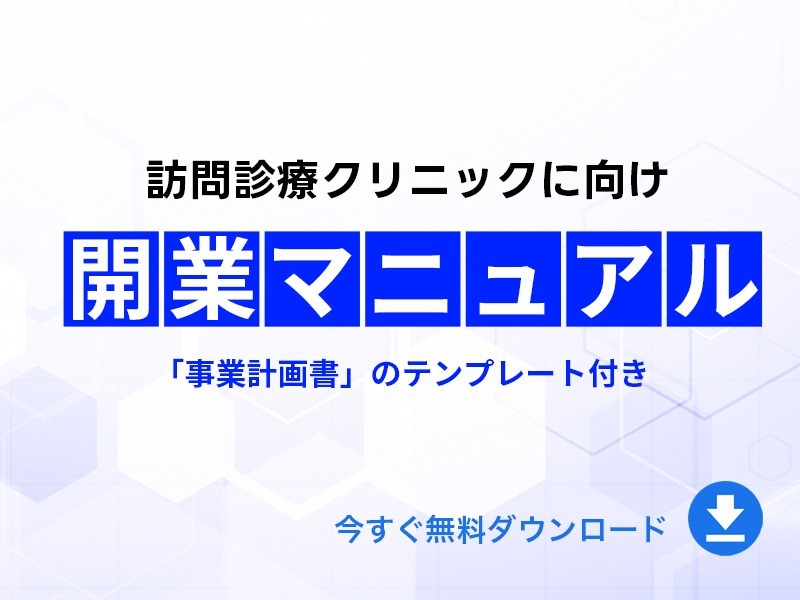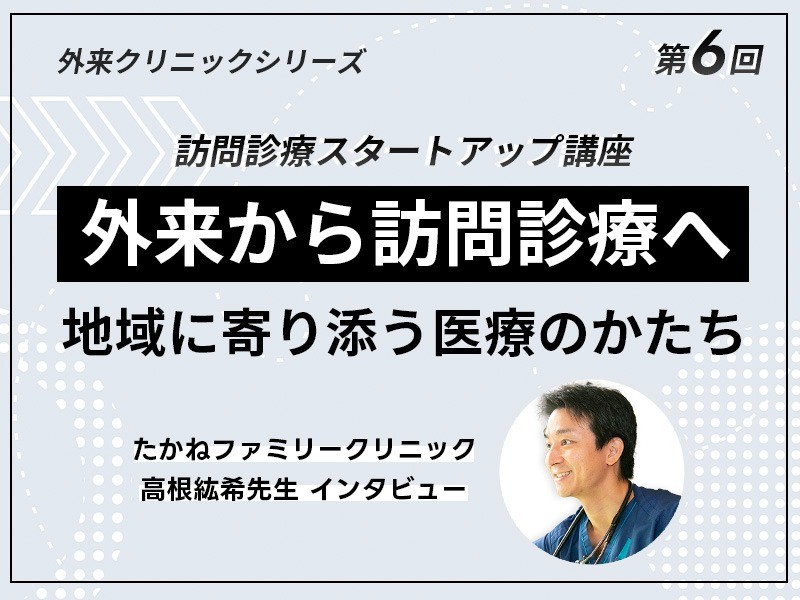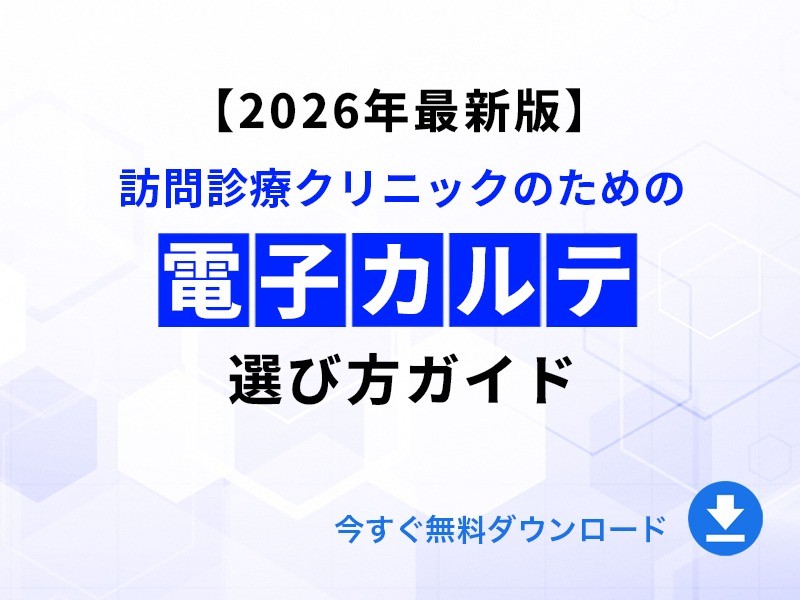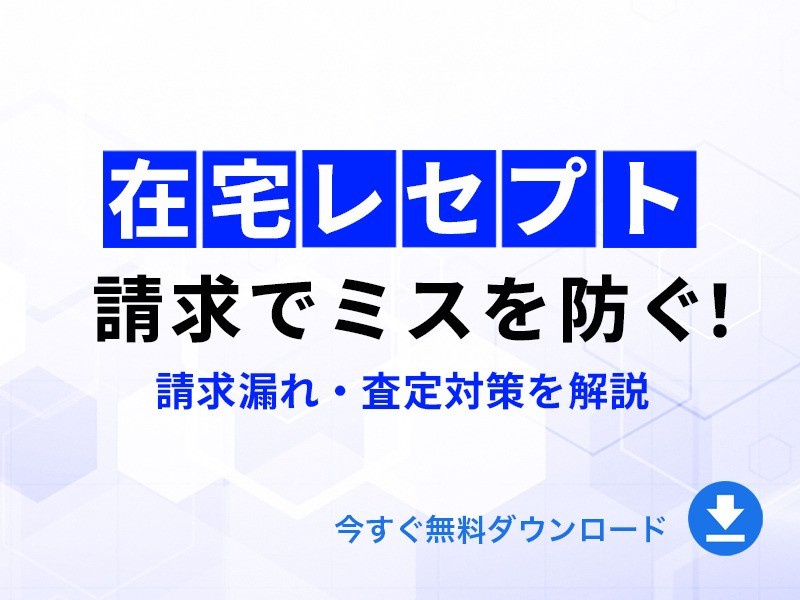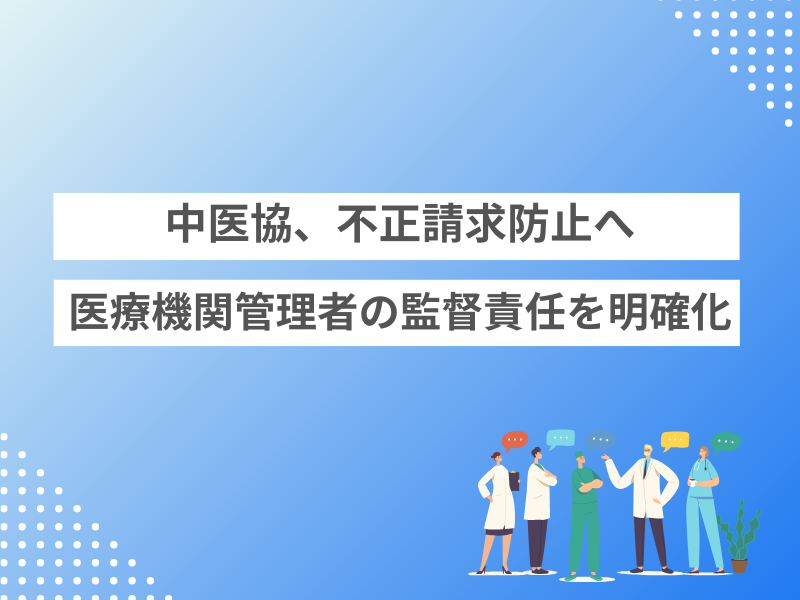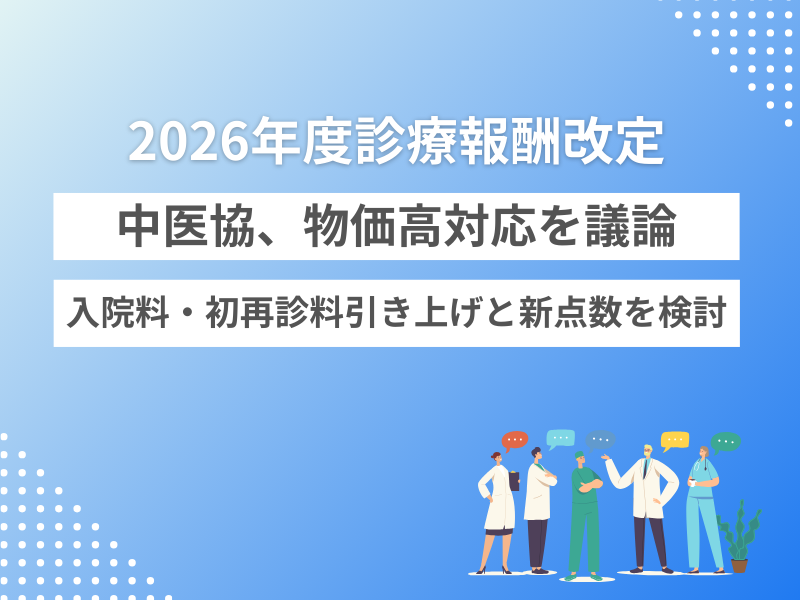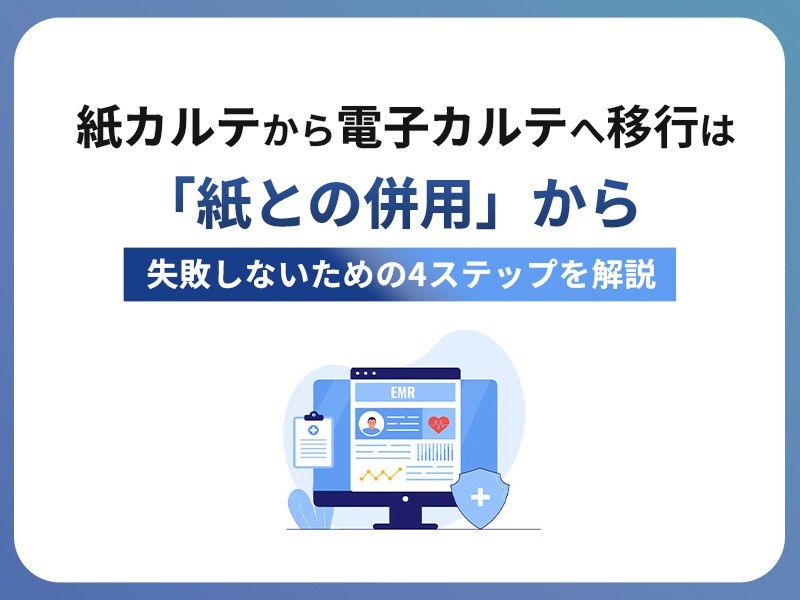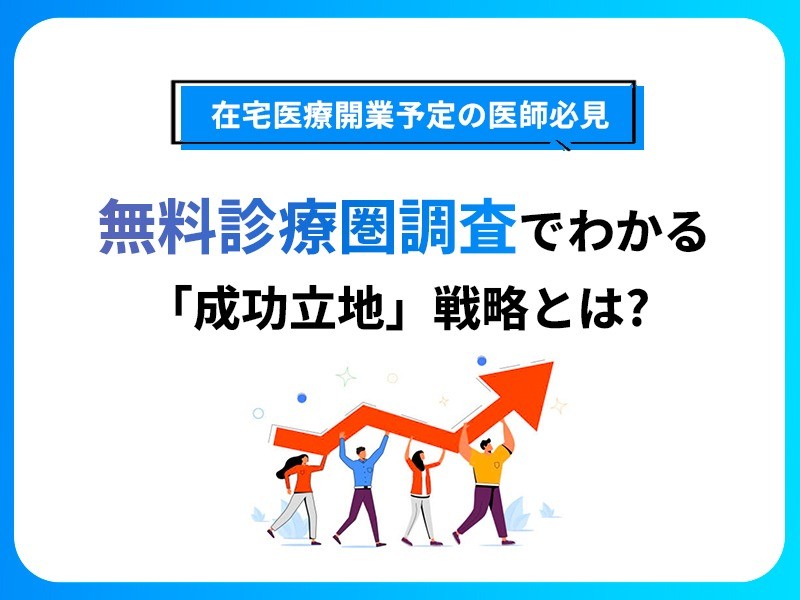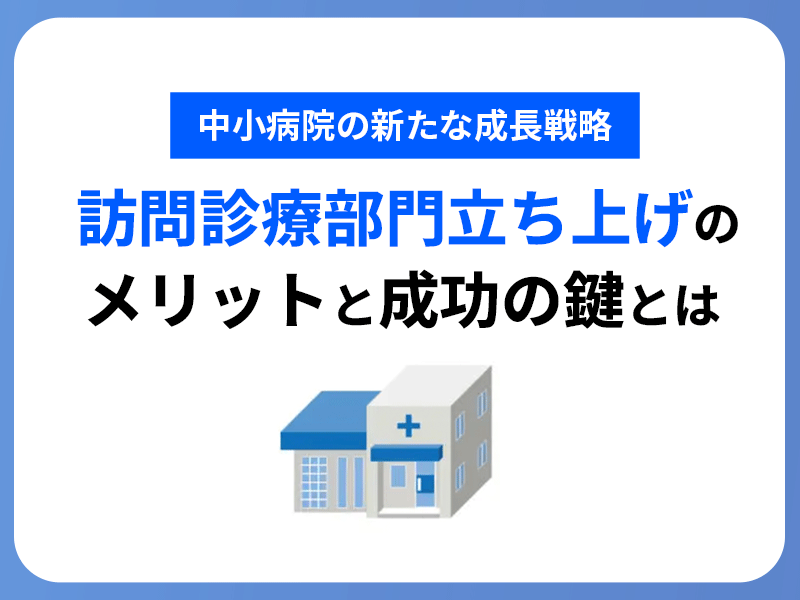- #開業
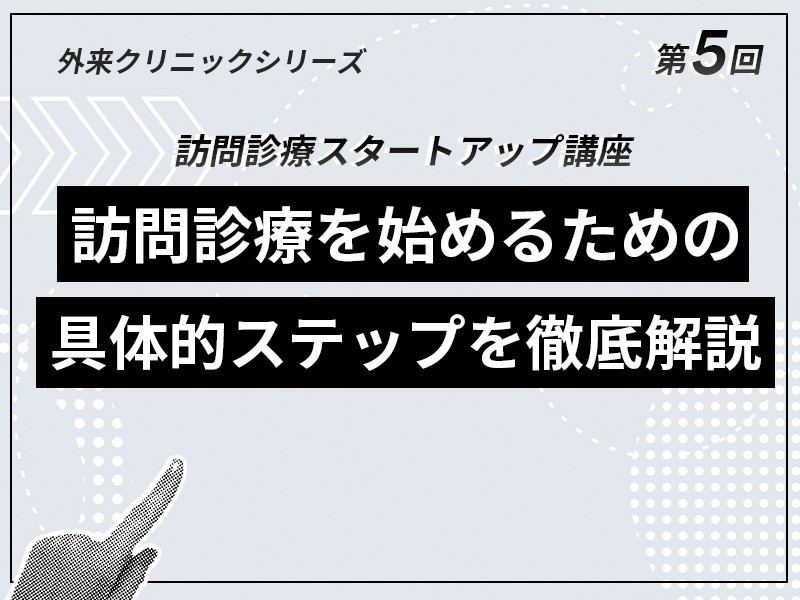
「いつも来てくれていた患者さんが、最近足腰が弱って通院が難しくなってきた…」
「地域のために、もっと出来ることがあるのではないか?」
日々の外来診療の中で、このように感じている院長や事務長の方も多いのではないでしょうか。その解決策の一つが「訪問診療」です。 しかし、いざ始めようと思っても、「何から手をつければいいのか」「外来との両立は可能か」「24時間対応なんて無理だ」といった不安がつきまといます。
そこで今回は、数多くのクリニックの在宅医療立ち上げを支援してきた在宅医療専門の経営コンサルタントに、外来クリニックが訪問診療を「無理なく、着実に」始めるための具体的なステップと成功の秘訣について、詳しくお伺いしました。
インタビュアー: 早速ですが、外来クリニックが訪問診療を始めようと考える際、まず何から検討すべきでしょうか?
コンサルタント: まず最初にやるべきは「構想と計画」です。思いつきで始めてしまうと、後で必ず壁にぶつかります。具体的には、以下の5つの視点で自院の状況を整理し、計画を立てることが重要です。
- 外来と訪問の両立は可能か?: 医師やスタッフの稼働時間、院内スペースなど、時間・人・設備の観点から実現性を冷静に評価します。
- 誰を診るか?どこまで行くか?: 対象とする患者層(疾患、重症度など)と、訪問するエリアを具体的に定めます。
- 地域のニーズはあるか?: 診療圏の高齢者人口や要介護者数、競合クリニックの有無、連携できそうな医療・介護資源などを分析します。
- 事業として成り立つか?: ざっくりで構わないので、収支を試算し、損益分岐点がどのあたりになるかを確認します。
- 外来との相乗効果は?: 通院困難になった外来患者さんの受け皿になる、地域の多職種との連携が深まり外来にも良い影響がある、といった外来診療とのシナジーを考えます。
第1章:はじめの一歩 - 無理のない「スモールスタート」の秘訣
インタビュアー: なるほど、まずは足元を固めることが大切なのですね。とはいえ、最初から大きな体制を組むのは難しいと感じます。最初はどのくらいの規模から始めるのが一般的でしょうか?
コンサルタント: まさにその通りで、成功の鍵は「スモールスタート」にあります。多くのクリニック様が、まずは患者さん2〜3人程度から始めています。例えば、外来の午前と午後の診療の合間や、週に一度の午後休診日などを利用して対応できる範囲ですね。
インタビュアー: 具体的には、「週に何日」「1日何件」くらいが現実的なスタートラインでしょうか?
コンサルタント: 「週に1日、1日に2〜3件」が一つの目安になるでしょう。まずはこの範囲で始め、オペレーションに慣れていくのがお勧めです。
インタビュアー: 訪問診療を始めるにあたり、既存の外来診療とのバランスはどのように考えれば良いですか?
コンサルタント: 最初から完璧を目指す必要はありません。まずは「外来を圧迫しない範囲」で始めることが肝心です。「量・質・経営・運営」の4つの観点からバランスを取ることが重要です。
| 量 | 外来と訪問の業務量・患者数の割合をどうするか。 |
| 質 | どのような疾患や重症度の患者さんを対象にするか。 |
| 経営 | クリニック全体の売上の中で、訪問診療がどの程度の割合を占めることを目指すか。 |
| 運営 | 外来スタッフと訪問スタッフがどう連携し、役割分担するか。 |
インタビュアー: 例えば、「看取りはまだ自信がないので、まずは軽症の患者さん中心で始めたい」といった段階的なスタートは可能ですか?
コンサルタント: もちろんです。むしろ、その方がスムーズです。まずは、通院が困難になってきた既存の外来患者さんに「これからはお家に伺いますよ」とお声がけして、在宅医療に移行するケースから始めるのが最も自然な流れです。 「お看取り」というと重症な終末期医療をイメージしがちですが、老衰など、穏やかな経過を辿るケースも多く、全ての看取りが重症とは限りません。経験を積む中で、徐々に対応範囲を広げていけば良いのです。
インタビュアー: スモールスタートを成功させるために、最初に「これだけは押さえておくべき」というポイントはありますか?
コンサルタント: 押さえておくべきポイントは4つあります。
- 外来と兼務できるスタッフの活用: まずは既存のスタッフで兼務することから始め、新たな人件費を抑制します。
- リーダーの配置: 院長が自ら、あるいは熱意のあるスタッフをリーダーに任命し、在宅医療を推進するエンジン役を明確にします。
- 小さな成功体験の蓄積: 「患者さんやご家族に感謝された」「多職種連携がうまくいった」といった小さな成功をチームで共有し、モチベーションを高めます。
- 訪問診療の「窓口」を明確化: 既存のスタッフの中から、訪問診療に関する問い合わせや相談の担当者を決めます。これは、将来的に外部からの紹介患者さんを受け入れるための重要な布石となります。
第2章:チームを作る - 人員体制の構築
インタビュアー: 次に人の問題です。訪問診療を始めるにあたり、最低限必要な人員体制を教えてください。
コンサルタント: 極論を言えば、医師1名でも始めることは可能です。ただ、安全かつ効率的な運営を考えると、医師1名+同行スタッフ1名(看護師または事務)の体制が望ましいでしょう。運転や診療の補助、物品の準備などを分担できます。
インタビュアー: 既存のスタッフだけで対応できるのは、どのくらいの段階まででしょうか?
コンサルタント: まずは試行段階や、患者数が少ない小規模のうちは、既存スタッフの兼務で十分対応可能です。しかし、中長期的に事業の柱の一つとして育てていきたい、あるいは患者さんが増えてきて兼務では回らなくなってきた、という段階になれば、専属スタッフの採用を検討すべきタイミングと言えるでしょう。
インタビュアー: 訪問診療を導入すると、医師の役割や働き方にはどのような変化が求められますか?
コンサルタント: 大きく3つの変化が求められます。これはマインドセットの転換とも言えます。
- チーム医療の中心へ: 院内だけでなく、ケアマネジャーや訪問看護師など、地域の多職種と連携し、患者さんを中心としたチームの一員としての役割が求められます。
- 「治す」から「支える」医療へ: 診断・治療だけでなく、患者さんの生活や価値観に寄り添い、緩和ケアやご家族のケアも含めた全人的な医療を実践する視点が必要です。
- タスクシフトの推進: 全てを医師が抱え込むのではなく、看護師や事務スタッフ、地域の専門職へ適切に業務を委譲し、チーム全体のパフォーマンスを最大化するマネジメント能力が問われます。
インタビュアー: 事務スタッフの役割も外来とは変わりそうですね。
コンサルタント: おっしゃる通りです。訪問診療における事務スタッフは、単なる受付や会計業務にとどまりません。
- 訪問スケジュールの調整・管理
- 医療物品の在庫管理・発注
- 患者さんやご家族、多職種からの電話相談・問い合わせ対応
- 複雑な在宅医療の診療報酬や関連制度への深い理解
- (診療に同行する場合)運転業務、バイタル測定の補助など
まさに、事務業務の司令塔とも言える重要な役割を担います。
第3章:道具を揃える - 設備・ツールの準備
インタビュアー: ハード面についてお伺いします。新しく調達が必要な医療機器や備品には、どのようなものがありますか?
コンサルタント: まずは基本的なものから揃えれば十分です。
| 【必須】バイタルセット | 体温計、血圧計、パルスオキシメーター、聴診器。これらをまとめて入れておく往診鞄も必要です。 |
| 【任意】検査・医療機器 | エコー、心電計、ポータブルX線、血糖測定器、痰吸引器、ネブライザーなどは、対象とする患者さんの状態に応じて徐々に揃えていけば良いでしょう。最初から全てを揃える必要はありません。 |
| 車両 | コンパクトカーで十分ですが、雪道や悪路が多い地域ではSUVなども選択肢になります。 |
| その他 | 訪問先でカルテ入力や情報確認をするためのモバイル端末(スマートフォンやタブレット)は必須です。 |
インタビュアー: ITツールについてはいかがでしょうか。電子カルテや情報共有の仕組みで導入すべきものはありますか?
コンサルタント: クラウド型の電子カルテの導入を強くお勧めします。院外からでもカルテの閲覧・入力ができ、情報共有が格段にスムーズになります。外来でオンプレミス型(院内サーバー設置型)の電子カルテを使用している場合は、連携可能か、あるいは訪問診療用カルテと併用をどうするかを検討する必要があります。 また、地域のケアマネジャーや訪問看護師と安全に情報共有ができる、医療介護者向けのコミュニケーションツールも導入すると、連携が飛躍的に効率化します。
インタビュアー: 物品の準備で、意外と見落としがちなものはありますか?
コンサルタント: 細かいですが、以下のようなものは忘れがちです。いざという時に無いと困るので、チェックリストを作っておくと良いでしょう。
- 携帯Wi-Fi
- ポータブルプリンター(訪問先で処方箋などを印刷する場合)
- 印鑑(各種書類に押印が必要な場面で)
- 針捨て容器
- 採血検体を保管するための保冷バッグ
第4章:お金の話 - 収支・資金計画
インタビュアー: やはり気になるのが費用です。訪問診療を始める際の、初期費用の目安を教えてください。
コンサルタント: どこまで揃えるかによりますが、一つの目安として合計100万〜300万円程度を見ておくと良いでしょう。
- 車両: 50~200万円(中古車やリースを活用すれば初期費用を抑えられます)
- 医療機器: 30~100万円(まずは最低限のものからで構いません)
- IT環境の整備: 10~30万円
インタビュアー: 黒字化の目安はどのくらいでしょうか?どのくらいの患者数で採算ラインに乗ることが多いですか?
コンサルタント: 常勤医師1名体制の場合、月の訪問患者数が50〜60人程度になると、事業として安定してきます。月の売上で言うと、250万円前後が損益分岐点の一つの目安となることが多いです。もちろん、これは人件費や診療内容によって変動します。
第5章:ルールを知る - 制度・申請・手続き
インタビュアー: 制度面についてです。訪問診療を始めるにあたり、どのような届出や申請が必要ですか?
コンサルタント: 最も重要なのは、「在宅時医学総合管理料(在医総管)」等の施設基準の届出です。これを厚生局に届け出ることで、訪問診療の主要な診療報酬を算定できるようになります。
インタビュアー: 地域の医師会や行政との連携は必要でしょうか?
コンサルタント: 必須ではありませんが、連携しておくに越したことはありません。特に、夜間や休日の緊急時対応を、同じように訪問診療をされている他の医師会員の先生方と連携する方法もあります。
インタビュアー: 申請にあたって、何か実務的なアドバイスはありますか?
コンサルタント: 施設基準の届出は、「いつまでに届け出れば、いつから算定できるか」という締め切りが毎月決まっています。これを事前に管轄の厚生局に確認しておくことが重要です。また、申請書類に記載する緊急時の連絡先や連携体制など、要件を満たしているか、添付書類に不備はないか、といった点も注意深く確認しましょう。
第6章:仲間を増やす - 地域連携と患者獲得
インタビュアー: 患者さんは、どうやって見つけるのが効果的でしょうか?
コンサルタント: まずは、先ほどもお話ししたように「通院が困難になりそうな既存の外来患者さん」からが最も確実でスムーズです。その上で、並行して地域のケアマネジャーや地域包括支援センターからの紹介を得られるように働きかけることが重要になります。
インタビュアー: ケアマネジャーや訪問看護ステーションとの連携は、いつ、どのように始めれば良いですか?
コンサルタント: 訪問診療を正式に開始する前に、挨拶回りをしておくのが理想です。「〇月から訪問診療を始めます。〇〇なことでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください」と、自院の強みや診療方針を伝えていきましょう。地域の医療・介護に関する勉強会や研修会に積極的に参加して顔を覚えてもらう、あるいは自院で多職種向けのセミナーを企画するのも非常に効果的です。
インタビュアー: 地域で信頼を得るために、導入初期にやるべき広報活動はありますか?
コンサルタント: 以下の3つはぜひ実施してください。
- ホームページでの告知: 訪問診療を開始したこと、対応エリア、診療内容などを分かりやすく掲載します。
- PR資料の作成: クリニックの特色や連絡先をまとめたリーフレットを作成し、挨拶回りの際に手渡せるようにします。
- 個別訪問: 地域の主要な居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)や地域包括支援センター、訪問看護ステーションには、実際に訪問をなさる先生が直接足を運び、顔を知っていただくだけでなく、想いをしっかりと伝えることが、何よりの信頼構築に繋がります。
第7章:無理なく続ける - 24時間対応体制の構築と負担軽減
インタビュアー: 多くの先生が最も懸念するのが「24時間365日対応」です。これを、なるべく負担を少なく始める方法はありますか?
コンサルタント: はい、方法はあります。いきなり全てを自院で抱え込む必要はありません。
- 日中のケアを手厚くする: 定期訪問で患者さんの状態をしっかり把握し、状態変化を予測して先手を打つことで、夜間の緊急コールそのものを減らすことができます。
- 訪問看護ステーションとの連携: 信頼できる訪問看護ステーションと連携し、夜間や休日の最初の電話連絡を訪問看護師さんにお願いする体制を構築します。看護師さんの判断で、医師の出動が必要な場合は連絡をもらうようにします。
- 地域の開業医との連携: 在宅療養支援診療所の仲間を見つけ、グループで当番制を組むなど、連携体制を構築します。
インタビュアー: 夜間や休日のオンコールは、どのような体制で始めるクリニックが多いですか?
コンサルタント: 最初は院長一人が対応するケースも多いですが、看護師と持ち回りにしたり、週末だけ非常勤の医師を雇用したりと、事業規模の拡大に合わせて徐々に分担体制を築いていくのが一般的です。
インタビュアー: 外部のサービスを利用して負担を軽減する方法はありますか?
コンサルタント: あります。最近では、夜間や休日の電話対応を代行してくれるコールセンターや、緊急往診のみを請け負うプラットフォームサービスも増えてきました。自院の状況に合わせて、こうした外部サービスをうまく活用することも有効な手段です。
第8章:訪問診療導入の壁と成功の秘訣
インタビュアー: 導入初期に、よくある相談やトラブルにはどんなものがありますか?
コンサルタント:例えば、
- 約束の時間に訪問できない、遅れる
- 緊急往診の依頼に対応できない
- 紹介された新規患者さんの受け入れ可否の返事が遅い
- 連携している地域の多職種への情報共有が不十分
- 書類の作成が遅い
- 訪問診療の制度の理解不足
- 訪問診療請求の誤り
といった声はよく聞かれます。特に、患者さん・ご家族への不十分な対応や地域の多職種とのコミュニケーション不足はクリニックの信頼を大きく損なう原因になります。事前のルール作りと、迅速・丁寧なコミュニケーションを徹底することが何より重要です。
インタビュアー: 最後に、訪問診療の導入を成功させているクリニックに共通する特徴があれば教えてください。
コンサルタント: 成功しているクリニックには、明確な共通点があります。
- スモールスタートで着実に: 最初から完璧を目指さず、できる範囲から始めて徐々に拡大しています。
- スタッフの理解と協力: 院長だけでなく、スタッフ全員が在宅医療の意義を理解し、協力的です。
- オープンな地域連携: 地域の多職種をパートナーとして尊重し、積極的にコミュニケーションを取っています。
- 専任スタッフの配置: 事業が軌道に乗る段階で、訪問診療の専任コーディネーターや看護師を配置し、運営を効率化しています。
- 業務の標準化: 業務マニュアルや各種テンプレートを整備し、誰が対応しても一定の質を担保できる仕組みがあります。
- ITツールの活用: クラウドカルテや情報共有ツールをうまく活用し、業務の無駄をなくしています。
インタビュアー: それでは最後に、これから訪問診療を始めようとする外来クリニックの先生方へ、成功のためのアドバイスをお願いします。
コンサルタント: はい。大切なのは3つです。
第一に、「小さく始めて、大きく育てる」という視点を忘れないでください。背伸びせず、無理のない範囲から一歩を踏み出すことが大切です。
第二に、「続けられる仕組みを作ること」。情熱だけでは続きません。ITツールや外部サービス、多職種連携をうまく活用し、チームとして持続可能な体制を構築してください。
そして最も重要なのが、「地域の多職種とフラットな関係を築くこと」です。それぞれの専門性を尊重し、患者さんを中心に置いたチーム医療を実践することが、地域からの信頼を得て、事業を成功に導く唯一の道です。
まとめ
本日は、訪問診療を始めるための具体的なステップから、事業を継続させるためのマインドセットまで、実践的なお話をお伺いしました。
今回のインタビューで、訪問診療成功の鍵は、
- 無理のない「スモールスタート」で着実に始めること
- 地域の多職種と「チーム」になること
- ITツールや外部サービスも活用し、「続けられる仕組み」を構築すること
にあるということがわかりました。
これまで「何から手をつければいいか分からない」「自院にはハードルが高い」と感じていた先生方も、今回の記事を通して、訪問診療開始までの道のりが具体的に見えてきたのではないでしょうか。
この記事が、通院が困難になった患者さんのために、そして地域医療の未来のために、「次の一歩」を踏み出すきっかけとなれば幸いです。