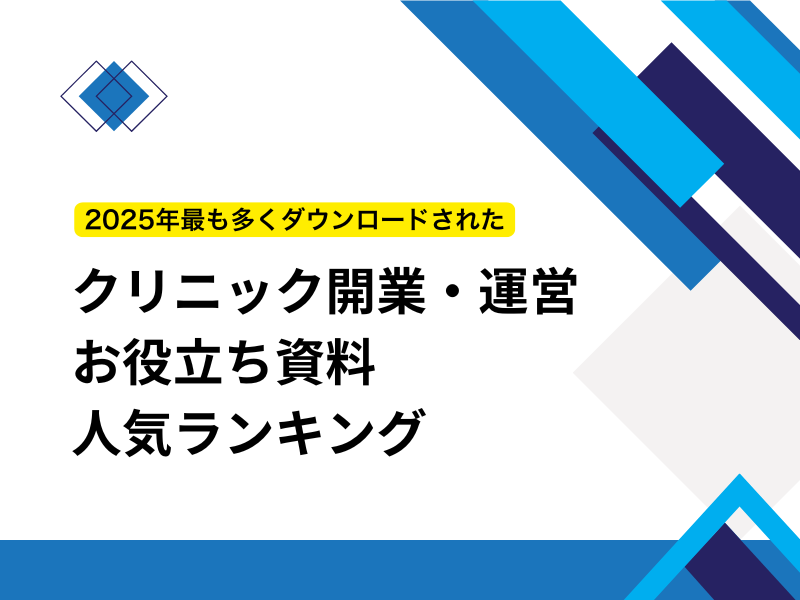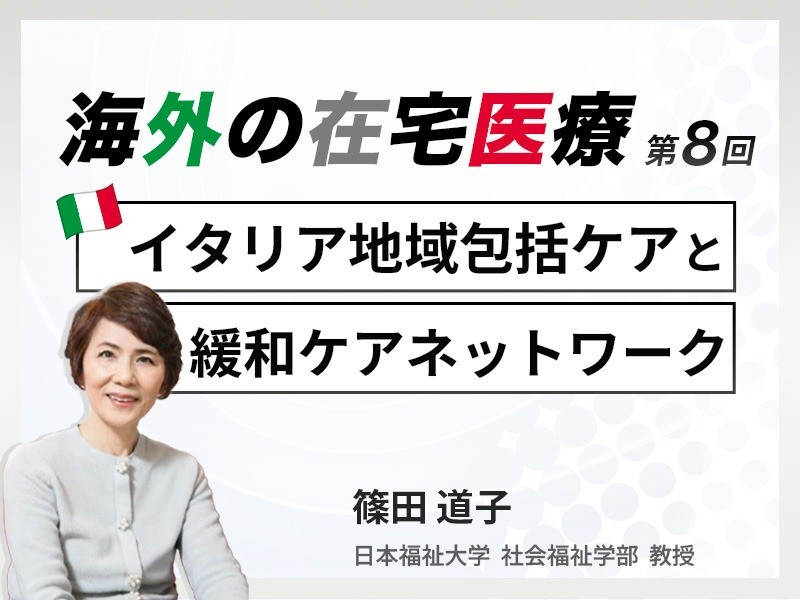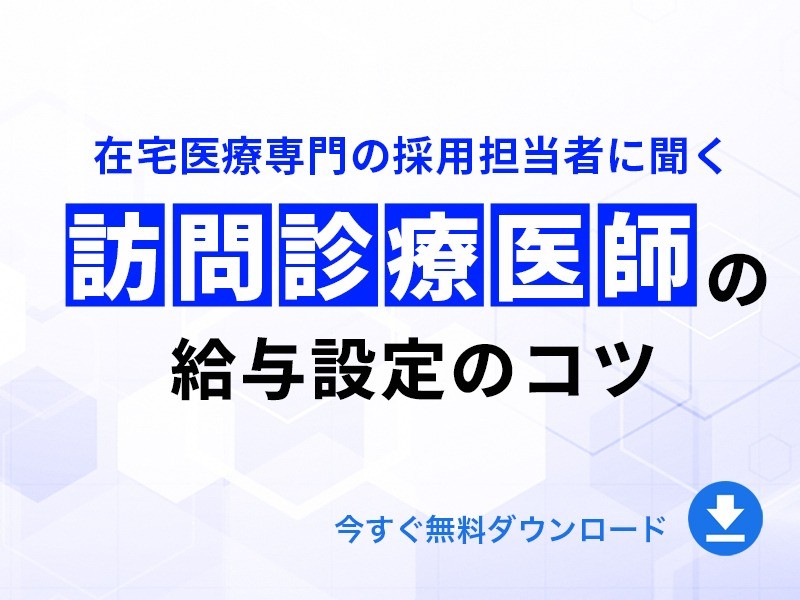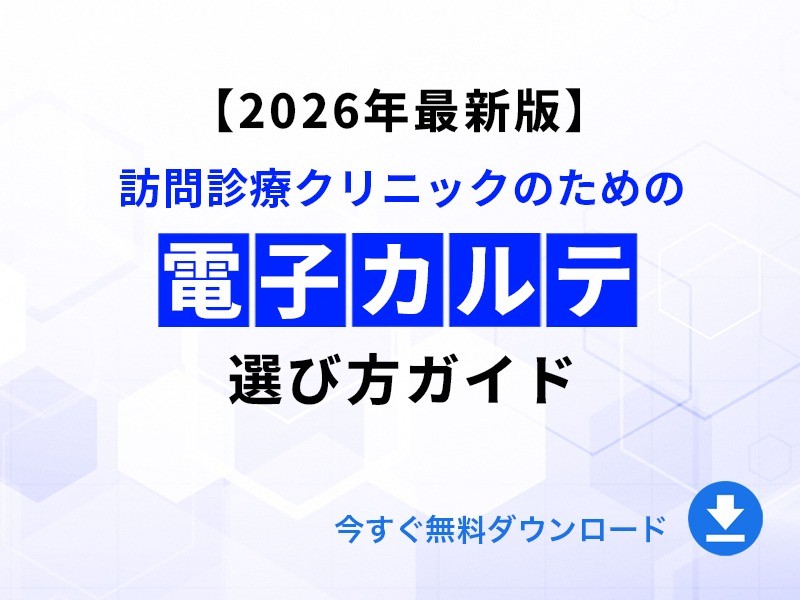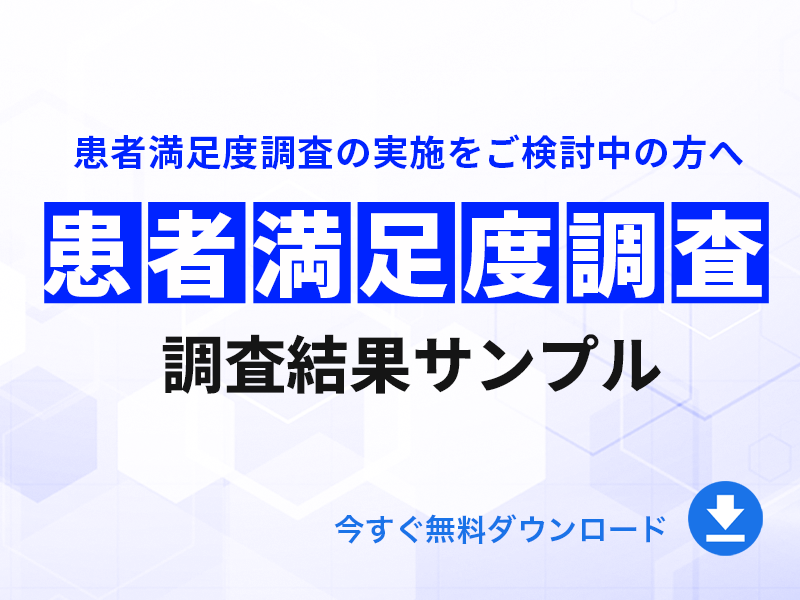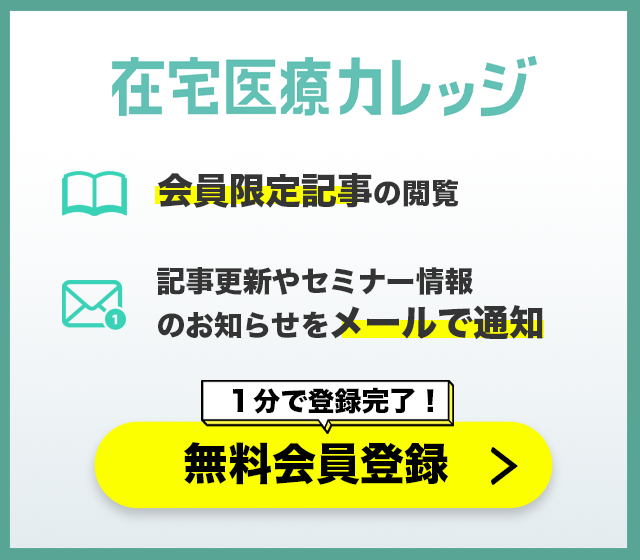【海外から学ぶ在宅医療】ドイツ編|「小規模」が原則の施設型緩和ケア
- #在宅医療全般

※本コンテンツは医療法人社団悠翔会が2019年に公開した記事を転載、一部編集したものです。内容が最新の情報とは異なる可能性があります。
ドイツの施設緩和ケア OUTLINE
- 在宅が基本、在宅で看きれない人だけが施設に
- 施設緩和ケアも必要な緩和ケアレベルに応じて3段階
- ボランティアの役割の重要性
ドイツの緩和ケアは在宅が基本だが、在宅療養の継続が困難になった人たちに対しては、3つの受け皿がある。
6月12日は午前中にドイツで最初の入所型ホスピスハウスホーン(Haus Horn)のあるアーヘン市を訪ねた。
ハウスホーンの入所型ホスピスの視察とともに、アーヘン大学病院・緩和ケア部長のロマン・ロルケ教授から緩和ケア病棟について教えていただいた。
また午後はケルン大学病院に移動し、緩和ケア病棟を実際に見学させてもらった。
その内容を含め、ご紹介したい。

(5)一般的な老人ホーム(ナーシングホーム)や高齢者向けの住まい
緩和ケアというよりも長期的ケア(介護)が主たるニーズの人は、通常、入所型ホスピスや緩和ケア病棟ではなく、一般的な老人ホームや高齢者向けのすまいに入居する。老人ホーム以外の高齢者向けのすまいもあるが、多くは要介護度の高いケースには対応が難しいという現状もある。ここは当然、自己負担が発生する。
これについては、緩和ケアとは直接関係ないため、別にまとめたい。

(6)入所型ホスピス
ハウスホーン(Haus Horn)はドイツで最初の入所型ホスピスとして有名だが、実際には老人ホームやケア付き住宅、デイサービス、リハビリテーション、在宅ホスピス、在宅介護など、さまざまなサービスを複合的に提供している。
介護看護専門職、ソーシャルワーカー、事務職に加え、神学者など、さまざまな背景を持つ220人の職員が在籍している。
ハウスホーンの運営主体はカトリック系の福祉団体
。 教区の神父が1968年に老人ホームを開設したのがスタート。
その後、高齢者向け住宅が併設され(自立の高齢者も含む)、そして1986年にドイツ初の入居型ホスピスが併設された。
当時、ドイツでは新しいムーブメントが生まれつつあった。
病院や老人ホームに閉じ込められ、ベッド上で亡くなっていくという人生の最終段階のあり方に対し、多くの人が疑問を呈するようになっていたという。
シシリー・ソンダースがロンドンに世界で初めてのホスピス(セントクリストファーホスピス)を開設した時期でもあり、彼らはイギリスに新しい終末期ケアのモデルを求めた。
小規模がよいというアドバイスは受けたものの、運営面の効率も考慮し、結果として大規模施設(53床)を作ることになった。そして当初は、死期が近い人ばかりではなく、不治の病の人、宗教的な手当てを必要とする人も受け入れていた。
2002年の法改正後、ホスピスは「家族的な雰囲気」であることが求められ、最大定員が16人と定められた。
そこでハウスホーンでは、施設を入所型ホスピスと長期的ケア施設の2つに分け、ホスピスの入所定員を12人に減らした。

ナデナウさん(写真の左から2番目の女性)は7年前からホスピス部門の責任者をしている。
ハウスホーンホスピスの運営の実際について話を聞いた。
ここでは入所者を「ゲスト」と呼ぶ。
病気を治すのではなく、病気の症状を緩和し、よりよい生活の質を取り戻すための支援をしている。
入所するためには、主治医(病院医または家庭医)の入所型ホスピスの必要性を認める書類が必要。それを疾病金庫(保険者)に提出すると、95%が償還される。残る5%は運営者の責任で賄う(寄付金やその他の事業収入など)。
本人の自己負担はここでもゼロ。
ゲストの主要な疾患はがん(悪性腫瘍)だが、神経難病、COPD、心不全なども増えてきている。
ここは成人向けの入所型ホスピスで、18歳以上を対象としている(小児用ホスピスは全く違うコンセプトのもとに運営されているので、成人と小児を分ける必要があるのだという)。入所者の平均年齢は73歳。高齢者が多い。
平均滞在日数は54日。2018年は80人がこのホスピスで亡くなった。

入所型ホスピスでは主に4つの機能を提供している。
①緩和看護
看護師によって提供される緩和ケア。本人中心のケア、本人の気持ち、やりたいことなど、対話する時間を十分にとる。自分でできることは自分でやってもらう。
②緩和医療
随伴症状(疼痛など)の治療や合併症の治療、それらによる生活の質の向上。緩和看護ケアとの連携が重要。ただし、入所型ホスピスには医師の配置はない。患者ごとの主治医(家庭医)が施設を訪問する。
③スピリチュアルケア
人生を振り返り、自分のやり残したこと、やるべきこと、謝罪・仲直りしておくことなど。スピリチュアルカウンセラーも在籍。家族や友人たちとの橋渡しなども。
④心理社会面の支援
感情面の支援、社会的支援(人生の最終段階においても、社会に属する一因として、参加を継続できるよう)、主にソーシャルワーカーが担う。例えば、「最後に海を見たい」という希望を叶えるために、家族と調整したり、ボランティアをコーディネートしたり、ACPのお手伝いをしたり、など。

おしゃれなスカーフのこの男性は、ボランティアのポールさん(65歳)。毎週水曜日、朝7時から午後2時までここで、入居者と食事をしたり、話し相手をしたり、庭を散歩したりしているという。退職してからボランティアをされているのかと思いきや、実は現在も現役で仕事しているとのこと。
3年前、ブリュッセルで起こった爆弾テロで友人が亡くなったことをきっかけに、よりよい世界を作るために、自分のできることをやりたい、と思うようになった。その時以来、2つのことを心掛けているという。1つはいつも笑顔でいること、そしてもう1つは、「よいこと」を続けること。
ここでボランティアをするようになったきっかけやモチベーションは何ですか?と聞いてみたら、そんなエピソードを教えてくれた。
12床はすべて個室。
常勤換算で13.5人分のポストを19人の職員でシェアしている。
職員は緩和ケア・疼痛治療・創傷治療の追加的資格を持つ看護・介護専門職。病院や介護施設よりも人員配置は厚い。
ここにソーシャルワーカー、スピリチュアルケアカウンセラー、生活(家事)支援チーム、ボランティア、各種セラピスト、そして医師が加わる。
彼女の言葉でもっとも印象に残ったのは、次の一文。
「ここでは家族も多職種も、その人の人生・日常生活に統合(Integrate)する。」
彼女は、この多職種チームが「その人にとっての最善の生活の質の実現」という目的を共有し、対等な関係性の中で連携できているということがとても大切だ、と強調されていた。
日本でいえば、一定の医療処置に対応できる看取り力のある老人ホーム、あるいはグループホームという感じだろうか。
(16床などという小規模なところはほとんどないが)
僕らが連携医療機関として関わらせていただいている特定施設、サービス付き高齢者向けやグループホーム、住宅住宅型有料老人ホーム、特別養護老人ホームの中には、入所型ホスピスと同様のケアが提供できているところもある。
施設看護師(または連携する訪問看護師)のスキルやマインドを高めていくことで、ドイツの入所型ホスピスに近いサービスを提供することは十分可能なのではないかと思った。
もちろん医師の配置はないため、入所型ホスピスは看護的な支援が中心となる。
より高度な緩和医療的処置が必要になるケースでは、緩和ケア病棟が選択される。
(7)緩和ケア病棟
アーヘン大学病院・緩和ケア部長のロマン・ロルケ教授からは、最初にドイツにおける緩和医療の取り組みについて教えていただいた。

前述の通り、全ドイツ2000病院のうち、300の病院(15%)が緩和ケア病棟を持っている。これは日本に比べて、かなり充実していると思う。
また、素晴らしいと思ったのは、緩和ケア病棟がない病院でも、少なくとも緩和ケア部門(緩和ケアの専門的知識を持つ医師・看護師のチーム)を持っており、全科横断型で緩和ケアの診療を支援しているということだ。
全科横断型ということは、イメージとしては、例えば在宅栄養サポートチームのように、病棟や専門診療科の枠を超えて、患者さんの診療に直接関与する、ということになる。緩和ケア病棟を持つ病院を除けば、このような緩和ケアチームによる診療支援は日本では非常に少ないと思う。
入所型ホスピスも、病院の緩和ケアも、人生の最終段階の支援という点では同じ仕事をしている。
緩和ケア病棟は、疼痛や呼吸困難などに対する症状緩和的治療が中心になる。
アーヘン大学の緩和ケア病棟は9人の入院病床を持つ。在院日数は平均11日。年間250人の患者さんを診ている。50~60%の方が入院中に亡くなり、残る方は退院(在宅復帰・ホスピス入所)となる。
全科横断的に病院全体を支援する緩和ケア部門もあり、ここでは年間600人の病院入院患者に対応しているという。
緩和ケア病棟入院患者の主たる原因疾患は80%ががん、7%が脳神経系、7%が循環器系。現在はがんが治るようになってきているので、今後、非がんの割合が増えることになると予想しているという。
従って、これまではがんの緩和医療に対応できれば仕事はできたが、今後は脳神経系・循環器系疾患に対する緩和ケアがしっかりと提供できる体制を作っていく必要があると、ヨースト医師と同様の指摘をされた。

午後はケルン大学を訪問した。
ケルン大学病院の緩和ケア部門は、緩和ケア病棟の他、病院の他科入院患者を支援する全科横断型の緩和ケアチーム、そして在宅緩和ケア(SAPV:専門的訪問緩和ケア)も提供する、ケルン左岸の総合的な緩和ケア拠点となっている。
緩和ケア病棟は15の個室を持ち、年間450人が入院する。
90%ががん、平均在院日数が10日、60%がホスピスで死亡するという。
このあたりはアーヘン大学の緩和ケア病棟とほぼ同じ。
全科横断型の緩和ケアチームは年間850人の他科入院患者に対応、延べ訪問回数は2700回に上る。
この件数は年々増加してきているという。
在宅緩和ケア(SAPV:専門的訪問緩和ケア)はライン川左岸地域を担当する。
年間400人の専門的訪問緩和ケアに対応、在宅での看取りも行っている。また、在宅ホスピス事業も行っている。


広報担当のハーバーさんに、緩和ケア病棟を案内してもらった。
ケルン大学病院の緩和ケア病棟では、多職種チーム(医師・看護師・ケースマネジャー(心理社会的ケアを担当))が患者ケアにあたり、ボランティアがそれを支援する。医師は10名(緩和ケア医のみならず、総合診療、老年精神科、精神科、腫瘍内科、麻酔科など)、昼間は3人の看護師が、夜間は2人の看護師が病棟に待機する。
また、理学療法士・スピリチュアルケアカウンセラーの訪問に加え、心理療法、動物療法、音楽療法、芸術療法など、さまざまな支援が受けられるという。
緩和ケア病棟の入り口には、家族や患者のための安らぎのスペースがあった。
不透明なガラス壁で区切られ、中には本棚や水槽が。居心地のよいリビングという感じだ。
真ん中に置かれた大きな木のテーブルを数人の患者や家族が囲んでいる。テーブルの上にはクッキーやティーカップ。そこに、ベッドに寝たままの一人の患者が加わった。
「お楽しみの午後」というイベントらしい。
心理士を囲んでの患者と家族のおしゃべりの時間。五感に働きかけて、病気以外のことを考えることを目的としているという。
緩和ケア病棟の個室は、ブルーの窓枠が印象的な「居心地のよい病室」という感じ。
高い天井の広い部屋、テラスにはベッドのまま出られるようになっている。天気のよい日は日光浴もできる。ベッドサイドには小さな正方形の窓は、寝たきりになっても外の風景を楽しめるように設置されているのだという。
部屋は中庭を囲むように半円形状に配置されている。庭にはハーブや実のなる木が植えられていて、「大学病院の中のオアシスのような空間」とハーバーさんは表現されていた。
日本の緩和ケア病棟とは違い、白衣の医師や看護師の姿は見えない。
その代わりに、私服のコーディネータやボランティアが。患者の家族との見分けがつかない。
そして、病院的なにおいや音はなく、ゆったりとした時間が流れている感じがする。
しかし、やはりここは病院。
生活空間という感じはしなかった。
ちなみにドイツの緩和ケア病棟には、看護師数などの人員配置基準はないが、ボランティアの配置は法定要件になっているとのこと。
ケルン大学病院の緩和ケア病棟では、3人のコーディネータとともに、40人のボランティアが活動中。
在宅ホスピスのボランティアと同様、100時間の教育に加え、ボランティア間でのOJT、月に1度経験を共有するためのミーティング、スーパービジョンなどが行われている。

■小規模多機能・看護小規模多機能の強みを生かせば
ドイツでも高齢者ケア、緩和ケアは在宅が基本、という流れになっている。
私が個人的に感じたのは、小規模多機能や看護小規模多機能と訪問診療を組み合わせれば、そして、それぞれがしっかりと専門性を発揮して、きちんと連携できれば、「在宅緩和ケアは無理だ」という閾値を上げることができるのではないかという点。
小規模多機能・看護小規模多機能が3つの機能をしっかり使いこなしながら、在宅医の緩和医療に関する知識やスキルの平均レベルを上げることができれば、在宅で過ごすことができる人はもっと増やせるのではないだろうか。
また日本では、ドイツとは異なり、緩和ケア病棟がAIDS以外の非がん疾患に対応できない。在宅医や訪問看護師は、特に非がん疾患に対する緩和ケア的な対応能力を高めていかなければならないと感じた。
補足1 ※入所型ホスピスの入居、緩和ケア病棟の入院にかかる費用
いずれも患者の自己負担はゼロ。95%が疾病金庫から償還され、残る5%は運営者が寄付等で賄わなければならない。 診療報酬は医療団体ごとに価格を交渉する。
アーヘン大学の緩和ケア病棟の場合、504ユーロ/日、ハウスホーンの入所型ホスピスの場合、346ユーロ/日。 入所型ホスピスで、日本の緩和ケア病棟の入院医療費とほぼ同等、という感じか。
補足2 ※事前指示書について
ドイツでは事前指示書は法的拘束力を持つ。医師はそれに従わなければ(非合法な内容でない限り)追訴される。
事前指示書を書いている人の割合は入所型ホスピスでも緩和ケア病棟でも80%くらいで、徐々に高くなってきているという。7年前の統計では、老人ホームの入居者で事前指示書を書いている人の割合は12%であった。現在、急速に増えてきている。
2015年にホスピス・緩和ケア法が作られてから、ACPが広く周知されるようになった。昨年より、それに対する特別な教育も始まった。施設によっては、事前指示書を入居の条件として求めるところも出てきている。
事前指示書を作成する上で重要なのは、チェックリスト式ではなく、その場の状況に合わず、役に立たないことが多い。 もっと細かい情報を患者に提供し、一緒に考えていくことが大切という。
事前指示書の作成においては、家庭医は相談に乗る(患者の経過の見通しや可能な医療の選択肢について詳しく説明する)ことができる。これは診療報酬で評価される。ただし、義務ではない。事前指示書に医師のサインがなくても無効にはならない。医師は事前指示書に従わなければならない。変更がなされない限り無期限で有効。