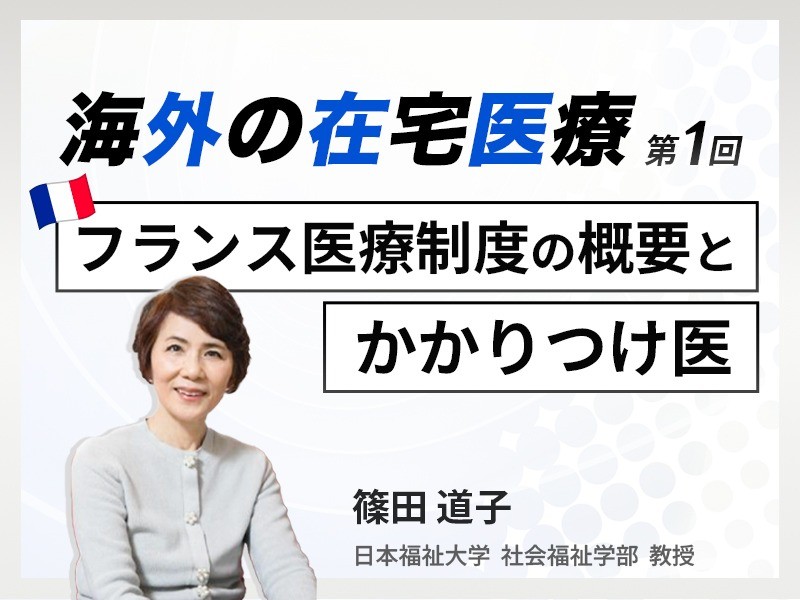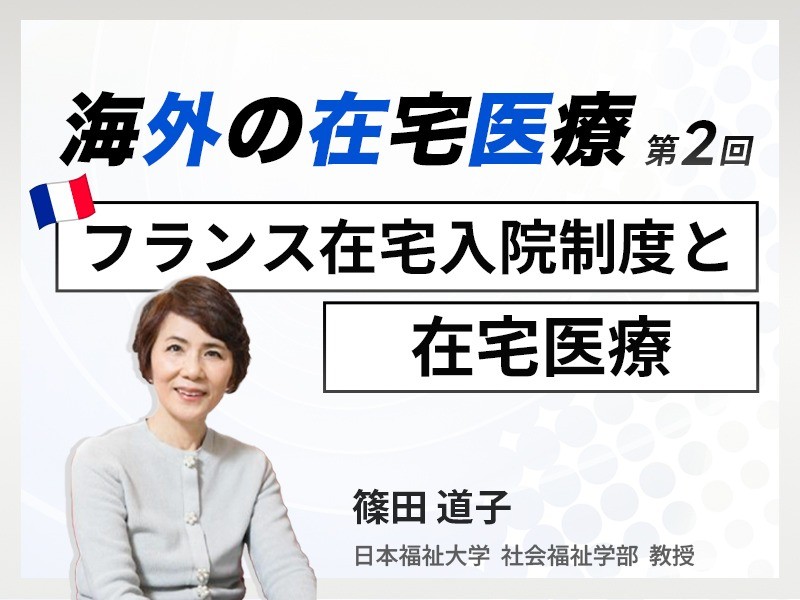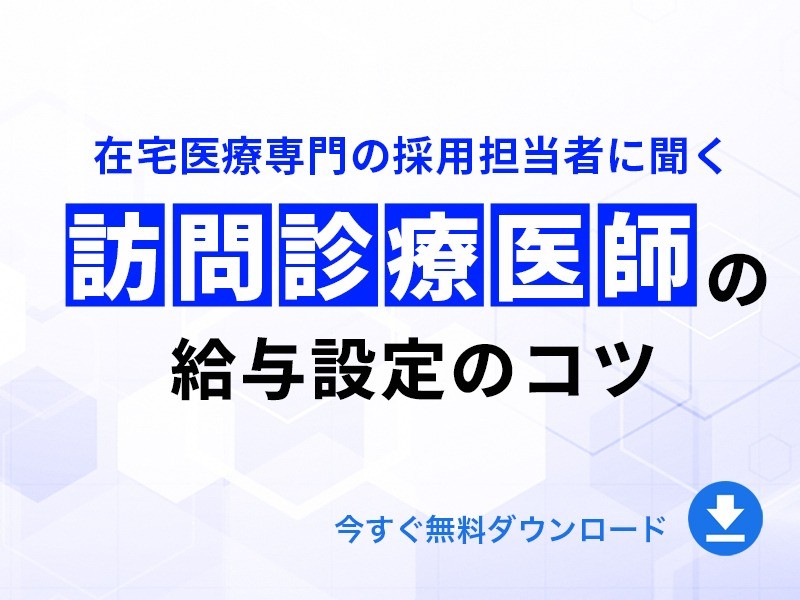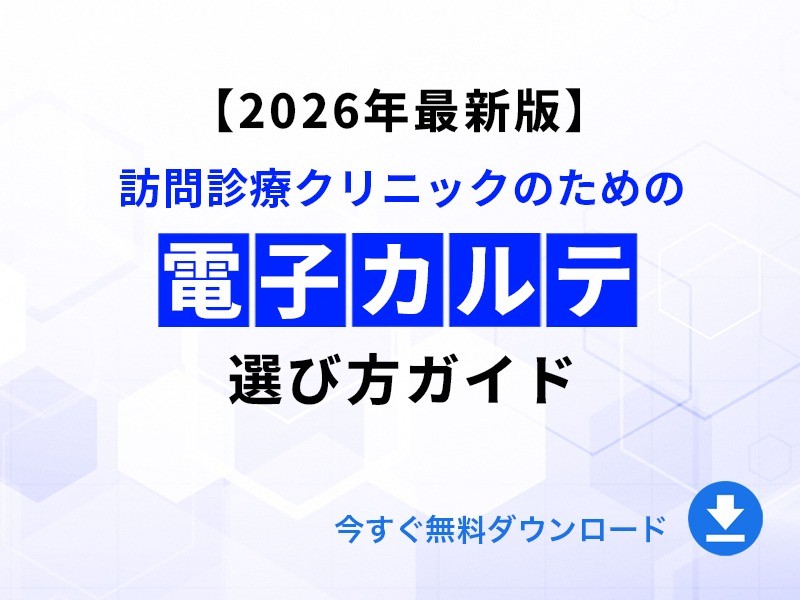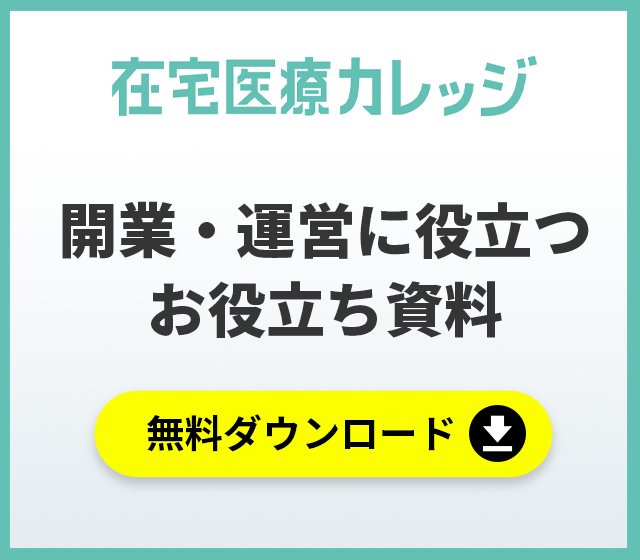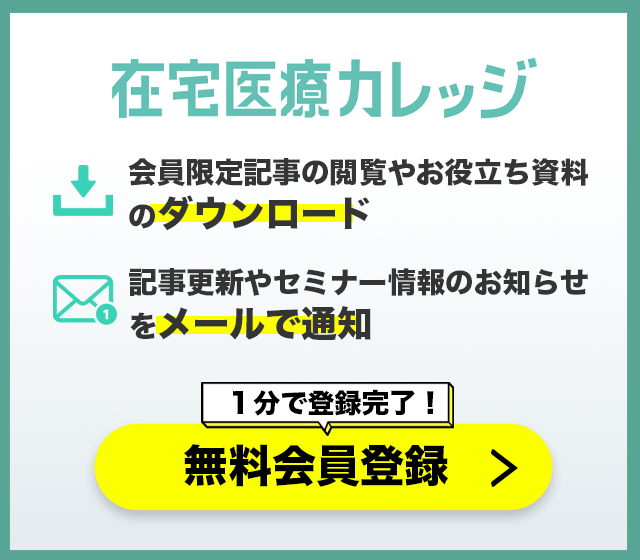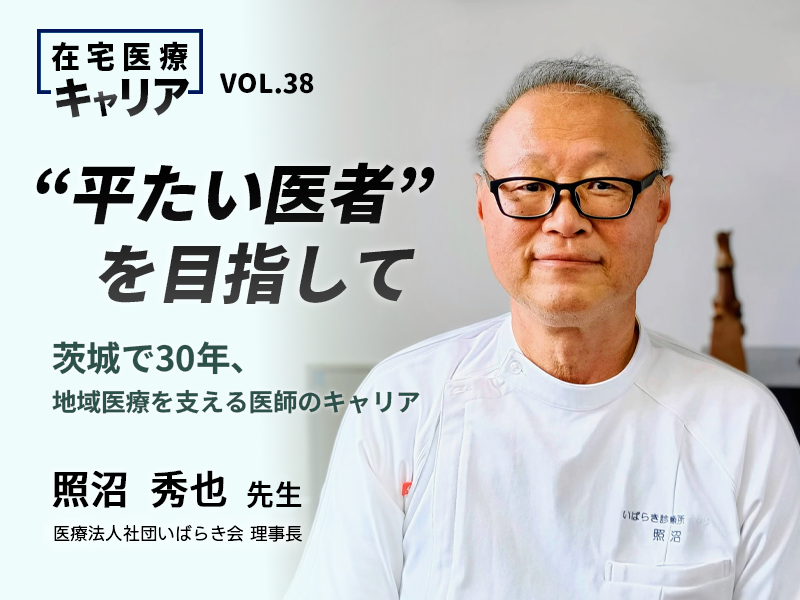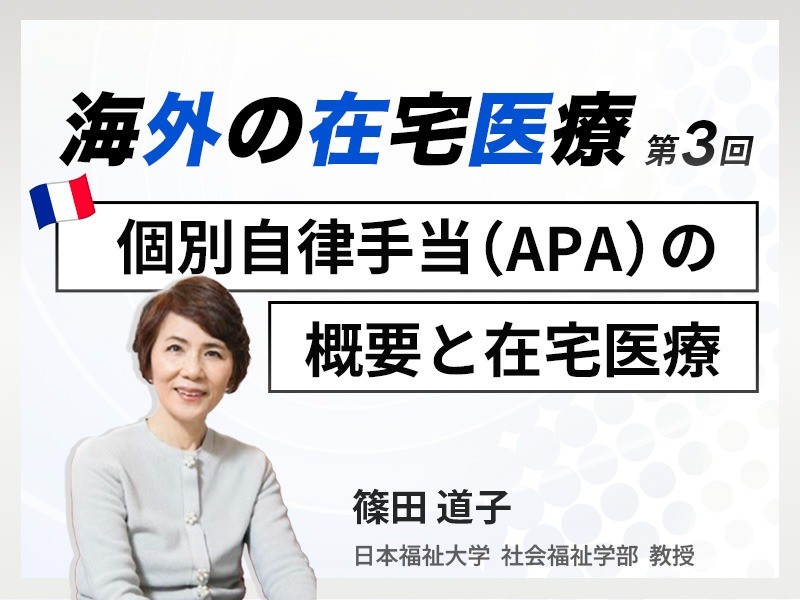
前回は在宅医療の中核的な存在である「在宅入院制度(HAD)」の概要、提供される医療行為と保険給付、病院・在宅入院機関・個人開業者とのトライアングル連携の実際、さらに在宅入院制度の課題について整理した。
今回は、フランス介護保障の中核的な制度である「個別自律手当(APA)」の概要と動向、在宅医療の関係を紹介する。APAはドイツの介護保険制度を参考にしており、日本の介護保険制度との共通点も多いが、制度上は社会扶助の位置づけであり社会保険ではない。
日本福祉大学 社会福祉学部 教授
篠田 道子 先生
筑波大学大学院教育研究科修了。病院勤務、民間企業を経て日本福祉大学社会福祉学部赴任。2008年日本福祉大学社会福祉学部教授(現在に至る)。2011年から1年間は慶応義塾大学大学院経営管理研究科で、訪問教授としてケースメソッド教授法を学ぶ。主な研究テーマは、医療・福祉マネジメント、終末期ケア、ケースメソッド教授法、フランス・イタリアの医療・看護・介護制度と人材育成
1.個別自律手当(APA)の概要
フランスでも高齢化に伴い、要介護高齢者の長期入院や医療費の高騰が問題となり、医療と介護で分離している法律や制度を統合した新しい介護制度が検討されていた。1991年以降に全国でモデル事業が実施され、それを受けて1997年1月に依存的特別給付(PDS:Prestato Specifique Dependence)が導入された。PDSは社会扶助(aide sociale)としての位置づけで、実施主体は県、財源は租税を充てた。この制度では、要介護認定(AGGIR :la Grille Autonome Gerontologique-Groupes Iso-Ressources)という全国一律の判定基準を採用し、6段階の要介護度(GIR)に分類するという、わが国の要介護認定に類似したシステムが導入された。
しかし、利用にあたっては次のような問題が指摘されていた。①資産調査による所得制限が義務付けられた、②所得の低い者と重度な要介護者に限定した、③介護施設は給付対象外とした、④県によって給付格差が生じた、など課題が多かったため、利用者数が伸び悩み、早くから制度改革を期待する声が強かった。
このような課題をクリアするために、PDSの代わりに個別自律手当(APA:Allocation Personalisee D’autonomie)が、2001年3月に議会に提出され、成立後の2002年1月1日から施行された。APAは給付対象者を広げ、評判の悪かった資産調査を廃止し、所得による自己負担額を設定した。さらに、介護施設も給付対象とするなど利用者の拡大を図った。財源は、県税、年金金庫からの拠出金、一般社会拠出金などで構成されている。
2002年の制度開始から利用者数は徐々に増加し、2020年の受給者は131.9万人、年間給付額6278百万ユーロにものぼり、フランス介護保障の中核的な制度に位置付けられている。以下にAPAの概要を紹介する。
【対象者】
次の3点を満たしている者。
①フランス国内に15年以上合法的に居住している。
②60歳以上である。
③自律の一部を喪失したために、日常生活に支障のある者で、要介護認定で要介護者(GIR
1~4)と判定された者。
虚弱者(GIR5)および自立者(GIR6)は給付対象外であるが、介護予防事業(財源は
老齢保険金庫)が利用できる。
【要介護認定と支給限度額】
要介護認定(AGGIR)から給付決定までのプロセスを示す。
①在宅での介護サービスを希望する場合(在宅APA)は、本人または家族、法廷代理人のいずれかが県の窓口に申請する。
②申請後に書類が送付されるので、申請者は必要事項を記入し、添付書類(ID証明書、納税書類等)とともに返送する。
③県の社会医療チーム(医師・看護師・ソーシャルワーカーで構成)が申請者宅を訪問し、要介護認定調査項目に沿ってアセスメントをする。【注1】その後6段階からなる要介護度区分を判定する。表1にAGGIRによる要介護度区分と支給限度額を示す。施設入所者の場合、医師の責任において施設によって行われる(施設APA)。
④申請から2か月以内に、県の担当者がAPAの給付の有無を通知する。
わが国と同様に在宅APAではGIR別に支給限度額を設定している。2021年の在宅APAの支給限度額は、最重度のGIR1が1737ユーロ、GIR2が1394ユーロ、 GIR3が1007ユーロ、GIR4は672ユーロである。施設APAについては支給限度額ではなく、実際に給付される介護費用である。
表1 要介護認定による要介護度区分と支給限度額(在宅/施設※)
| GIR1 | 1日中ベッドに就床または座った状態。心身機能が低下し、社会的自律を失っている(在宅1737ユーロ/施設335ユーロ) |
| GIR2 | ひとりでは移動不可能、または移動は可能であるが認知能力が低下している(在宅1394ユーロ/施設335ユーロ) |
| GIR3 | 認知能力正常、運動能力は最低限維持されているが、1日数回のADL援助を要する(在宅1007ユーロ/施設167ユーロ) |
| GIR4 | 自分ひとりで移動可能であるが、ADLに時々援助を要する (在宅672ユーロ/167ユーロ) |
| GIR5 | 自宅での移動や生活にほぼ問題はないが、清潔、食事の用意、買い物等に限定的な援助が必要 |
| GIR6 | 基本的な動作において自律を維持している |
※施設APAは実際に給付される介護サービス費である
2019年12月のAPA受給者の要介護度区分の割合は表2のとおりである。在宅APAはGIR4が58%と軽度の要介護者が多く、施設APAはGIR1とGIR2を合わせると59%となり、重度者が多い。
表2 APA受給者の要介護度区分の割合(%)
| GIR1 | GIR2 | GIR3 | GIR4 | 計 | |
| 在宅APA | 2 | 17 | 22 | 58 | 100 |
| 施設APA | 15 | 44 | 18 | 23 | 100 |
出典:DREES Les bénéficiaires et les dépenses brutes de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de 2002 à 2019; Répartition des bénéficiaires de l’APA par GIR, payés autitre du mois de décembre
2.APAで給付されるサービス
給付されるサービスは、在宅APAと施設APAとで異なる。在宅APAは、社会医療チームが作成したケアプランによって提供される。給付対象となるサービスは、家事援助、食事の介助、配食サービス、移動介助、福祉用具購入費(車いす・杖・歩行器・医療用ベッド・失禁用品等)、家族等の介護者に対するレスパイトケアである。
施設APAは、高齢者向け介護施設で要介護状態(GIR1~GIR4)と認定されれば、給付が受けられる。医療費及び宿泊滞在費(ホテルコスト)を除いた介護費用のみが給付される。【注2】
フランスの高齢者向け介護施設は次の4種類がある。①医療付き高齢者住宅(EHPAD:Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ②高齢者用共同住宅(Logement-foyers) ③老人ホーム(Maisons de retraite で、EHPADの認定を受けていない老人ホーム)④高齢者のための長期入院施設(Unités de soins de longue durée)。
①のEHPADは、日本の療養病床と特別養護老人ホームの中間的な位置づけである。高齢者向け介護施設の7割、居室数で8割を占めており、多くの入居者が施設APAのサービスを受けている。介護度の重い入居者が多く、移動・排泄・食事・入浴などは介護職員による介助が提供されている。EHPADは介護だけでなく、医療サービス(主に訪問診療で、HADが対応)も多く提供されている。医療サービスの詳細は次回(第4回目)で述べる。
3.ケアマネジメント機関としてのMAIA
フランスでは、2009年7月21日法により医療計画と地方健康計画が統合されたことで,制度上縦割りであった保健・医療・介護(APA)を包括した行動計画が策定されるようになった。これにより,地域全体を大きな施設として捉え,在宅入院制度(HAD)をネットワークとして位置づけ,場所や制度を越えてサービスを提供する仕組みを整えてきた。
しかし、APAにはわが国の介護支援専門員に該当する職種を位置付けなかったことから、医療と介護の連携に課題が残った。そこで「自律と包括的ケアのためのネットワーク」(MAIA:Methode d’action pour l’integration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie)という保健・医療・福祉・介護サービスをマネジメントする機関を設置した。
MAIAは認知症の人や家族に対する相談や包括的なサービスを提供する機関として2009年にスタートした。その後徐々に役割を拡大して、現在は60歳以上の自立困難な高齢者(主にAPAの受給者)に対し、3つのサービスを提供している。①医療・介護サービスへのアクセスを目的とした総合相談窓口、②標準化された包括的なアセスメントによる在宅支援、③ケアマネジメントによる多職種連携である。2018年には352か所に設置されている。
さらに、MAIAは2008年から資格化されたケアマネジャー(coordonnateur)を配置した。ケアマネジャーに必要な基礎資格は、看護師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、作業療法士の4職種で、一定の実務経験を経た後,大学などの教育機関で研修を受けなければならない。2013年にはフランス全土で750人のケアマネジャーが誕生した。一人のケアマネジャーが担当できるのは40ケースまでである。
MAIAについては、第1回の連載でも少し紹介したが、医療と介護のワンストップサービス拠点で、中重度者のケアマネジメントを担っている。ケアプラン作成にあたっては、かかりつけ医の助言を受け、コーディネーション会議(ケアカンファレンス)で検討する。この会議の参加者は、県の担当者・かかりつけ医・APAの担当者・開業看護師・HADのコーディネート医師または看護師・介護職員などである。司会はMAIAのケアマネジャーが担当する。わが国の地域ケア会議のような位置づけである。
4.APAと在宅医療
APAは介護保障であり、給付されるサービスは介護サービスに限定されるため、在宅APA・施設APAともに在宅医療との連携が不可欠である。在宅APAについては、在宅入院制度(HAD)のコーディネーター医師との連携が中心になる。第2回で紹介したように、HADの医療行為は緩和ケアと特殊・複雑なガーゼ交換(創傷管理)で約半分を占める。以下、重度ナーシング(術後ケア含む)、経静脈栄養、経腸栄養と続く。急性期~亜急性期を過ぎ、症状が安定したらかかりつけ医と開業看護師に引き継ぐ。
EHPADなどの高齢者向けの介護施設は、医師・看護師の配置が手薄で、夜間はオンコール対応となる。そのため、HADの医療チームが24時間・365日対応している。HADは入院医療と同レベルの医療を提供することから、医療行為のために病院に入院することは少なく、住み慣れた施設で過ごすことができるというメリットがある。
在宅APA・施設APAともに介護サービスに限定されているため、医療サービスとの連携が不可欠である。特にGIR1やGIR2のような重度要介護者にとっては、HADのコーディネーター医師と連携しながらケアプランを作成し、サービスを提供し、モニタリング・再アセスメントするというケアマネジメントのプロセスを共有する体制づくりは有効である。
【注1】要介護認定調査項目は、①身体・精神機能評価項目(コミュニケーション、時間空間認知・着替え・食事・排泄・移動など10項目)、②手段的日常生活機能項目(金銭管理・食事の準備・家事・買い物・処方箋の理解・交通手段の利用・レクレーションへの参加の7項目)である。
【注2】介護施設の入所費用は、介護サービス費・ホテルコスト(部屋代+光熱費)・医療サービスの3種類であるが、APAの支給対象は介護サービス費に限定されている。ホテルコストは自己負担、医療サービスは医療保険から支給される。