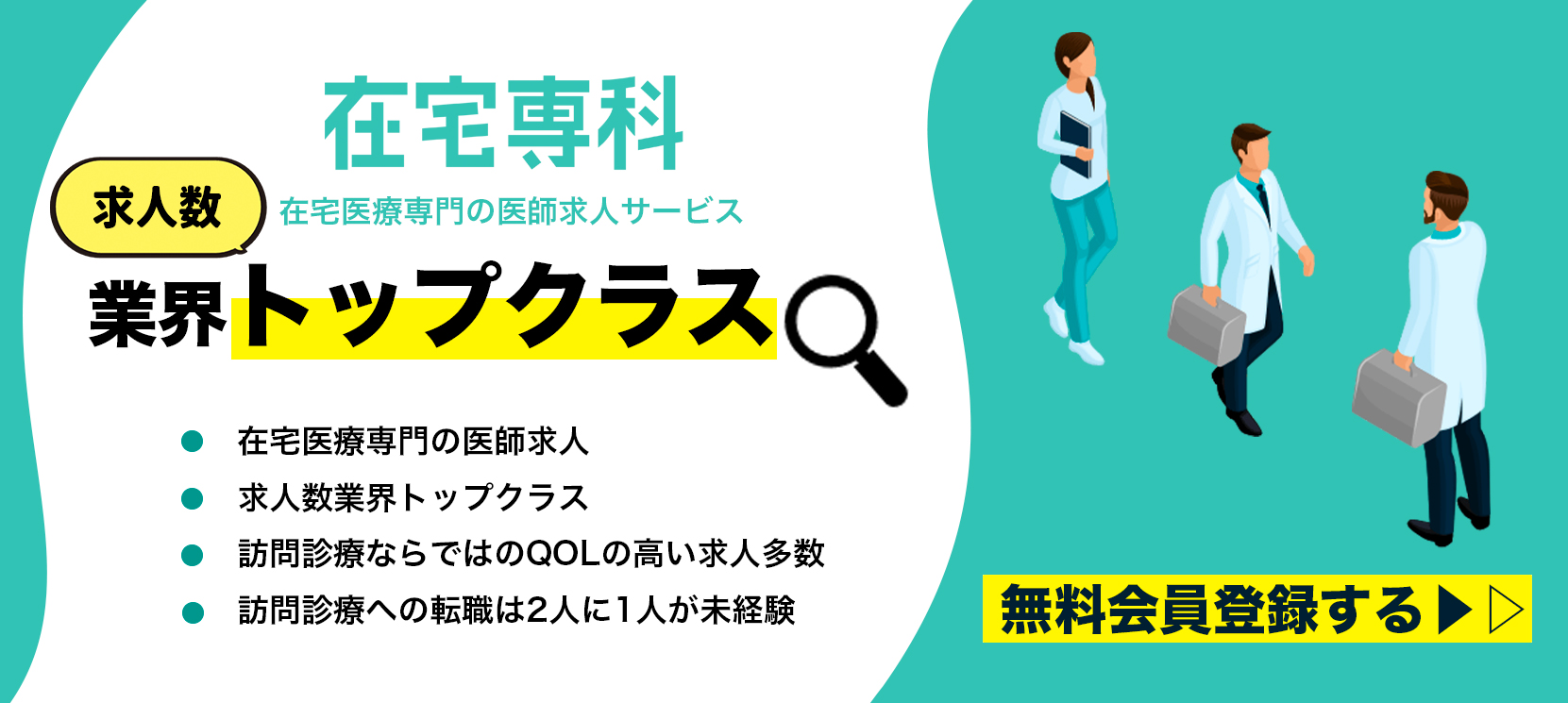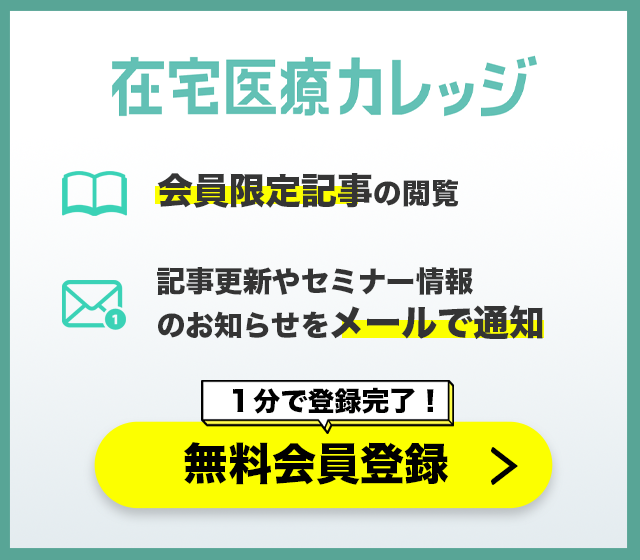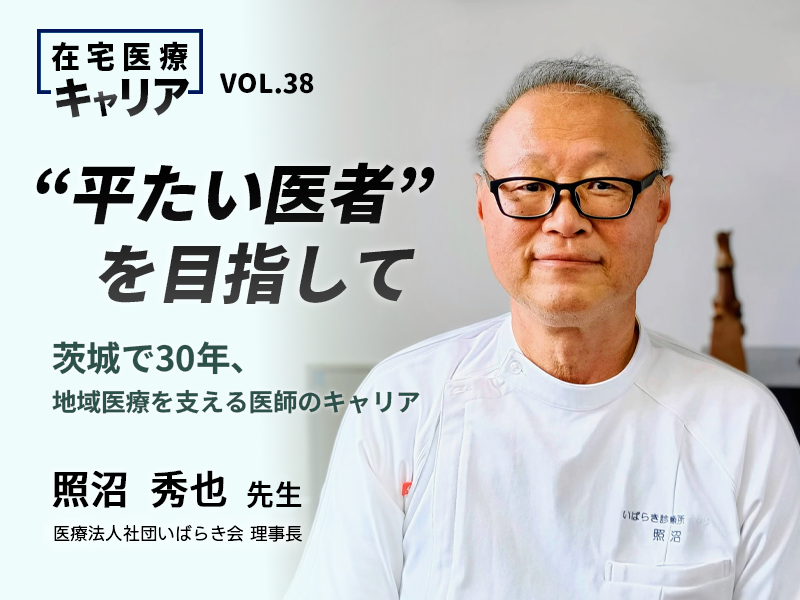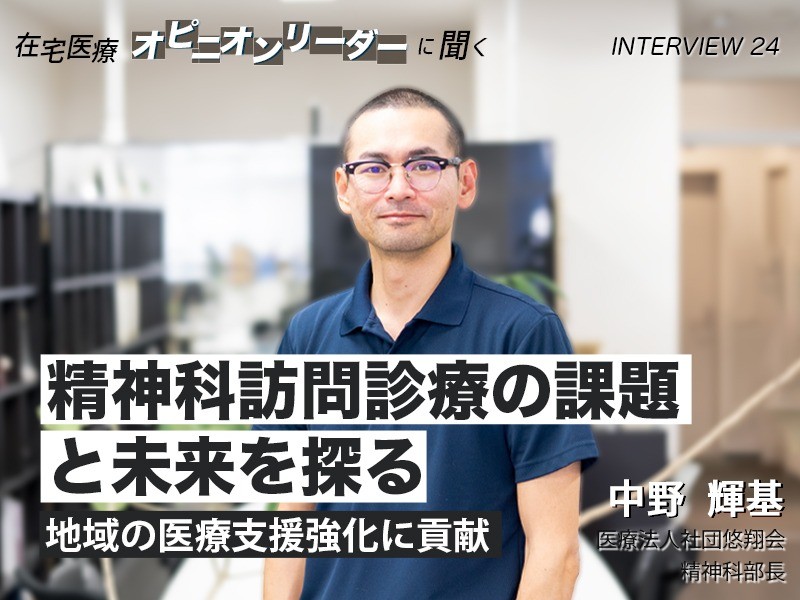
精神科の訪問診療は、高齢者を中心に需要が増加している一方で、治療を望まない患者への治療介入の難しさや、精神病床数の削減など、さまざまな課題を抱えています。
今回は、精神科訪問診療に従事する中野先生に、現場で感じる課題や今後の展望についてお話を伺いました。
医療法人社団悠翔会 精神科部長
中野 輝基 先生
2007年千葉大学医学部医学科卒業。沖縄県立中部病院外科コースで初期臨床研修修了後、岩手県立中央病院消化器外科を経て、2011年より順天堂大学精神医学講座にて研鑽を積み、2016年より医療法人社団悠翔会での勤務開始。2020年The Open University Business School卒業しMBA授与。2024年より精神科部長就任。現在常勤2名体制で広域リエゾン診療を行っている。
治療を望まない患者にどう関わるべきか——訪問診療の課題
—まずは、精神科訪問診療の現状について、先生が感じている課題があれば教えてください。
まず「治療に関われるかどうか」という点が、大きな課題の一つだと感じています。
認知症の患者さまの場合には、ご本人が診療を拒否したとしても、それが明らかに本人の不利益になる場合は、ある程度の治療への介入が許容されることが多いです。
しかし、非認知症患者さまにおいては、事情が異なります。ご本人が病気を自覚していながらも治療を望まないケースも少なくないのですが、家族や周囲の人が治療を求めている場合に、どこまで診療として関わっていけるか、という点が非常に難しいポイントです。
例えば、外来診療において、患者さまの体調や事情により来院が難しい場合、ご家族が代理で薬を受け取りに来られることがあります。医師の適切な判断と患者さまの同意のもと、必要な手続きを経て対応することで、治療の継続を支援することが可能です。
しかし、こうした患者さまがそのまま全員訪問診療に移行できるかというと、やはり本人の意思や同意の問題があり、単純には進められません。
一方で、現在では、非認知症患者の方に関しては、オンライン診療という新たな選択肢も増えています。患者さま本人が治療を受ける意思さえあれば、訪問診療でなくとも受診が可能となり、治療のハードルは下がります。
ただ、どれだけ診療手段が多様化しても、やはりそもそも本人が治療を受ける意思をもっていなければ、適切な医療につなげることは難しいと考えています。
退院後の生活支援が、地域医療の充実のカギとなる
—精神科訪問診療を取り巻く社会的な状況については、どのような課題があるのでしょうか?
日本は海外に比べて、精神科の入院病床が非常に多いのが現状です。国の政策としては、精神科の入院病床を減らし、地域での医療を充実させる方向性が示されています。
実際に、長期間入院していた精神疾患の患者さまの退院後の診療に関わるケースは増えてきています。
高齢化が進んでいるため、老人ホームなどの高齢者施設が退院後の受け入れ先になってくると考えられますが、比較的若い世代の患者さまが退院したあとの生活支援については、まだ十分な解決策が確立されていません。
今後、訪問診療の充実によって、地域での医療支援が強化される方向性になると確信しています。しかし、それだけでは十分でなく、病院やメンタルクリニックとの連携をさらに強化し、退院後も継続的な医療サポートを提供できる仕組みを構築することが重要です。
こうした連携が進めば、退院後も安心して地域で生活できる患者さまが増えていくと考えています。
—お話しいただいたように、今後、精神科訪問診療のニーズもさらに高まっていくかと思います。需要の増加に伴い、どのような変化が考えられますか?
現在の訪問診療では、主に認知機能障害をもつ方々への対応が中心となっています。しかし今後、団塊ジュニア世代の高齢化にともない、訪問診療の対象となる患者層も変化していきます。
現在の高齢者の多くは、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスを扱うことが難しく、訪問診療でしか対応できないことも多いです。
しかし、これから先、日常的にデジタルデバイスを使用している50代・60代の世代が患者層の中心となっていく中で、診療の手段も変わってくる可能性もあると考えています。
具体的には、オンライン診療への移行が進み、従来の訪問診療の一部は、オンラインに置き換わる形で変化していくことも考えられます。
また、今後、訪問看護指示書がオンライン診療で記載可能になったり、さらには自立支援、障がい者手帳の申請、年金関連の手続きなどがオンライン診療で可能である点が周知されていくと、オンライン診療の需要はさらに高まるかもしれません。
しかし、すべての患者さまがオンライン診療を利用できるわけではないので、デジタルデバイスの使用が難しい方や、対面でのサポートが必要な方には、引き続き訪問診療が不可欠です。
今後の精神科訪問診療の役割として、病院との連携を強化した退院後の生活支援が重要になると考えています。とくに、入退院を繰り返している患者さまに対し、次の入院をどれだけ回避できるかが、精神科訪問診療に期待される役割のひとつになると思います。
環境に応じたコミュニケーション能力と柔軟な対応力が求められる
—精神科の訪問診療を行ううえで、どのようなスキルが求められるのでしょうか?
精神科に限らず、訪問診療では多職種との連携が非常に重要です。病院では医師主導で診療が進みますが、訪問診療ではケアマネジャーや訪問看護師、福祉関係者など、さまざまな職種と協力しながら患者さまを支援していく必要があります。
そのため、関係各所との調整を行う「コミュニケーション能力」は非常に求められますね。医師が積極的に関係者にアクセスしなければ、患者さまへの適切な医療提供が難しくなることも多く、実際の現場においても、その重要性を強く感じています。
また、外来では患者さまにとって診察室というのは”アウェイ”な環境ですが、訪問診療では患者さまの”ホーム”に我々が赴くことになります。外来の診察とは異なる環境になることで、ご本人はもとより、ときにはご家族など周囲の方が、より率直に意見を述べる場面もあります。
このように環境によっても、人の雰囲気やコミュニケーションが変化することを理解し、柔軟に対応できる力も必要なスキルだと思います。
精神科訪問診療は「地域医療」と「災害医療」への貢献へと広がる
—ありがとうございます。最後に、精神科訪問診療の未来について、どのような展望をお持ちか、お聞かせください。
現在、悠翔会の精神科には常勤医師が2名在籍しており、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県など、約20のクリニックで診療を行っています。各クリニックの主治医と連携し、主治医だけでは対応が難しいケースをサポートする「リエゾン診療」を実施することで、すべてのエリアで一定の診療の質を提供することを目指しています。
リエゾン診療とは、ご自宅や施設で療養中の方が、体の病気だけでなく不安や気持ちの落ち込みなど心の不調を抱えたときに、訪問診療の医師が必要に応じて精神科や心療内科の専門医と連携し、心のケアも含めたサポートを行う仕組みのことです。身体と心の両方を支えることで、安心して療養生活を続けられるようサポートします。
今後も、私たちが関わることで、総合診療の先生方が精神疾患を持つ患者さまを安心して診療できる環境を整え、継続的な医療サポートを提供していきたいと考えています。
また、将来的には精神科がメインとなって、再入院を防ぐための対応がより求められるようになるでしょう。とくに、悠翔会のように複数の都道府県にまたがって訪問診療を行う医療機関は、地域医療のなかでより大きな役割を担うことになると考えています。
さらに、大規模災害時における精神科訪問診療の役割も重要です。私自身、東日本大震災で被災した経験もあり、災害時に病院とどのように連携を取り、急性期の対応を進めるかは今後の大きな課題だと考えています。
訪問診療の視点から、地域医療や災害医療にどのように貢献できるのかを模索し、積極的に発信していくことも、私たちの重要な使命だと感じています。