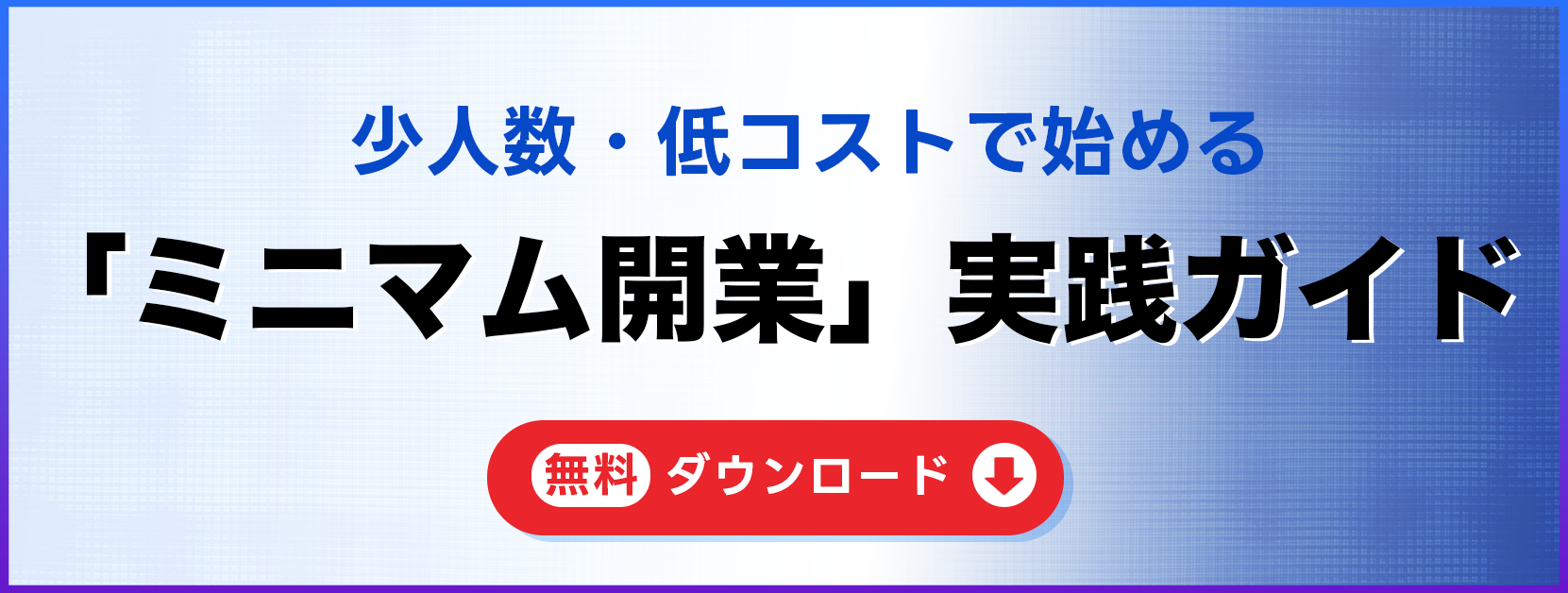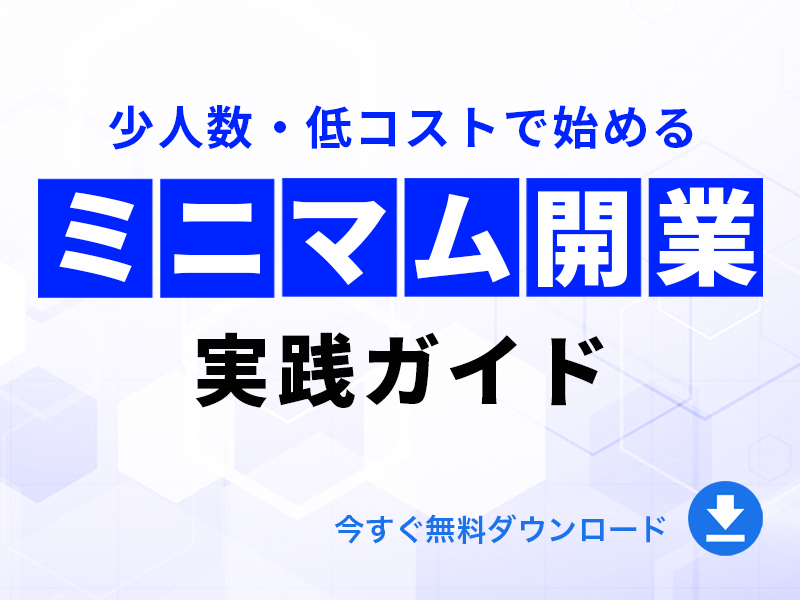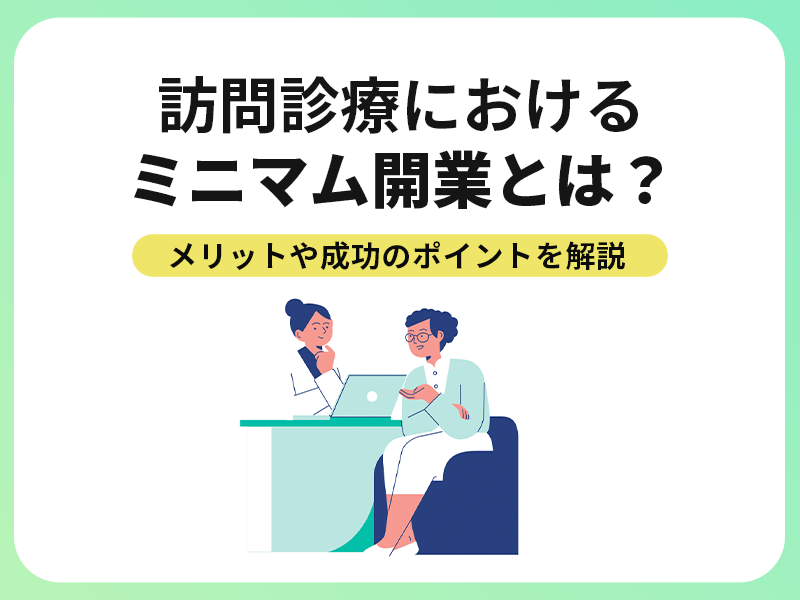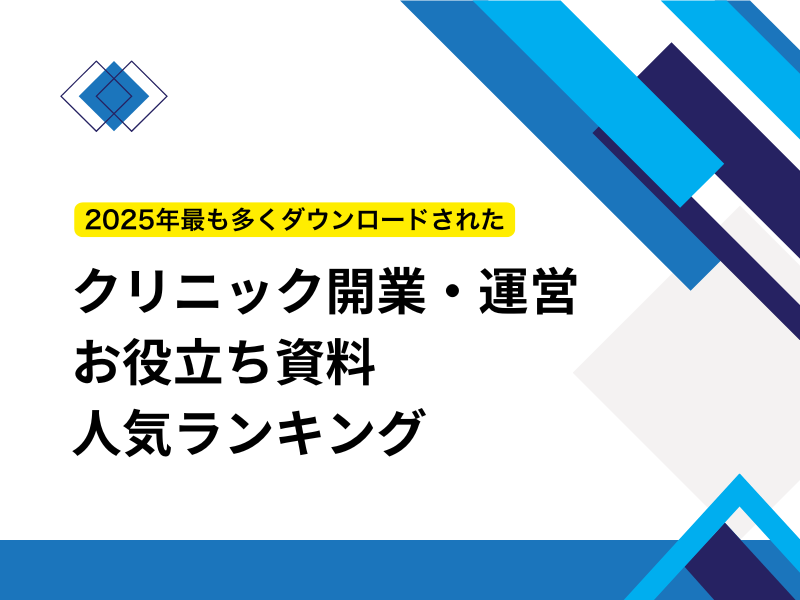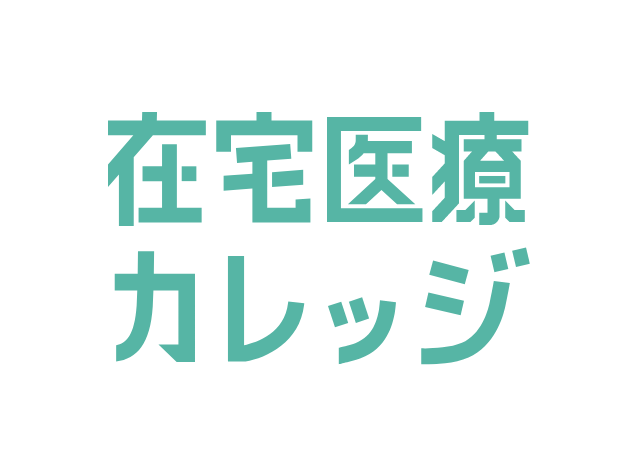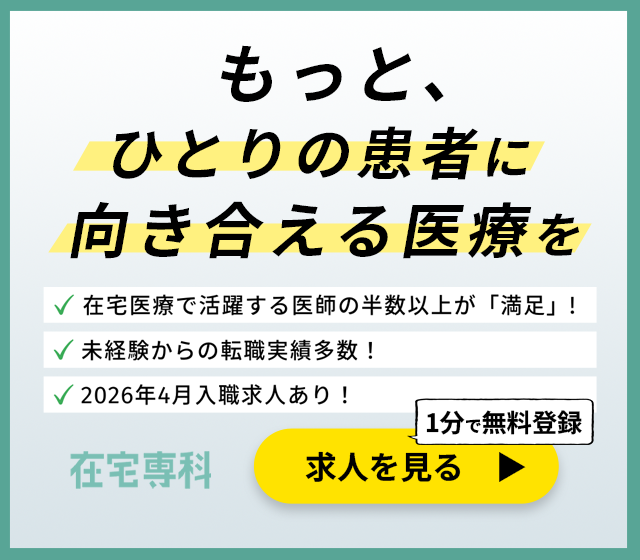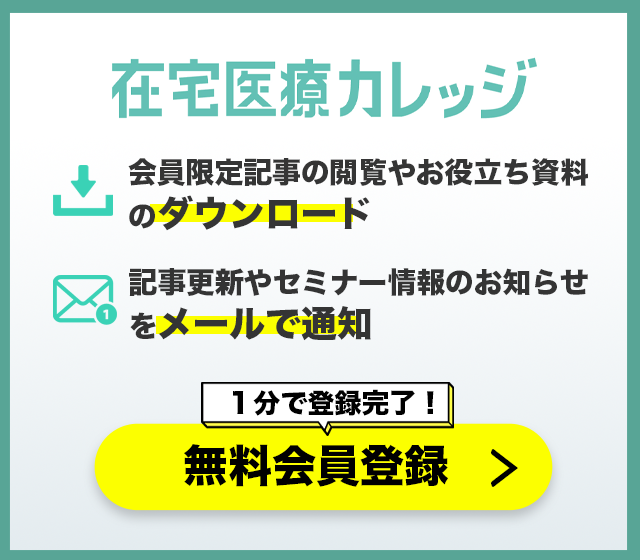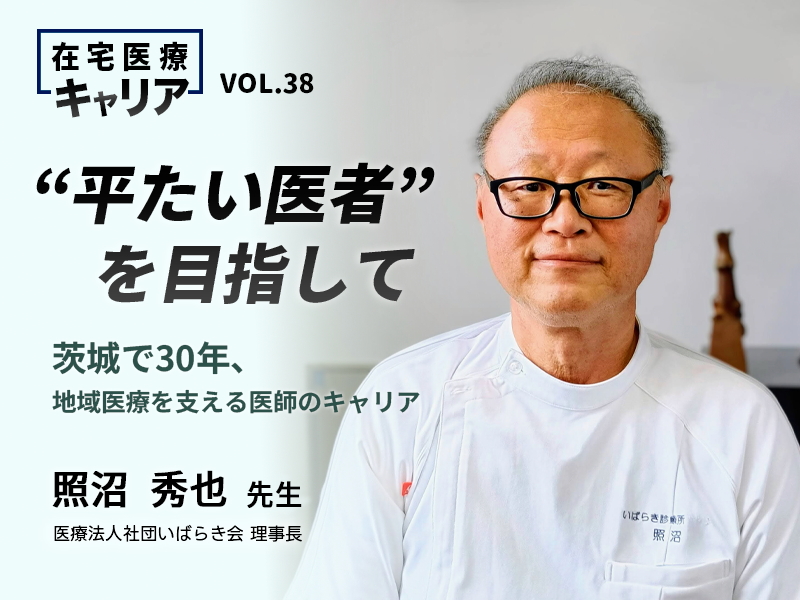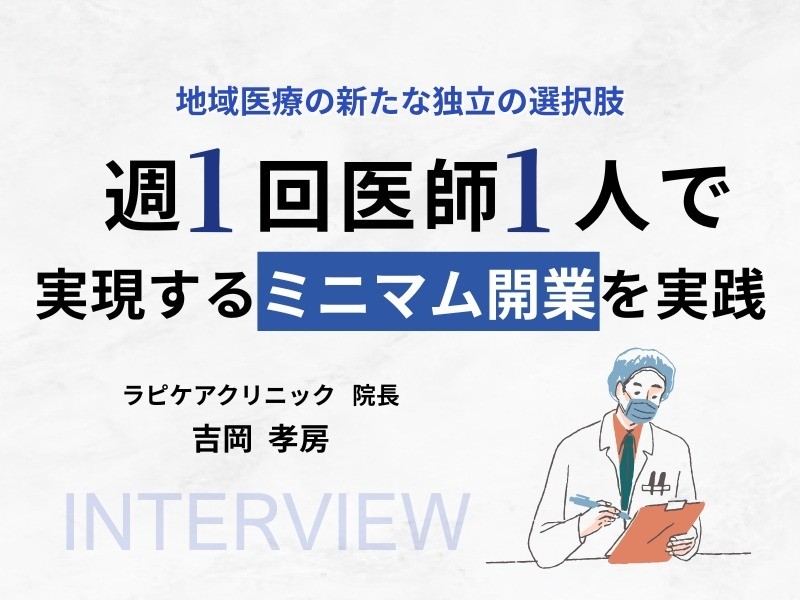
吉岡孝房先生は、千葉県旭市に週1日だけ開業する「ラピケアクリニック」を立ち上げました。特別養護老人ホーム80人弱の訪問診療をスタッフの雇用なく1人で管理しています。
初期費用300万円というコストで実現したミニマム開業。勤務医として働きながら、自らの診療所を経営するという新たな地域医療の可能性についてお伺いしました。
ラピケアクリニック 院長
吉岡 孝房 先生
2010年宮崎大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院等を経て、配偶者の「自分の地元で介護施設を開業したい」というビジョンを支えるため、千葉県旭市に移住。訪問診療クリニックに勤務し、地域の介護業界の方々とも関わりながら、介護施設開設に向けた準備を進めていた。そのかかわりの中でご縁のあった介護老人福祉施設と個人的に連携することとなり、自分の診療所を開設。現状では人を雇わない形の診療所を運営している。
特別養護老人ホームの配置医の打診を機に開業
— 吉岡先生が勤務医をやりながら、開業を決意した経緯についてお聞かせください。
ラピケアクリニックは2024年10月に開業しました。最初は看護師である妻がきっかけです。妻が「地元である千葉県旭市で看護小規模多機能型居宅介護事業をはじめたい」と、一緒に移住しました。
そこで地元の介護関係の方々と繋がっていくなか、新規で特別養護老人ホームを開業される方と知り合いました。その方から施設配置医のお誘いをいただいたのです。地域医療や介護業界に興味があり、将来的には家族でやっていこうと思っていた矢先だったため、施設配置医を引き受けることにしました。
私が勤務医として働いている医療機関と施設との間では契約に至らなかったという経緯もあり「施設医として保険診療するための保健医療機関をどうするか」という問題を解決する手段としてミニマム開業という形で自身の診療所を立ち上げることになりました。
— ミニマム開業という選択肢を選んだ最大の理由はなんですか。
施設配置医がメインであれば、必要な設備や機能は最低限で済むと考えました。週1回の施設の訪問以外、患者受け入れの予定も少ないため、金銭面も考えてミニマム開業にしました。
初期にかかった費用は300万円程度です。一般的な開業で、建物を建てるとなったら億単位、M&Aで承継するとしても手数料で数千万単位のお金が必要になると思います。
今回設立にあたり、事務所は親族の空き家を使用し、自分1人で開業したことで人件費なしで開業できたのがコストカットに繋がっていると思います。初期費用でかかったのは、パソコン等機器とレセコン・医師会の入会金くらいです。
施設を建てて従業員を雇うと、ある程度まとまったお金がかかります。もちろんお金を借りることになりますし、生涯覚悟が必要になります。さらに、集患にも注力しなければなりませんし、従業員を養うという大きなプレッシャーも生まれます。
入居者数からある程度の収入の見込みもたったので、人件費をかけなければ、大きな収入にはならなくとも低リスクで経営できるという試算ができたことが、精神的負担が少なく開業できたポイントです。
ミニマム開業の実情
— ラピケアクリニックの稼働状況や訪問スケジュールをお聞かせください。
施設の入居者数は約80人で月に1回定期診察、定期処方を発行しています。定期診察日以外の開業日は臨時診察や事務作業を主に行っています。
外来診察とオンライン診療も受け付けていますが、患者さんの利便性を考えると集患は難しいですね。わざわざ週1日開業の診療所に受診してみようという発想にはならないでしょう。
— 今後は現状を維持するのか、開業日を増やすのか、ご予定などはありますか。
現在80人の施設を受け持ち1人で切り盛りして経営は最低限やっていけるという程度です。ただ実際に1人で稼働してみて、もう80人程度の施設であれば人を雇わずに稼働できそうであると感じています。
もちろんご縁があり、受け持ち施設がさらに増えるようであれば開業日を増やしたり、人の雇用も必要になってくるでしょう。
目の前の仕事をおろそかにせず、真摯に向き合いながらも、状況に応じて柔軟に対応していきたいと考えています。
人を雇わずBPOサービスを利用するという選択肢
— 1人で運営するにあたり、BPOサービスの活用は必須ともいえると思います。レセプト業務のBPOサービスを導入されているそうですが、導入を決めた理由と実際に導入していかがでしたか。
レセプト業務に関しては自分1人では手が回らないと感じていたため、初期からBPOサービスを利用しています。
レセプトのチェックから修正・請求まで行ってもらえる上、診療報酬の疑問点についても詳細に答えてもらえるので、非常に助かっています。
「レセプトを外注するとクリニック内にレセプトを理解しているスタッフが育たない」とよくいわれますが、私1人で運営している状況では全く問題ありません。
ほかにはクレジット決済や医療費後払いサービスを利用しています。人員がいないため、小さな仕事も全て自分がやらなくてはなりません。そのため、とにかく効率化が最重要です。効率化に役立つBPOサービスは積極的に取り入れたいと思っています。
ミニマム開業のリスク管理
— 週1日の開業で、施設スタッフなどとのコミュニケーションや急変時のリスク管理はどのようにされていますか。
スタッフとはチャットツールで連絡を取り合っています。チャットは開業日以外もこまめに確認するようにしており、大体のことはチャットで完結しますね。
緊急時は電話連絡もありますし、時間外に訪問することもあります。急変の場合は施設の協力医療機関に繋ぐことが多いです。
「このようなときはこうする」といった対応の共有をし、こまめにチャットで報告・相談できる環境がスタッフの安心感にも繋がっていると思います。
そのためか、緊急電話の数もさほど多くありません。文章で記録が残ることで、聞き間違いや伝達ミス・認識相違も防げるので、良いツールだと思っています。
ミニマム開業のメリットとデメリット
— 実際に開業してみて、ミニマム開業するメリットとデメリットはどう感じられますか。
メリットとしてはさまざまな働き方ができ、自由度が高いというところだと思います。
勤務医として技術を磨きながら、院長として自分の城を持つことも可能です。ミニマム開業が軌道に乗ったら、診療所を拡大して仕事の比重を変えることも可能です。
デメリットとしては集患面でしょう。完全新規開業では、私のように施設医が確定していなければ難しいかもしれません。
とくに競合が多い都市部では、施設医なしでミニマム開業するのであれば事業承継しないと経営が難しいのではないかと思います。
医療過疎地域を検討する、専門性の高い領域で開業するなど、工夫が必要だと思います。
事業主になると、医師としての仕事以外の作業が非常に多くなります。とくにミニマム開業は最低限の人員でスタートすることが多いと思うので、医師としての仕事以外の仕事が増える覚悟は必要でしょう。
地域医療における新しい可能性
— ミニマム開業のスタイルは今後の地域医療に新たな可能性をもたらすと思われますか。
地方では今後人口減少に伴い、診療所や病院もどんどん減っていくことが考えられます。
都心部で働いている医師が、自身の地元に貢献するために、地方でミニマム開業して医療提供するというスタイルもいいのではないでしょうか。今後、地方自治体の診療所誘致施策で「週1日開所でも可」などの条件がついたら、もっとやってみたいという医師が増えるのではないかなと思っています。
とくに介護施設とミニマム開業の相性は良いと思っています。医療と介護の隙間を埋めやすい形態なので、私のように介護施設と縁があれば、ミニマム開業を検討してもよいのではないでしょうか。
事務作業など、やらなくてはならないことは増えますが、自身の診療所を運営するという経験も積める働き方だと思っています。
参考資料
第24回医療経済実態調査の報告(令和5年度)|厚生労働省