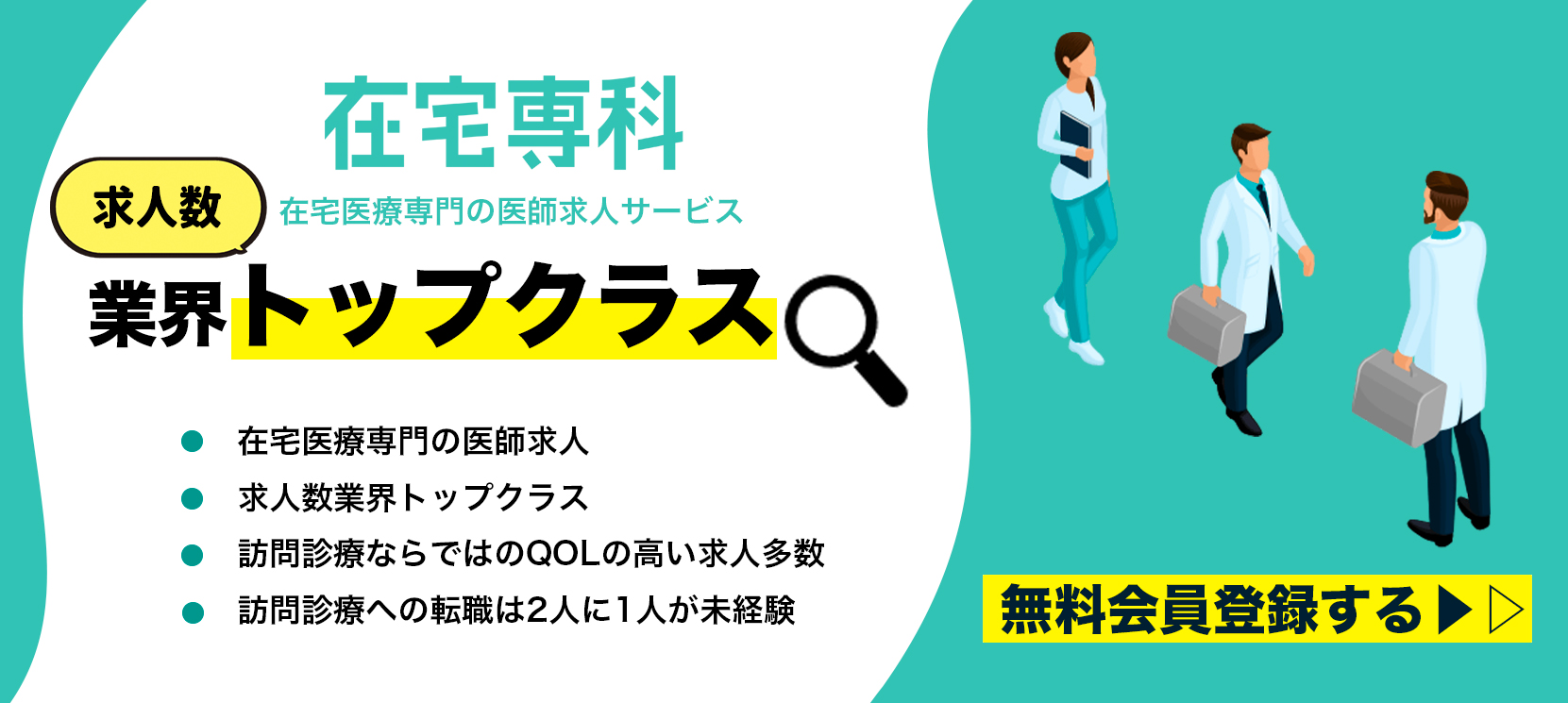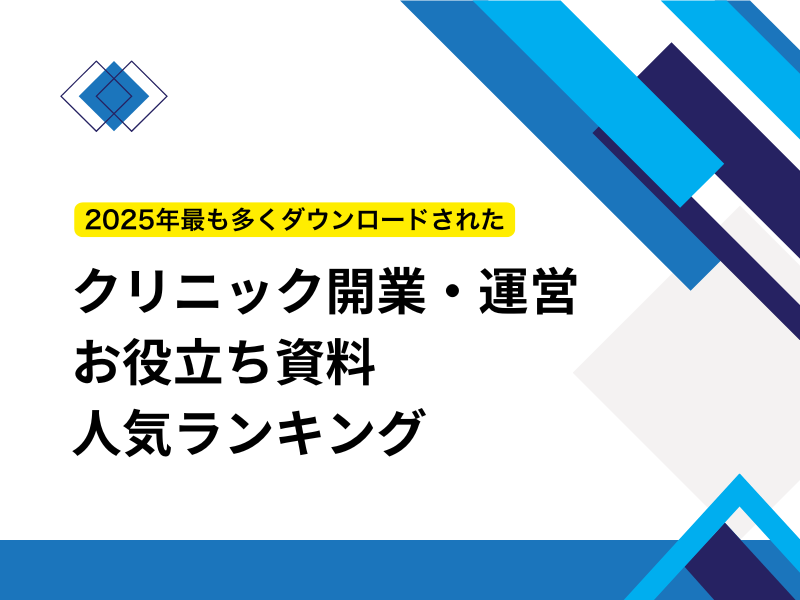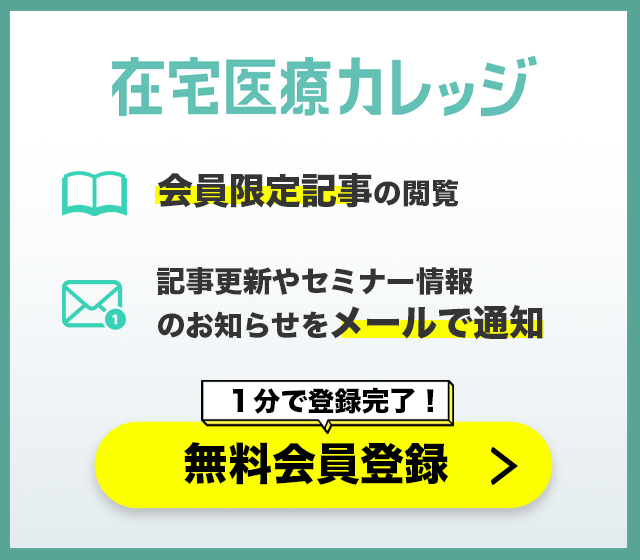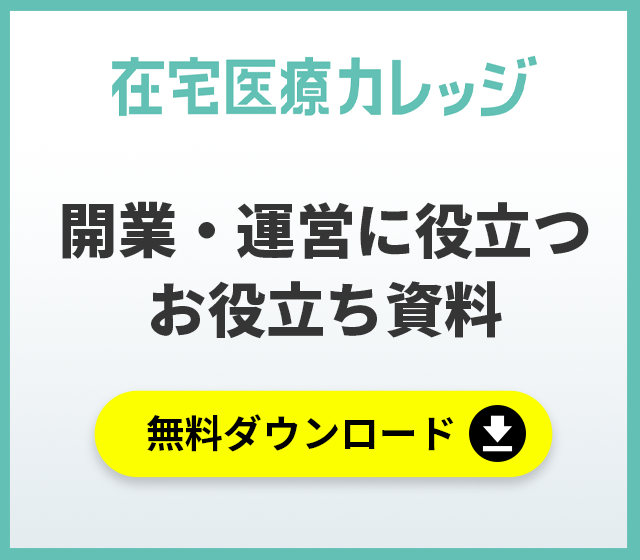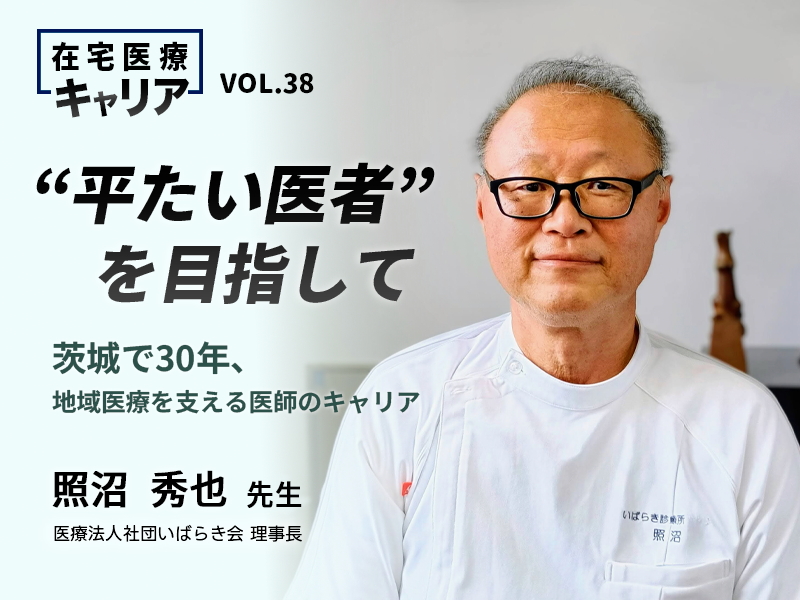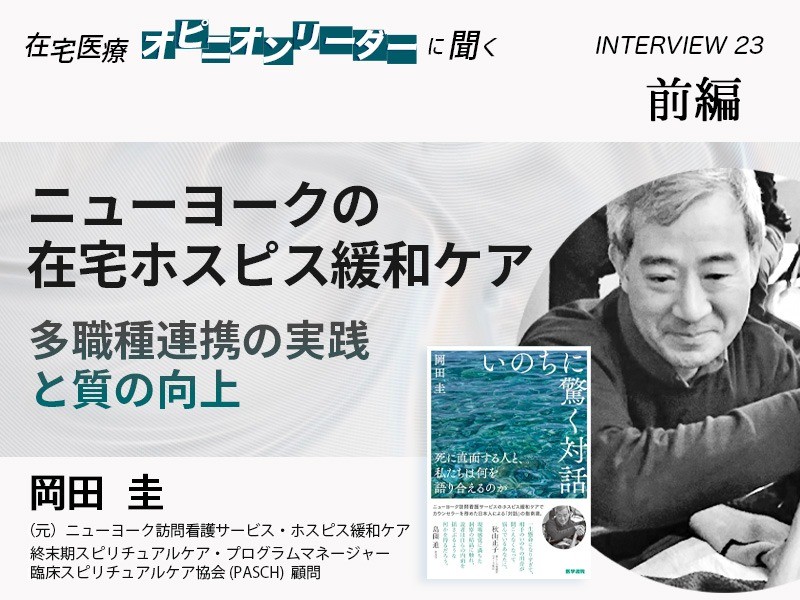
42年間のアメリカ生活、そのうち40年をニューヨーク市で過ごした岡田圭氏。このたび、著書『いのちに驚く対話 ― 死に直面する人と、私たちは何を語り合えるか』(医学書院)の刊行を機に、活動の拠点をニューヨークから金沢に今年移される岡田氏は、ニューヨーク訪問看護サービス(Visiting Nurse Service of New York:現VNS Health)のホスピス緩和ケア部門で、スピリチュアルケア・カウンセラーとして15年半の経験を持ちます。ニューヨークの在宅ホスピス緩和ケアの実際についてお話を伺いました。
(元)ニューヨーク訪問看護サービス・ホスピス緩和ケア
終末期スピリチュアルケア・プログラムマネージャー 岡田 圭さん
1981年に上智大外国語学部ポルトガル語学科卒業、翌年、ロータリー財団奨学生として渡米。ニューヨークの美大を卒業後、舞台芸術創作を経て、ユニオン神学校卒(神学修士)。2006年より ニューヨーク訪問看護サービス・ホスピス緩和ケアでスピリチュアルケア・カウンセラーとして勤務。2021年末、終末期スピリチュアルケア・プログラム・マネージャーの職務から退職。専門チャプレン協会APC の全米認定チャップレン。コロンビア大学「死に関するセミナー」準会員、国際スピリチュアルケア協会IASC会員。著書:「いのちに驚く対話」(医学書院)
貧しい人々への医療から始まった在宅医療
まずニューヨークの在宅医療の歴史を教えてください。
VNSNYは、ニューヨーク市民なら誰もが知る、歴史の長いアメリカで最も大きな訪問看護組織の一つです。1933年の経済恐慌のとき、医療費を払えない貧しい人々が増えていることに心を痛めた看護師・社会福祉士のリリアン・バウドが、その状況を憂慮し、行動を起こしました。医療を受けられない人々のために、看護師たちが自ら訪問し、病気の予防や保健指導を行う活動を始めたのです。これが組織の出発点です。
※日本の「訪問看護」は、主に看護師が自宅を訪問して行う看護ケアを指しますが、ニューヨークの「訪問看護」は、多職種からなる医療チームが自宅を訪問して行う包括的なケアを指します。
どのような規模で運営されているのでしょうか。
ホスピス緩和ケア部門は、ニューヨーク市のborough(行政区)と呼ばれる5つの地域それぞれで、郵便番号によって小地区に分け、一つのチームが100〜110人の患者さんを担当するよう編成していました。私が就職した当初から15年半の間に患者数は大幅に増加し、退職時には市内5つの地域を担当するチームの総数は14チームにまで拡大していました。多職種で連携しながらケアを提供する体制を取っていました。
WHOの定義に基づくホスピス緩和ケアの本質
WHOの定義する緩和ケアとは具体的にどのように実践されているのでしょうか?
緩和ケアとは、人の苦痛を予防し和らげるため、身体的症状を超えた課題に気を配ることと定義されています(WHOの最新の定義については、岡田著『いのちに驚く対話』p.64参照)。私たちは、この定義に基づき実践を重ね、身体性、心理社会性、霊性の側面それぞれについて、専門職からなるチームで評価と支援を行っていました。
(参考:WHO ”Palliative Care”)
がん以外の疾患への対応についてはいかがでしょうか。
私の職場では、がん患者は6割で、残りの4割はWHOの定義に沿った心臓疾患や呼吸器系疾患、認知症などの患者さんたちでした。心理社会的な面を担う社会福祉士や、霊性の側面を担うスピリチュアルケア・カウンセラー(あるいはチャップレン)の配置は、地方ではまだ十分とは言えませんが、ニューヨークの医療機関ではほぼ整っています。
多職種チームによる包括的なケア
どのようにして患者さんの受け入れを行っていますか。
入所専門の看護師チームが、最初の窓口になります。病院や家族からの依頼を受けると、この看護師チームが患者のかかりつけ医とホスピス専門医と連携しながら、患者さんの状態を確認し、私たちのサービスが適切かどうかを判断します。そこでOKが出れば、担当地域のチームにつなぎ、在宅でのケアが始まります。
チームの基本構成はどのようになっているのでしょうか。
組織は非営利団体で、チームの全てのスタッフが同じ組織に所属しています。日本では多職種チームのメンバーがそれぞれ別の組織に所属しているのが一般的ですが、私たちの場合は全員が同組織の直接雇用のスタッフなのです。
一つのチームの構成は以下のとおりです。
チーム・マネージャー(看護師)1人、医師1人、看護師3〜4人、社会福祉士2〜3人、スピリチュアルケア・カウンセラー1人、死別カウンセラー1人が所属。複数のチームを担当するNurse Practitioner(診療看護師)も配置されていました。チームの全職員が毎週の定例会議で報告を行い、全体的な理解を深める体制になっていました。
なお、日本でいう「ヘルパー」にあたるホーム・ヘルス・エイド(在宅健康援助士)は別部門からの派遣となり、定例会議への参加はありませんでした。
ボランティアも大きな役割を担っており、その訓練や教育、患者さんへのボランティアによる定期訪問を管理するマネージャーを4人置いていました。
遺族へのケアも含まれているのでしょうか。
死別カウンセラーは、大学で専門的に悲嘆を学び、州の資格を持つ専門家です。患者さんが亡くなってから1年忌を含む13ヶ月間、遺族がいつでも無償で受けられる支援です。
一対一のカウンセリングと並行して、グループでの語らいを望む遺族のために「父をなくした人たちの会」など、喪失の種類による遺族会を定期的に開催。予定表を送付し、希望に応じて参加できるようにしていました。
この死別カウンセラーもチームの一員として週例会議に参加し、患者さんの生前から、訪問スタッフを通じて家族の状況を把握し、死別後の遺族支援の準備をしていました。
どのように情報共有を行っていますか。
多職種チームは週例会議で、患者さんと家族一人一人の状況について包括的に情報共有します。医師や看護師は身体的な側面を、社会福祉士は心理社会的な側面を、スピリチュアルケア・カウンセラーは価値観や死生観、人生哲学など倫理的、文化的、宗教的な側面を含めて生き方の背景となる霊性の側面での現状と介入目的を報告します。それぞれの専門性から、患者さんの状況を全体的に理解し解釈するための評価を共有していました。
さらに専門的な支援体制もあるのでしょうか。
必要に応じて、理学療法士、作業療法士、栄養士、音楽療法士などもチームのケアプランに関わっていました。また複雑困難な事例の相談に応じたり、地域教育活動をしたりする専門チームとして、倫理委員会、がん専門支援、心臓疾患専門支援、呼吸器系専門支援、退役軍人支援会、有色人種支援会なども置いていました。
このような包括的な体制のメリットを教えてください。
それぞれの専門職による視点が共有されることで、単なる分業ではなく、患者さん一人一人の状況を包括的に理解する体制が築かれていたことです。どの専門職に相談しても自分の状況が総合的に理解されているという安心感を患者さんに持ってもらうために、そのような連携を大切にしていました。
日本では複数の事業所から異なる職種が関わってチームを形成するのに対し、VNSNYでは一つの組織内に多職種が所属していることで、緊密な連携と包括的なケアの提供が可能になっているのが特徴です。
質の高いケアを支えるシステム
チームの質はどのように担保されているのでしょうか。
多職種チームの患者さんへの支援の質は、国や州で決められた査定組織によって定期的に査定を受け、評価や管理をされています。例えば、新規入所者の初回評価が入所日から5日以内に行われているか、実際の訪問頻度と電子カルテ上の訪問頻度が一致しているか、提供された療法や支援がケアプランに合っているかなど、具体的な指標があります。
新任の医師への教育について教えてください。
新任医師には、最初に多職種との同行訪問を行い、各職種の活動を直接見て学ぶ機会を設けています。チームにあたたかく迎え入れる歓迎のしかたでもありますね。
他職種と一緒に訪問することで、どのような学びがありますか。
私も看護師や社会福祉士、死別カウンセラーと時々一緒に訪問すると、いつも新しい学びがあります。向こうも同じことを言ってくれます。互いに学び合うことが重要ですね。お互いの実践を具体的に知ることで、相互の専門性の違いと共通点を知り、その知識と敬意をもって連携し合えます。
患者さんの満足度はどのように評価されているのでしょうか。
患者さんが亡くなった後、遺族にアンケート調査が送られます。『患者ケアの評価』、『このホスピスを他の人たちに勧めたいか?』といった包括的な評価から、『夜間、週末、あるいは休日でも、いつも援助を受けた』、『患者は、いつも尊厳と敬意をもって扱われた』、『気持ちの支援は、ちょうど良かった』などまで、具体的に評価されます。私たちはこの評価結果をチームで共有し、改善に活かしていました。
多職種連携のあり方を考える
日本の在宅医療がニューヨークから学ぶべき点について教えてください。
多様な専門職がそれぞれの角度から状況を観察し、その視点をチームで共有することで、人をより多角的に、総合的に支えられることを実感しました。
VNSNYの体制は、長い歴史の中で築かれた一つのあり方です。日本では医師の権威が「父権」として捉えられ、すべてを統一する医療の頂点になる傾向があります。VNSNYで大切にしてきたのは、患者さんやその家族が必要とされていることを包括的に多角的に理解して支えるため、それぞれの個人と地域が持つ文化や特徴を尊重し活かしながら、多職種が対等に連携して患者さんと家族を支えていくことでした。
いま各地の医療現場で、その土地の特色を活かした素晴らしい取り組みが行われています。それぞれの地域で、どのように多職種が連携し、支え合えるのか。その可能性を探っていくことが、これからの日本の在宅医療には求められているのではないでしょうか。
【参考情報】
- 岡田圭著『いのちに驚く対話 ― 死に直面する人と、私たちは何を語り合えるか』(医学書院)
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/112992 - 書評:東京新聞(2024.11.24)若松英輔
https://www.bookbang.jp/review/article/788819