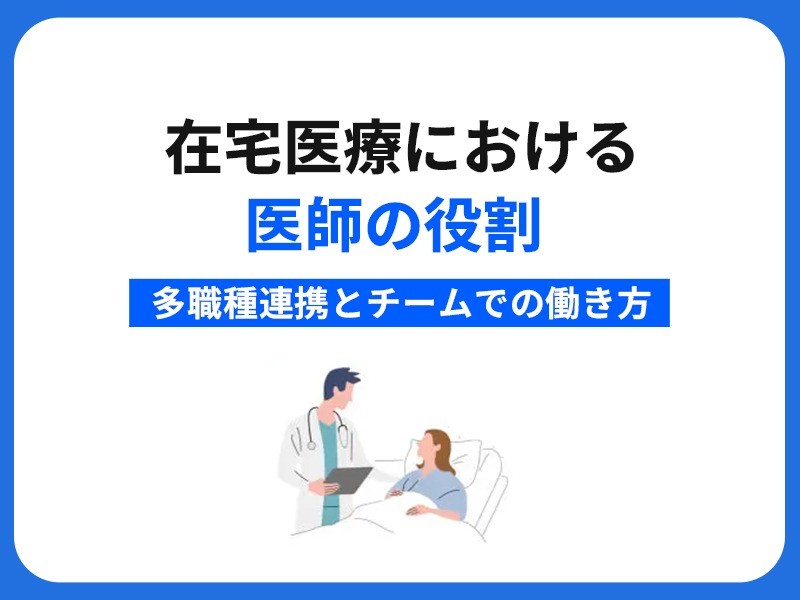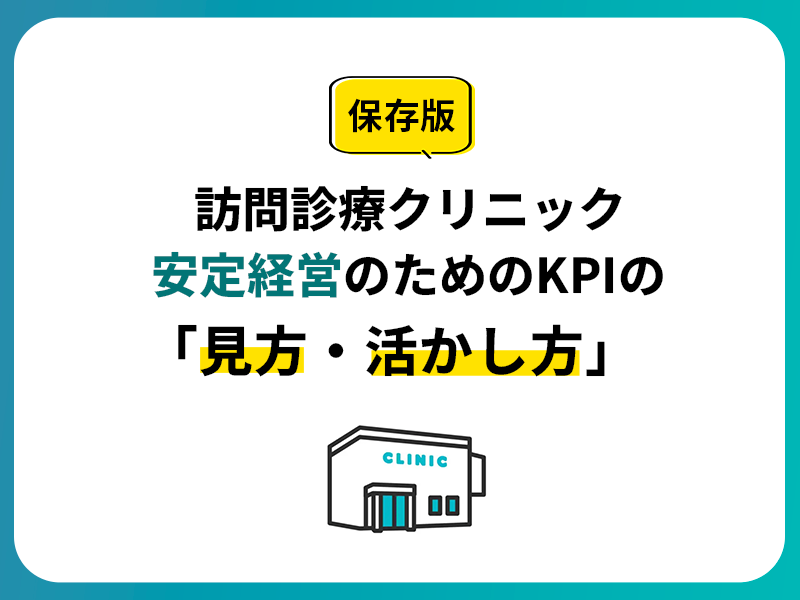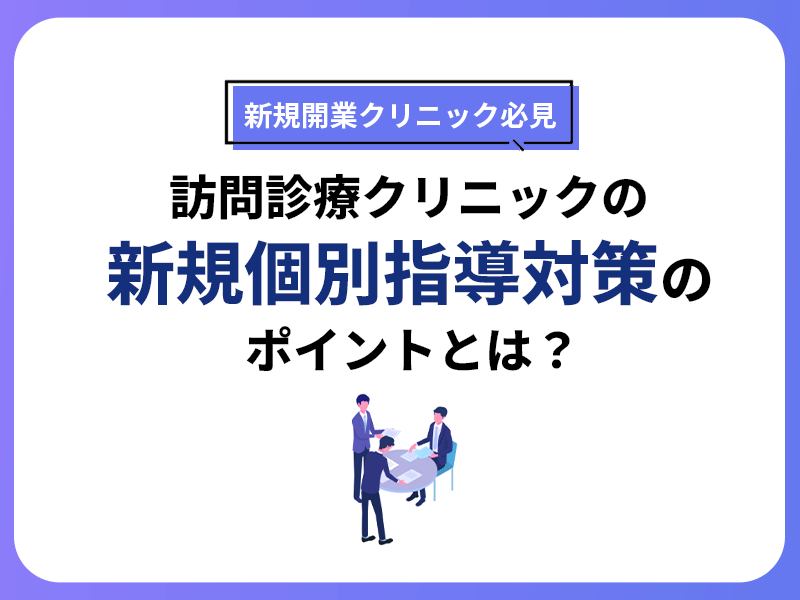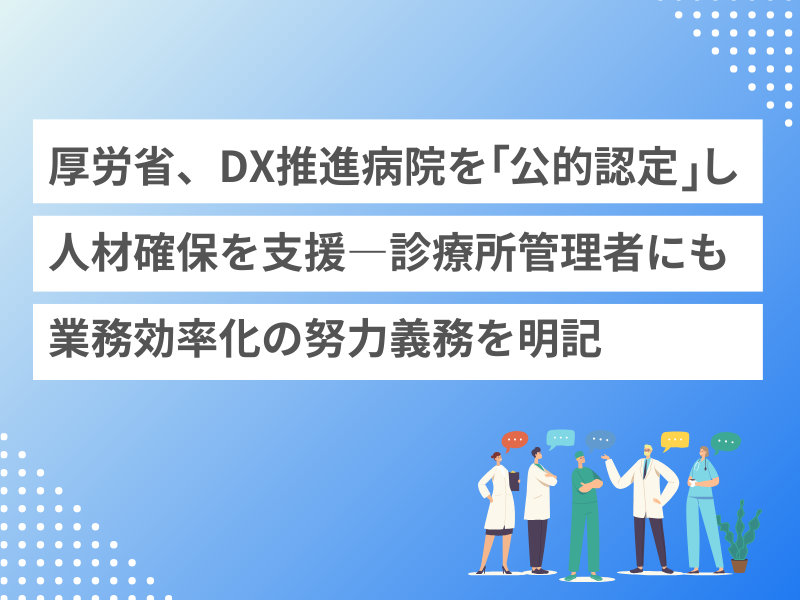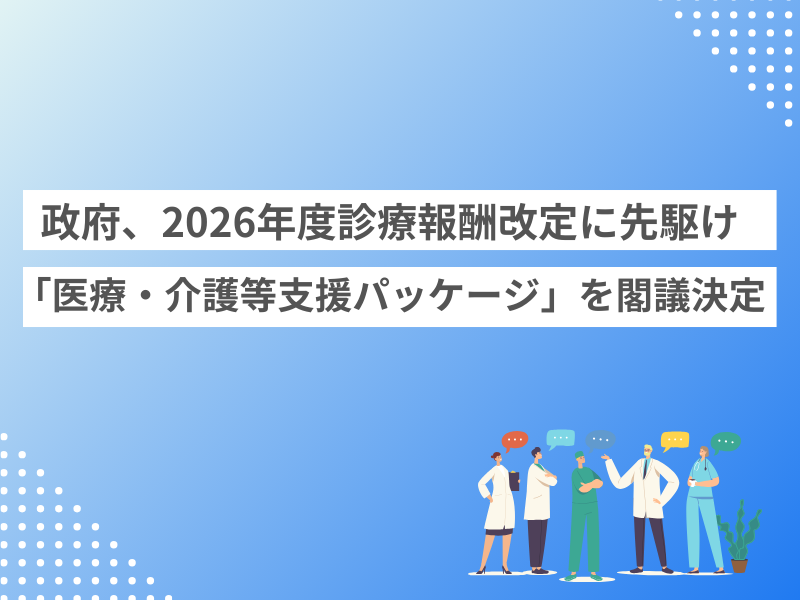厚労省、往診代行サービス利用時の「事前説明」について議論【2026年度診療報酬改定議論】
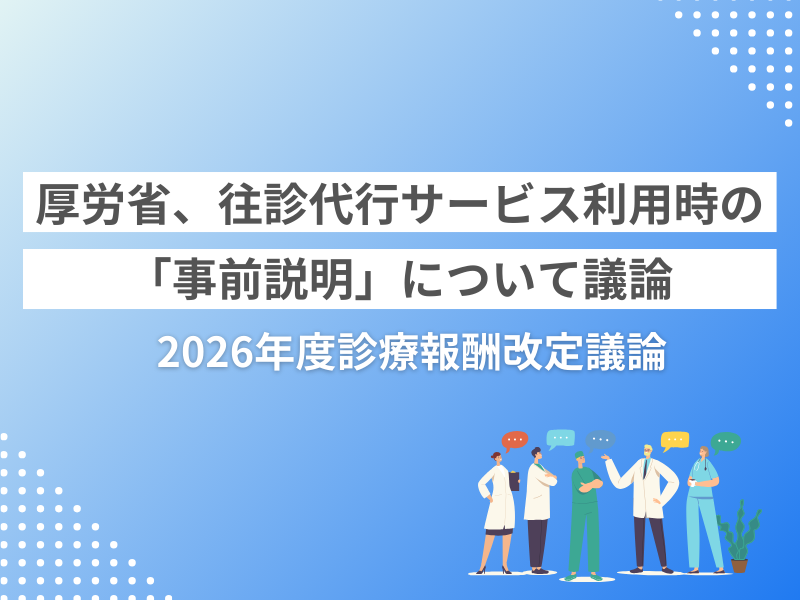
厚生労働省は2025年11月12日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開催し、2026年度診療報酬改定に向けた在宅医療に関する議論を行いました。
今回の総会では、24時間の連絡・往診体制を確保するために民間企業の代行サービスを活用する場合の運用や、在宅療養後方支援病院の評価、および在宅療養指導管理材料加算の算定ルール統一について意見が交わされました。
民間の連絡・往診代行サービス利用に関する議論とは
24時間の往診体制確保に向け、民間企業など第三者への委託を行っている在宅医療提供医療機関は6.1%存在します(「2024年度診療報酬改定の結果検証にかかる特別調査」より)。中でも、機能強化型在宅療養支援診療所(在支診)・在宅療養支援病院(在支病)において、委託を行っている割合が高い傾向にあります。
これに関して、サービス会社に登録されている医師が、かかりつけ医療機関の非常勤医師としてその場で雇用契約を結び往診を行う事例などが報告されています。 今回の中医協では、こうしたケースにおいて、「時間外や夜間に誰が連絡応需や往診を行うか」について、患者への事前説明が十分に行われていないことへの懸念が指摘されました。
現行の施設基準では、以下の対応が定められています。
- 連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を事前に患者へ説明する。
- 往診担当医の氏名と担当日を文書で患家に提供する。
支払側委員(健保連理事)は、「誰が連絡を受け、誰が往診するのかを患者が知らない場合、連絡・往診体制の要件を満たしているとは言えない」と指摘。
「外部委託を行う場合であっても、自院の患者からは事前に了解を得ておく必要がある」と述べ、体制要件としての適格性を厳しく問う姿勢を見せました。
診療側委員(日医常任理事)も、「本来は患者のことをよく理解している従事者が対応するのが望ましい」と、かかりつけ医機能の原則論を強調しました。
その上で、「第三者によるサービスの利用実態や往診提供の実態について把握し、今後の対応に生かしていくべき」とし、サービスの質が担保されているかを慎重に見極める必要があるとの見解を示しています。
その他の主な論点
1. 在宅療養後方支援病院による「D to P with D」の活用
在宅療養後方支援病院が連携医療機関を支援した際に算定する「在宅患者共同診療料」の算定回数が年間14回(2023年時点)と限定的であることが示されました。 これを受け、厚労省は患者と医師がいる場でのオンライン診療(D to P with D)を活用する方向性を提示。委員からは、医療の質や効率の観点から、ICT活用を含めた要件整理に肯定的な意見が出されました。
2. 在宅療養指導管理材料加算の算定ルール統一
現在、材料加算ごとに「月1回」「2カ月に2回」「3カ月に3回」と算定ルールが異なっており、複数種類を併算定するケース(月15万例程度)において診療頻度の調整が生じている現状があります。 厚労省は、医師の医学的判断に基づく診療頻度の決定を推進するため、算定ルールを「3カ月に3回」に統一する方向性を示しました。これに対し、支払側・診療側双方から概ね賛同が得られています。
在宅医療業界への影響
「体制要件を満たさない」とみなされ、算定不可となる可能性
今回の議論で特筆すべきは、支払側より「誰が来るかを患者が知らない場合、そもそも連絡・往診体制の要件を満たしていない」というロジックを提示された点です。
これは、往診代行サービスを利用している医療機関において、患者への事前説明が不十分な場合、「24時間の往診体制」そのものが不成立であると判断され、関連点数が算定できなくなるリスクがあることを示唆しています。
今後、体制要件として厳格化される可能性を見据え、「夜間・休日に誰が(どの機関の医師が)対応する可能性があるのか」について、患者等の具体的な了解を得ているか、説明文書や同意書のフローを再確認しておくことが推奨されます。