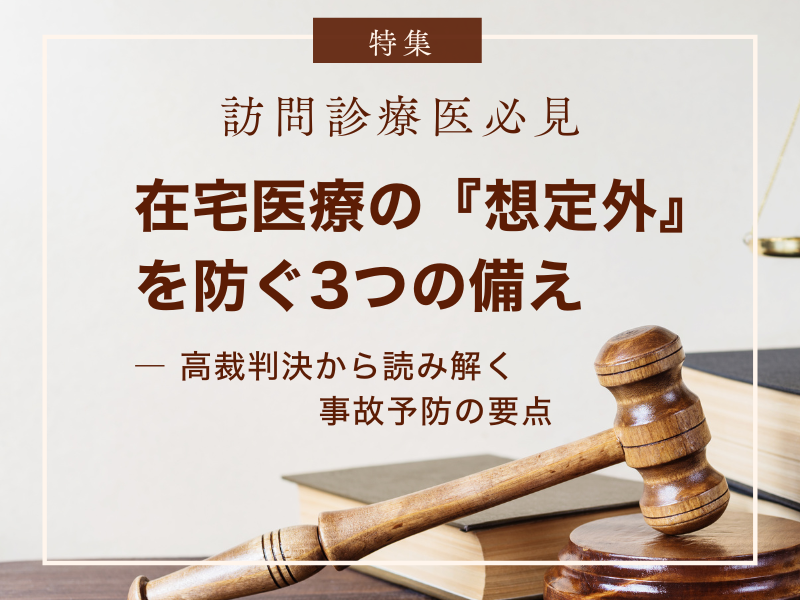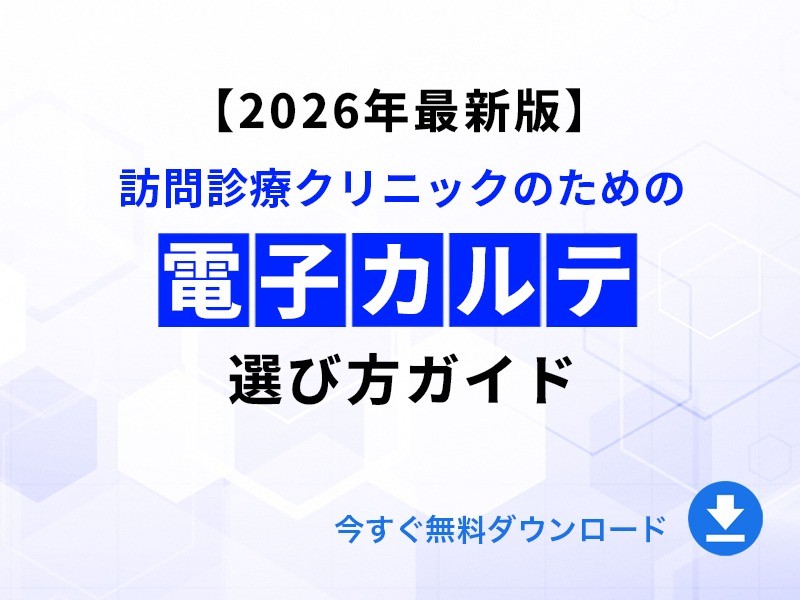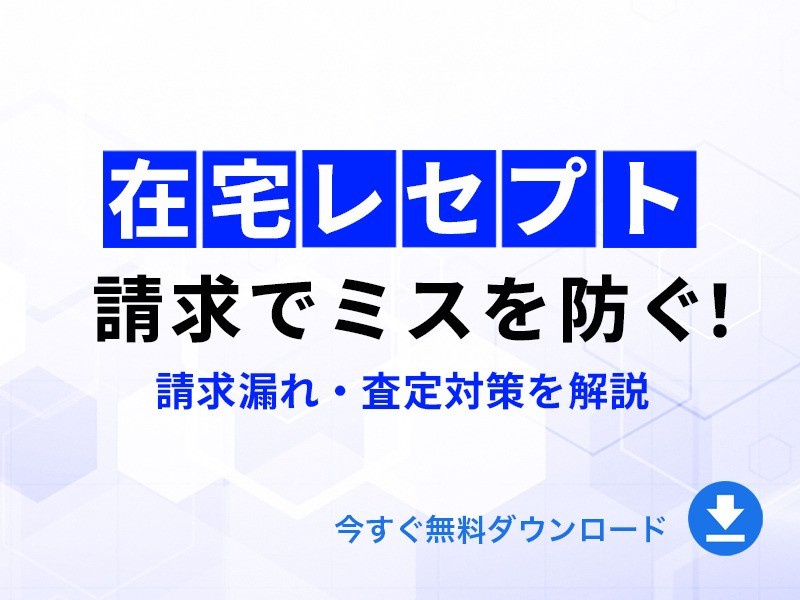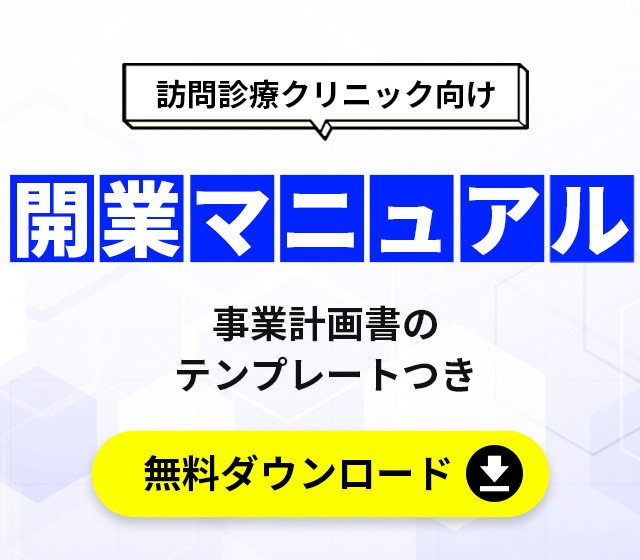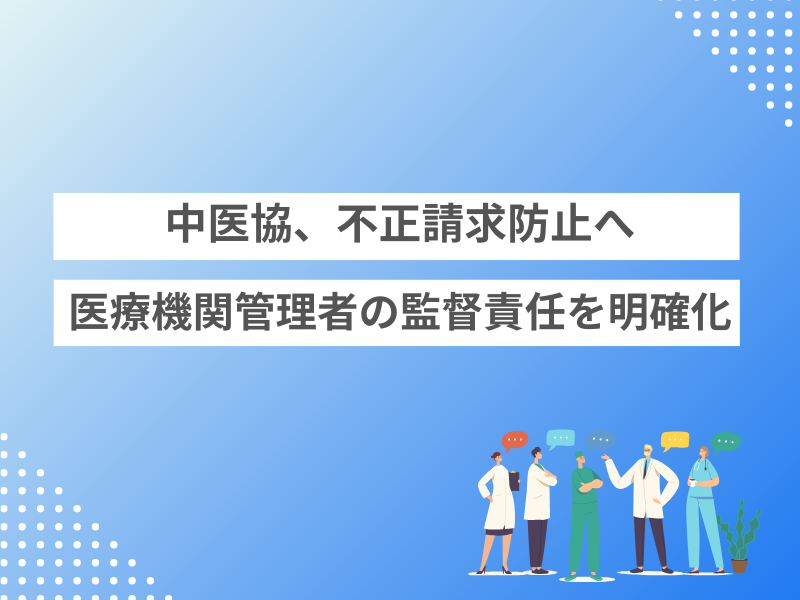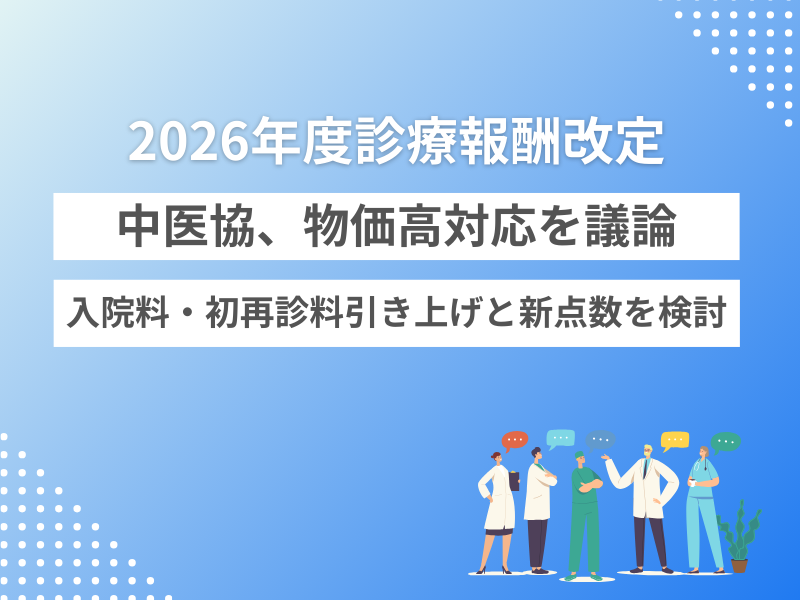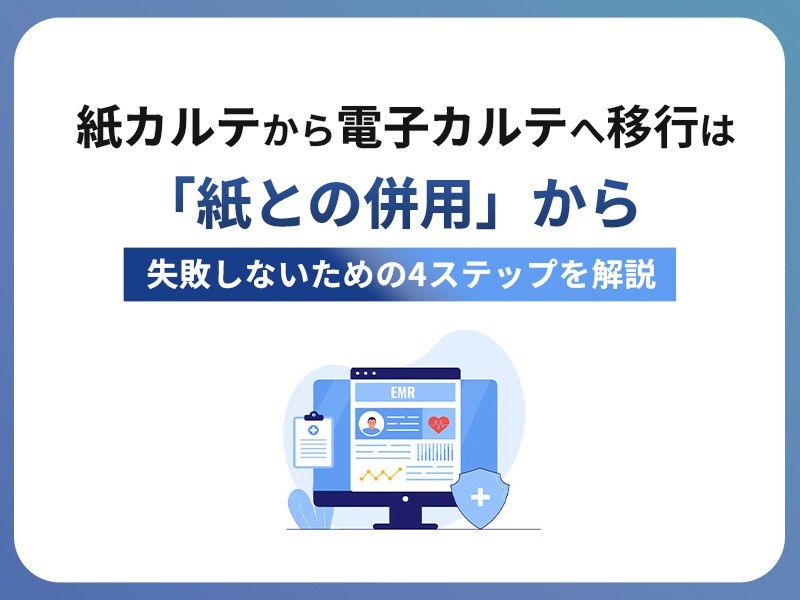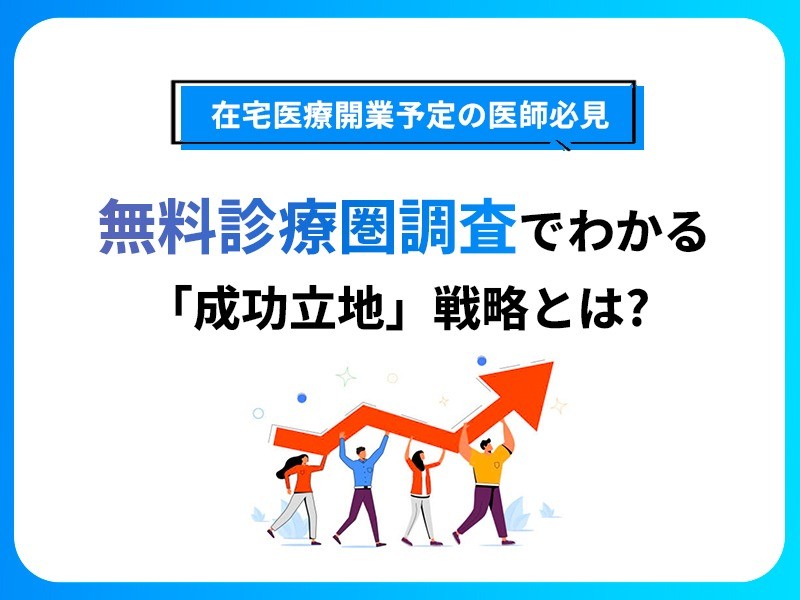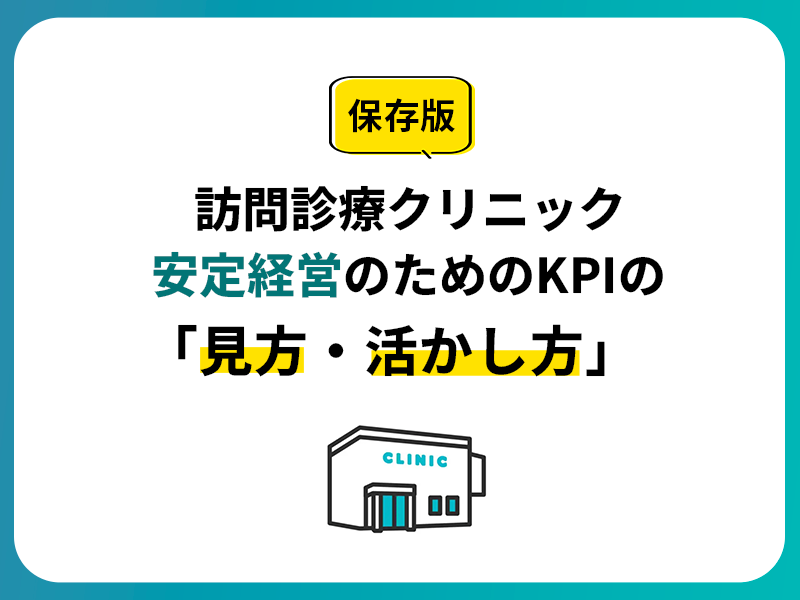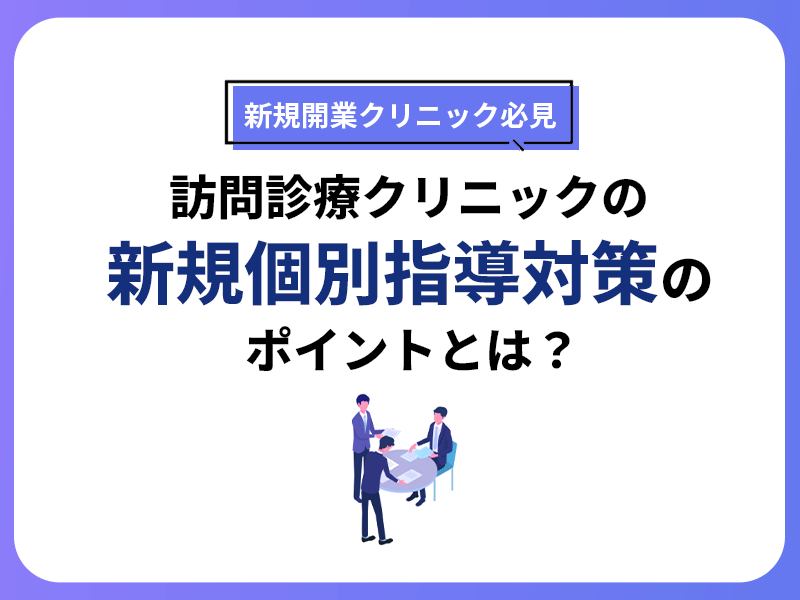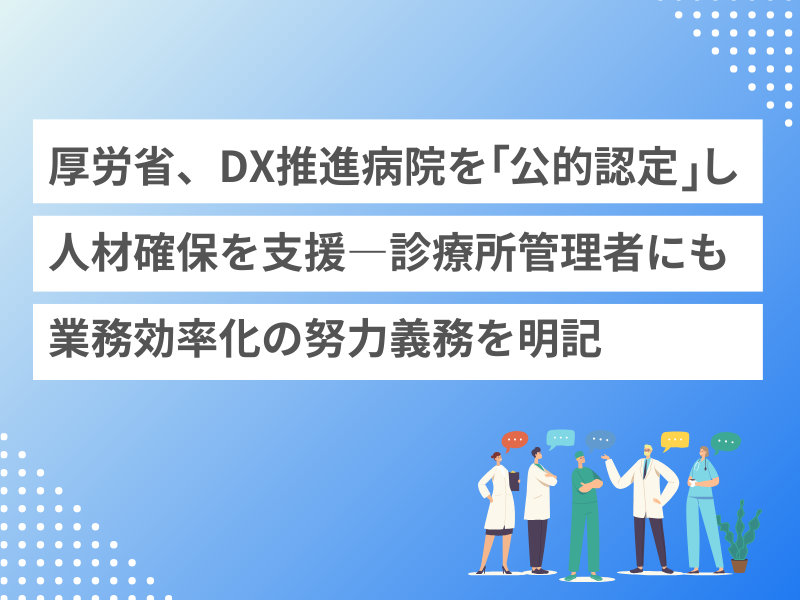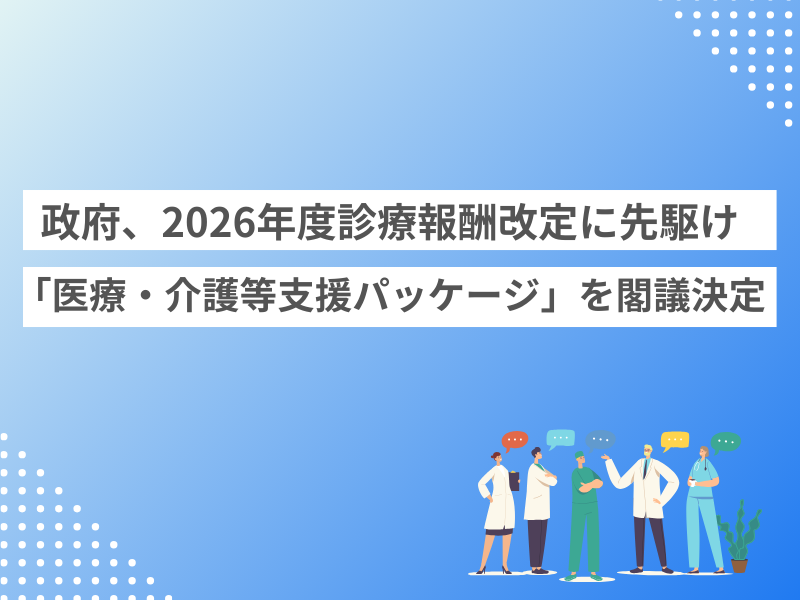- #運営
- #開業
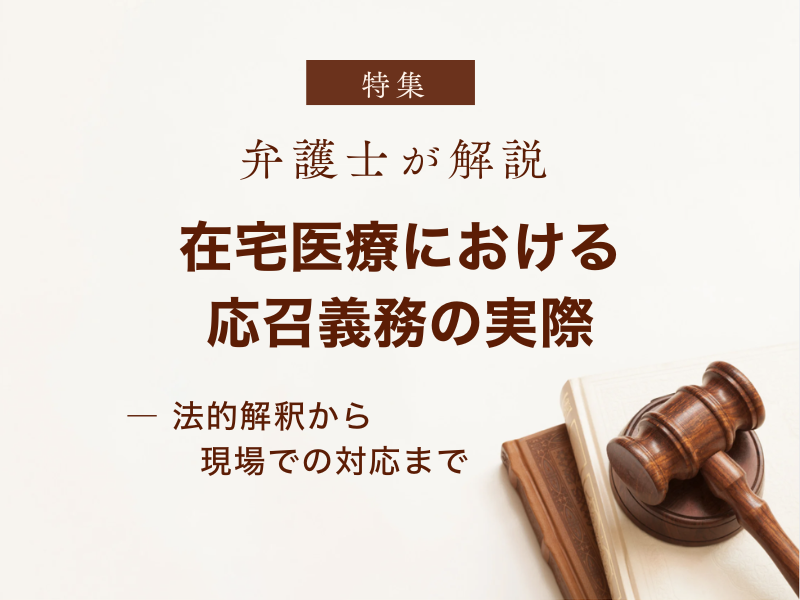
はじめに:深夜の往診依頼、あなたならどうしますか?
「先生、急に熱が出たので今すぐ来てください」 深夜、患者家族から切羽詰まった声で電話がかかってきた。 「専門外の症状を訴える患者さん、どこまで対応すべきだろうか?」 「度重なるクレームや医療費の不払いがある患者さんの診療を、断ることはできないのだろうか?」
訪問診療(在宅医療)に携わる医師であれば、一度はこのような場面に直面し、いわゆる「応召義務」の解釈に悩んだ経験があるのではないでしょうか。
応召義務は、医師法第19条に定められた「正当な事由がなければ、診療の求めを拒んではならない」という医師の基本的な義務です。しかし、24時間365日、患者の生活の場で医療を提供する在宅医療の現場では、病院での外来や救急とは異なる特有の状況が数多く存在します。地理的・時間的な制約、患者との人間関係、利用可能な医療資源の限界など、様々な要因が複雑に絡み合い、個々のケースで「正当な事由」に当たるかどうかの判断は決して容易ではありません。
本記事では、応召義務の法的な基本解釈から、厚生労働省の最新の通知や裁判例を紐解き、特に在宅医療の現場で医師が直面しがちな具体的なケースについて、その考え方の指針を解説します。医師が安心して医療に専念し、患者と良好な関係を築きながら持続可能な在宅医療を提供していくための一助となれば幸いです。
応召義務の一般論:法的根拠と解釈
まず、応召義務の基本について確認しましょう。
医師法第19条の規定
医師の応召義務は、医師法第19条第1項に定められています。
医師法第19条第1項 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
この条文は、医師が患者から診療を求められた際、「正当な事由」がない限り拒否できないという法律上の義務を課しています。
法的性質と罰則
応召義務の法的性質は、医師免許という公的な資格を持つ医師が国に対して負う「公法上の義務」と解釈されています。これは、患者個人との診療契約に基づく「私法上の義務」とは異なります。
そのため、応召義務に違反しても、医師法に直接的な刑事罰の規定はありません。しかし、違反が悪質で繰り返し行われるなど、「医師としての品位を損するような行為」と見なされた場合、行政処分(医師免許の取消しや業務停止など)の対象となる可能性はあります。
また、診療拒否によって患者に損害が生じた場合には、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。過去の裁判例では、応召義務が患者保護の側面を持つことから、正当な事由なく診療を拒否して患者に損害を与えた場合、医師側の過失が推定されるとの判断が示されたケースもあります。
「正当な事由」とは
では、診療を拒否できる「正当な事由」とは具体的に何を指すのでしょうか。 この点について、過去の厚生労働省の通知では、原則として「医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」という厳しい解釈が示されてきました。 しかし、医療提供体制の変化や医師の働き方改革の流れを受け、2019年(令和元年)に厚生労働省は新たな通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」を発出し、現代の医療状況に合わせたより具体的な考え方を示しました。この通知が、現在の応召義務を理解する上で最も重要な指針となります。
応召義務に関する主要な裁判例
応召義務の解釈は、いくつかの重要な裁判例によって形作られてきました。多くは病院の救急外来を舞台としたものですが、在宅医療における判断を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。
応召義務違反を認めた事例
千葉地裁昭和61年7月25日判決(君津中央病院事件)
1歳の幼児が気管支炎または肺炎の疑いで地域の基幹病院に救急搬送されましたが、病院側は「ベッド満床」を理由に受け入れを拒否。その後、幼児は別の病院で死亡しました。 裁判所は、「たとえ他科のベッドもすべて満床であったとしても、とりあえずは救急室か外来のベッドで診察及び応急の治療を行い、その間にベッドが空くのを待つという対応を取ることも可能であった」旨指摘。単なる「満床」は正当な事由に該当しないとして、病院側の応召義務違反を認め、損害賠償責任を命じました。
神戸地裁平成4年6月30日判決
交通事故で重傷を負った患者の救急搬送依頼に対し、病院が「脳外科医・整形外科医が不在」との理由で受け入れを拒否し、患者が死亡した事案です。 判決では、実際には院内に外科医がおり対応が可能だったにもかかわらず受け入れを拒否した点を問題視。「担当医師不在は、場合によって診療拒否の正当理由となり得る」としつつも、本件では「外科専門医師が在院していた」ことなどから、正当事由には当たらないと判断しました。
これらの判例は、特に緊急性が高いケースにおいて、医療機関側が持てる資源を最大限活用して患者に対応するべきであり、安易な理由での診療拒否は許されないという厳しい姿勢を示しています。
診療拒否に正当事由を認めた事例
一方で、患者側の問題行動により、診療拒否が正当と認められたケースもあります。
東京地裁平成26年5月12日判決
手術結果に不満を持つ患者が、病院内で長時間にわたり居座り、執拗に謝罪を要求するといった迷惑行為を繰り返した事案です。 裁判所は、「診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される」との考え方を示し、医師と患者の信頼関係が治療に支障をきたすほど破壊された状況下では、診療を行わないことも正当であると判断しました。
この判決は、医師の応召義務が無制限のものではなく、健全な診療を維持するための前提として、患者との信頼関係が不可欠であることを示唆しています。
在宅医療における応召義務の考え方【令和元年通知を基に】
それでは、本題である在宅医療の現場に特有の状況について、どのように応召義務を考えればよいのでしょうか。ここでは、令和元年の厚生労働省通知で示された考え方を基に、具体的なケースごとに整理します。
この通知の重要なポイントは、「患者の緊急対応が必要であるか否か」を最も重要な考慮要素とし、それに加えて「診療時間内・勤務時間内か否か」「患者との信頼関係」などを総合的に勘案して判断する、という点です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【注意】 以下の内容は、あくまで一般的な考え方の指針を示すものです。個別の事案における判断は、具体的な状況によって大きく異なります。特に診療を断るという判断は、法的なリスクを伴う非常にデリケートな問題です。現場での判断に迷った際には、決して自己判断で完結せず、弁護士などの法律専門家に速やかに相談することを強く推奨します。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 診療時間外・勤務時間外の対応
在宅医療では、24時間対応が求められることが一般的です。しかし、医師の労働環境への配慮も不可欠となります。
- 緊急性が低い場合:深夜に「日中から出ていた湿疹の薬がほしい」「いつも飲んでいる睡眠薬がほしい」といった、緊急性の低い依頼があった場合、即座に対応する必要はなく、診療しないことも正当化されるように思われます。 この場合、「明日の診療時間内にもう一度ご連絡ください」など、他の受診方法を丁寧に案内することが望ましい対応です。
- 緊急性が高い場合:一方で、患者が激しい胸痛や呼吸困難を訴えているなど、直ちに必要な応急措置を施さなければ生命・身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合には、時間外であっても診療を拒むことは、応召義務との関係で法的リスクがあります。 ただし、在宅という限られた環境下でできることは限られます。必ずしも往診が唯一の選択肢ではなく、電話で症状を詳しく聞き取り、救急車の要請を指示するなど、その状況で取りうる最善の対応(応急処置や適切な医療機関への連携)を行うことが求められます。
2. 担当エリア外など地理的制約
訪問診療は、担当エリアを決めて行われるのが一般的です。
担当エリアを大きく超える遠隔地の患者から往診を依頼された場合、物理的・現実的に対応が困難であること自体が、診療を拒否する正当な事由となり得ます。大雪や台風などの悪天候で、物理的に移動が不可能な場合も同様です。 ただし、その場合でも「お近くの○○病院に相談してみてください」「地域の在宅当番医制度をご利用ください」といった代替案を提示することが、トラブルを避ける上で重要です。地域で整備されている夜間・休日の救急診療体制を案内する対応は、原則として医師法に反しないとされています。もっとも、これはあくまで緊急対応が不要な場合の話であり、症状が重篤で直ちに応急措置が必要な患者をそのまま他院へ行くよう指示するだけでは義務違反を問われる可能性があるため、注意が必要です。
3. 専門外の疾患への対応
在宅医療を担う医師は総合的な診療能力が求められますが、当然ながら専門領域には限界があります。
明らかに自身の専門外であり、より高度な医療が必要と判断される場合、専門外であることを理由に診療を断ること自体は、一概に応召義務違反とはなりません。 しかし、その場合でも患者を放置することは許されず、可能な範囲での応急処置を行った上で、速やかに適切な専門医や高次医療機関へつなぐ(紹介・転送する)義務があります。バイタルサインの確認や、救急搬送の手配など、目の前の患者の安全を確保するための初期対応は不可欠です。
4. 患者との信頼関係が破綻している場合
先の裁判例でも示された通り、患者との信頼関係は診療の根幹をなすものです。
令和元年の通知では、「診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける」など、迷惑行為によって診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される、と明記されました。 在宅医療においても、医療者に対する暴言や暴力、理不尽な要求を繰り返す、あるいは医師の治療方針に全く従わず危険な自己判断を繰り返すなど、適切な医療関係を維持することが困難なケースでは、診療の継続を断ることが認められる可能性があります。
ただし、「信頼関係の破綻」を理由とするには、客観的な事実の積み重ねが必要です。一度や二度のトラブルで直ちに診療を拒否することは困難であり、再三の話し合いや説得にもかかわらず、状況が改善されない悪質なケースに限られると考えるべきです。診療中止を検討する際には、それまでの経緯を詳細に記録し、事前に弁護士等へ相談することが不可欠です。
5. 医療費の不払い
患者の経済状況を理由に診療を拒否することは、原則として認められません。 しかし、令和元年の通知では、「支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等」には、診療しないことが正当化される、と示されました。 具体的には、度重なる督促にも全く応じない、意図的に支払いを拒否し続けるといった悪質なケースがこれに該当し得ます。単に保険証を忘れた、一時的に支払いが困難といった事情だけでは、診療拒否の正当な理由にはなりません。
まとめ:トラブルを回避し、質の高い在宅医療を続けるために
応召義務は、医師にとって重い責任ですが、決して無限責任を課すものではありません。大切なのは、その本質を正しく理解し、患者の安全を最優先しつつ、医師自身が疲弊しない持続可能な体制を築くことです。
応召義務をめぐるトラブルを防ぐために、日々の実務において以下の点を心がけることが重要です。
- 緊急度の的確な判断と記録:診療の求めがあった際は、まず患者の状態を冷静に評価し、緊急性を判断します。そして、その判断の根拠、患者や家族への説明内容、実際に行った対応(往診、電話指示、他院紹介など)を必ずカルテに詳細に記録しましょう。客観的な記録は、万一の際に自らの正当な対応を証明する最も強力な武器となります。
- 代替案の提示と連携体制の構築:自院で対応できない場合でも、「できません」で終わらせず、地域の救急病院や当番医、連携する他のクリニックなど、具体的な代替案を提示することが患者の安心につながります。日頃から地域の他の医療機関と良好な関係を築き、スムーズに連携できる体制を整えておくことが、医師自身の負担軽減にもつながります。
- 事前の十分な説明と合意形成:新規に訪問診療を開始する際には、診療契約書などを活用し、診療時間、対応可能な範囲、時間外や緊急時の連絡方法・対応体制について、患者・家族に書面で明確に説明し、理解を得ておくことがトラブル防止の鍵です。「このクリニックは、夜間・休日はこのように対応する」というルールを共有しておくことで、無用な誤解や過度な期待を防ぐことができます。
- 丁寧なコミュニケーション:やむを得ず依頼を断る場合でも、その理由を専門用語を避けて丁寧に説明し、患者側の心情に配慮する姿勢が求められます。誠実なコミュニケーションは、信頼関係の維持に不可欠です。
在宅医療における応召義務の判断は、常に個別性が高く、明確な答えがない難しい問題です。しかし、今回解説した厚生労働省の考え方や裁判例の積み重ねは、私たちが臨床現場で判断を下す際の重要な道しるべとなります。法的知識とリスク管理の意識を持ち、地域の医療資源を有効に活用しながら、患者と真摯に向き合っていくこと。それが、応召義務と適切に向き合い、質の高い在宅医療を実践していくための鍵となるでしょう。