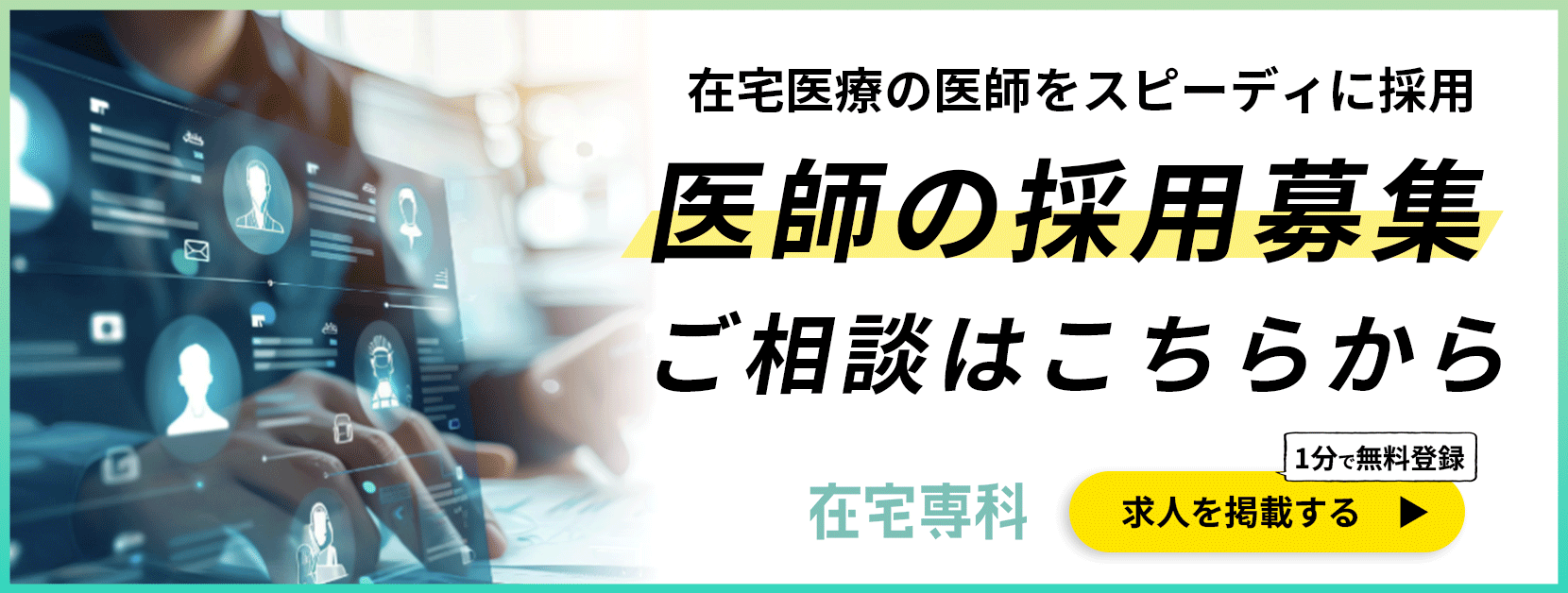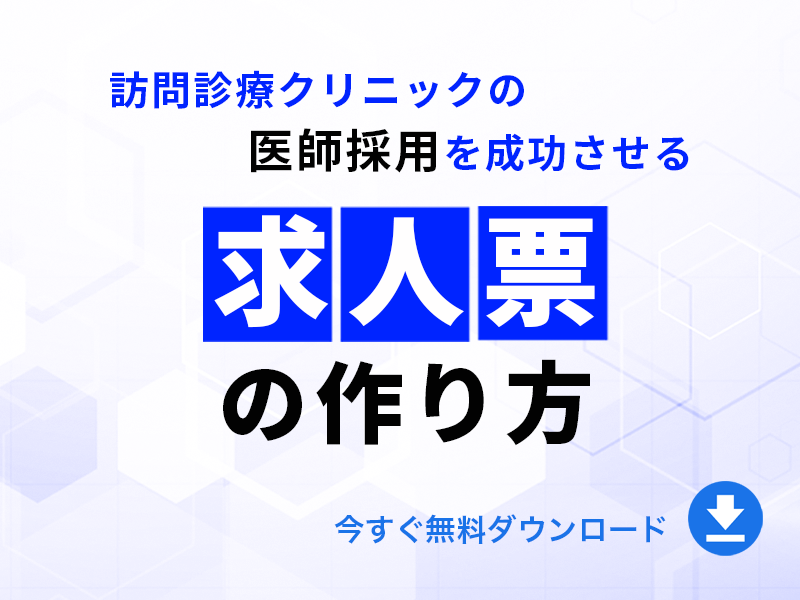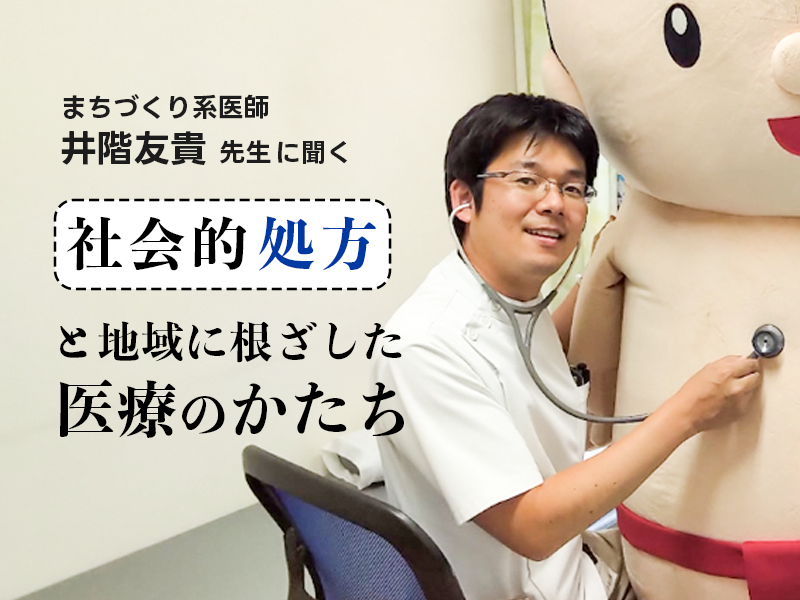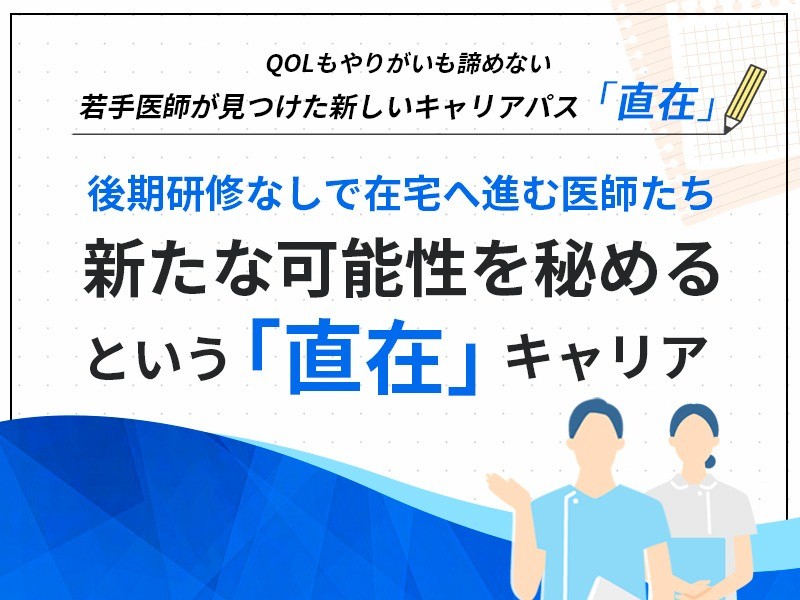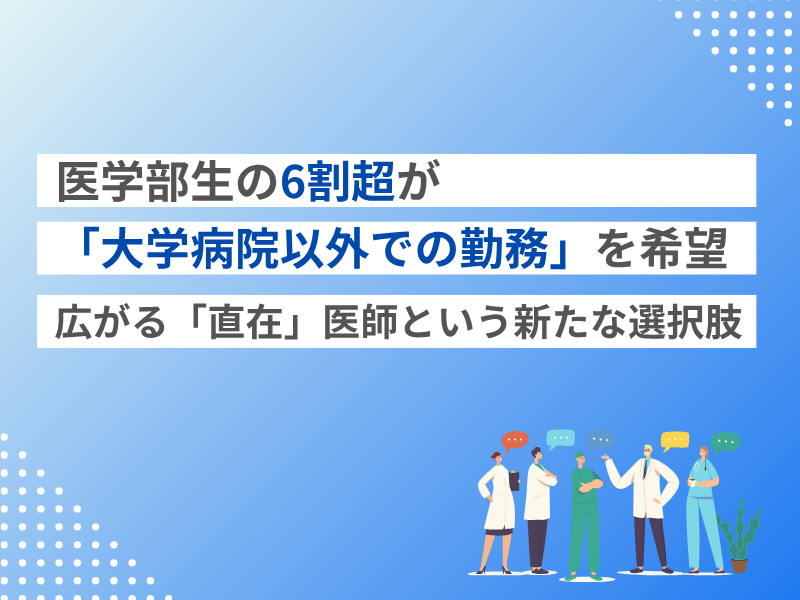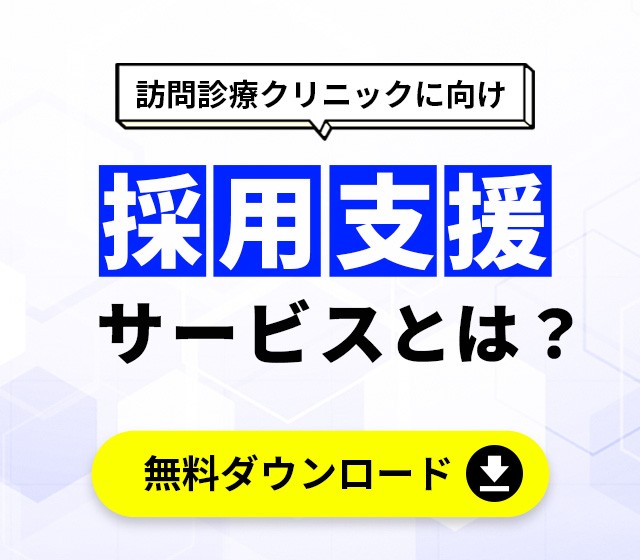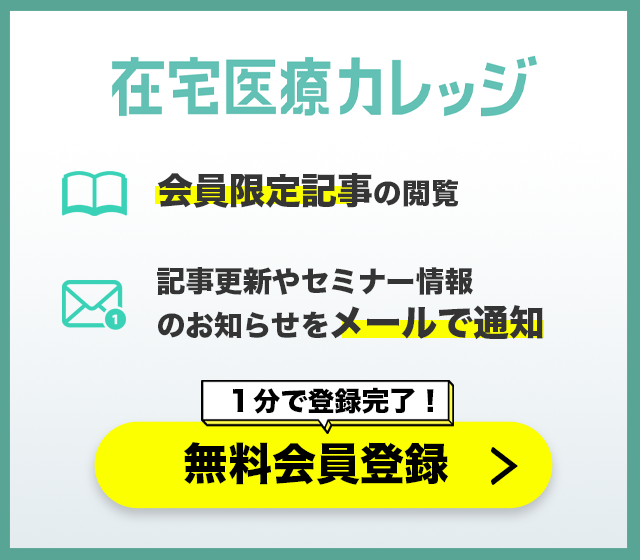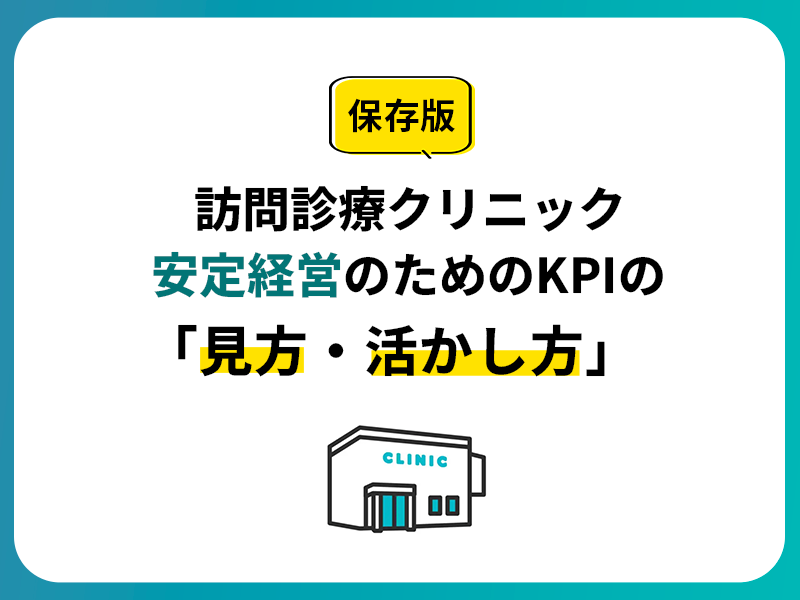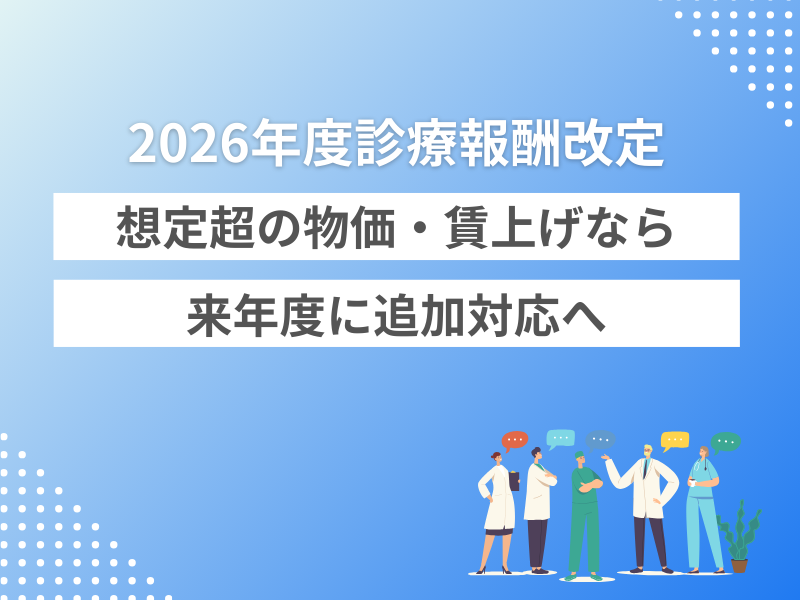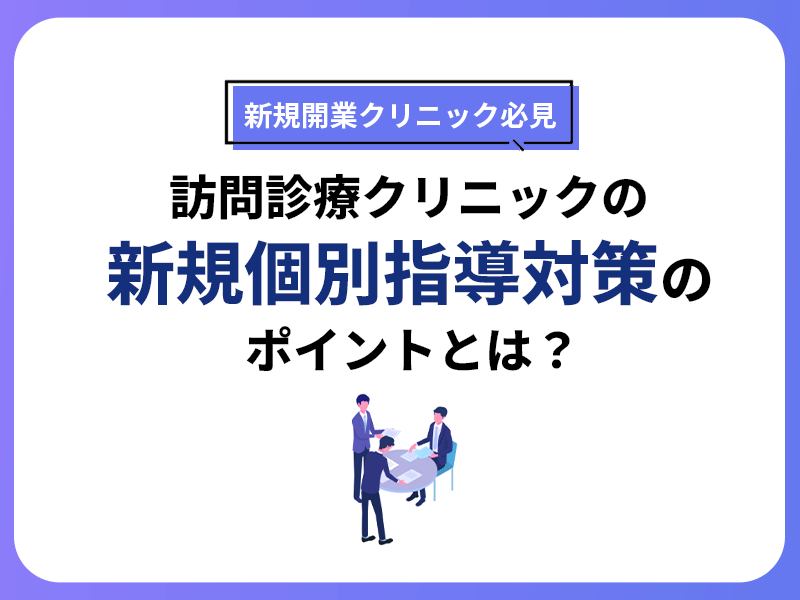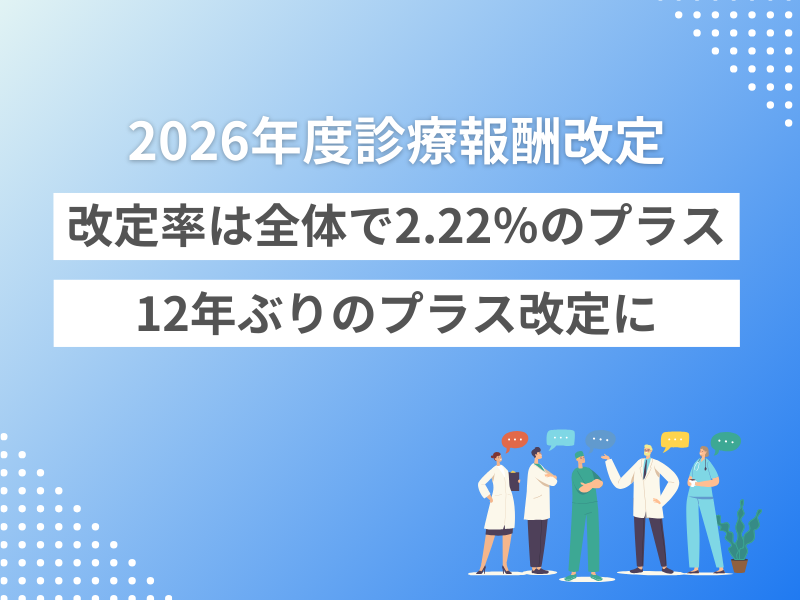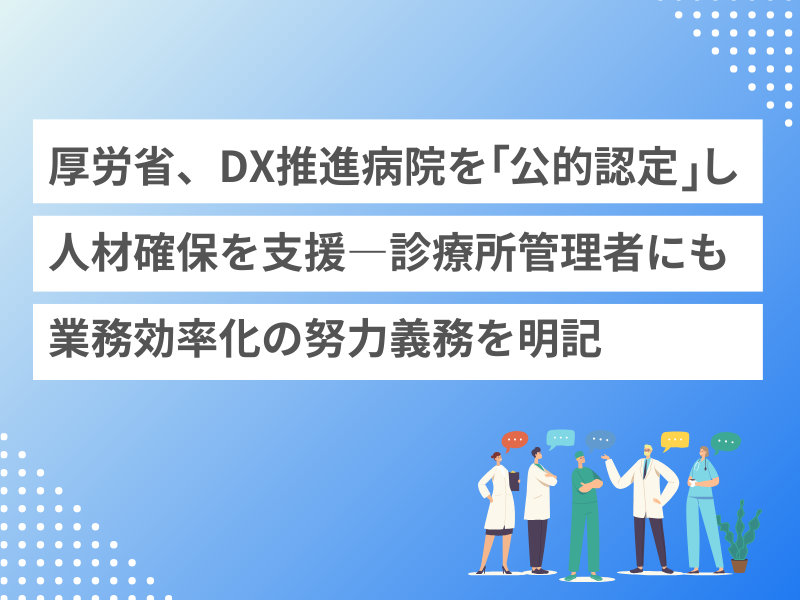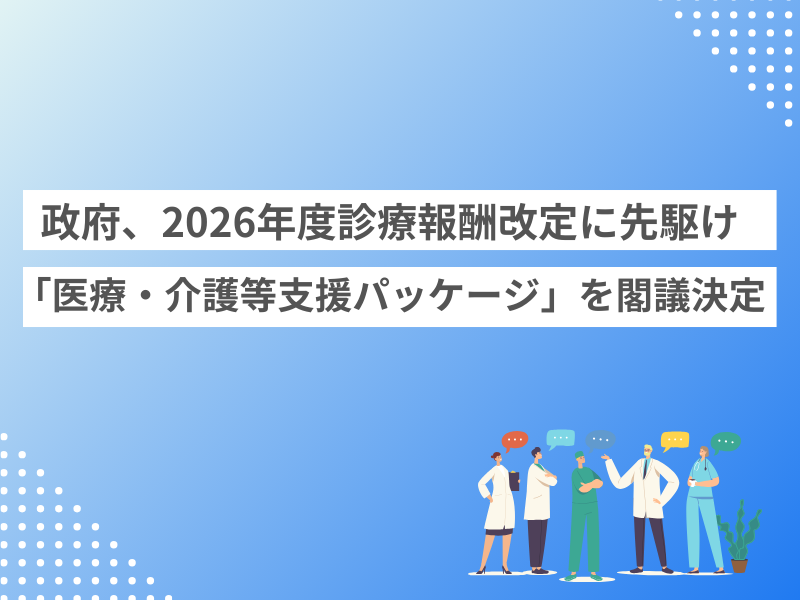- #運営
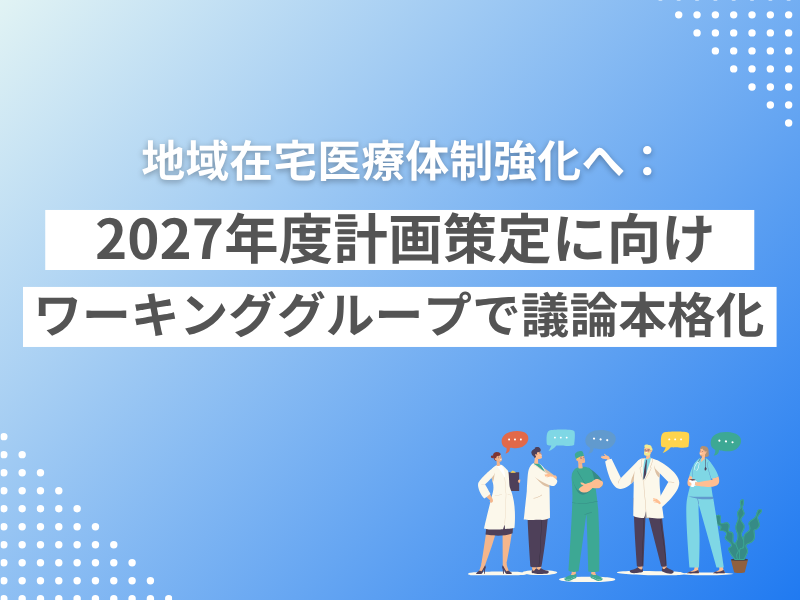
概要
2025年9月24日、「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(在宅WG)」が東京都内で開催され、2027年度から始まる新しい在宅医療整備計画を見据えた議論が始まりました。
地域の在宅医療提供体制の充実、医療・介護連携の強化、そして評価指標の見直しなどが主なテーマとして挙げられています。
今回のWG立ち上げは、現行の2024〜26年度計画がまさに最終局面を迎えており、次期計画の方向性を早期に固めておく意図が背景にあります。
在宅医療に求められる役割の明確化
地域の在宅医療体制を支えるためには、2つの重要な機能が求められます。
一つは、実際に患者の元へ訪問し、中心となって医療を提供する「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」。
もう一つは、地域の多職種・多機関のスムーズな連携を支える「在宅医療に必要な連携を担う拠点」です。
現状は、これらの機関・拠点の機能や要件が必ずしも明確に定義されておらず、地域によって取り組みに差があるのが実情でした。
このため、今後の計画において、これらの機関や拠点が具体的にどのような機能を持ち、どのような要件を満たすべきなのかを整理し、明確化していくべきだという議論が進められています。
これにより、患者が地域で安心して療養生活を継続できる、切れ目のない支援体制の構築を目指します。
地域の実情に応じた「在宅医療圏」の柔軟な設定
都道府県が設定する「在宅医療圏」についても、より地域の実情に合わせた弾力的な運用が論点となっています。
例えば、医療資源が比較的豊富な都市部では「市町村単位」の狭い圏域を設定する一方で、医療資源の乏しい地域では「二次医療圏単位」など広域な圏域を設定するといった具体例が挙げられました。
地域ごとの特性に応じた圏域設定を可能にすることで、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築が期待されます。
評価指標は「量」から「質」へ転換
これまでは診療所数や訪問回数といった「ストラクチャー(体制)」や「プロセス(過程)」に関する指標が中心でした。
今後は、「患者の満足度」「急変時の救急搬送件数の低減」といった、医療の「アウトカム(成果)」に着目した指標の重要性が強調されています。
これにより、在宅医療の質の向上を客観的に評価し、改善につなげていく狙いです。
まとめ
- 2027年度からの新計画に向け、在宅医療において積極的役割を担う医療機関の役割明確化と、在宅医療に必要な連携を担う拠点の整理が進められています。
- 地域の実情に応じた圏域設定が議論されています。
- 評価指標の見直しでは、従来の量的指標に加え、アウトカム指標に着目されています。
- 今後のワーキンググループでの議論を経て、各都道府県で具体的にどのような政策が進められていくのか、その動向が注目されます。