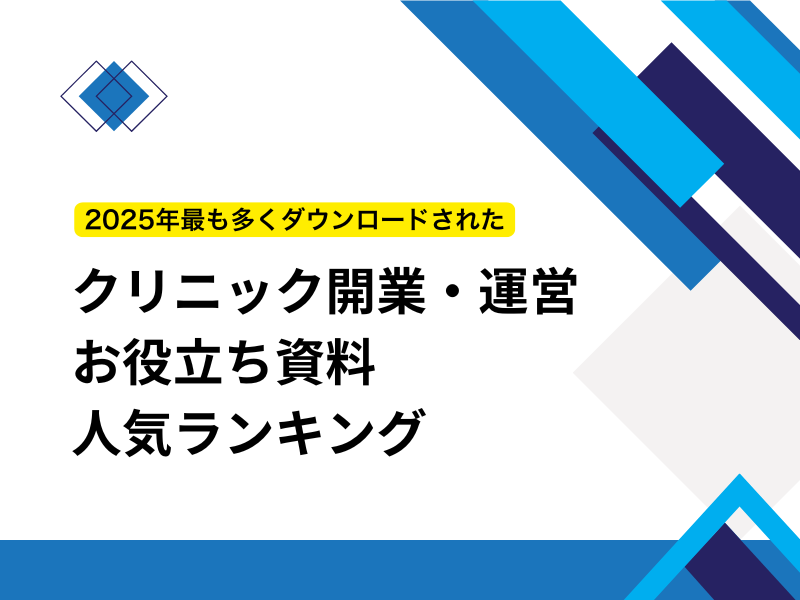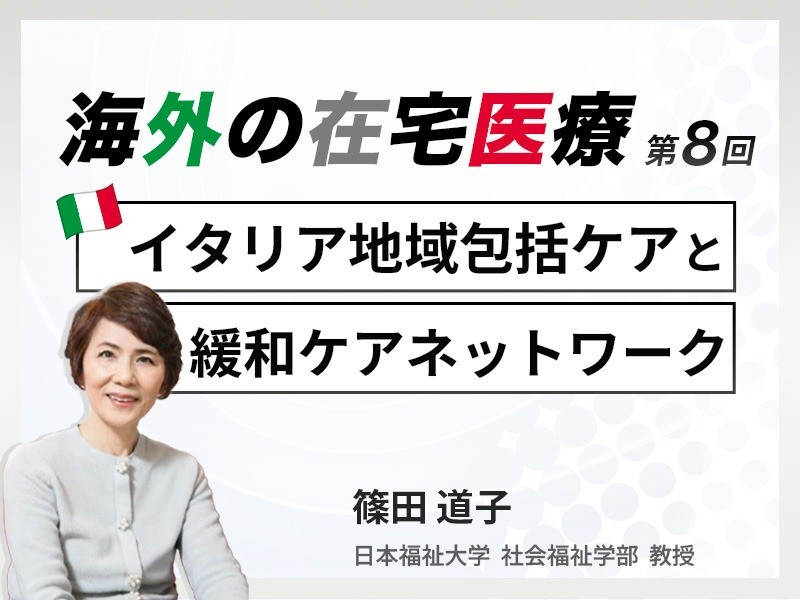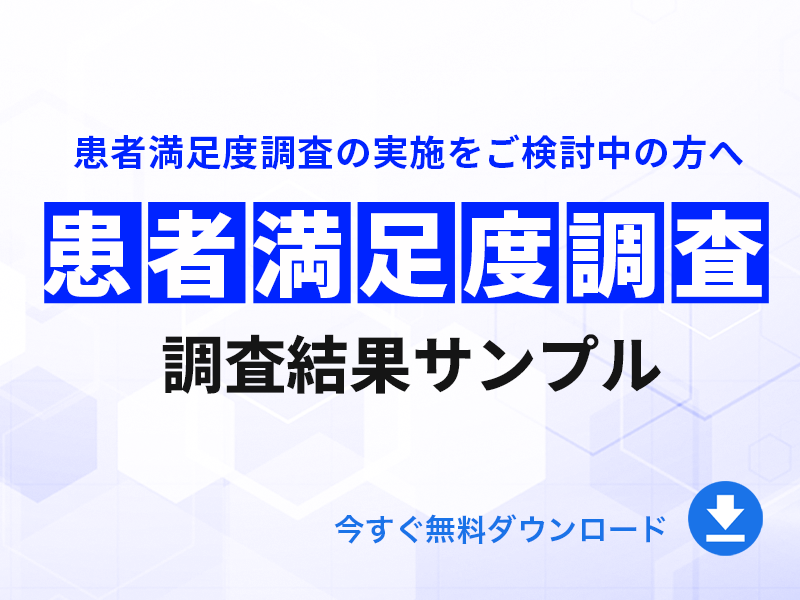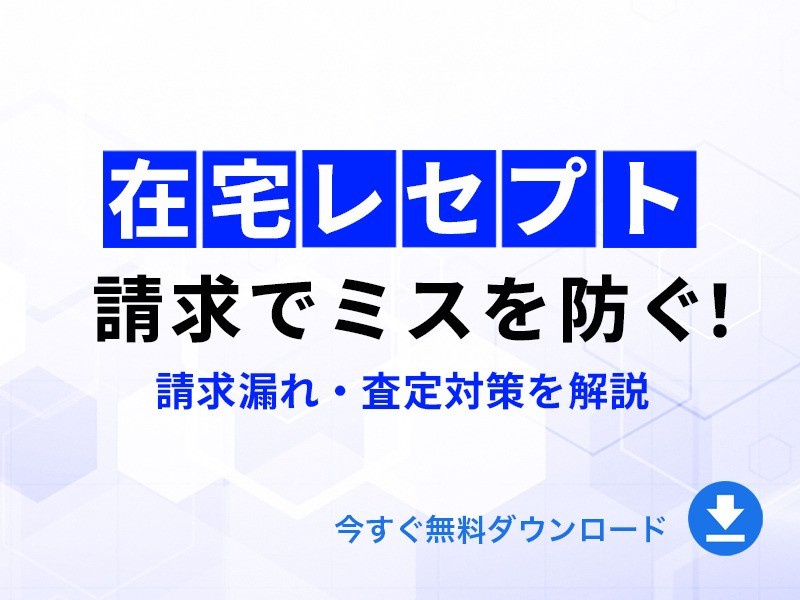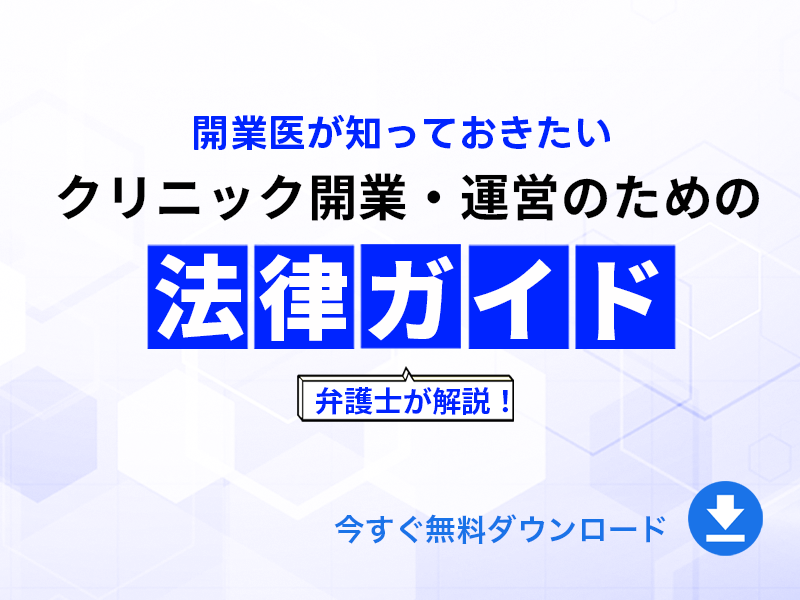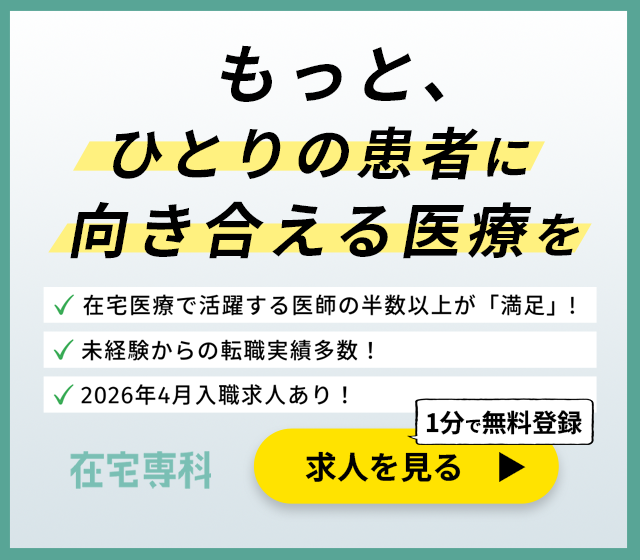「この人は、もっと早く家に帰れたかもしれない」。病院と在宅、双方の現場を知る医師が抱く課題意識。
香川県を舞台に、医療の分断をなくし、患者が望む場所で最期まで過ごせる社会を実現するために。
敬二郎クリニック院長・西信俊宏医師が描く、未来の地域医療の姿について伺いました。
医療法人社団慈風会在宅診療 敬二郎クリニック 理事長 西信 俊宏先生
香川県坂出市の社会医療法人社団大樹会回生病院で初期研修と救急後期研修を修了。
その後、栃木県の獨協医科大学病院総合診療科で2年間総合診療を修め、熱心な医学生や初期研修医、専攻医と共に学ぶ機会を持つ。
香川県の回生病院に戻り、内科医とともに総合診療科を立ち上げる。
香川大学医学部附属病院感染症教育センターで半年間感染症を研鑽し、現在に至る。
「手の届くところに、在宅が届いていない」—香川が抱える課題と医療者の役割
―先生の目からご覧になった、香川県の地域医療の現状と課題についてお聞かせください。
私の在宅医療の経験はまだ浅いのですが、香川では「もっと手の届くところに在宅医療が届いていない」と感じる場面が多々あります。
制度的、コスト的、マンパワー的な問題もありますが、「この方は在宅と病院を上手く使い分けることで、もっと質の高いケアを受けられたのではないか」と思うケースに出会うことがあります。
在宅医療はよい意味で自由度の高い現場です。
病院では「ここまでしかできない」と制約があることでも、自宅に帰ると「ほんの少し」プラスαのことができる。
その「ほんの少し」が、患者さんやご家族にとっては非常に大きな意味を持つことがあります。
この可能性を、まず私たち医療者自身がもっと身近に感じなければ、一般の方々にその選択肢が伝わっていかないのではないでしょうか。
クリニックは地域の「図書館」に。顔の見える連携で分断をなくす
―課題に対して、現在どのようなことに取り組まれていますか?
香川県内での医療の均てん化が重要だと考え、県内の総合診療に従事されている先生方と密にコミュニケーションを取るための研究会を立ち上げました。
また、クリニック運営においては、訪問看護師さんやケアマネジャーさんといった多職種の皆さんと、患者さんについてしっかりとディスカッションする時間を確保しています。
現場で一緒に診察をしながら話し合ったり、情報共有ツールを活用したりと、お互いの共通認識を持てるよう工夫を重ねています。
―多職種連携を促すための、ユニークな取り組みがあると伺いました。
当院は元々お菓子屋さんだった建物を改修したため、喫茶店のような広いスペースがあるんです。
そこを地域の皆さんが集まって、勉強会や相談会が開けるような場にしたいと考えています。
実際に、地域の看護師さんが相談に来られたり、遠方のご家族が来院された際にゆっくりお話しできる場として、あるいは在宅医療について知りたいという一般の方への情報提供の場として、少しずつ活用の幅が広がっています。
前の名誉院長が蔵書を多数所蔵されていたこともあり、大きな本棚を設置して、地域の図書館のような「誰もが自由に学べる場所」にしたいねという話も出ています。
「続けることが大事」。学生たちとの関わりが5年後、10年後の香川を創る
―未来の担い手である、医学生との関わりも積極的だと伺いました。
きっかけは、私が独協医科大学で学んだ経験を聞いた香川大学の学生から、直接病院に電話をもらったことでした。
今では学生さんたちが主体で活動している会に、私がお邪魔させてもらっている状況です。
彼らと関わる中で感じるのは、私以上に行動力があり、とても頼もしいということです。
世代が変わっても、規模は変わっても活動を継続していくことが、在宅医療に興味を持つ人たちにとっての希望になるはずです。
そのため、私は「継続すること」が最も重要だと考えています。
それが巡り巡って、5年後、10年後の香川県の医療に貢献するのではないかと信じています。
「困った時にすぐアクセスできる」理想のかかりつけ医と、それを支えるDX
―先生がお考えになる、訪問診療クリニックが担うべき「かかりつけ医」の役割とは何でしょうか。
「困った時にはいつでも駆けつけるよ」という、すぐにアクセスできる存在こそが真の「かかりつけ医」だと思っています。
理想論かもしれませんが、夜間に救急搬送された患者さんでも、その夜のうちにご自宅へお帰りいただいて診療体制を整えられるような、そこまでの対応力があれば最良ですね。
たとえば、骨折を伴わない転倒をされた高齢の方、軽症から中等症の感染症、あるいは独居が理由で食事摂取が困難になったがバイタルサインは安定している方など、こうしたケースは病院でなく、ご自宅で診療できるのではないかと考えています。
「仕方がない」で諦めてしまうケースを、少しでも減らしたいのです。
究極の理想を言えば、救急外来で入院待ちをしている方に「それでは、もうお家に帰りましょう」と、私たちが"お迎え"に行けるような体制です。
病院のベッドに上がることなく、住み慣れたお家で医療を受けられる選択肢を当たり前にしたい。
そんな夢のような話を本気で追求しています。
―その理想を実現するためには、何が必要だとお考えですか?
これからの時代に不可欠なのは「マンパワーの充実」と、それをサポートする「DXの活用」の2つです。
人材確保については、そこで成長できる、そこで働く価値をスタッフ一人ひとりが見出せる「学びのある職場」であることが重要だと考えています。
DXに関しては、医療職には苦手意識を持つ方も多いため、外部の知見を積極的に取り入れ、トライアンドエラーを重ねていくしかありません。
書類作成が多い在宅業務の効率化などから、段階的に取り組んでいます。
瀬戸内海の島々へ。ニーズのある場所に医療を届けるという挑戦
―今後の展望として、四国全体で地域医療をどうしていきたいとお考えですか?
当院が実践している「複数医師で担当患者を診る」というシステムを活用し、医療過疎地や「ここに在宅クリニックがあれば」という地域をサポートできればと考えています。
重要なのは、そこに確実なニーズがあるかどうかです。既存のコミュニティを壊すことのないよう、明確な目的を持って参入することが大切です。
そう考えると、中四国という広範囲で、私たちが介入すべきニーズのある地域を見つけ出すことにチャレンジしたいです。
―島の診療にもご関心があるそうですね。
はい。以前、離島診療を学ばせていただいた経験から、特に市が運営している島の診療所に対して、民間の私たちが何らかのサポートができないかと常々考えています。
これは瀬戸内海ならではの課題だと感じており、ぜひ挑戦したいのですが、まだ検討段階です。
島の医療は、よくも悪くも昔ながらの"村社会"的な信頼関係で成り立っている側面があります。
「あの先生だから大丈夫」という強固な絆がある一方で、それは極度の属人化にもつながりかねません。
タスクシフトや権限移譲といった仕組みをより広く導入することで、その先生個人の負担を軽減しつつ、持続可能な形で島の医療を支えられるのではないかと考えています。
原動力は「家族が安心できる地域医療」への想い
―最後に、先生がこれらの活動に取り組む原動力についてお聞かせください。
自分の家族が安心して過ごせる地域で医療に従事したい。
そのためには、自分一人が優れた医師になるだけでは不十分だろう、と考えていました。
自分がいない場面でも、同じ志を持った先生が自分の家族を診てくれるような地域にしたい。
むしろ、それを実現するために一度外に出て学んできた、という感覚です。
私が話していることは、すでに地域で実践されている先生方が数多くいらっしゃると思います。
私も、そうした先生方の良いところを取り入れながら、この地域に適したやり方を模索していきたいと思います。