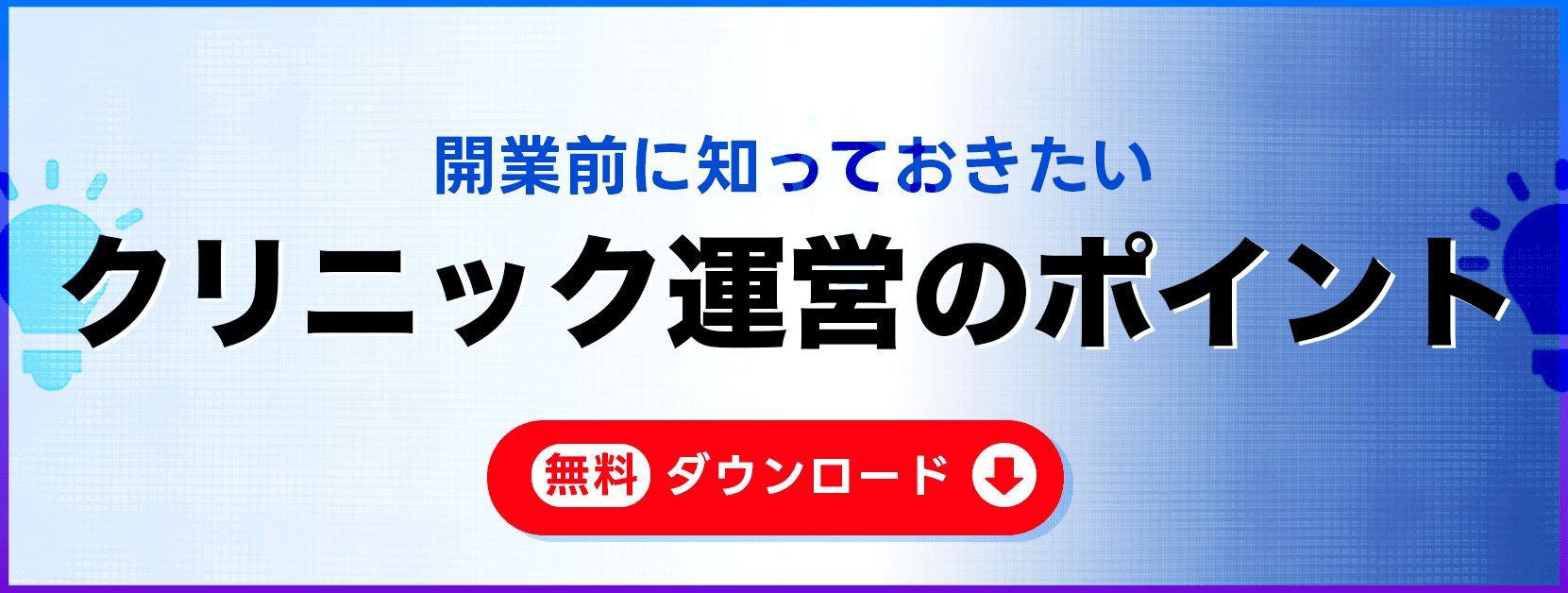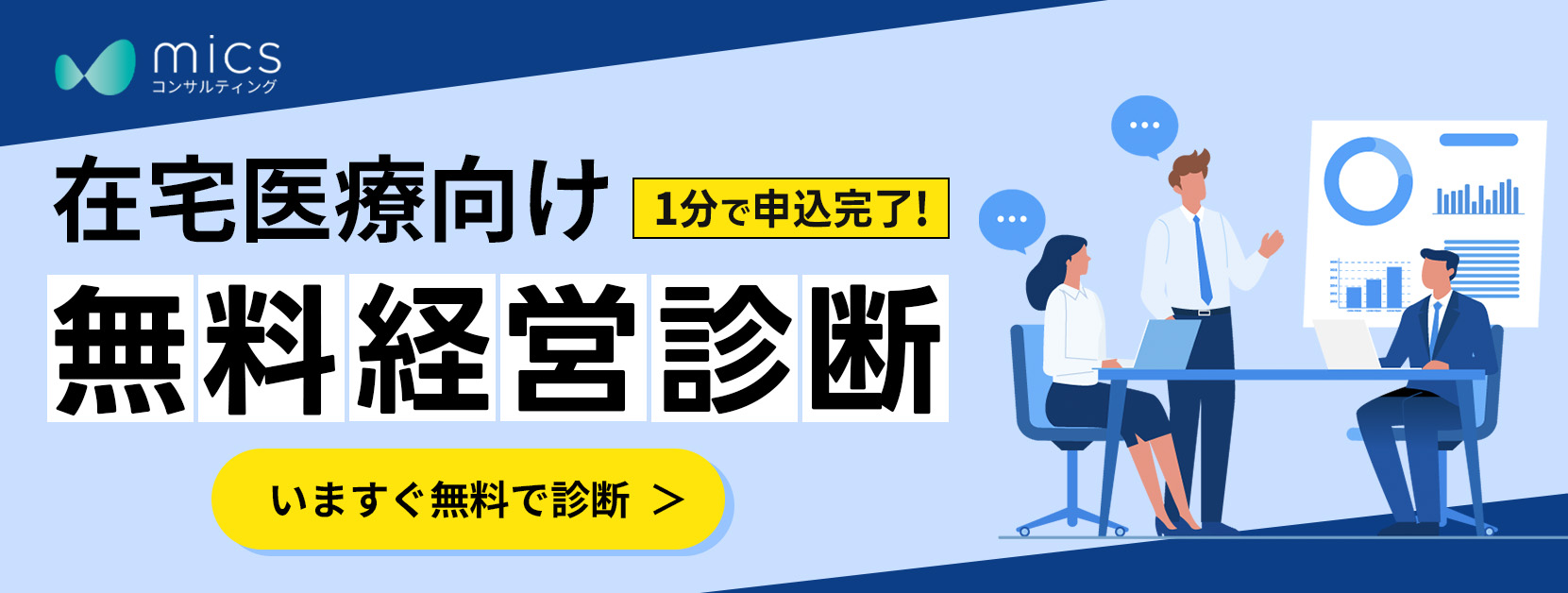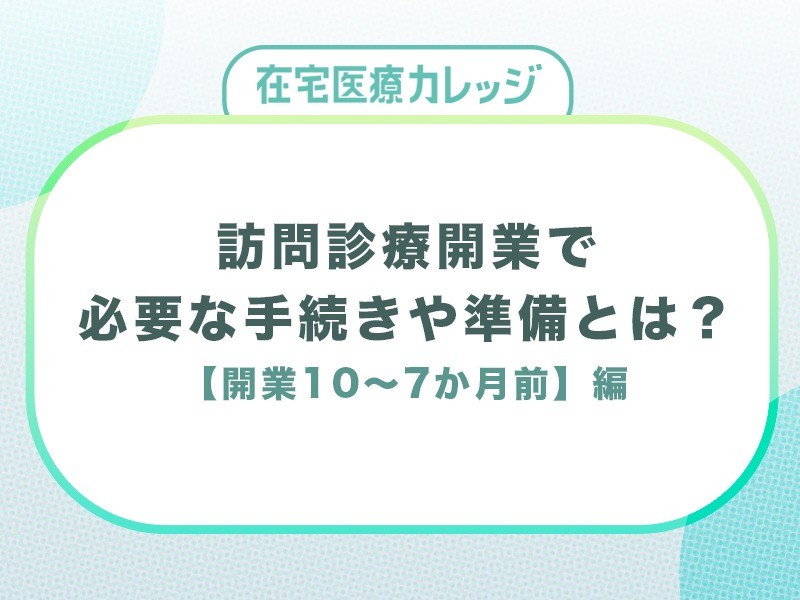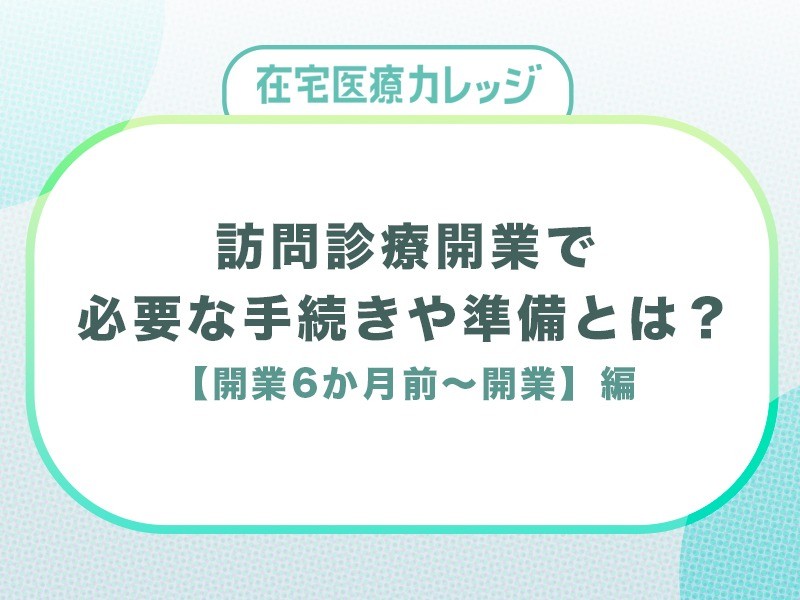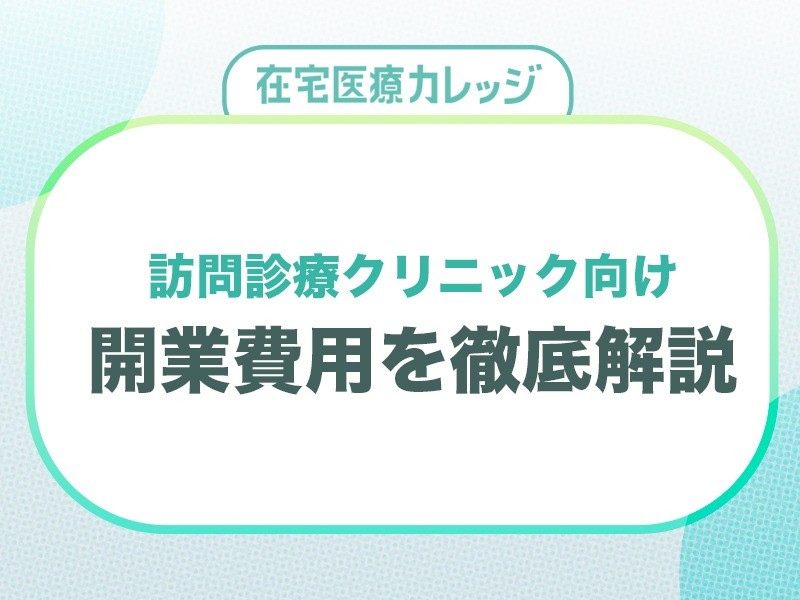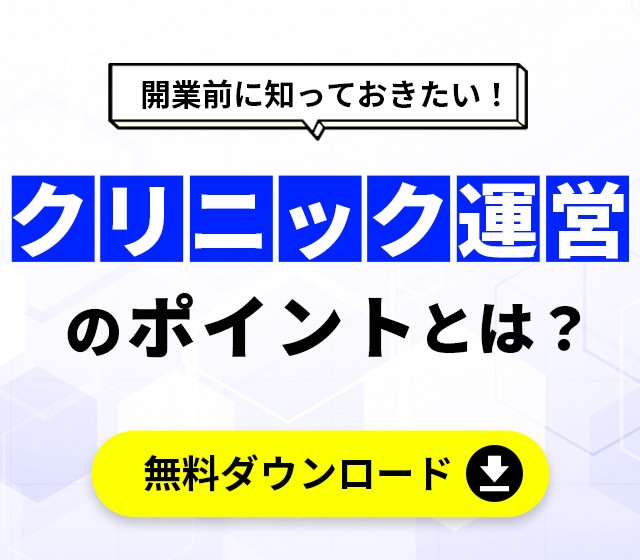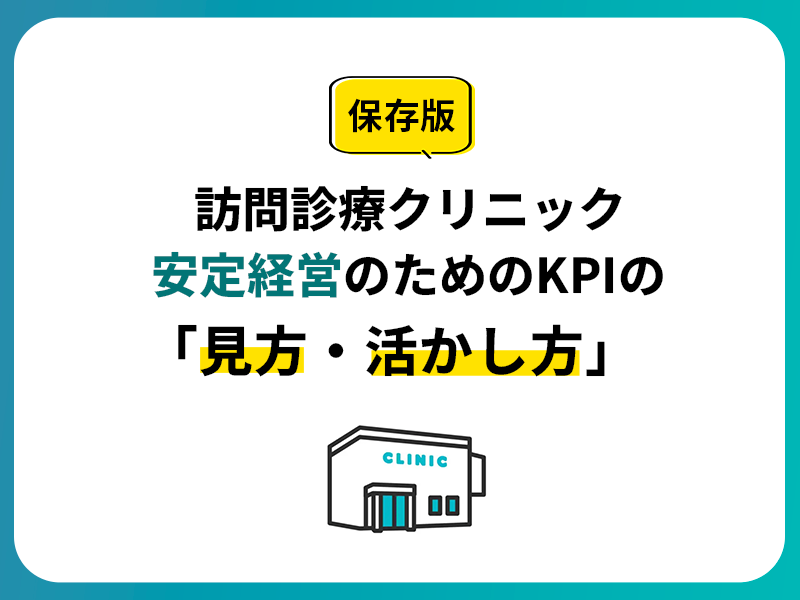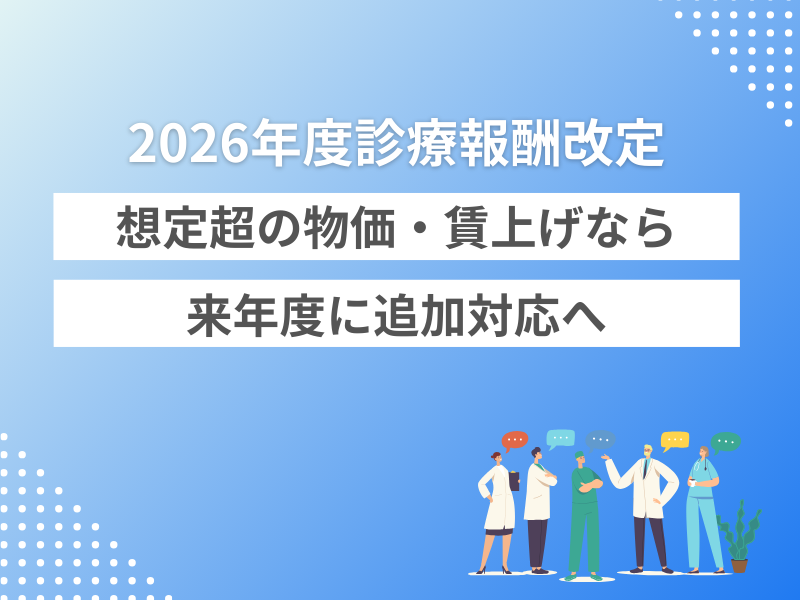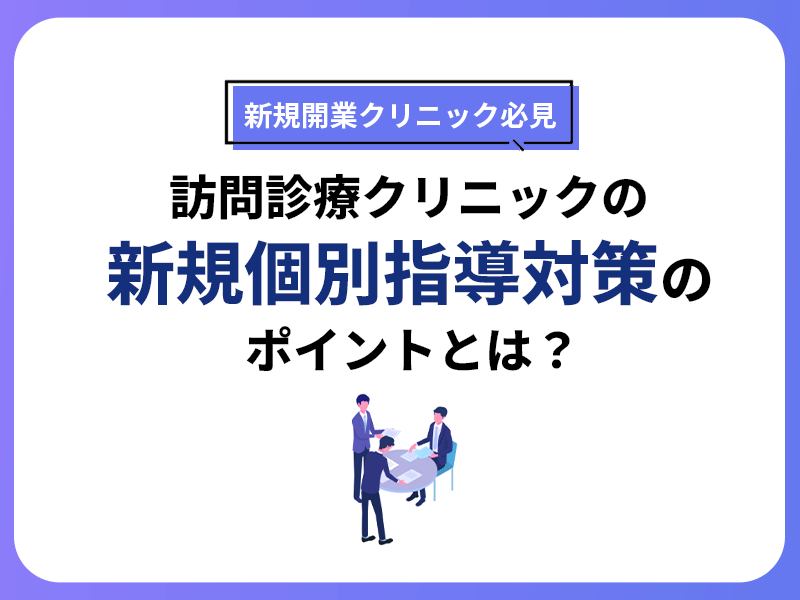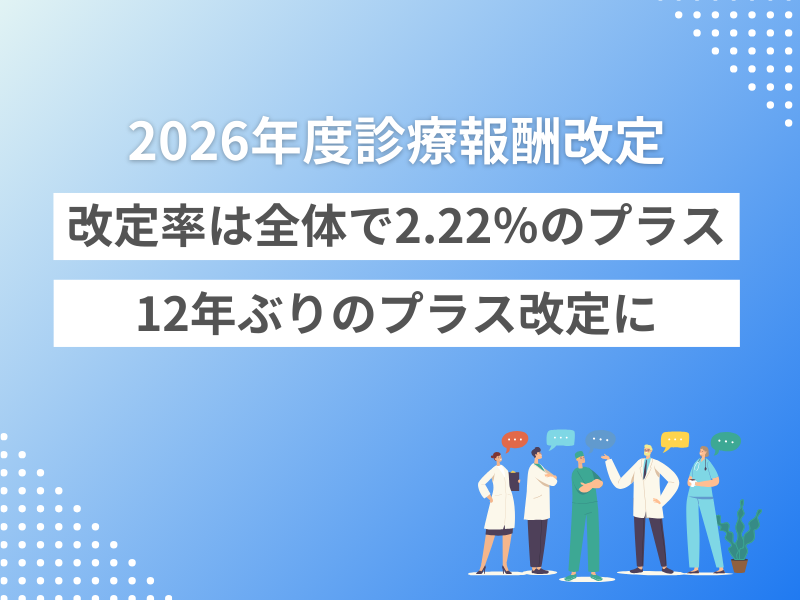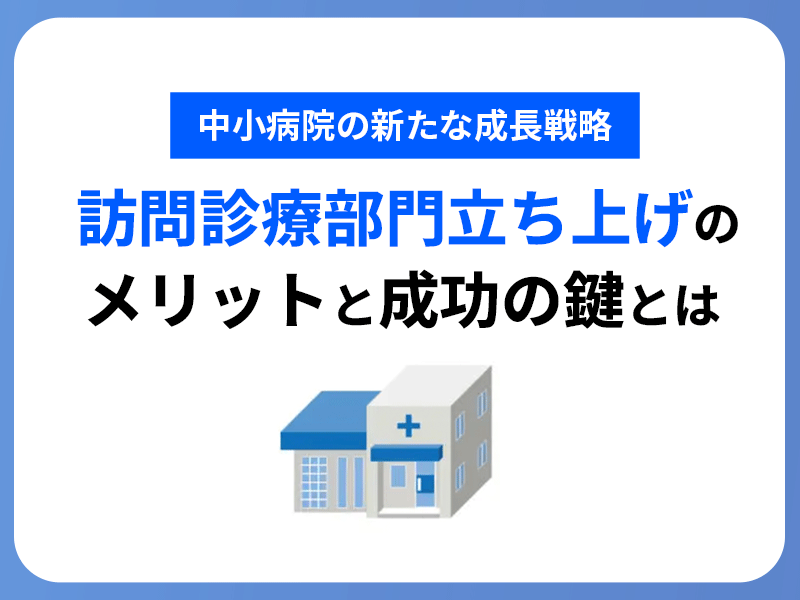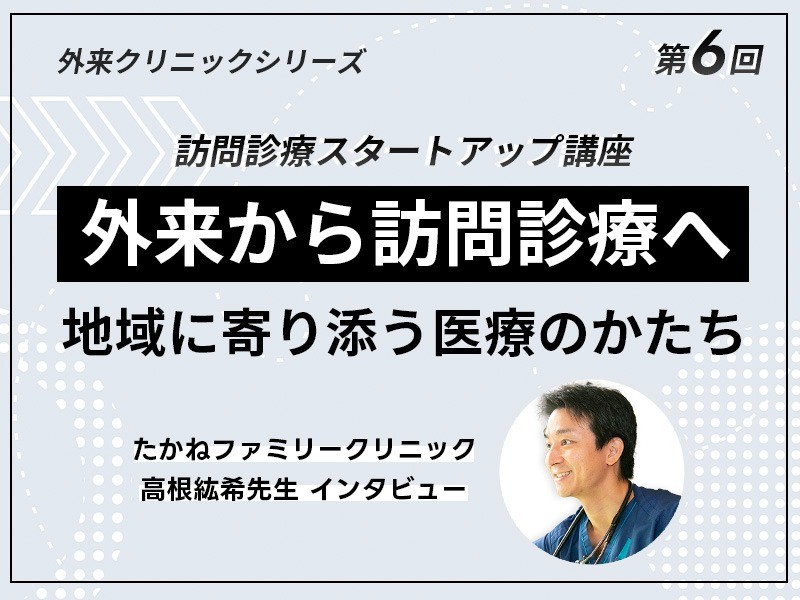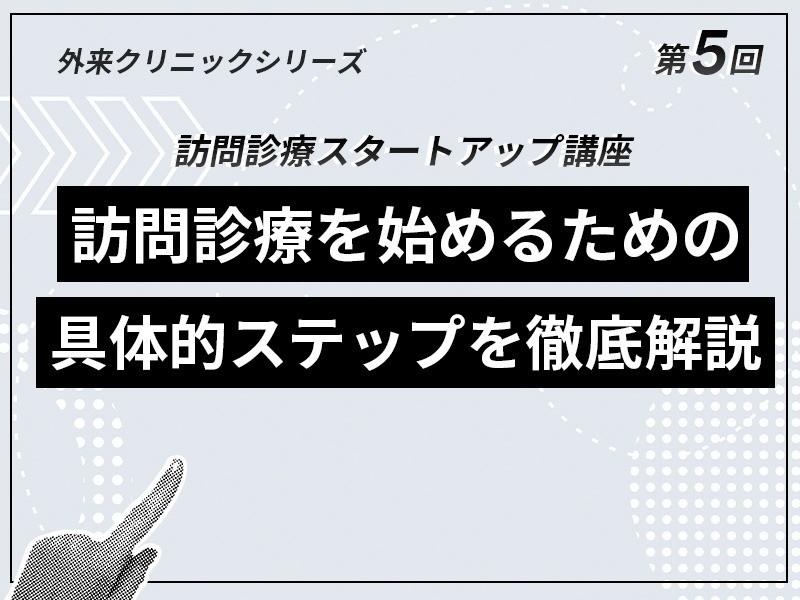- #開業

訪問診療クリニックの経営において、「何を指標として見ればいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
本記事では、医療機関の経営支援に多数の実績を持ち、現役の在宅医でもある岩本修一先生に、訪問診療クリニックにおけるシンプルかつ本質的な経営指標の見方を解説いただきました。
“医業利益”を軸に、自院に適した指標をどう見極め、どう活かすのか──。持続可能な在宅医療の実現に向けたヒントが詰まった内容です。
株式会社DTG 代表/おうちの診療所 経営補佐(医師)
岩本 修一 先生
広島大学医学部医学科卒業。福岡和白病院、東京都立墨東病院で勤務。2014年より広島大学病院 総合内科・総合診療科助教。2016年よりハイズ株式会社で病院経営およびヘルスケアビジネスのコンサルティングに従事。2020年1月よりおうちの診療所目黒(現・医療法人社団おうちの診療所)を共同開業。2021年10月より株式会社DTGを創業し、代表に就任。医療機関に対して医療DX支援、採用支援、組織開発支援をおこなっている。
訪問診療クリニックの経営で重視すべき指標
訪問診療クリニックの経営について、多くの経営者の方から「どの数字を見ればいいのか」「何を基準に判断すればいいのか」とご相談を受けることがあります。経営管理のために様々な指標がありますが、まず最も重視すべきなのは「利益」、特に「医業利益」です。
「医業利益」の重要性
医業利益とは、医療サービスの提供によって得られる売上(医業収益)から、それに要した費用(医業費用)を差し引いた金額を指します。つまり、本業である医業でどれだけの利益を生み出しているかを表す指標です。
なぜ医業利益が重要なのでしょうか。それは、医療機関の本業がどれだけ健全に運営されているかを端的に示すからです。医業利益をみれば、助成金などの一時的な収入でなく、本業で十分な利益を確保できているかどうかを把握することができます。
医業利益はその持続可能性を測る重要な尺度となります。十分な医業利益を確保できていれば、設備投資や人材確保、さらには診療の質向上に向けた取り組みに資金を回すことができます。反対に、医業利益が低い、あるいはマイナスであれば、早急な経営改善が必要なサインと言えるでしょう。
医業利益率の目安は7-14%
医業利益を医業収益で割った「医業利益率」は、クリニックの経営効率を測る指標として広く活用されています。在宅医療における医業利益率は7〜14%を目安に考えるといいでしょう。
この水準は、単なる目先の利益確保だけでなく、将来的な診療報酬改定への備えも含んだものです。診療報酬は2年ごとに改定され、特に在宅医療分野は政策的な影響を受けやすい側面があります。適正な利益率を維持しておくことで、たとえ報酬改定によって売上が減少した場合でも、経営の安定性を保つことができます。
実際には、30%以上の高い医業利益率を実現している訪問診療クリニックも存在します。しかし、そのような高利益率が適切かどうかは、各クリニックの費用構造や診療内容によって異なります。単純に高い利益率を目指すのではなく、自院の状況に合わせた適正な利益水準を設定することが重要です。
費用構造と利益水準の関係
訪問診療クリニックの費用構造は、立地や診療体制によって大きく変わります。自院の費用構造を正確に把握することが、適正な利益水準を設定するための第一歩です。
立地と賃料・人件費の関係
訪問診療クリニックの費用構造に大きく影響する要素の一つが、「立地(診療所の場所)」です。都心部では賃料が高くなる傾向がありますが、人口密度も高いため効率的な訪問が可能です。一方、郊外や地方では賃料は比較的安価ですが、訪問に時間がかかるため医師一人当たりの訪問件数が比較的少なくなります。
また、エリアによって人件費の相場も変わります。都市部ほど給与水準が高く、地方に行くほど相対的に低くなる傾向があります。医師・看護師・事務職といった人材確保のしやすさもエリアによって異なるため、人件費率に影響します。
このように、場所の特性に応じて費用構造が変わるため、自院が位置するエリアの特性を踏まえた利益率の設定、ならびに経営計画を立てることが重要です。
診療体制による費用構造の違い
診療体制も費用構造に大きな影響を与えます。例えば、医師一人で訪問する体制と、医師と看護師がペアで訪問する体制では、人件費構造が大きく異なります。
医師一人体制では人件費は抑えられますが、移動時間や診療時間が長くかかり、一日の訪問件数を増やすことに限界があります。一方、医師と看護師のペア体制では人件費は増加しますが、業務分担により効率化が図れ、訪問件数を増やせる可能性があります。
医師1人体制では、人件費率は比較的低く抑えられますが、1人あたりの業務負担が大きくなります。医師複数体制では、組織的な運営が可能になり、効率化が図れる反面、人件費の総額は上がります。
また、常勤医師中心の体制と非常勤医師を多く活用する体制でも費用構造は異なります。
患者数・患者構成と売上の関係
訪問診療クリニックの収益面に大きく影響するのが、患者数と患者構成です。医師一人当たりの患者数は、クリニックの収益性を左右する重要な指標です。一般的に、医師一人当たり80〜100人程度の患者を担当することが多いですが、診療圏の広さや患者の重症度によっても適正な人数は変わってきます。
また、患者構成も売上に大きな影響を与えます。例えば、在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施医総管)では点数体系が異なります。同様に、在宅がん医療総合診療料を算定できる患者の割合によっても売上構造は変わります。
自院の患者構成を分析し、どのような患者層がクリニックの収益にどう貢献しているかを把握することで、より戦略的な経営判断が可能になります。
自院に適した経営指標の設定と活用
医業利益と、その内訳の1年分を分析することで、自院がどのくらいの患者数を確保すれば経営が安定するかが見えてきます。その分析結果をもとに、自院に適した経営指標を設定し、定期的にモニタリングしていくことが重要です。
医師1人あたり患者数の適正値
多くの訪問診療クリニックでは、医師1人あたり患者数を重要な経営指標としています。この数値は、スタッフの労働負荷と収益性のバランスを図る上で重要です。
適正な医師1人あたり患者数を設定するためには、以下の要素を考慮する必要があります:
- 診療圏の広さと移動効率
- 患者構成
- 1件あたりの診療時間
- 緊急往診の対応体制
- 夜間オンコール・往診体制
例えば、診療圏が広く移動に時間がかかる場合や、じっくり時間をかけて診療する方針であれば、1人あたり患者数の水準は少なめに設定すべきでしょう。逆に、限られたエリアで効率的な診療を行う体制であれば、医師1人でより多くの患者を担当できます。
なお、上述したとおり、在医総管(居宅)と施医総管(施設)の診療報酬には異なるため、施設患者数には1/3〜1/4を掛けて、居宅患者数換算を用いることもあります。
適正な人件費率の設定
訪問診療クリニックでは、人件費が費用の大部分を占めることが一般的です。そのため、適正な人件費率(人件費÷医業収益)の設定は経営管理の要となります。
在宅医療の分野では、人件費率50〜60%程度が一つの目安とされていますが、これも診療体制や地域性によって適正値は異なります。医師の報酬体系によっても、適正な人件費率は変わってくるでしょう。
重要なのは、自院の状況に合わせた適正な人件費率を設定し、それを定期的にモニタリングすることです。必ずしも目標値を決める必要はありません。重要な経営指標は医療におけるバイタルサインと同様です。時間経過での変化を把握することは役に立ちます。人件費率が高くなりすぎる場合は、人員配置の見直しや業務効率化の検討が必要かもしれません。
経営指標の定期的モニタリング
設定した経営指標は、定期的にモニタリングすることで初めて意味を持ちます。例えば、月次で以下の指標を確認するとよいでしょう。
- 医業収益の推移
- 医業利益・医業利益率の推移
- 医師1人あたり患者数
- 人件費率
- 新規患者数と終了患者数
これらの指標を月次で追いかけることで、問題の早期発見や対策が可能になります。例えば、医業利益率が低下傾向にある場合は、収益面(診療単価や患者数)と費用面(人件費や医療材料費)の両面から原因を探り、適切な対策を講じることができます。
また、四半期や半期ごとに、より詳細な分析を行うことも有効です。患者構成や地域別の収益性、時間帯別の効率性など、より詳細な視点での分析が可能になります。
医療法人社団おうちの診療所(東京都)では、モニタリング結果を毎月、院内で共有し、医師や看護師を含めたスタッフ全員が経営状況を理解できるようにしています。こうした取り組みによって、経営の透明性を高めるとともに、経営感覚を持ったスタッフが増え、日々の業務の中から改善策が生まれることもあります。
まとめ:持続可能な在宅医療の実現に向けて
「患者と地域のためになる医療」を続けるための経営視点
訪問診療クリニックの経営において最も大切なのは、「患者と地域のためになる医療」を「続けられる」ようにすることです。どんなに理想的な医療を目指していても、経営が成り立たなければ継続することはできません。
適切な経営指標を設定し、それに基づいて運営することは、単に利益を追求するためではなく、良質な医療を持続的に提供するための基盤づくりです。特に訪問診療は、患者やその家族、地域の医療・介護関係者からの信頼関係の上に成り立つサービスです。その信頼を裏切らないためにも、安定した経営基盤が不可欠です。
シンプルな経営管理の重要性
経営管理においては、複雑な指標をたくさん追うよりも、シンプルに医業利益を中心とした基本指標を押さえることが重要です。医業利益率、医師1人あたり患者数、人件費率など、少数の重要指標に焦点を当て、それらを定期的にモニタリングする習慣をつけましょう。
また、経営指標は単なる数字ではなく、日々の診療活動や組織運営と密接に結びついています。数字の変化の背景にある現場の状況を常に意識し、経営改善と医療の質向上を両立させる視点を持つことが肝要です。
訪問診療クリニックの経営は、医療政策や地域の人口動態の変化など、外部環境の影響を受けやすい側面があります。しかし、自院の経営状況を適切に把握し、環境変化に柔軟に対応できる体制を整えておくことで、どのような環境下でも持続可能な在宅医療を実現することができるでしょう。
持続可能な在宅医療の提供には、医療の質と経営の安定性の両立が不可欠です。本稿で紹介した経営指標とその活用方法が、皆様のクリニック経営の一助となれば幸いです。