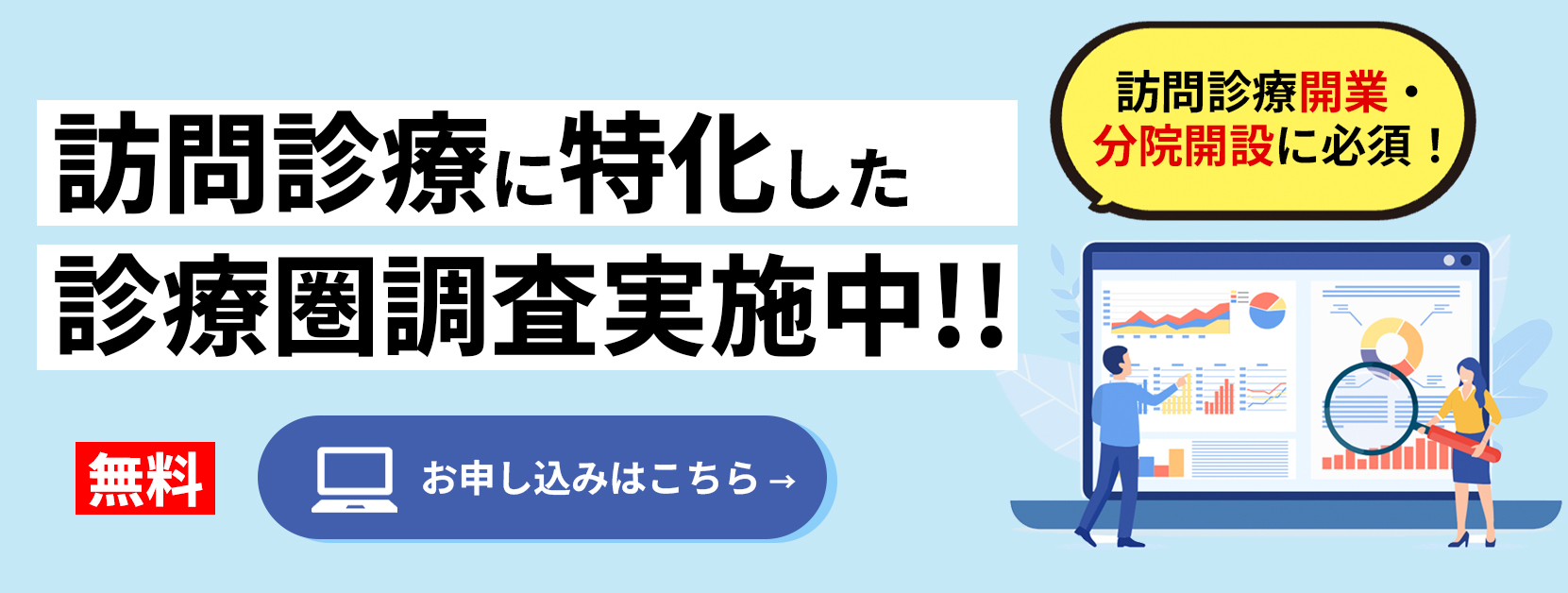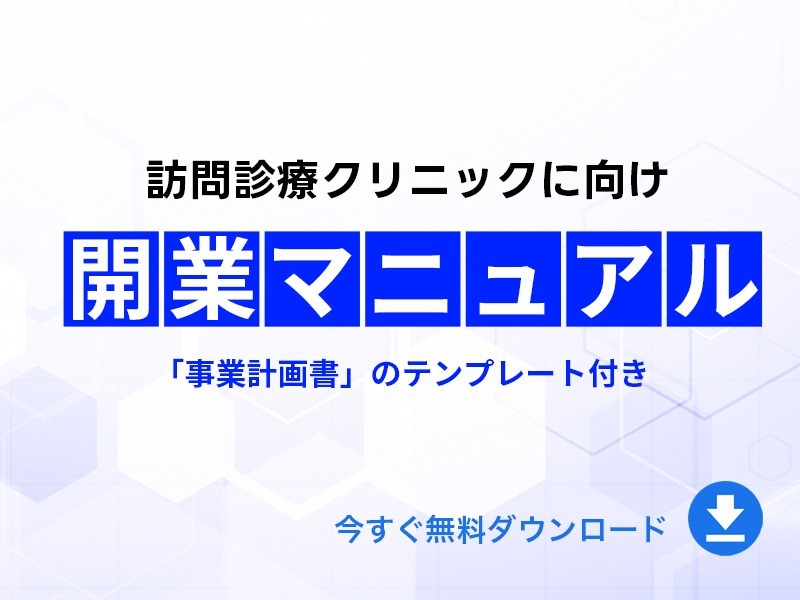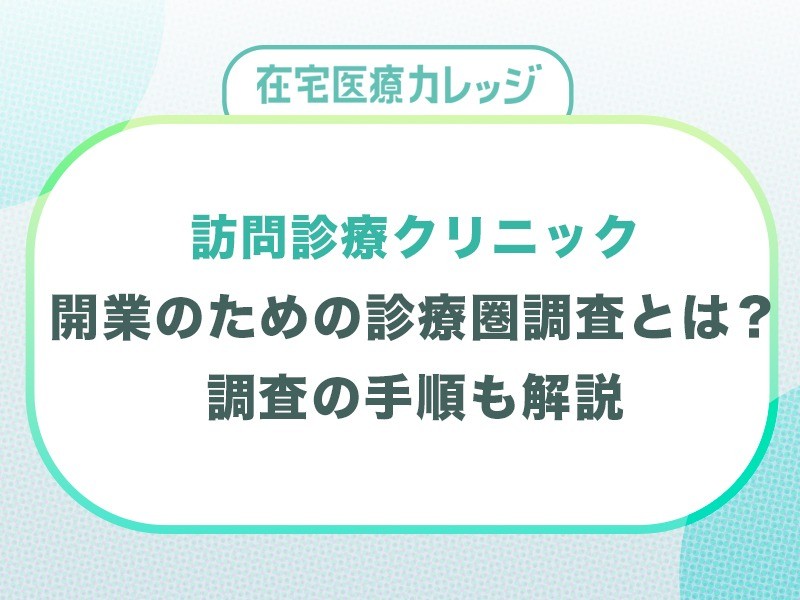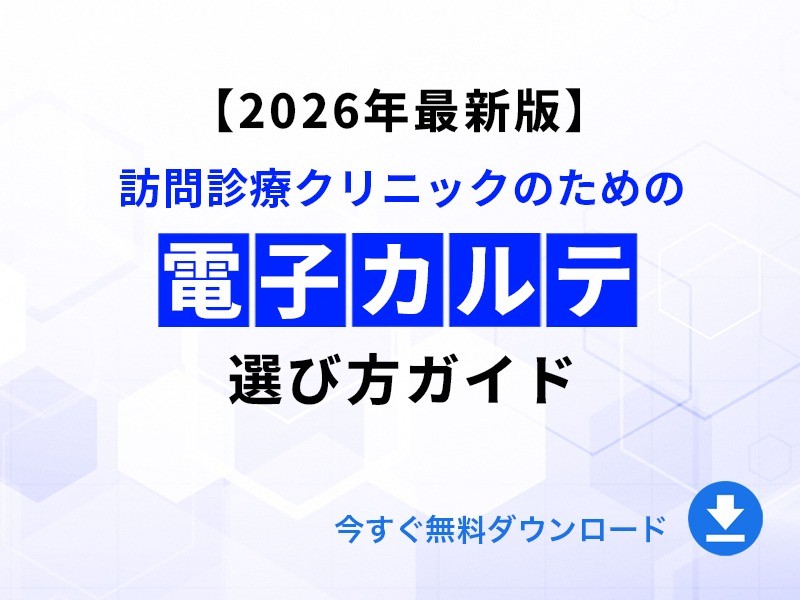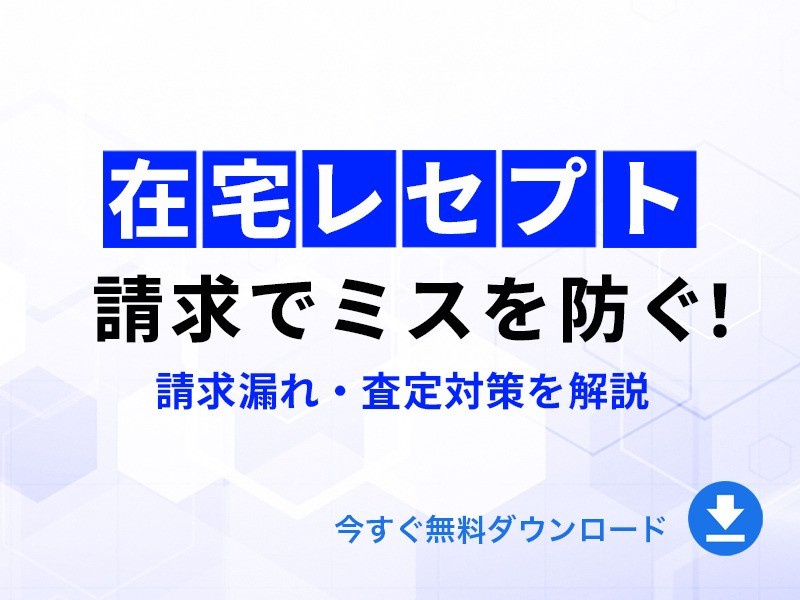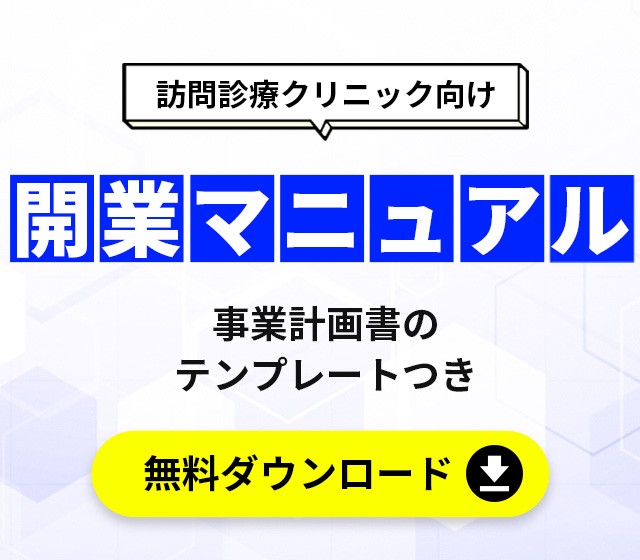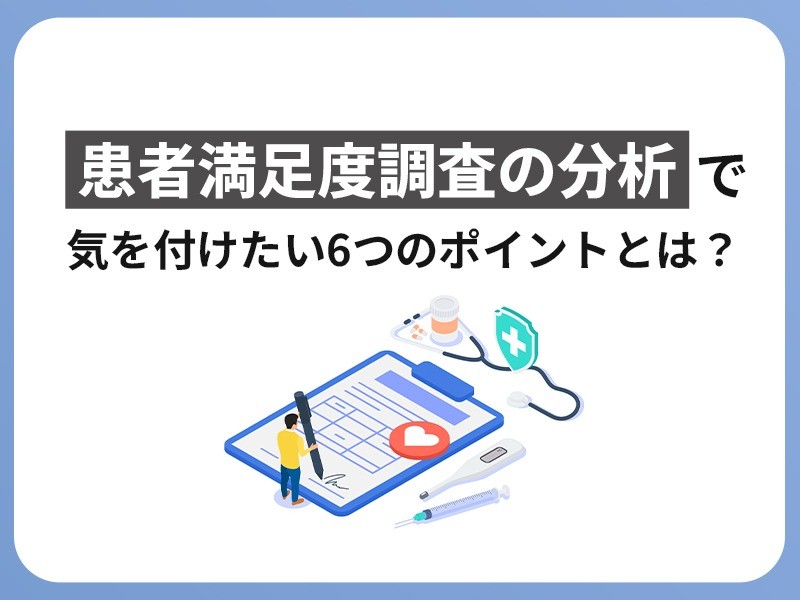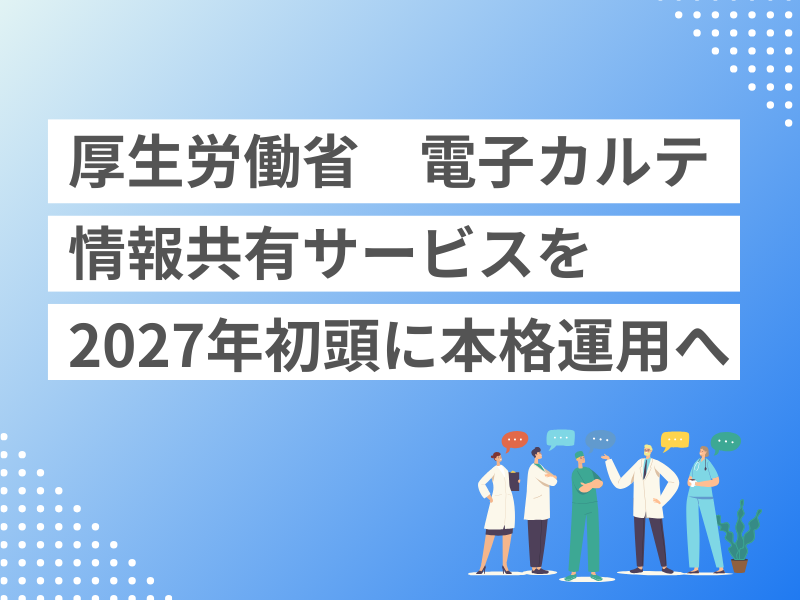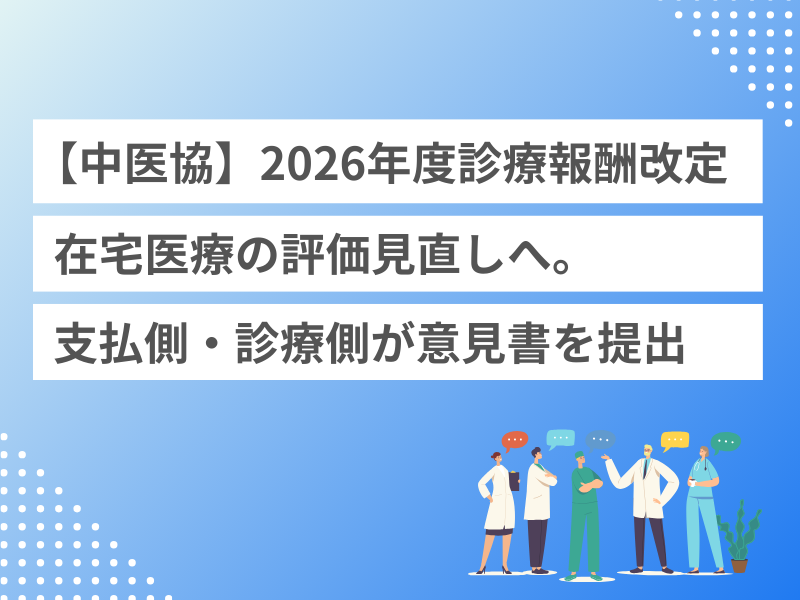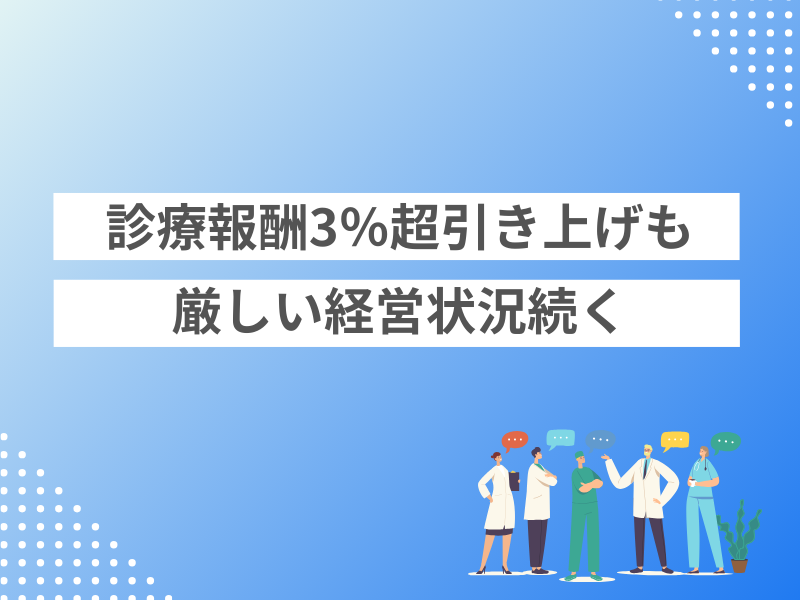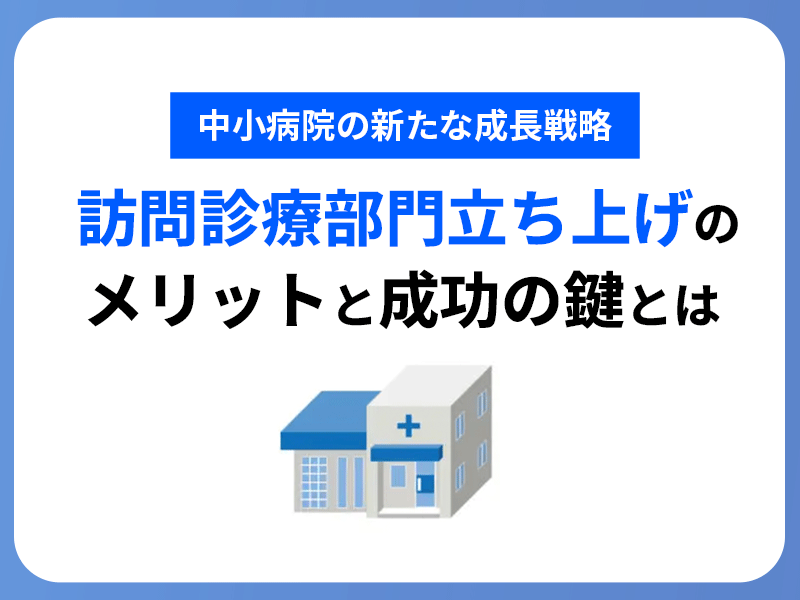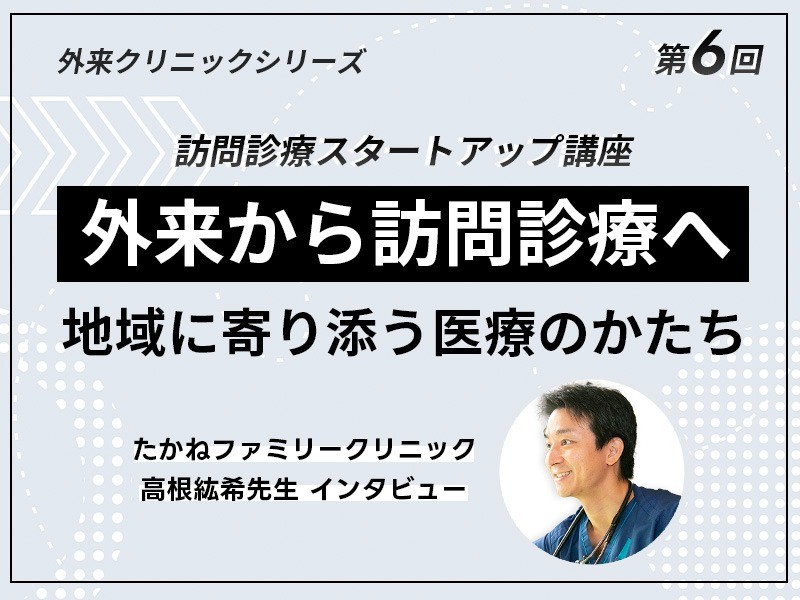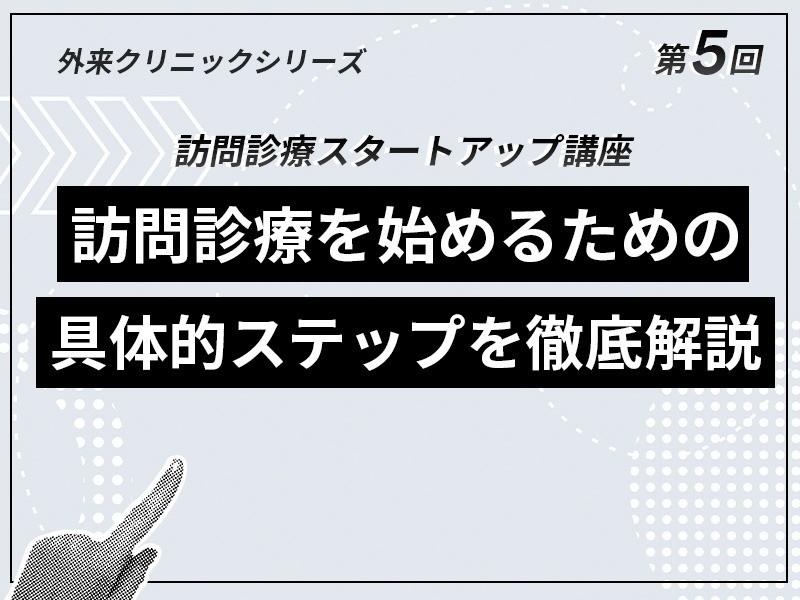- #開業
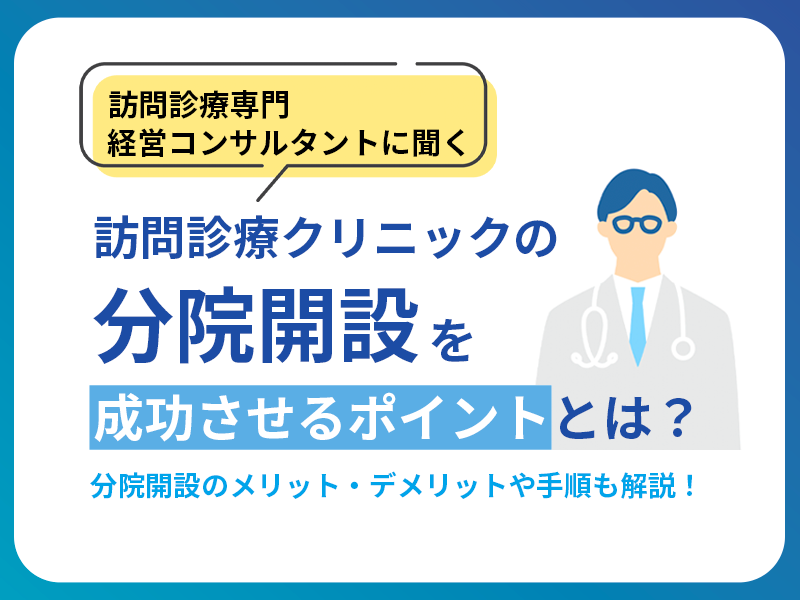
在宅医療の需要が高まる中、事業拡大の一環として分院開設を検討する先生も増えているのではないでしょうか。本記事では、訪問診療クリニックの分院開設を成功に導くポイントについて、在宅医療専門経営コンサルタントにインタビューしました。
分院開設とは
分院開設は、医療法人または病院・診療所が、本院の他に新たな病院や診療所を開設することです。
訪問診療における分院開設では、主に以下の4つのパターンがあります。
- 常設型: 既存の診療所から拠点を増やす形態で、当社への相談も最も多いタイプです。
- サテライトオフィス型: 開設届を出さずに拠点を増やす、非診療型の形態です。初期投資を抑えられるメリットがあります。
- 移動拠点型: 主に地方で見られる、車両をベースとした形態です。
- 併設型:既存の介護施設と連携し、施設の中に診療所を設置する形態です。
今回は、特にニーズの高い「常設型」の分院開設を前提として解説していきます。
分院開設のメリット・デメリットとは
分院開設のメリット
主なメリットは以下の通りです。
- 地域ごとの多様なニーズへの迅速な対応が可能になる
- より広範囲な医療圏をカバーでき、患者数増加が見込める
- クリニックのブランド力向上に繋がる
- 精神科、歯科など専門分野ごとの分院展開により、診療体制を強化できる
- 同一法人内でのレセプト処理等が可能となり、事務業務の効率化が期待できる
- 業務効率の向上とそれに伴う収益性の確保が期待できる
分院の開設は、地域貢献の拡大と経営基盤の強化の両立を実現する有効な選択肢と言えるでしょう。
分院開設のデメリット
一方で、以下のようなデメリットも考慮に入れる必要があります。
- 設備投資や人件費、維持費などコストが増加する
- 人的リソースの確保が困難な場合がある
- 提供する医療サービスの質を全拠点で均一に保つことが難しい(教育体制の構築が不可欠)
- 財務・人事を含む経営管理が複雑化する
- 集患が計画通りに進まない場合の赤字リスクが生じる
- 事務手続きや人事など、院内ルールの統一が必要となる
こうしたメリットとデメリットをしっかり把握し、冷静かつ戦略的に準備を進めることが、分院開設の成功には不可欠です。
分院を検討する適切なタイミングや必要な条件とは
分院開設を検討する適切なタイミングや条件としては、以下のような状況が挙げられます。
【患者ニーズ】
- 本院の患者数が増加し、診療体制に余裕がなくなってきた場合
- 本院の診療圏外の遠隔地に、一定の医療ニーズが存在する場合
- 競合クリニックが少ないエリアへ進出したい場合
【クリニック側の状況】
- 分院の運営を任せられる信頼できるスタッフ(医師や管理者)がいる場合
- 精神科や歯科など、特定の専門分野を強化・展開したい意向がある場合(本院で十分な教育・準備期間を経ることが望ましい)
適切なタイミングを図る上で重要なのは、一時的な需要に反応して分院を開設するのではなく、将来的な人口動態や医療需要の変化を見越した冷静かつ綿密な市場調査を行うことです。こうした長期的な視点こそが、分院展開の成否を左右します。
専門分野外への展開を模索するクリニックが増加中
近年、専門分野外への展開を目指すクリニックから「訪問診療を始めたい」という相談が増加傾向にあります。 例えば、美容系クリニックや皮膚科クリニックが、新たな収益の柱として訪問診療への参入を検討するケースなどです。 こうしたクリニックからは、訪問診療のノウハウに関する支援のニーズが高い状況です。
分院開設の流れ
分院開設の一般的な流れは以下の通りです。
- 企画・立案: 開設の目的、基本方針の策定
- 市場調査: 詳細なエリア分析、ニーズの把握
- 物件選定: 立地条件、規模、賃料などを考慮
- 事業計画策定: 収支計画、人員計画などを含む具体的な計画を策定
- 資金調達と設備計画: 事業計画に基づき、必要な資金を確保し、医療機器や什器などを計画
- 行政手続き: 医療法人の定款変更(※、保健所や厚生局などへの各種申請・届出。
【個人クリニックの場合】
分院を開設するには、まず医療法人化し、その法人のもとで新たに分院を設立する必要があります。医療法人化の際には、個人診療所を廃止し、法人立の診療所を新たに開設する手続きが必要です。手続きには都道府県、保健所、法務局、厚生局など複数の機関への申請が含まれます。 - 人材採用と配置計画: 医師、看護師、事務スタッフなどの採用と適切な配置
- 内装工事・インフラ整備: 必要に応じて内装工事を実施し、ネットワーク環境なども整備
- 医療機器・IT機器準備: 診療に必要な医療機器や電子カルテ等の準備
- 地域住民・関係機関へのアナウンス: 内覧会の開催やホームページでの告知など
準備開始から開設までには、通常1年程度の期間を見込む必要があります。 特に法的手続きは煩雑で時間を要するケースが多く、たとえば東京都の場合、定款変更だけでも3か月程度かかります。分院開設時は個人クリニックの新規開業より手続きが複雑となる場合が多くあります。
医療法人における定款とは、医療法人における名称や所在地などの基本的な情報に加え、クリニックの運営に関連するさまざまなルールが定められたものです。分院開設する場合は定款内容が変更となるため、「定款変更」という手続きが必要となります。
分院のエリア選定のポイント
分院の立地を選ぶ際に重要な指標・データは?
開業エリアの選定は、分院開設の成否を左右する極めて重要な要素です。 以下のような指標やデータを基に、慎重な検討が求められます。
- 人口統計: 厚生労働省などが公表する、地域の人口構成、将来推計など
- 疾患傾向: 行政や医師会などが保有する、地域における特定の疾患の罹患率や有病率などのデータ(自身のクリニックの強みと照らし合わせる)
- 競合状況: 特に都市部では競合クリニックが多いため、広範囲な視点での調査が必要
- 1日あたりの見込み患者数: 人口分布や年齢構成、診療圏の距離などを考慮して予測
しかし、重要な指標をすべて自分たちだけで調査・把握するのは、現実的にはなかなか難しいものです。
だからこそ、専門的な視点から地域特性や医療ニーズを分析する、訪問診療に特化した診療圏調査の活用をおすすめします。一般クリニック向けの診療圏調査やインターネット上の簡易調査では把握が難しい、訪問診療特有のニーズや患者分布などの指標を精度高く捉えることが可能です。
現在のクリニックとの距離感や、訪問エリアの重複・分離についてはどう考えるべき?
まずは本院の院長の意向に基づき、本院と分院それぞれの訪問エリアの範囲を明確に定めておくことが重要です。 今のリソースでどのくらいの範囲・人数の患者を診療できるのかというのをしっかりと把握しておきましょう。
無闇に広範囲をカバーしようとすると、移動効率の低下やスタッフの負担増を招き、分院開設のメリットが薄れてしまう可能性があります。
分院開設における人員確保のポイント
分院立ち上げに必要な最小限の人員体制とは?
分院を立ち上げるために最低限必要な人員体制は以下の通りです。ただし、これはあくまで立ち上げ時の目安であり、継続的な運営には更なる充実が求められます。
- 医師: 最低1名(週3日以上の常勤が目安だが、週5日が望ましい)
- 看護師: シフト制を組む場合、2名以上
- 医療事務: 1名(運転業務を兼務できると、より効率的)
このほか、運転専門のスタッフや、診療アシスタントのような医師や看護師の業務をサポートする職種の導入も有用です。 人手不足の場合は、レセプト業務などの一部業務を外部委託したり、タスクシフトを進めたりすることも検討すべきでしょう。
院長候補やコア人材は内部登用すべきか、外部採用すべきか?
分院の院長候補や中心となる人材の確保には、内部登用と外部採用それぞれにメリットとデメリットがあります。
内部登用
- メリット:
・法人の理念や運営方針への理解が深く、スムーズな立ち上げが期待できる
・既存スタッフとのチームワークが円滑で、信頼関係が既に構築されている - デメリット:
・本院の戦力が一時的に低下する可能性がある(後任者の育成が必要)
・リーダーシップやマネジメント経験が不足している場合、事前の教育・研修が不可欠
外部採用
- メリット:
・新しい視点やアイデア、異なる組織でのマネジメント経験などを取り込める可能性がある
・新院長が、以前の勤務先から信頼できるスタッフを伴って異動してくるケースもある
・本院の人員体制を維持したまま分院展開が可能 - デメリット:
・法人の理念や方針の共有、浸透に時間を要する場合がある
・期待した能力や人物像とのミスマッチが生じるリスクがある
・採用コストが発生する
理念や診療方針を円滑に浸透させるには、院長の発信力だけでなく、事務部門による組織的なマネジメント支援が不可欠です。
当社では、訪問診療クリニックにおけるスタッフマネジメント支援や組織力強化の観点からもサポートを行っており、分院開設にあたっての円滑な立ち上げを支援しています。
分院マネジメントのポイント
分院の経営やマネジメントを円滑に進めるためには、以下の点が重要となります。
- 院長のリーダーシップ: 分院長がクリニックの理念や目的を明確にスタッフへ発信し、浸透させる
- 組織文化の醸成: クリニックの組織文化を、トップダウンで形成するのか、あるいはスタッフ全員でボトムアップ的に作り上げていくのか、初期段階で方針を明確にする
- 信頼関係の構築: 分院長とスタッフ間、またスタッフ同士の良好なコミュニケーションと信頼関係を築く
- 役割と責任の明確化: 分院長および各スタッフの役割と責任範囲を明確に伝える
- 収支管理意識の徹底: 目標となる経営指標を定め、分院長やスタッフとその意識を共有する
これらのポイントを意識しながら分院のマネジメントに取り組むことで、本院との連携を保ちつつ、分院としての自立と成長を促すことができます。分院は単なる「拠点のひとつ」ではなく、地域医療における重要な担い手として機能させるためにも、組織全体での意識統一と戦略的な運営が求められます。
分院の収支モデル
初年度の収支見込みはどう見積もるべきでしょうか?
分院開設初年度からの黒字化は、一般的に難易度が高いとされています。 そのため、中長期的な視点に立ち、どのように患者数を増やしていくのか、具体的なシミュレーションに基づいた人員計画や資金計画を策定することが不可欠です。
収益モデルは、立地する地域の特性(都市部か地方か、高齢化率など)や、患者層(既存クリニックからの移行か、完全な新規開拓か)によって大きく異なります。 そのため、事前の詳細な診療圏調査が極めて重要となります。
支出面では、主に医師やその他スタッフの人件費、物件の賃料、その他諸経費(医薬品費、消耗品費、水道光熱費など)に加え、開設準備にかかる初期費用(内装費、医療機器購入費、広告宣伝費など)が発生します。 年間の支出総額としては、2,500万円から3,000万円程度を見込んでおく必要があるでしょう。 どの段階で黒字化を目指すのか、具体的な目標患者数を設定し、それに向けて計画的に運営していくことが求められます。
分院開設時のコンサルタントについて
分院開設は自分でできますか?
院長ご自身で分院開設の準備を進めることも不可能ではありません。
しかし、本院の運営を行いながら膨大な準備作業を並行して進めることの時間的な制約、過去の開業経験だけでは対応しきれない現在の市場環境の変化、煩雑な法的手続きなど、多くの困難が伴う可能性があります。
分院開設時にコンサルタント支援を受ける場合のメリットとは?
分院開設にあたり、専門コンサルタントの支援を受けることには、以下のようなメリットがあります。
現実的かつ精緻な事業計画の策定支援
客観的な市場分析や収支予測に基づき、実現可能性の高い事業計画を策定することができます。過去の事例や専門的な知見を活かしたアドバイスにより、判断ミスを未然に防ぎます。
最新の市場動向・法規情報の提供
変化の激しい医療情勢や法制度、経済環境(物価上昇の影響など)を踏まえ、常に最新情報に基づいた計画立案と対応が可能になります。
業務効率化と時間の節約
煩雑な調査や手続きを委託することで、先生は診療や本院の運営といった本業に専念できます。
複雑な法的手続きのサポート
保健所・厚生局などへの申請や届出業務もサポートし、スムーズな手続き進行を支援します。
適切なスケジュール設計と進捗管理
分院開設までに必要なタスクを整理し、無理のないスケジュールで計画的な準備が進められます。
診療体制・組織構築の支援
スタッフマネジメントや組織力強化の観点からも支援を行い、開設後の円滑な運営をサポートします。
分院開設は多くの判断と準備を要する一大プロジェクトです。だからこそ、専門コンサルタントの知見と経験を活用することで、リスクを最小限に抑え、より確実で持続可能なスタートを切ることができます。開設後の成功を見据えた計画と持続可能な体制づくりのために、外部の専門的な支援をうまく取り入れることをおすすめします。
分院開設を成功させているクリニックの4つの共通点とは
分院を開設したものの、思うように患者が集まらなかったり、スタッフ運営が安定しなかったりといった課題を抱えるケースは少なくありません。一方で、着実に分院展開を進め、地域に根差した医療体制を築いているクリニックも存在します。その違いはどこにあるのでしょうか。
実際に分院開設を成功させているクリニックには、いくつかの共通した特徴があります。
院長の明確なビジョンと目的
成功しているクリニックでは、院長ご自身が「なぜ分院を開設するのか」「将来的にどのような医療機関を目指すのか」といった目的とビジョンを明確に持っています。経営判断や人材育成においてこのビジョンが軸となり、組織全体の方向性を統一する役割を果たしています。
持続可能性と医療の質を重視した体制づくり
短期的な利益や患者数の増加だけを追い求めるのではなく、提供する医療の質を維持・向上させることに注力しています。長期的に地域医療に貢献できる、持続可能な体制を構築する姿勢が、結果として安定した運営につながっています。
スタッフへの信頼と適切な権限移譲
分院長やスタッフに対して信頼を持ち、一定の権限を委ねることで、スタッフの主体性や責任感が高まります。現場での判断や対応がスムーズになり、組織としての柔軟性とスピード感のある運営が可能になります。
外部専門家の知見を積極的に活用
経営や開設準備を院長一人で抱え込まず、コンサルタントなどの外部専門家の意見や知識を取り入れています。第三者の視点を交えることで、主観に偏らず、より客観的かつ効率的に事業を進められる点も成功の大きな要因です。
これから分院開設を考える院長に向けて、最も伝えたいメッセージ
分院開設は、クリニックの成長と地域医療への更なる貢献を実現する大きな一歩となり得ます。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。成功のためには、本記事で触れたように、周到な準備と明確な戦略が不可欠です。
特に、長期的な視点に立った市場調査、明確なビジョンと目的意識、そしてそれを共有できる信頼できるスタッフの確保と育成は、分院開設を成功に導くための基盤と言えるでしょう。また、変化の激しい現代においては、先生お一人で全ての課題に対応することは困難な場合もあります。必要に応じて専門コンサルタントのような外部の力も借りながら、現実的かつ着実に計画を進めていくことをおすすめします。