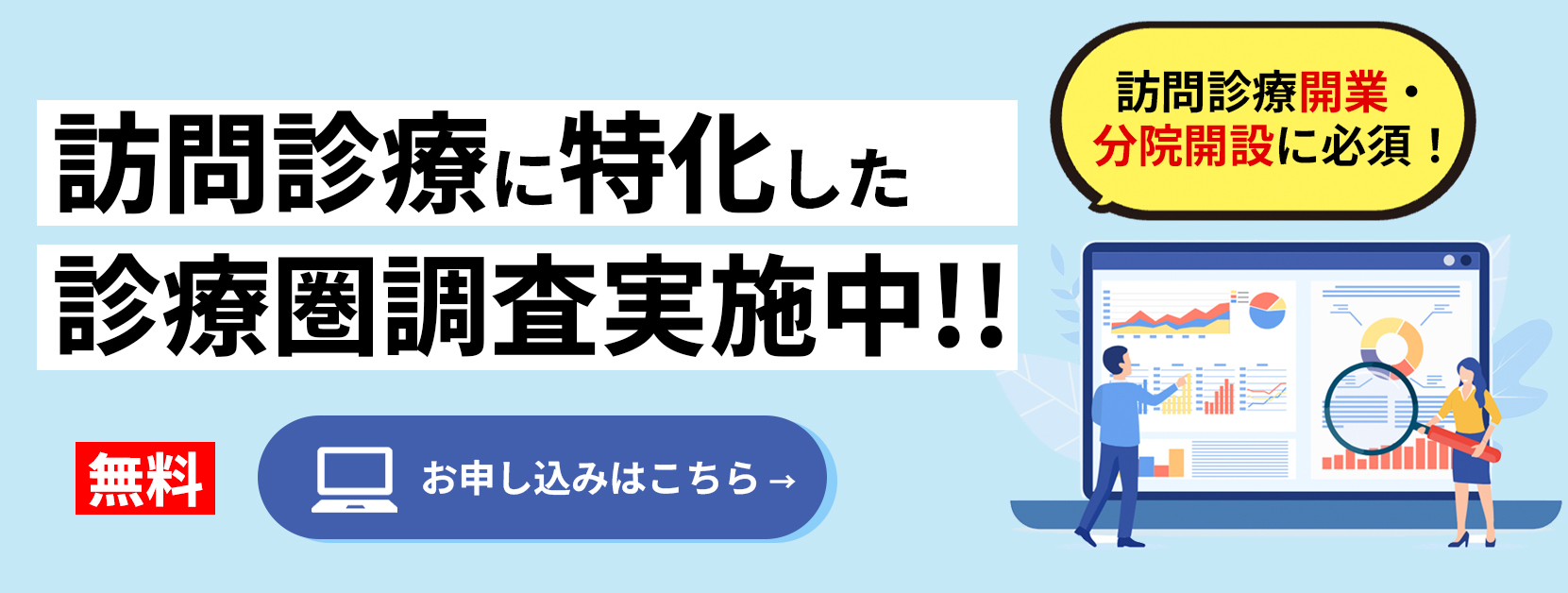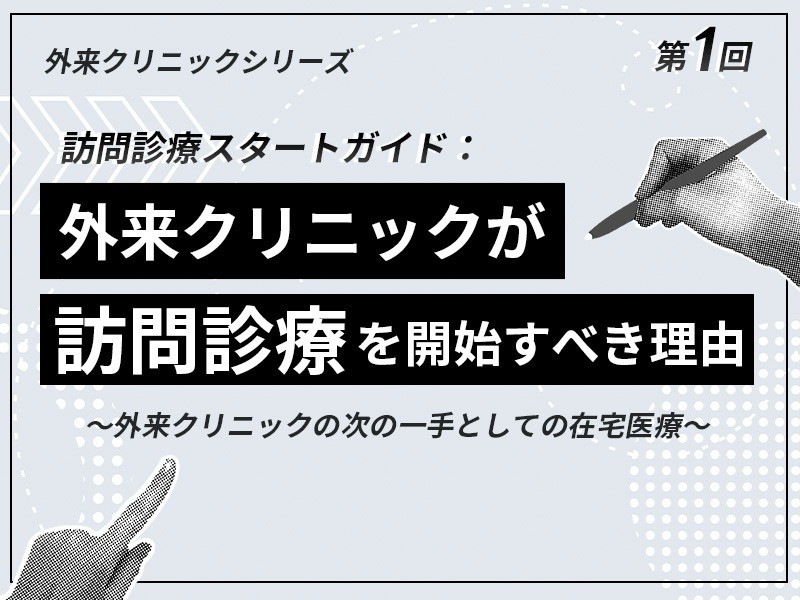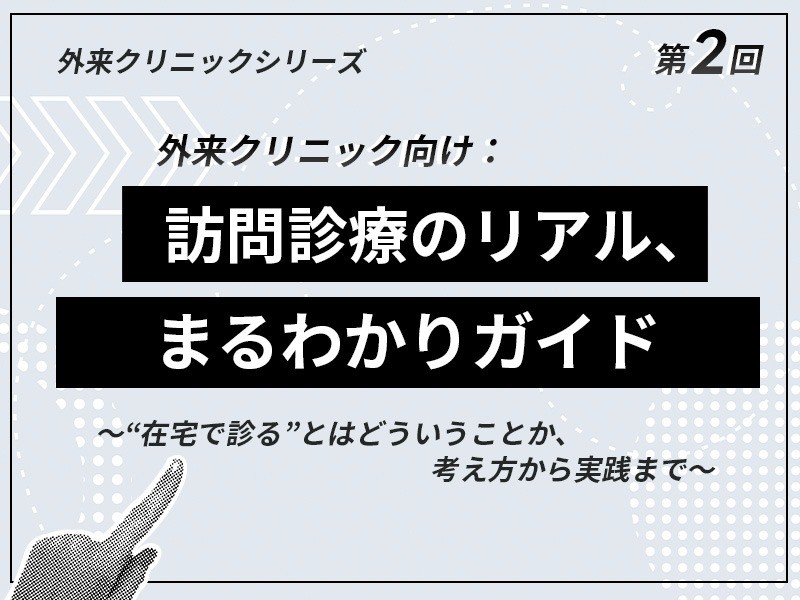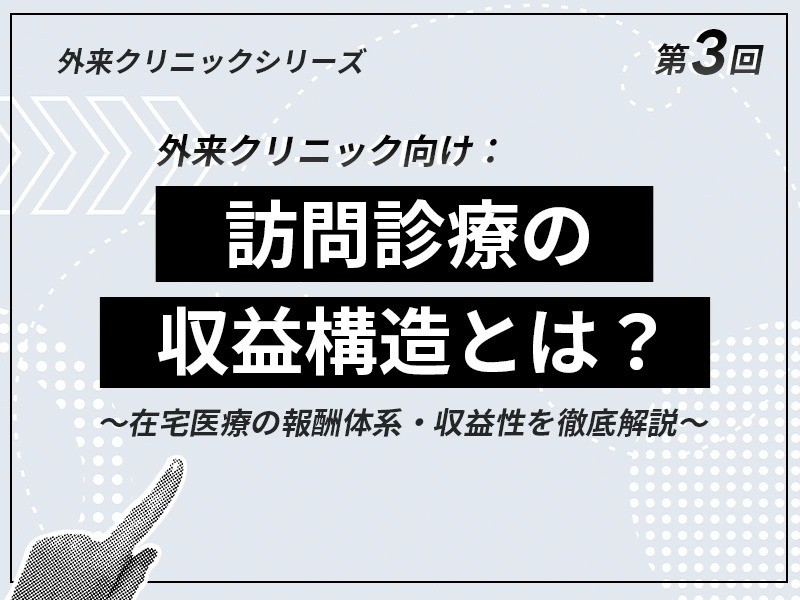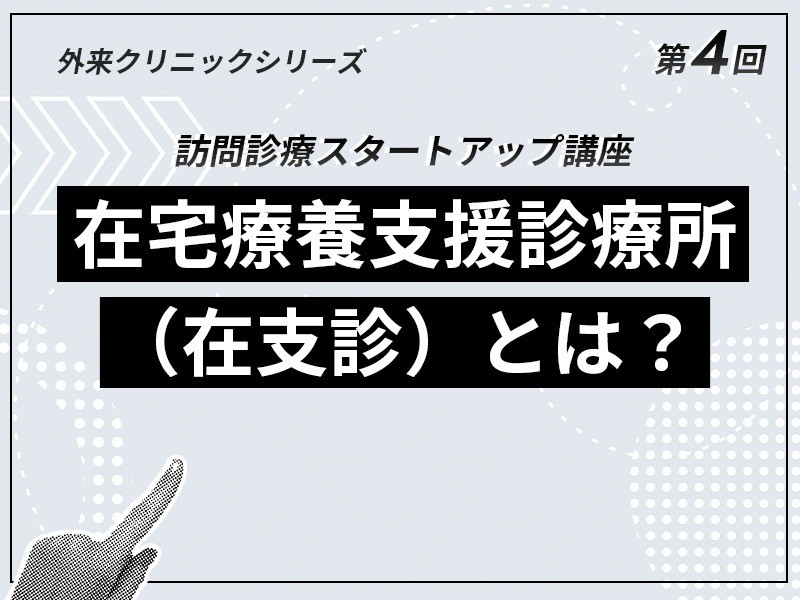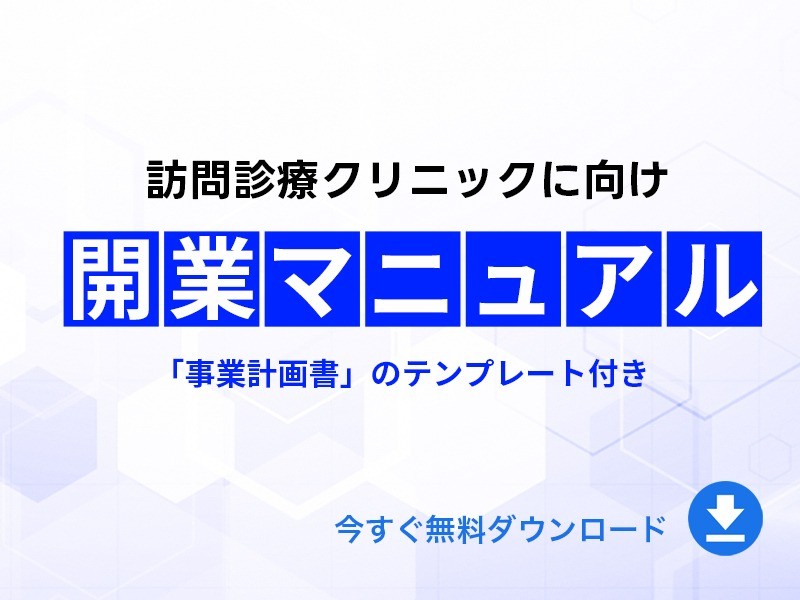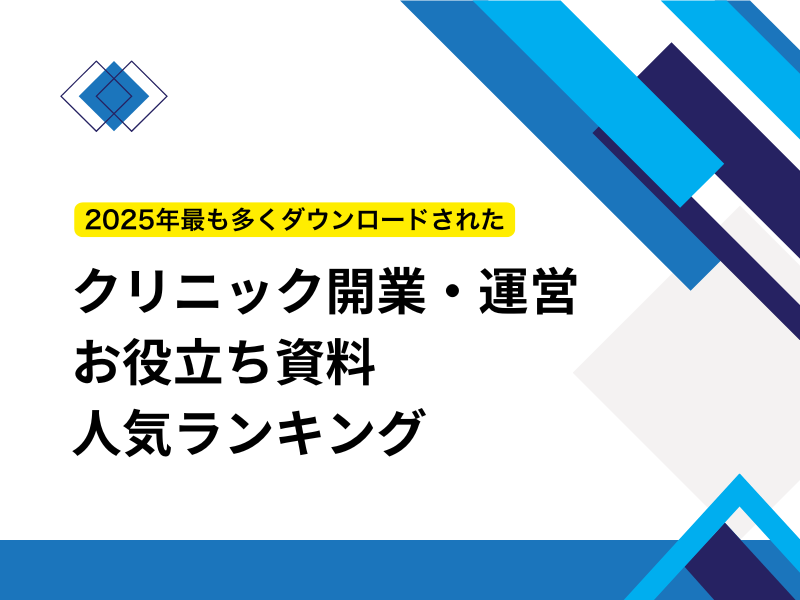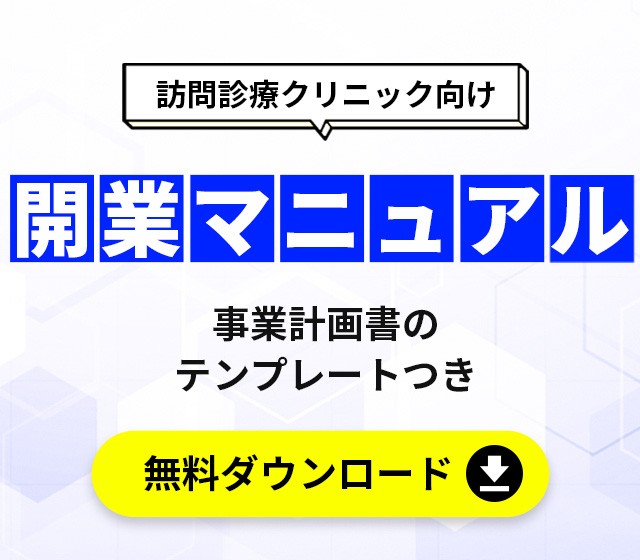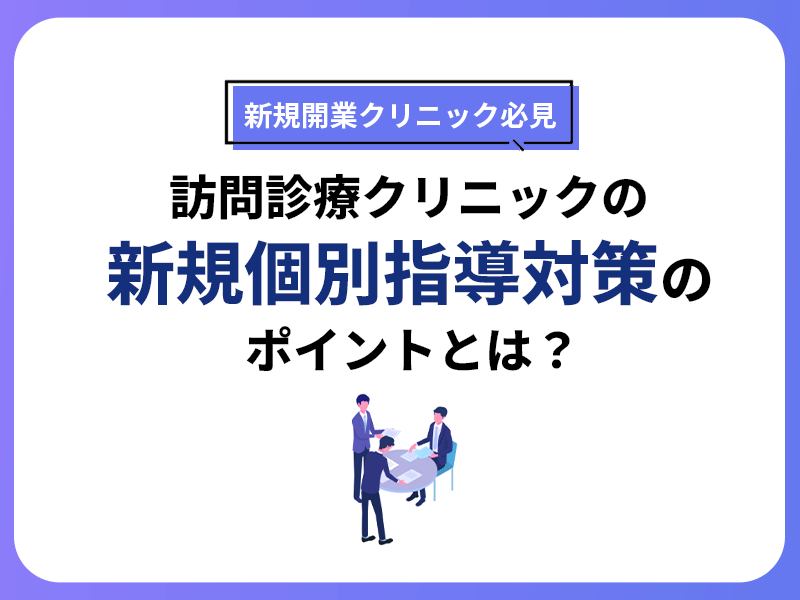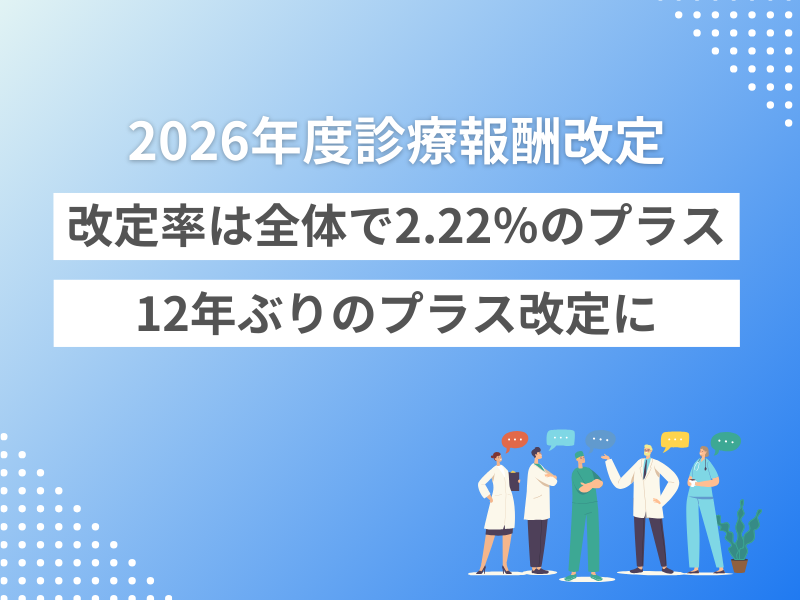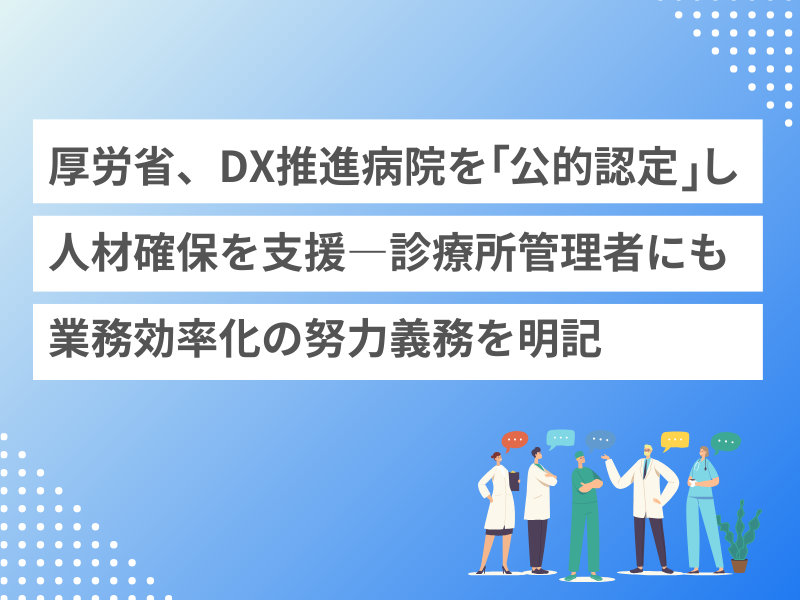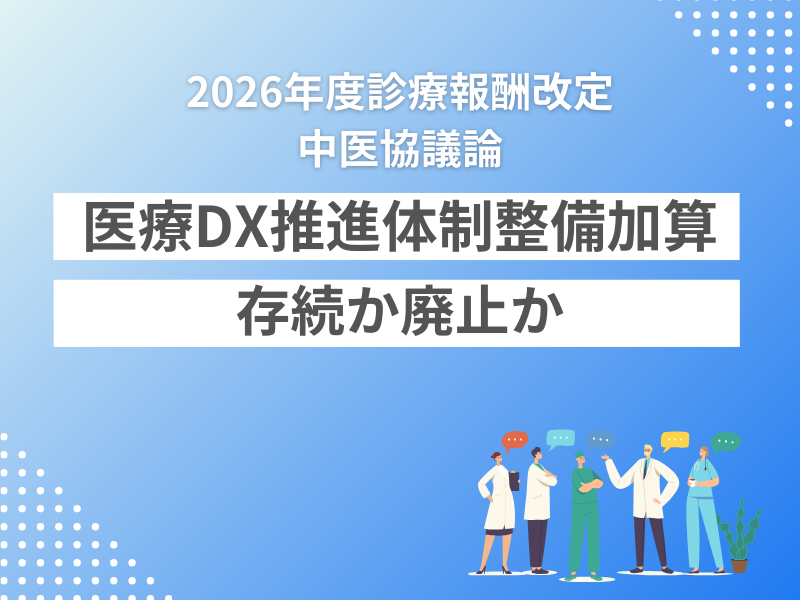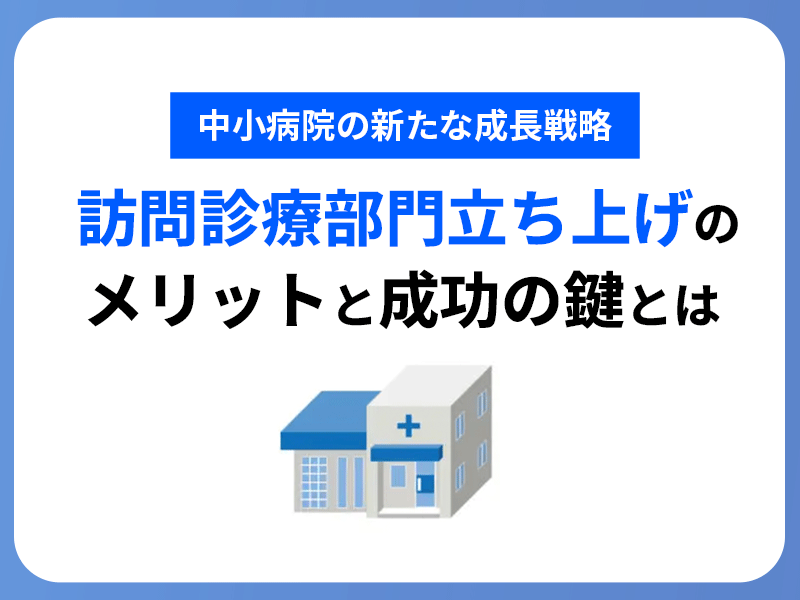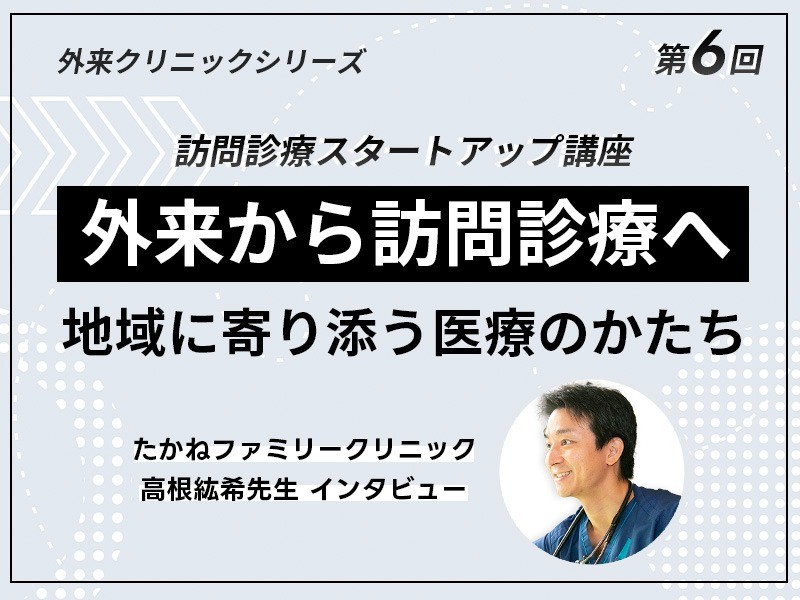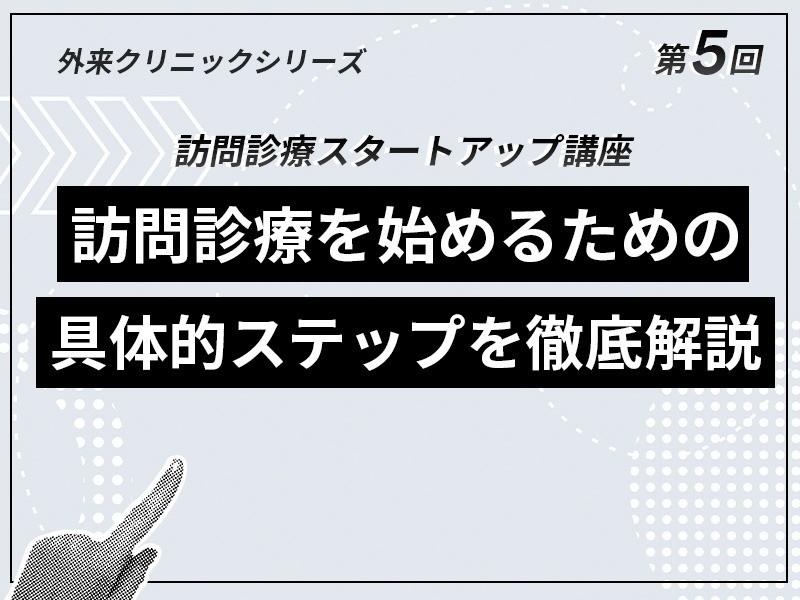- #開業
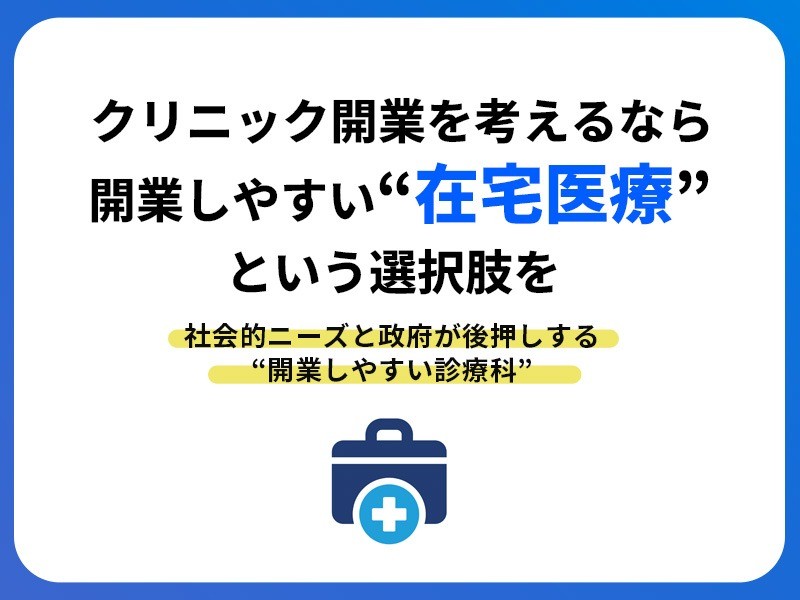
外来・入院診療を中心にキャリアを積んできた医師にとって、開業や独立は人生の大きな決断です。
そんな中、近年注目を集めているのが「在宅医療」の分野。
少子高齢化や医療ニーズの多様化により、地域社会に密着した医療提供のかたちとして、在宅医療クリニックの開業を選ぶ医師が増えています。
本記事では、なぜ今「在宅医療」が開業先として有望なのか、そのメリットを解説します。
高齢化社会が後押しする「在宅医療」ニーズの拡大
人生100年時代といわれる現代、医療に求められる役割は「治す医療」から「支える医療」へと大きくシフトしています。急性期治療に特化した病院中心の医療体制から、慢性疾患や高齢者医療を重視した地域密着型の医療体制への転換が、国レベルでも進められています。
こうした流れの中で注目されているのが「在宅医療」です。特に、加齢や病状によって通院が困難になった患者にとって、自宅で医師の診療を受けられる仕組みは、日常生活を維持しながら安心して療養できる選択肢として非常に重要です。また、病院での長期入院を避ける「地域包括ケア」の考え方とも親和性が高く、医療・介護を一体で支える体制として、ますますニーズが高まっています。
実際、厚生労働省のデータでも、在宅医療を必要とする高齢者人口は今後も右肩上がりで増加すると予測されており、地域によっては訪問診療の担い手が不足している状況も見られます。こうした背景から、在宅医療は“社会的ニーズの高い医療分野”として注目されており、開業を考える医師にとっても、有望なフィールドのひとつと言えるでしょう。
政策的にも「在宅医療」は中核的な位置づけに
政府は在宅医療を、高齢化社会に対応する“重要戦略”と位置づけ、地域包括ケアシステムの中核として推進しています。第8次医療計画(2024年度~)では、在宅医療の体制整備が重点項目とされ、2024年度の診療報酬改定でも評価が強化されました。
さらに、「在宅医療・介護連携推進事業」を通じて、医師会や自治体との連携体制づくりを財政的に支援。地域ごとに持続可能な在宅医療提供体制を構築する取り組みが全国で進められています。
初期投資を抑えて始められる事業モデル
一般的な外来クリニックを開業する場合、物件取得費や内装工事、医療機器の購入などに数千万円単位の初期投資が必要です。一方で、在宅医療では患者宅を訪問する形式のため、院内の設備は最低限で済み、開業資金を大幅に抑えることができます。
さらに、患者数や訪問件数をコントロールしながら、スモールスタートで運営できる点も魅力です。
近年では、訪問診療に特化した事務代行やコールセンター、ICTツールの活用により、少人数でも負担なく運営できる仕組みも整ってきています。
■あわせて読みたい
訪問診療におけるミニマム開業とは?メリットや成功のポイントを解説!
安定した収益構造も、在宅医療の大きな魅力
訪問診療は、外来診療とは異なり、「月額制+加算型」の診療報酬体系が採用されているため、収益が安定しやすいという特長があります。これは、定期的に訪問する前提で報酬が設計されている在宅医療ならではの仕組みです。
たとえば、居宅の患者1人あたりの月間診療報酬は平均で5〜6万円前後、施設患者では2〜3万円前後が相場です。実際の金額は、各種加算などの取得状況によって変動しますが、1人の患者から安定した収入が継続的に得られる点が大きなメリットです。
これは、1回あたりの診療で約5,000円前後が一般的な内科外来に比べ、1人あたりの収益単価が圧倒的に高いことを意味しています。
このような報酬構造により、訪問診療は以下のような経営上の利点があります。
- 患者数が比較的少なくても、事業として成立しやすい
- 訪問件数を調整すれば、収益と労働負担のバランスを取りやすい
- 季節変動や突発的な混雑に左右されにくく、計画的な経営が可能
さらに、看取りや医療依存度の高い患者が増えると、月間診療報酬が8〜10万円に達することもあり、地域ニーズに応じた体制構築で、より高い収益性を実現できる可能性もあります。
医師としての“やりがい”を実感できる医療現場
在宅医療の現場では、医師が診るのは患者さんの“病気”だけではありません。自宅という生活の場に足を運ぶからこそ、患者さんの暮らしや家族の思い、介護を支えるスタッフの苦労や工夫など、医療だけでは完結しない「人間の営み」そのものと向き合う機会が日常的にあります。
医師は、ケアマネジャーや訪問看護師、薬剤師、リハビリ職、介護スタッフなど、多職種と密に連携しながら診療にあたります。その中で、単なる「処方や処置」ではなく、「この人がどう生きたいのか」「家族はどう支えたいのか」といった背景を踏まえて判断し、支援していく必要があります。
そのため、在宅医療では「医師がすべてを指示する立場」ではなく、チームの一員として、人と人との信頼関係を築きながら医療を届けていくスタイルが求められます。
「病気を診る」のではなく、「人を診る」——
そんな医療の原点に立ち返れるのが、在宅医療ならではの醍醐味です。
ときには、長年関わってきた患者さんを自宅で看取ることもあります。そこには、“最期までその人らしく生きる”ことを支える深いやりとりと、医師としての使命感と感謝の気持ちが交錯する、他にはない経験があります。
こうした現場に身を置くことで、「自分が医師になった原点は何だったのか」「医療とは誰のためにあるのか」といった問いに、もう一度向き合える時間が増えていきます。
在宅医療は、患者さんの人生に触れながら、自分の医師としての在り方を見つめ直せる、非常に豊かな医療のかたちです。
自分らしいワークライフバランスを実現しやすい
訪問診療は基本的に予約制で行われるため、1日のスケジュールをあらかじめ組み立てやすいという特徴があります。外来のように、急な混雑や診察待ちのプレッシャーに追われることが少なく、時間の見通しが立てやすい点は大きなメリットです。
また、訪問ルートや訪問件数も自分たちの体制に応じて柔軟に調整できるため、過剰な長時間労働になりにくく、「どれくらい働くか」も自分でコントロールしやすい働き方といえます。
このように訪問診療は、医師自身の価値観やライフステージに合わせて、柔軟で持続可能な働き方を実現しやすい診療スタイルといえるでしょう。
24時間対応が不安?実はハードルは下げられます
在宅医療では、診療報酬の算定要件に「24時間対応体制」が求められるケースがあります。そのため、「夜間も休日もずっと対応し続けないといけないのでは…」と不安に感じる医師も少なくありません。
しかし実際には、すべての訪問診療クリニックが“完全自前で24時間対応している”わけではなく、体制の組み方には柔軟な選択肢があります。
代表的な対応パターンは、次の3つです。
- 自院だけで完結(24時間自前体制)
医師やスタッフを交代制にするなどして、365日・24時間の対応を自院内で完結させる方法です。中規模〜大規模クリニックで採用されることが多いです。 - 夜間・休日のみ他院と連携(輪番・協力医師制)
夜間や休日など、平日日中以外の時間帯のみ、近隣の在宅医療機関や協力医師と連携して当番制で対応するパターンです。医師同士で役割分担することで、無理のない運営が可能になります。 - 夜間オンコール代行サービスを活用
最近では、夜間・休日のコール対応やトリアージ、訪問の初期判断を代行する外部サービスも登場しており、これを利用することで日中の訪問診療に専念できる体制を整えるクリニックも増えています。夜間訪問を外部医師に依頼する連携サービスを利用したり、非常勤医師と契約して対応するケースもあります。
このように、訪問診療における「24時間対応」は一律の負担を強いるものではなく、自院の体制・人員・方針に合わせて設計できる柔軟な仕組みになっています。
「在宅医療をやってみたいけど、24時間対応がネックで…」と感じている方も、最初からすべてを抱え込む必要はないという点をぜひ知っておいてください。
今注目されている「ミニマム開業」
ミニマム開業は、開業時の投資を最小限に抑え、少人数で運営するクリニックの形態です。家賃や人件費といった固定費を軽減できるため、経営の安定性が高まります。
通常のクリニックでは広い診察室や高額な医療機器が必要で、スタッフも多く必要となるため固定費が大きく、一定の患者数を確保しなければ収益維持が難しくなります。一方、ミニマム開業では、診療スペースや医療機器を必要最小限にし、医師一名と最小限のスタッフで運営可能です。
訪問診療は特にミニマム開業と相性が良く、大規模設備が不要なため初期投資を抑えられます。また、レセプト業務など専門的な事務は外部委託することで、少人数体制でも持続可能な経営が可能です。
ミニマム開業のメリットとしては以下の通りです。
- 少ない開業資金で始められる
- 分の理念を反映し、柔軟性がある運営ができる
- 採用やスタッフマネジメントの負担軽減
ミニマム開業は、初期投資や運営負担を抑えつつ、自分らしい診療スタイルを実現できる、これからの訪問診療クリニック開業の新しい選択肢と言えるでしょう。
ミニマム開業を成功させるための3つのポイント
ミニマム開業を成功させるには、以下の3つのポイントが重要です。
開業場所の選定と診療圏の分析
地域の高齢化率や要介護者数、競合クリニックの有無などを確認し、訪問診療のニーズを把握します。介護施設や連携先となる訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所などの分布も調査しておくと、診療圏設定がより適切になります。客観的データをもとに開業場所を選ぶことが、安定運営の第一歩です。
地域の医療機関との連携
小規模クリニックでは24時間対応の負担を軽減するため、周辺の訪問診療クリニックや訪問看護ステーション、緊急受け入れ病院との協力体制を構築することが重要です。
ネットワークを整えることで、訪問診療の質向上と患者・家族の安心につながります。
効率的な運営体制の構築
訪問診療では移動や連絡調整など、診療以外の業務も多いため、BPOサービスの活用が有効です。
電話代行サービスやレセプト代行サービスを利用すれば、医師やスタッフは診療に集中でき、業務負担を軽減できます。
こうした仕組みを取り入れることで、少人数体制でも安定したクリニック運営が可能になります。
>>電話代行サービスについて詳しくははこちら
>>レセプト代行サービスについて詳しくはこちら
これらのポイントを押さえ、地域に根ざしたネットワークと効率的な運営体制を整えることで、ミニマム開業でも安定した訪問診療クリニックの運営が実現できます。
あなたの次のキャリアに「在宅医療」という選択肢を
将来の独立・開業を見据える医師にとって、在宅医療は高齢化社会の中で大きな可能性を持ったフィールドです。
やりがいのある診療と、安定した収益モデルの両立が見込めるこの領域で、一歩を踏み出してみませんか?