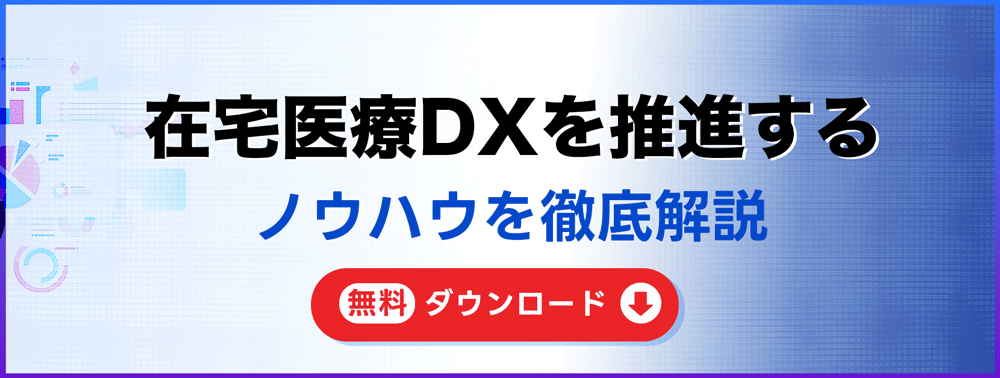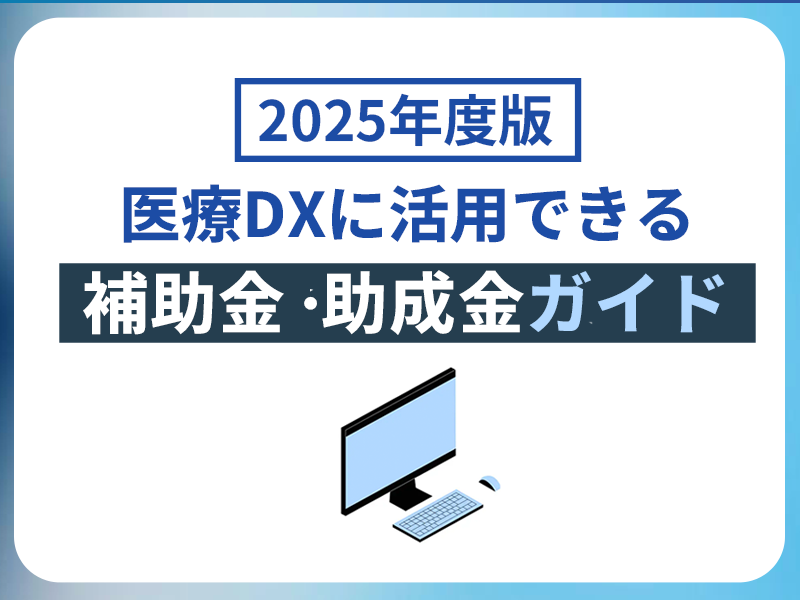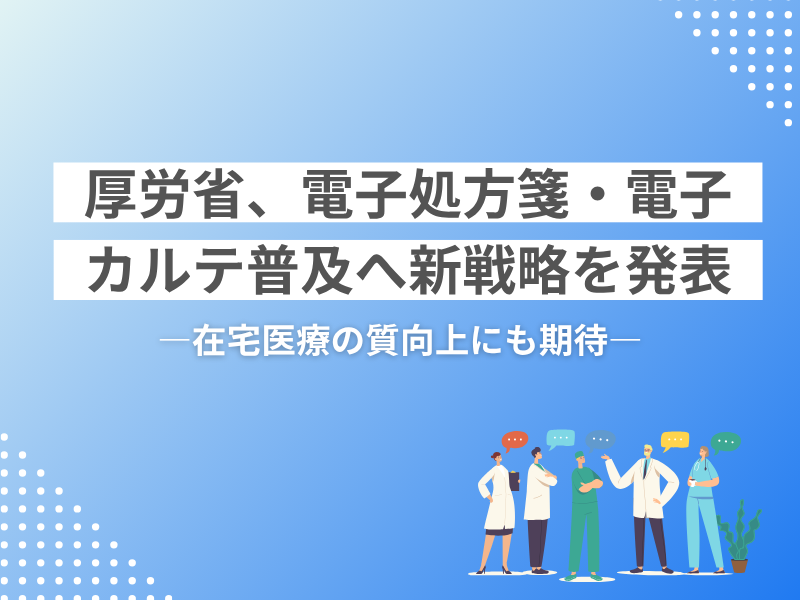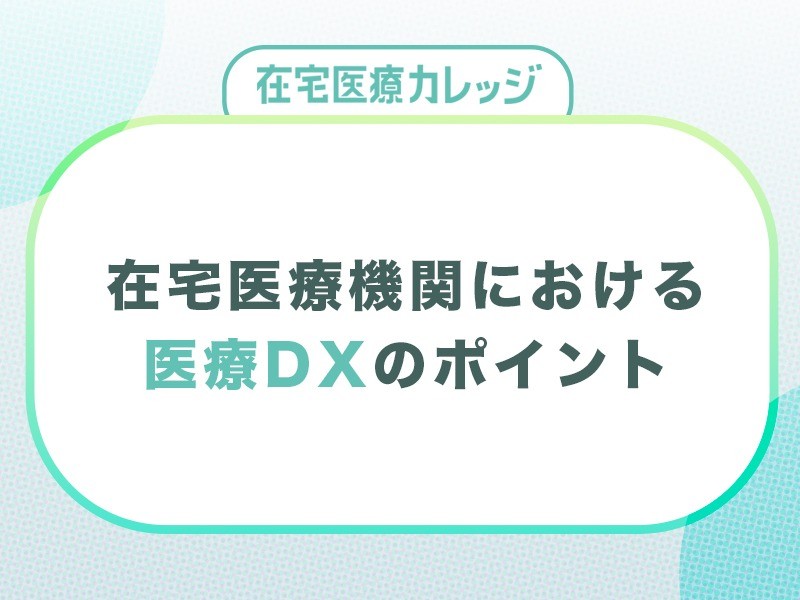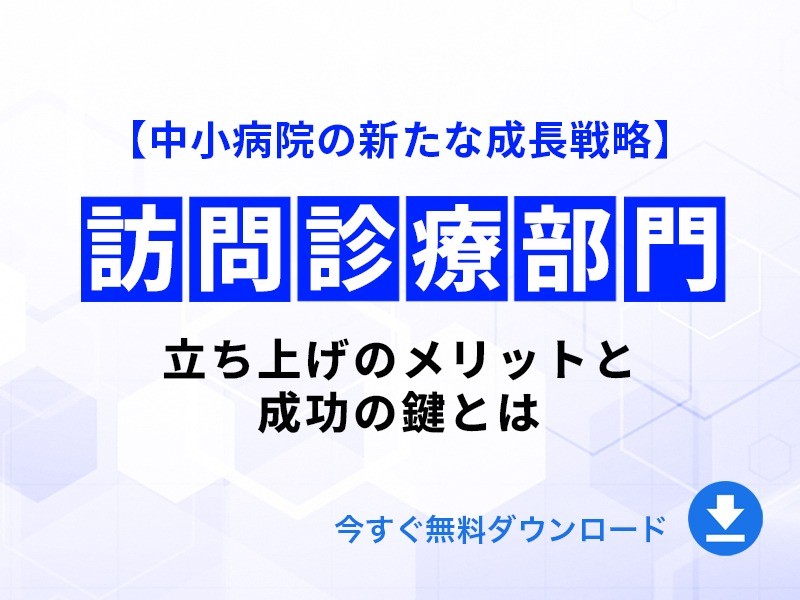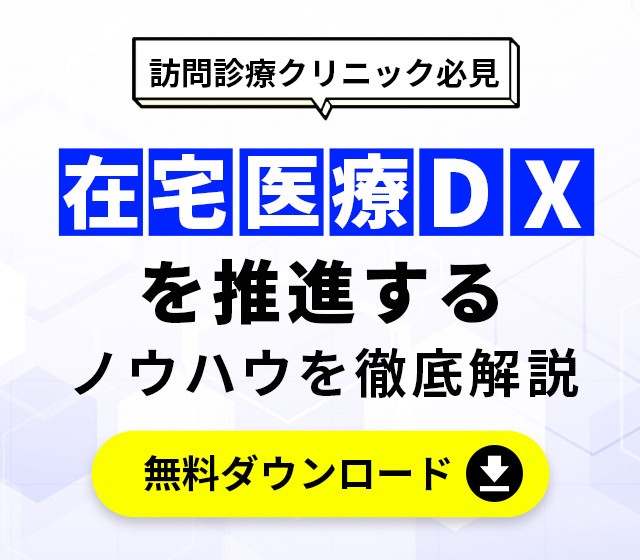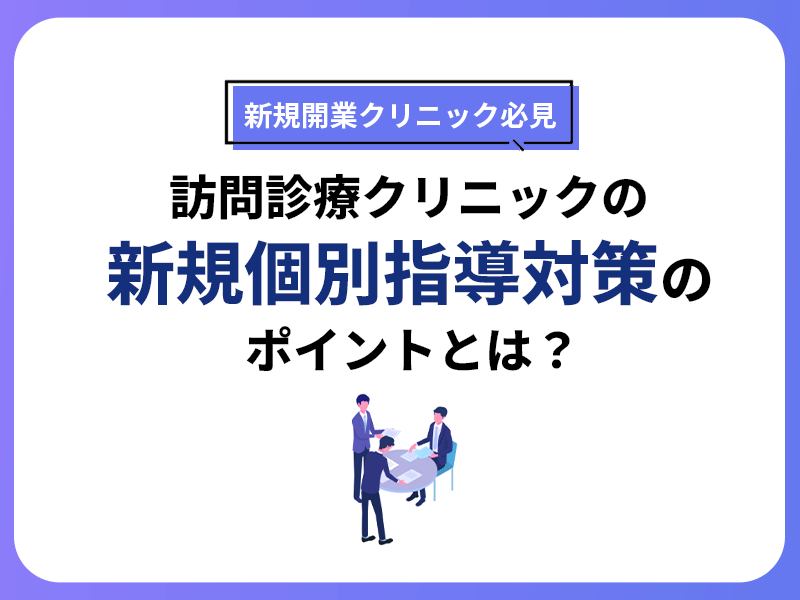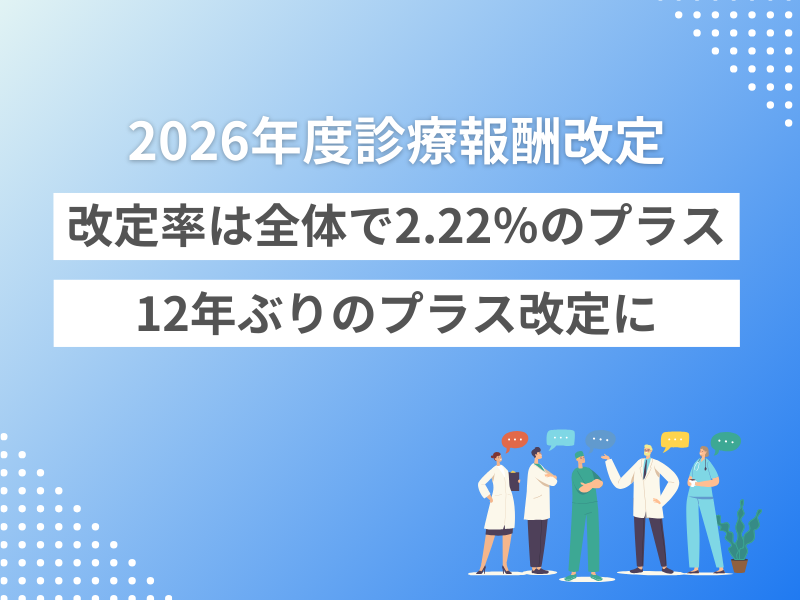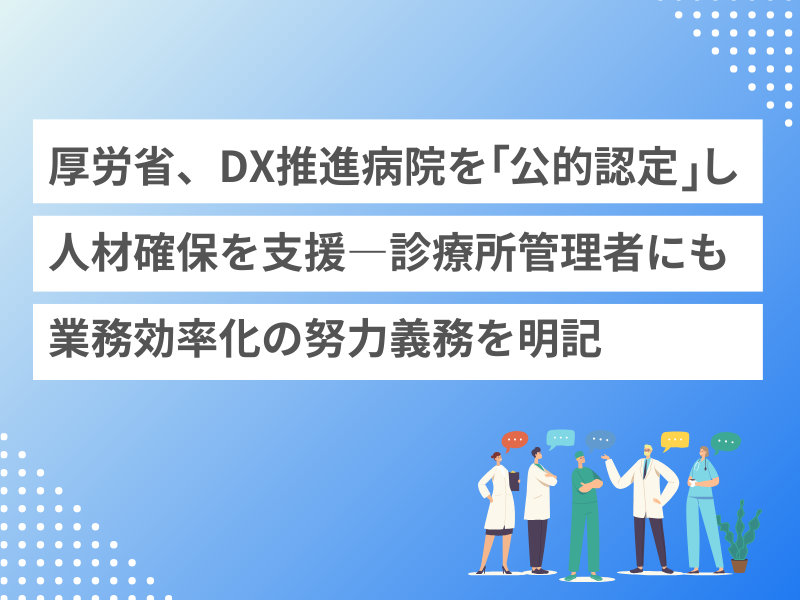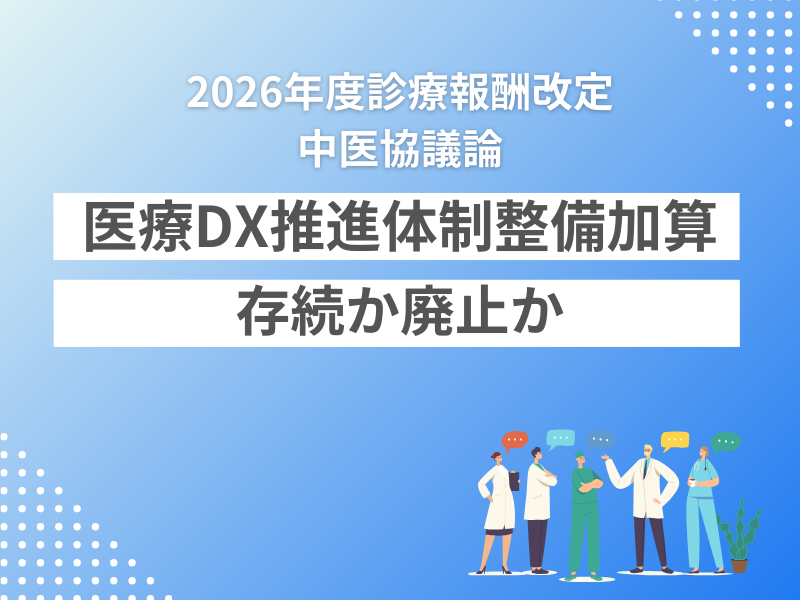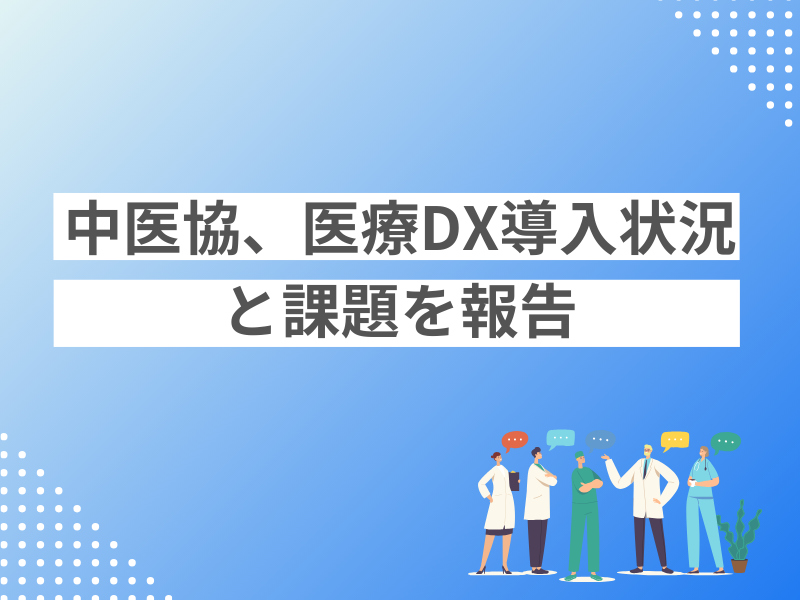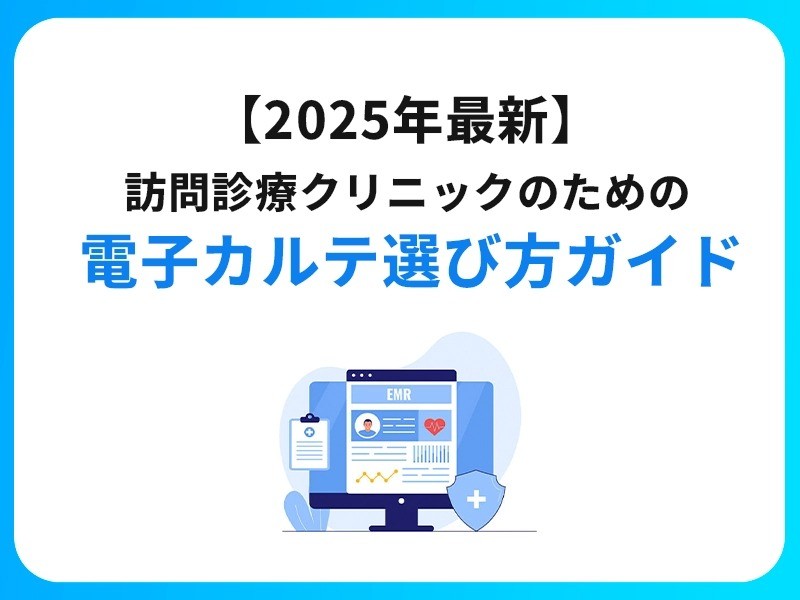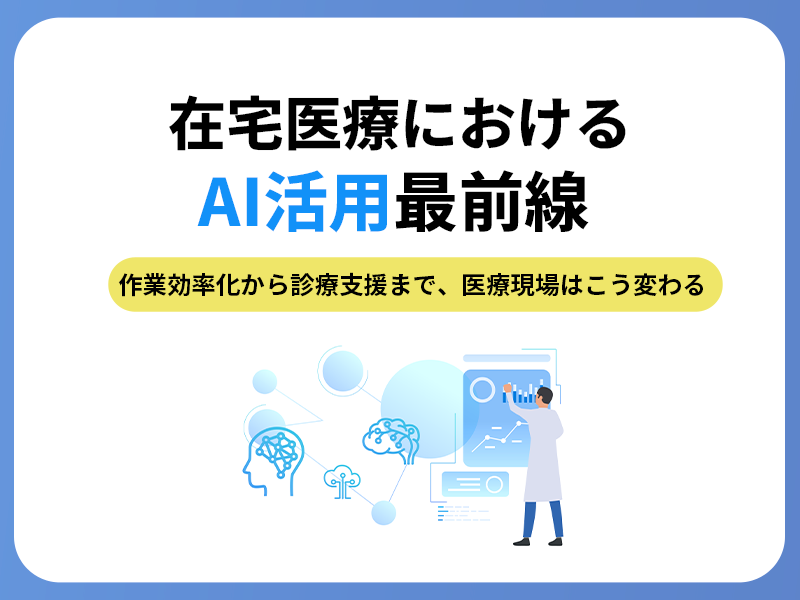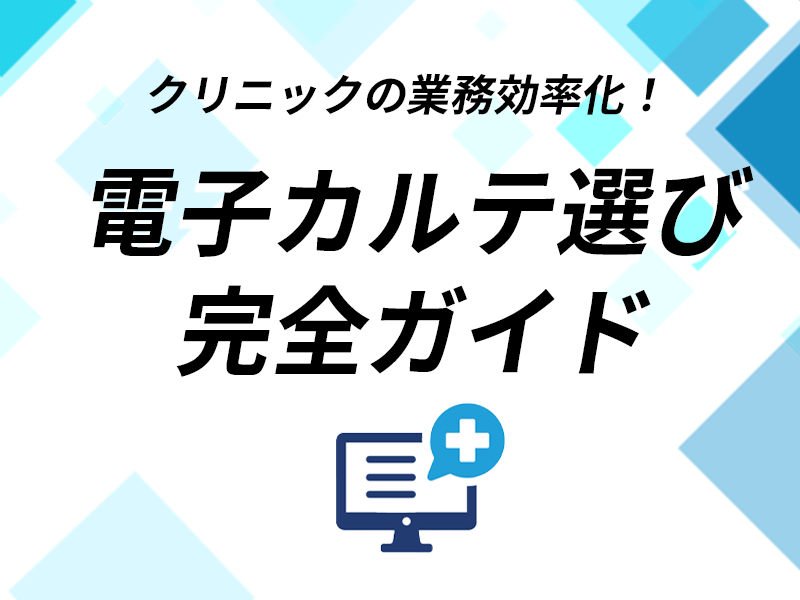- #DX
- #運営

2030年に向けて、日本の医療は大きな変革期を迎えています。
「医療DX令和ビジョン2030」―この言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
本記事では、在宅医療従事者の皆様に向けて、このビジョンの全体像と、特に在宅医療に与える影響、そして「今から何をすべきか」を分かりやすく解説します。
■あわせて読みたい
医療DXに活用できる補助金・助成金ガイド【2025年度版】
「医療DX令和ビジョン2030」とは?
「医療DX令和ビジョン2030」とは、政府が主導し、デジタル技術を活用して医療現場の課題を解決し、国民一人ひとりがより質の高い医療を受けられる社会を目指すための国家戦略です。2022年5月に自由民主党政務調査会により提言されました。
このビジョンが策定された背景には、新型コロナウイルス感染症への対応で浮き彫りになった、医療機関間の情報連携の遅れや、医療従事者の業務負担の増大といった課題があります。これらの課題を克服し、来るべき超高齢社会においても持続可能な医療提供体制を構築することを目指しています。
ビジョンが掲げる目標は大きく3つです。
- 国民の健康増進:患者自身が自分の医療情報にアクセスし、健康管理に活かせるようにする。
- 医療現場の業務効率化:デジタル技術の活用により、診療の質の向上や業務負担の軽減を目指す。
- IT人材の有効活用:医療分野でIT人材を有効活用し、医療DXを推進する。
この壮大なビジョンを実現するため、政府は以下の3つの具体的な施策を柱として進めています。これらは訪問診療クリニックの運営にも密接に関わってきます。
- 「全国医療情報プラットフォーム」の創設
- 電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討
- 診療報酬改定DX
ここからは、「医療DX令和ビジョン2030」を実現するための上記の3つの施策について、それぞれの目的やこれまでの政府の動向、今後の見通し、さらには在宅医療の現場にどのような影響をもたらすのかを解説していきます。
1.「全国医療情報プラットフォーム」の創設
これは、全国の医療機関、薬局、そして将来的には介護事業所などが、分断されていた患者情報を安全かつ円滑に共有するためのプラットフォームです。いわば、医療情報が全国を行き交うための高速道路網を整備する事業と言えます。
目的と仕組み
このプラットフォームの目的は、患者がどの医療機関にかかっても、過去の診療情報や薬剤情報、アレルギー情報などを正確に共有し、切れ目のない質の高い医療を提供することです。救急時や災害時にも、迅速かつ的確な治療を可能にします。
その基盤となるのが、2023年4月から導入が原則義務化された「オンライン資格確認システム」です。マイナンバーカードを健康保険証として利用するこの仕組みが、プラットフォームへの「入口」となり、患者本人の同意を「鍵」として、必要な情報にアクセスすることを可能にします。
このプラットフォーム上で提供される主要なサービスと動向は以下の通りです。
電子処方箋(2023年1月〜運用開始)
紙の処方箋を電子化するだけでなく、複数の医療機関や薬局で処方・調剤された薬剤情報を一元的に参照できる仕組みです。これにより、訪問診療で特に問題となりやすい高齢者の重複投薬やポリファーマシー(多剤併用)のリスクを、処方時点で正確に把握し、回避することが可能になります。
電子カルテ情報共有サービス(2025年度〜本格稼働予定)
他の医療機関が作成した診療情報提供書(紹介状)や、健診結果、患者の6情報(処方情報・検査・傷病名・感染症・薬剤アレルギー・その他アレルギー)を、全国の医療機関が電子的に共有・閲覧できるようになる仕組みです。
在宅医療への影響
これまで電話やFAXで行っていた他院への情報照会や、患者が持参する紹介状に頼っていた情報収集が劇的に変わります。特に、訪問先でタブレット端末などを用いて患者の同意を得て情報にアクセスできる「居宅同意取得型」のオンライン資格確認の仕組みは、訪問診療にとって革命的です。初診の患者宅でも、その場で過去の正確な医療情報を確認し、質の高い診療計画を立てることが可能になります。
将来的には、このプラットフォームは介護情報基盤とも連携することが計画されており、ケアマネジャーや訪問看護ステーションとの情報共有もデータレベルで実現され、真の多職種連携が加速します。
■あわせて読みたい
電子処方箋とは?仕組みや在宅医療でのメリット、導入の流れを解説
電子カルテ情報共有サービスとは?メリットや補助金情報を解説
2.「電子カルテ情報の標準化」の推進
政府が構築を進める全国医療情報プラットフォームは、医療データを安全かつ迅速にやり取りできる“医療情報の高速道路”ともいえる存在ですが、その上を走る医療データ(=電子カルテ)が、各ベンダーごとに異なる形式では意味がありません。こうした課題を解決するカギとして進められているのが、「電子カルテ情報の標準化」です。
目的と仕組み
これまで、電子カルテは各ベンダーが独自の仕様で開発してきたため、異なるメーカーのシステム間ではデータをスムーズに交換できない「サイロ化」という問題がありました。標準化は、この壁を打ち破り、どの電子カルテからでもデータを取り出し、他のシステムで活用できるようにするための「データの言語と形式を統一する」取り組みです。
何を標準化するのか:「3文書6情報」
まずは医療連携に最低限必要な情報として、以下の「3文書6情報」から標準化が進められています。
3文書:診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書
6情報:傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報、処方情報
どうやって標準化するのか:「HL7FHIR」の採用
医療機関同士などでのスムーズなデータ交換や共有を推進するため、標準化の技術として、国際標準規格である「HL7FHIR(エイチエルセブンファイア)」が採用されました。
これにより、医療機関や診療所、薬局、介護施設など異なるシステム間でも、患者の診療情報や検査結果、投薬履歴といった医療データを共通の形式でやり取りできるようになります。従来はベンダーごとに仕様が異なり、情報連携に多大なコストや労力がかかっていましたが、HL7FHIRの導入により、より迅速かつ正確な情報共有が可能となり、診療の質向上や業務の効率化、さらには患者中心の医療実現が期待されています。
標準型カルテの開発
また、政府は、小規模な診療所が電子カルテを安価で導入できるよう、この標準規格に準拠したクラウドベースの「標準型電子カルテ」の開発を進めています。2025年3月に山形県の診療所にて試行版のモデル事業が開始され、2026年度の本格実施を目指しています。
開発しているデジタル庁では、標準型カルテが在宅医療でも利用できるよう機能拡充していけるよう検討を始めています。
参考)デジタル庁|標準型電子カルテの本格展開に向けたα版の改修において、令和7年度のプロダクトワーキンググループ構成員の募集を開始しました
訪問診療クリニックが押さえるポイント
今後、電子カルテを選定・更新する際の最重要基準は「クラウド型」かつ「HL7FHIRに準拠しているか、またはその予定があるか」になります。現在利用中の電子カルテが対応予定か、ベンダーに確認することが急務です。対応が遅れるベンダーのシステムは、将来的に国の情報基盤から取り残されるリスクがあります。
■あわせて読みたい
標準型電子カルテとは?訪問診療クリニックが知っておきたいポイントを解説
3.診療報酬改定DX
これは、2年ごとに行われる診療報酬改定に伴う、医療機関やベンダーの膨大な事務作業とシステム改修の負担を抜本的に効率化する改革です。
4つの具体的施策
診療報酬改定DXの実現に向けて、政府は以下の4つの施策を柱に改革を進めています。それぞれの取り組みは、医療機関の業務効率化やコスト削減に直結するものであり、今後の制度改定にもスムーズに対応できる環境づくりを目指しています。
共通算定モジュールの導入
政府が診療報酬改定に対応した算定プログラムをクラウド上で提供することで、医療機関は自動的に最新の制度に対応可能になります。これにより、従来ベンダーが行っていた開発作業が不要となり、医療機関の負担やコストが削減されます。このモジュールは2026年6月からの本格運用が予定されています。
共通算定マスタ・コードの整備
点数や算定条件を統一したマスタ・コードを使うことで、診療報酬改定時のレセプト対応が効率化されます。また、電子点数表の改善により、算定チェックの精度も向上します。
帳票の標準化と電子連携
診療情報提供書などの書類をアプリ化し、電子的にやり取りする仕組みが整うことで、紙・FAXによる非効率な運用から脱却し、事務作業の効率化が図れます。
施行時期の柔軟化
診療報酬改定の施行を後ろ倒しすることで、準備期間が確保され、システム対応や業務の混乱が緩和されるとともに、改定内容の理解もしやすくなります。
診療報酬改定DXによる医療機関側のメリット
診療報酬改定のDXが進むことで、医療機関には大きな利点があります。
レセプト業務・書類業務の効率化
共通算定モジュールやマスタ・コードの整備により、レセプト請求や診療費計算の業務が効率化され、事務負担の軽減が期待されます。また、統一様式の電子共有により書類作成もスムーズになり、残業削減など院内の業務改善にもつながります。
システム関連費用の削減
政府が改定プログラムをクラウド経由で提供することで、システムベンダーへの開発依存が減り、導入費用や保守コストの削減も見込めます。
診療報酬改定DXは、医療現場の業務フローを根本から見直し、将来的な人手不足や働き方改革にも対応できる基盤づくりでもあります。今後の改定スケジュールやベンダーの対応状況を把握しながら、早めの準備を進めていきましょう。
■あわせて読みたい
診療報酬改定DXとは?各施策の概要やメリット・デメリットを解説
これからの動向:訪問診療クリニックに訪れる3つの変化
今後、これらの取り組みが本格化するにつれて、訪問診療クリニックの現場ではどのような変化が起こるのでしょうか。特に注目すべき3つのポイントを解説します。
1.全国医療情報プラットフォームによる「多職種連携」の深化
現在、厚生労働省は2025年度中の本格稼働を目指し、「全国医療情報プラットフォーム」の構築を進めています。これが実現すると、患者の同意のもと、診療所、病院、薬局、そして訪問看護ステーションや介護事業所などが、必要な医療情報をオンラインで共有できるようになります。
訪問診療クリニックは、ケアマネージャーや訪問看護師、地域の薬局など、多くの職種との連携が不可欠です。これまでは電話やFAX、連絡帳で行っていた情報共有が、プラットフォーム上でリアルタイムかつ正確に行えるようになります。
- 業務効率の飛躍的向上:患者の薬剤情報や他院での検査結果などを即座に確認でき、電話での問い合わせや書類のやり取りが大幅に削減されます。
- 医療の質の向上:最新かつ正確な情報に基づいた診療計画が立てやすくなり、重複投薬や不要な検査を防ぎ、より安全で質の高い医療を提供できます。
2.電子カルテの「標準化」と導入の加速
現在、政府は2030年までにほぼ全ての医療機関で標準規格に対応した電子カルテの導入を目指しています。
標準化された電子カルテは、前述の全国医療情報プラットフォームと連携するための「鍵」となります。今後は、この標準規格に対応しているかどうかが、電子カルテ選定の重要な基準となるでしょう。
訪問先でもリアルタイムにカルテを記録・閲覧できるクラウド型の電子カルテは、訪問診療の効率化に不可欠です。
- クリニックの業務効率化:院内に戻ってからカルテをまとめる作業がなくなり、医師や同行スタッフの残業時間削減に繋がります。
- BCP(事業継続計画)対策:データがクラウド上に保管されるため、災害時にも診療情報が失われるリスクを低減できます。
政府は電子カルテの導入を後押しするため、様々な補助金制度を設けています。導入を検討する際は、これらの制度を積極的に活用することが重要です。
■あわせて読みたい
医療DXに活用できる補助金・助成金ガイド【2025年度版】
3.診療報酬改定における「DX評価」の本格化
診療報酬改定においても、医療DXを推進するクリニックを評価する流れが明確になっています。その代表例が「在宅医療DX情報活用加算」です。
これは、オンライン資格確認システムを通じて得られた患者の薬剤情報や特定健診情報を活用し、在宅での診療計画を立てた場合に算定できる加算です。2024年度の改定で新設され、今後もこうしたDXの取り組みを評価する点数は拡充されていくと予想されます。
DXへの投資が、そのままクリニックの収益に繋がる時代が到来しています。
- 新たな収益源の確保:DX関連の加算を確実に算定できる体制を整えることが、経営の安定化に寄与します。
- 質の高い医療提供の証明:これらの加算を算定していることは、国の方針に沿って質の高い医療を提供しているクリニックであることの証にもなります。
まとめ:訪問診療クリニックが「今」取り組むべきこと
医療DXの大きな潮流は、もはや避けて通ることはできません。この変化を前向きに捉え、いち早く対応することが、今後のクリニック経営の鍵を握ります。
訪問診療クリニックの院長、事務長の皆様が今から取り組むべきことは以下の3点です。
- 情報収集の継続と計画策定:厚生労働省の発表や関連情報を常にチェックし、自院のDX化に向けた中長期的な計画を立てましょう。
- システムの検討と準備:クラウド型電子カルテの導入や、オンライン資格確認の体制強化を具体的に検討しましょう。導入にあたっては、IT導入補助金などの活用も視野に入れましょう。
- 院内体制の整備:職員のITリテラシー向上のための研修や、新しい業務フローへの移行準備を進め、クリニック全体でDXに取り組む意識を醸成することが大切です。
医療DXは、単なる業務効率化のツールではありません。医療の質を高め、患者との信頼関係を深め、そして何よりも医療従事者がやりがいを持って働き続けられる環境を作るための重要な基盤です。この変革の波を乗りこなし、地域医療の未来を支えるクリニックであり続けるために、今こそ第一歩を踏み出しましょう。
参考)厚生労働省|「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム