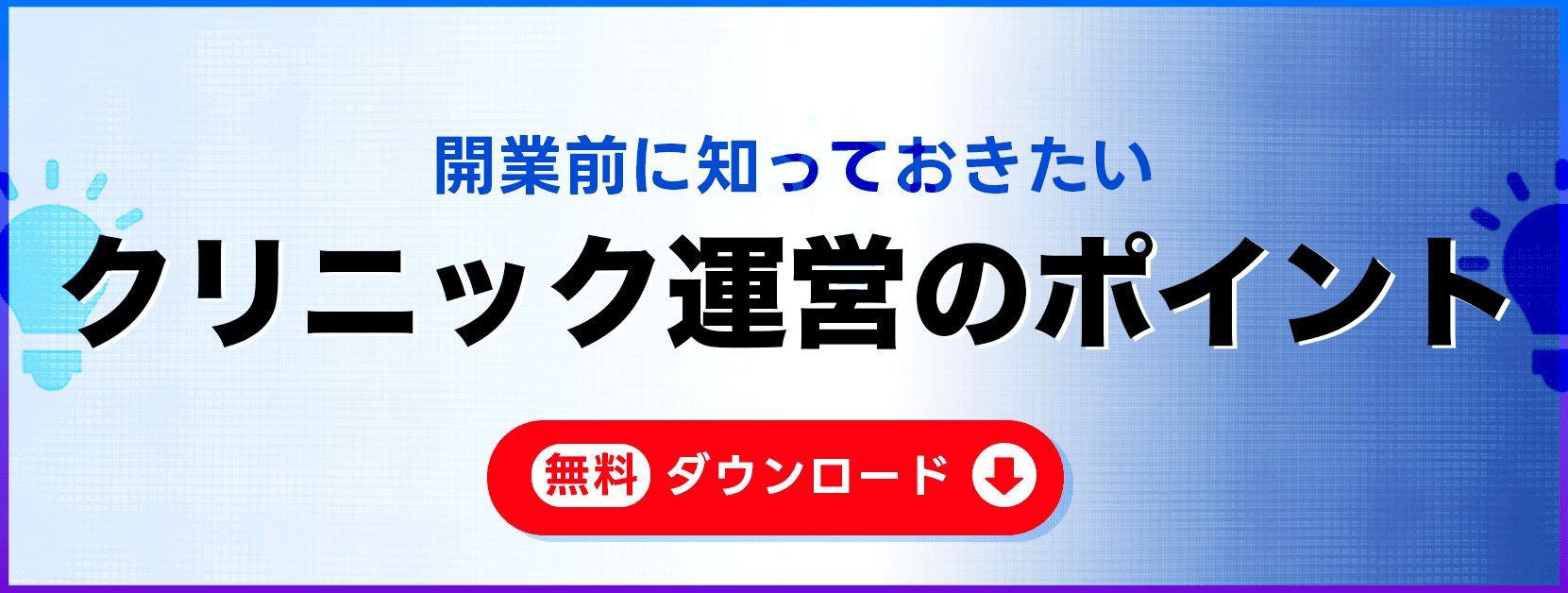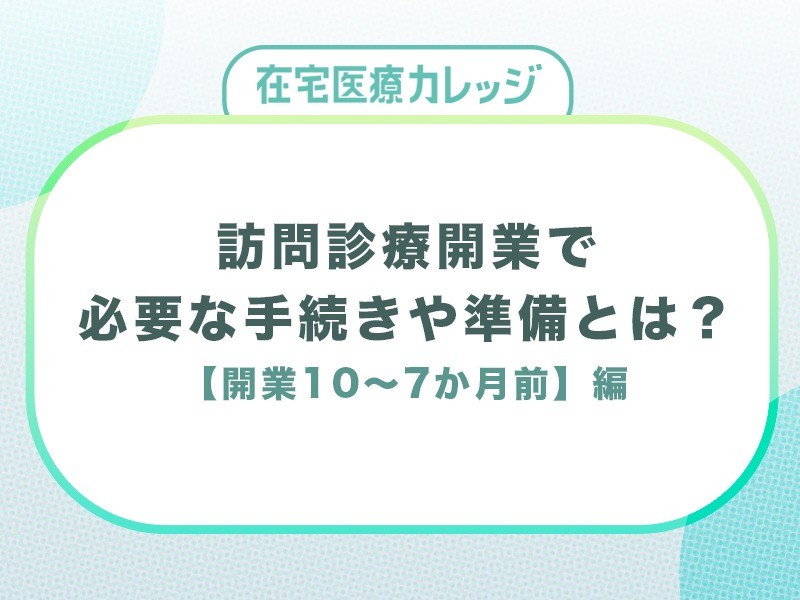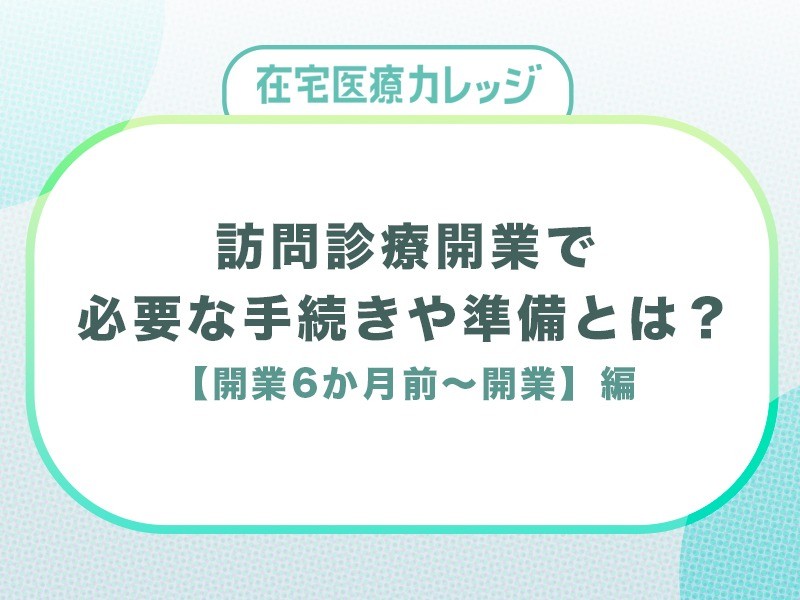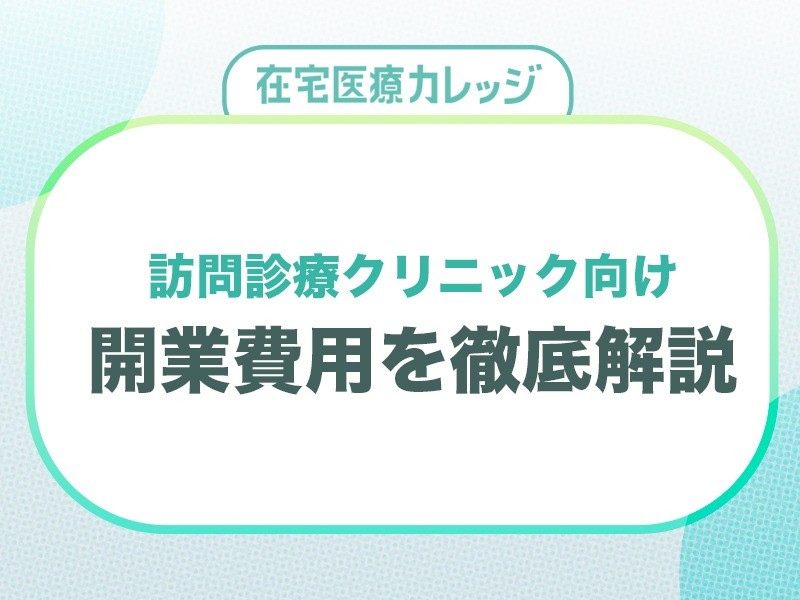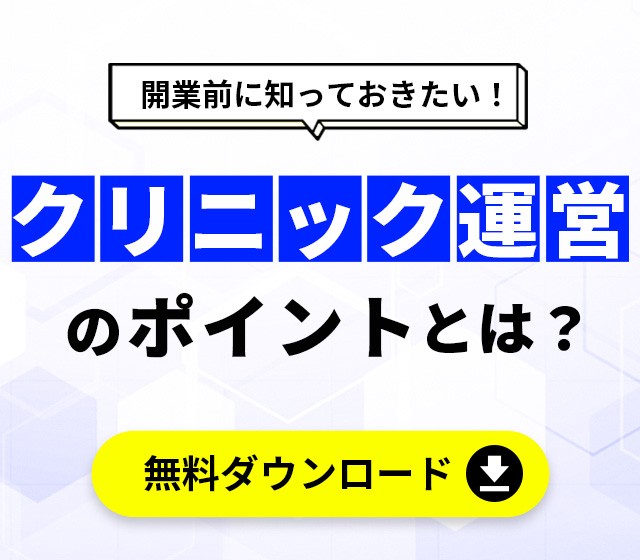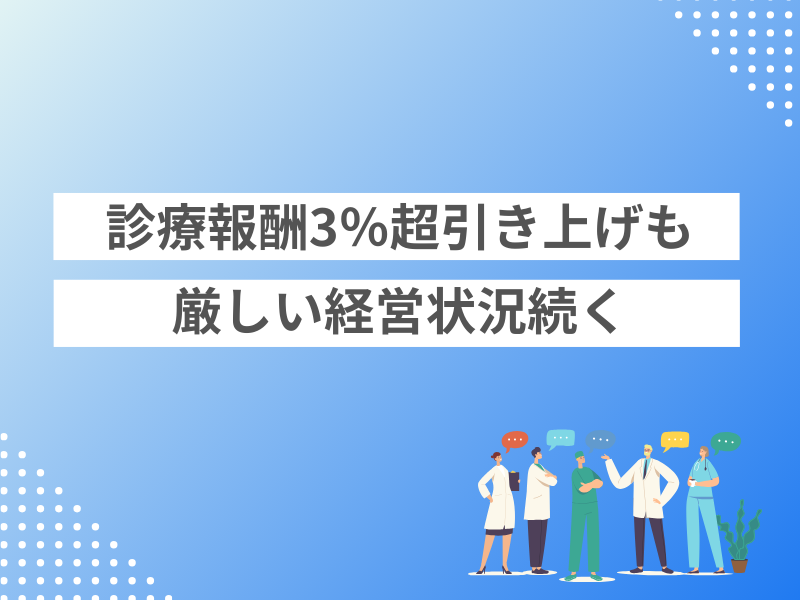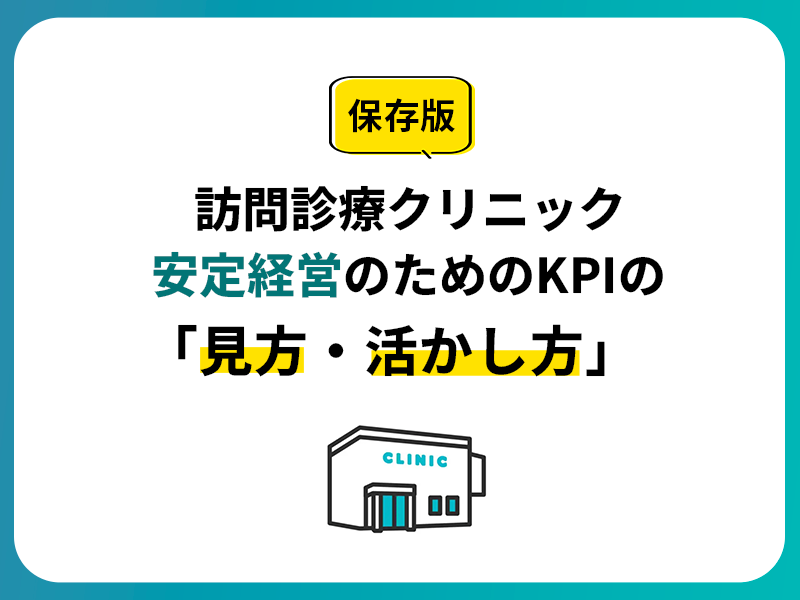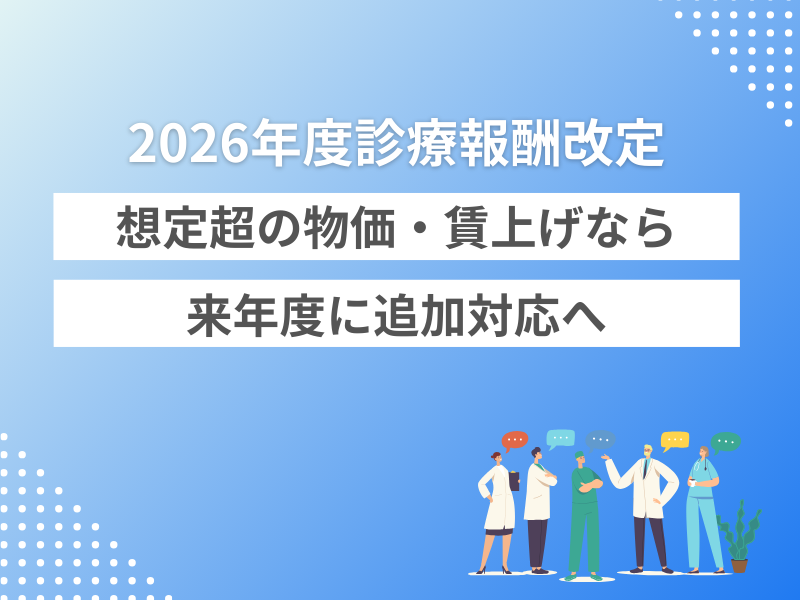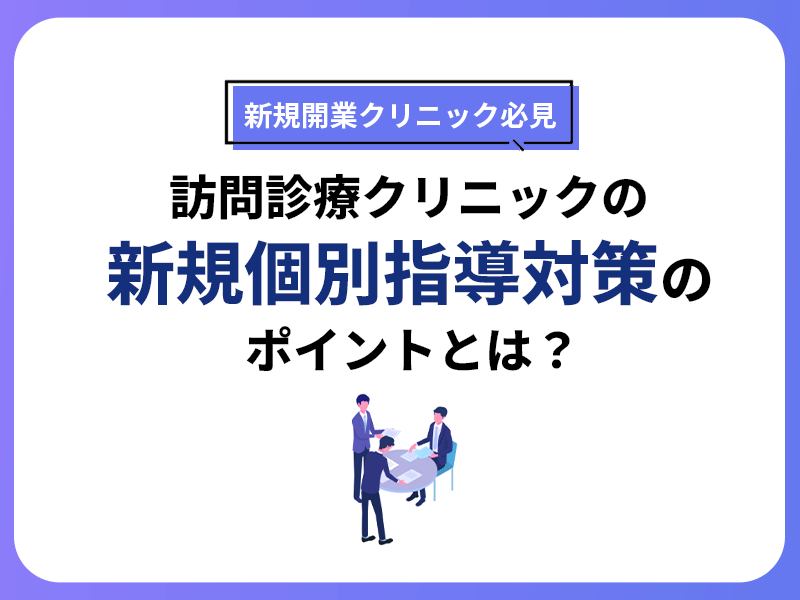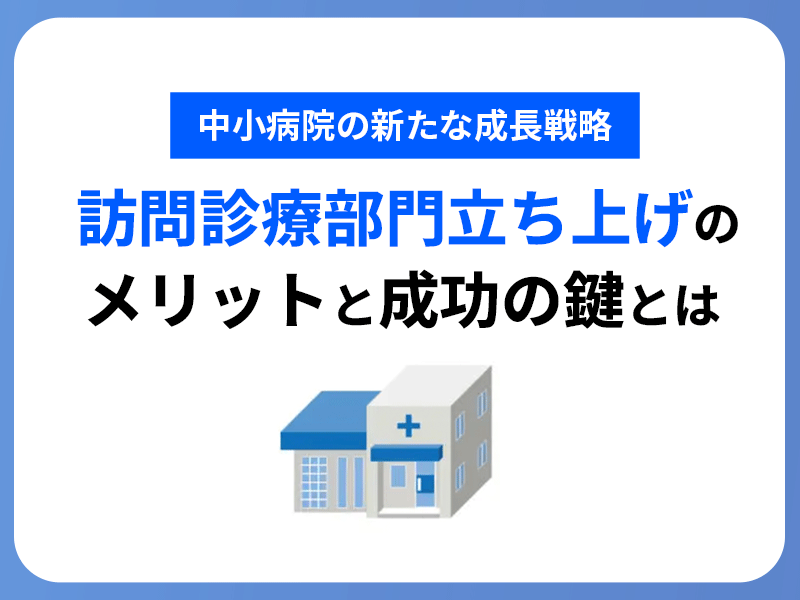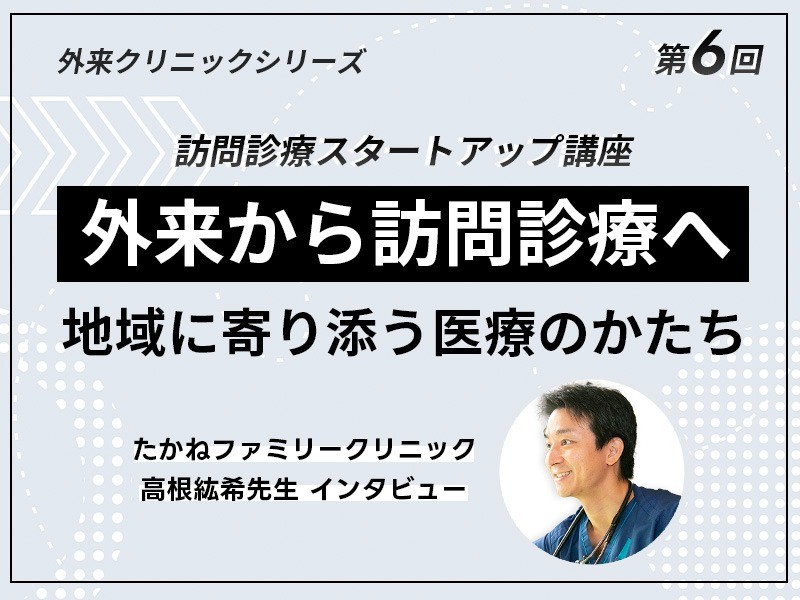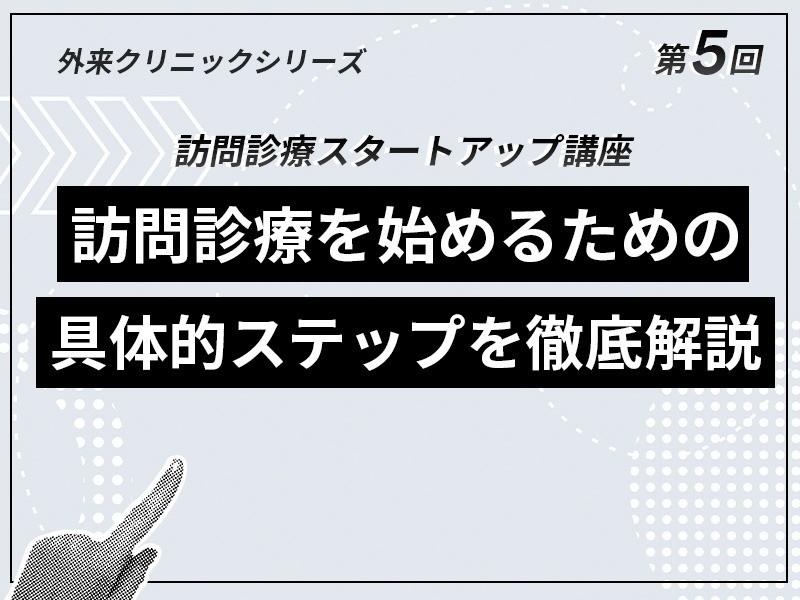- #開業
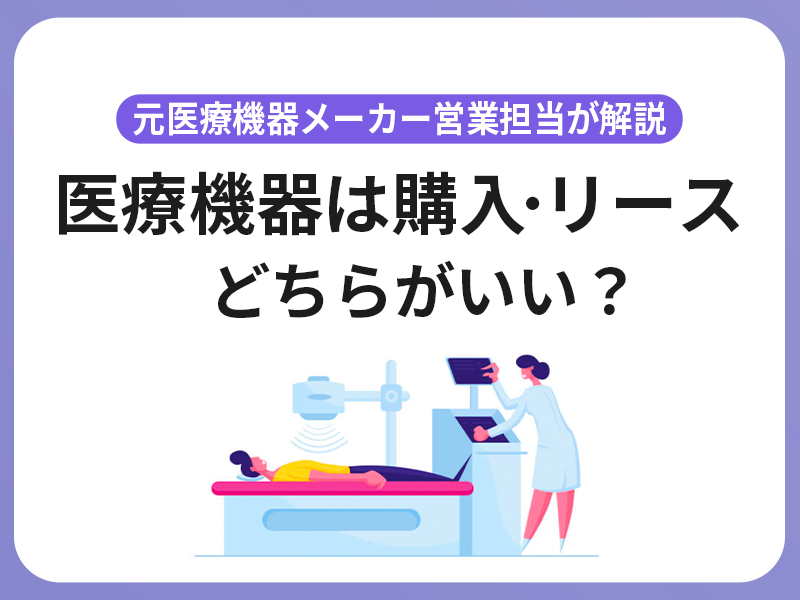
これから医療機器を導入する予定の医師のなかには、「購入とリースどちらがいい?」と疑問を持つ方がいるのではないでしょうか。
購入・リースのメリット・デメリットがわからず、判断が難しいと感じることもあるでしょう。
本記事では、医療機器を導入する際の購入・リースにおけるメリット・デメリットを解説します。
それぞれの違いを理解し、自院の方針に合った選択肢を選びましょう。
訪問診療における医療機器は?
訪問診療で使用するおもな医療機器は以下のとおりです。これから医療機器の導入を検討している方は参考にしてみてください。
| 訪問診療における医療機器(例) | 機器の概要 |
| ポータブル心電計 | 心疾患を診断する。充電式でコードレス使用可能であり、持ち運びがしやすい。 |
| パルスオキシメーター | 血液に含まれる酸素量を測定する。呼吸器疾患のスクリーニングや睡眠中の呼吸状態を確認するために役立つ。 |
| スパイロメーター | 肺の容積や換気機能を調べる。喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器系疾患の診断にも用いる。 |
| 骨密度測定器 | 片足の骨密度を測定する。骨粗鬆症のスクリーニングに役立つ。 |
| ポータブル超音波画像診断装置 | おもに循環器疾患や心臓、腹部の状態を調べる際に用いる。 |
| ポータブル式レントゲン撮影機 | 充電式のX線管球とフラットパネルを組み合わせ、高画質なX線写真を撮影する。 |
医療機器を購入するメリット
医療機器を購入するメリットは以下のとおりです。
総額を抑えられる
購入の場合、導入時に一括で支払えばそれ以降に発生する費用がないため、トータルでかかるコストが抑えられます。
一方でリースの場合、リース会社側の手数料が発生するため、購入よりも総額が増える可能性があります。
特別償却が適用される
特別償却とは、特定条件を満たしたうえで医療機器を購入することで、税負担を軽減できる制度です。
たとえば、500万円以上の医療機器を購入すると12%、30万円以上の備品やソフトを購入すると15%が初年度に減価償却費として計上できます。これにより、所得税や法人税が大幅に軽減できます。
減価償却を費用として計上できる
減価償却とは、高額な資産の購入費用を、耐用年数を踏まえ分配して経費として計上することです。
経費が多いほど所得が減るため、所得税や法人税における節税効果が期待できます。なお、医療機器の耐用年数は4〜8年程度です。
医療機器の購入費用が数百万円であれば、減価償却によって数十万円の金額を経費に計上できます。
医療機器を購入するデメリット
医療機器を購入するデメリットは以下のとおりです。
初期費用の負担が増える
購入の場合、多額の初期費用がかかるケースがあります。自己資金で対応できる場合は問題ありませんが、不足する場合は借入れをする必要があります。
中古品の場合は新品よりも費用が抑えられますが、複数の機器を購入するケースだと、数百万円以上の資金が発生する場合もあるでしょう。
短期間で機種の変更がしにくくなる
医療機器を更新する場合、旧機種を処分する際に専門業者の買い取りや廃棄に関する手続きが必要になります。
リースに比べると、機種変更の手間がかかるといえるでしょう。
会計処理の手間がかかる
購入の場合は税制上の優遇措置が受けられる一方で、損害保険料や減価償却費用、償却資産税などの会計処理の手間がかかります。
税理士に依頼することも可能ですが、その分の顧問料や決算料を支払う必要があります。
医療機器をリースするメリット
医療機器をリースするメリットは以下のとおりです。
初期費用が抑えられる
リースの場合、毎月リース費用を支払うだけで済むため、初期費用が抑えられます。初期費用が抑えられれば、設備拡張や広告費用などに投資できます。
新機種への入れ替えがしやすくなる
リース契約の場合、リースアップ時に契約を解除すれば廃棄料などがかからず新機種への移行が可能です。
新しい医療機器に更新ができれば、患者満足度が上がったり、質の高い医療が提供しやすくなったりするでしょう。
会計処理の手間が省ける
リースの場合、リース会社に支払う費用をそのまま経費として計上できるため、償却資産の申告が不要です。
毎月の会計処理の手間が省けるため、事務作業の負担が軽減できます。
医療機器をリースするデメリット
医療機器をリースするデメリットは以下のとおりです。
導入費用が割高になる
リースによる医療機器の導入は、リース料率によって余分にリース会社へ費用を払うことになるため、割高になります。
リース期間を短くすることでリース料の総額は抑えられますが、契約期間が短いほどリース料率が上がるため、毎月のリース料が高額になる場合があります。
導入後の仕様が変えにくくなる
医療機器をリースで導入する場合、医療機器一式すべてをリース契約するため、仕様が決まった状態で医療機関へ納品されます。
そのため、オプション品を途中から導入しようとした場合はリース扱いにならないため、導入が難しくなります。
解約した場合に費用が発生する
リース契約を済ませた場合、途中で解約すると違約金の支払いが必要です。また、残りのリース料の支払いも必要になるため、金額的な負担が増えます。
【徹底比較】医療機器のリースと購入、自院にはどちらが最適?
リースが向いているケース
- 開業初期で初期投資を極力抑えたいクリニック: 手元資金を温存し、運転資金や他の重要な投資に充てたい場合に最適です。
- 常に最新の医療機器を導入したいクリニック: 医療技術の進歩が早い分野の機器(例:最新の超音波診断装置、内視鏡システムなど)で、数年ごとにリプレースを検討している場合に陳腐化リスクを回避できます。
- キャッシュフローを安定させたいクリニック: 月々の費用が固定されるため、資金計画が立てやすくなります。
- 事務負担を軽減したいクリニック: 資産管理や会計処理の手間を省きたい場合に有効です。
- 高額で技術革新が著しい機器: MRI、CTスキャン、高性能なレーザー治療器など、導入費用が高く、技術の進歩が速い機器はリースに向いています。
購入が向いているケース
- 資金力に余裕があり、初期投資を問題としないクリニック: 多額の自己資金がある、または有利な条件で融資を受けられる場合に、総支払額を抑えられます。
- 長期間同じ機器を使い続けたいクリニック: 汎用性が高く、陳腐化の心配が少ない機器(例:診察台、簡易的な検査機器、手術台など)で、10年以上の長期利用を想定している場合。
- 機器のカスタマイズや改造を自由に行いたいクリニック: 独自の診療スタイルに合わせて機器を調整したい場合に、所有権を持つ購入が有利です。
- 減価償却による節税メリットを享受したいクリニック: 課税所得が多く、減価償却費を計上することで節税効果を期待したい場合に有効です。
項目別比較!リース vs 購入 早見表
| リース | 購入 | |
|
初期費用 |
大幅に抑えられる(不要な場合も) |
高額な資金が必要 |
|
総支払額 |
購入より割高になる傾向 |
リースより安くなる傾向 |
|
中途解約 |
原則不可 |
自由 |
|
会計処理 |
原則として費用として処理(経費計上) |
資産計上し、減価償却費を計上 |
|
固定資産税 |
不要(リース会社が負担) |
支払い義務あり |
|
陳腐化リスク |
契約満了時に最新機器へ交換しやすく、リスク軽減 |
自院で負担。買い替えには新たな資金が必要 |
|
カスタマイズ |
原則不可、または要相談 |
比較的自由 |
|
資金繰り |
月々定額支払いで安定しやすい |
初期に多額の資金流出。借入時は返済負担 |
|
銀行借入枠 |
温存できる |
消費する可能性がある |
知っておきたい主なリース契約の形態
リース契約には初期費用を抑えつつ、最新の機器を導入できるという大きなメリットがありますが、その契約形態によって特徴やリスクは異なります。
ここでは、代表的な3つのリース形態について、それぞれの仕組みとメリット・デメリットを解説します。
ファイナンスリース
ファイナンスリースは、最も一般的なリース契約の形態です。
リース会社がクリニックの代わりに医療機器を購入し、クリニックはその機器を一定期間賃貸借する仕組みです。
契約期間中の中途解約は原則として認められませんが、期間満了後は機器を返却するか、再リース(延長)することができます。
リース料には、機器代金に加えて金利や諸経費(保険料など)が含まれます。
初期費用を抑えられるうえ、会計上は原則として資産計上が不要なため費用処理がしやすく、保険や税務面の手続きも簡便です。
一方で、契約途中で不要になっても解約できない点や、長期的に見ると購入より総支払額が高くなる場合がある点には注意が必要です。
購入選択権付リース
購入選択権付リースは、契約期間終了時にリースしていた医療機器を「買い取る」か「返却する」かを選べるリース方式です。
契約期間は比較的短めに設定されることが多く、技術革新の早い医療機器に適しています。
リース期間終了後には、低価格で機器を買い取れるオプションが用意されているため、最終的に所有したい機器を初期費用を抑えて導入できる点が大きなメリットです。実際に使用してみてから購入を判断できる点も魅力です。
ただし、ファイナンスリースよりリース料が高くなる場合があり、買い取る際には経年劣化や保証切れに注意が必要です。
据置型リース
特に開業医向けに提供されることがあるリース形態です。
リース開始から一定期間(例えば開業当初の数ヶ月〜1年間)のリース料を低額に設定し、その後、通常のリース料に戻すことで、開業初期の資金繰り負担を軽減することを目的としています。
初期の経営が軌道に乗るまでの期間をサポートする形ですが、トータルでの支払総額は通常のリースよりも高くなる傾向があるため、契約内容をよく確認する必要があります。
リース契約開始までの一般的なステップ
医療機器のリースを活用する際は、契約までの流れを把握しておくことが重要です。
手順を理解しておくことで、スムーズに導入を進められるだけでなく、見積もりや契約条件の交渉も有利に進められます。
以下では、クリニックが医療機器リースを開始するまでの一般的な流れを紹介します。
- 機器選定と見積もり
まず、クリニックに導入したい医療機器を選定し、メーカーや販売店から機器の本体価格、設置費用、保守費用などの見積もりを取得します。 - リース会社への相談
選定した機器情報と、希望するリース期間(通常は5年~7年程度)、月々の支払希望額などをリース会社に伝えます。複数のリース会社に相談し、条件を比較検討することをおすすめします。 - 審査
リース会社は、クリニックの経営状況、信用情報、事業計画などを基にリース契約の審査を行います。この際、決算書や開業計画書などの提出を求められることがあります。 - 契約
審査を通過すると、リース会社からリース契約書が提示されます。契約内容(リース期間、リース料、中途解約に関する条項、保守責任など)を十分に確認し、納得した上で契約を締結します。 - 機器納入
リース会社がメーカーから医療機器を購入し、クリニックへ納入されます。機器の設置や初期設定は、通常メーカーや販売店が行います。 - リース開始
機器の検収が完了した時点からリース契約が開始され、月々のリース料の支払いがスタートします。
リース契約は「資金調達」と「設備導入」を同時に進められる便利な仕組みですが、契約条件や期間、総支払額などを十分に理解したうえで進めることが、後悔しない設備導入のポイントです。
医療機器を導入するときによくある質問
医療機器を導入するときによくある質問と回答は以下のとおりです。
-
Q
医療機器を購入するときは新品・中古のどちらがいい?
A中古品の場合、新品よりも安く導入できる場合があるため、導入費用を抑えたい場合にはおすすめです。
しかし、適切なメンテナンスがされていない場合、導入後に動作不良などが起こる可能性があります。 -
Q
医療機器を安く購入するコツは?
Aメーカーの決算時期やキャンペーンのタイミングを狙って購入することで、通常より安く購入できる場合があります。
また、医療機器を複数種類(複数台)購入することで割引してもらえることもあるでしょう。 -
Q
医療機器のリースとレンタルの違いは?
Aリースの場合は、一般的に5〜7年程度の期間で医療機器が使用できます。
一方で、レンタルの場合は1日から数週間単位で使用可能です。
短期間の利用であればレンタルのほうがコストを抑えられますが、年単位で利用する場合はリースのほうが安くなる可能性があります。
医療機器選定・購入の相談はmicsコンサルティングへ
医療機器を導入するなかで、購入かリースのどちらを選択すべきか悩む方がいるのではないでしょうか。
また、メーカーや業者選びの基準がわからない方もいるでしょう。
このような方におすすめなのがmicsコンサルティングです。
当サービスでは、お客様のお悩み解決のために、医療機器に精通した専門のコンサルタントがサポートします。
クリニックに必要な集患・増患支援や患者満足度の向上支援などにも対応します。無料経営相談も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
医療機器を導入する際の手段として、おもに購入とリースが挙げられます。
購入の場合、総額費用が抑えやすくなったり、節税メリットが得られやすかったりします。一方で、初期費用の負担や会計の手間が増える可能性があるでしょう。
リースの場合、初期費用が抑えやすくなったり、会計の手間が省けたりします。
一方で、導入費用が割高になり、導入後のオプション導入などが難しくなる可能性があります。
医療機器を導入する際は、購入・リースそれぞれのメリット・デメリットを理解し、自院に合った選択肢を選びましょう。