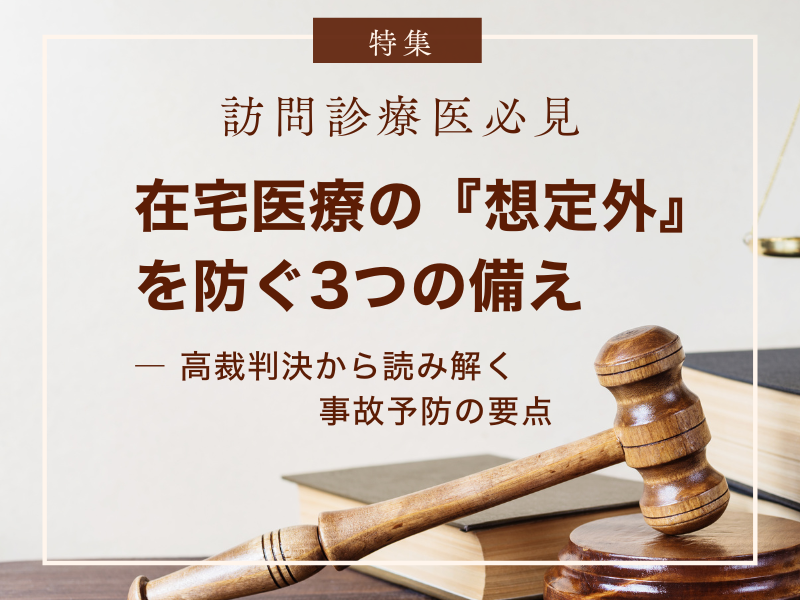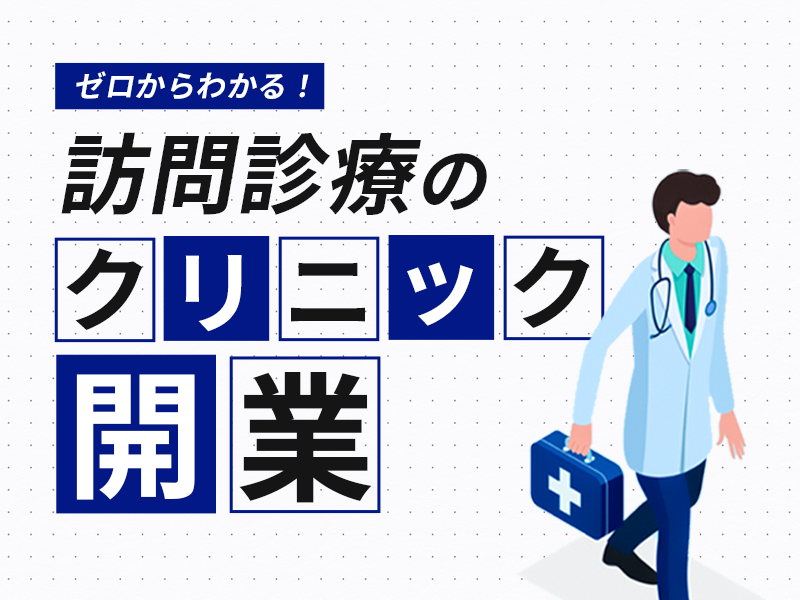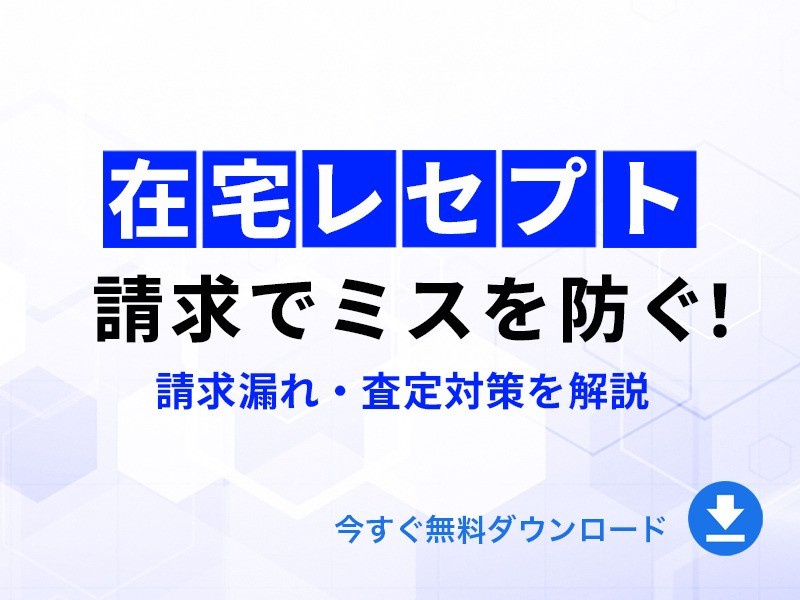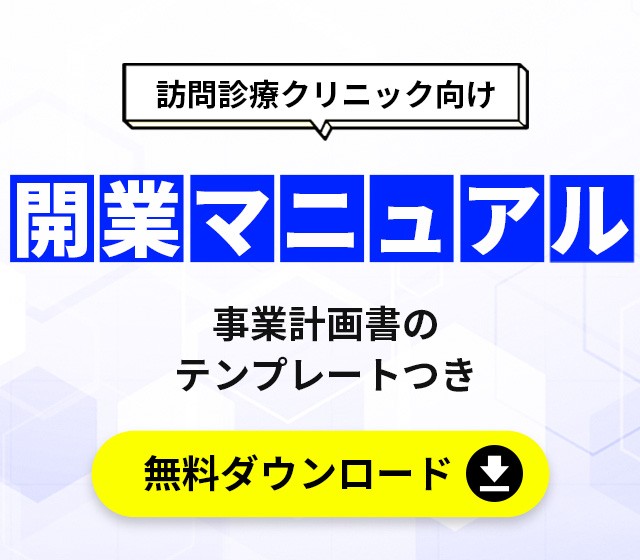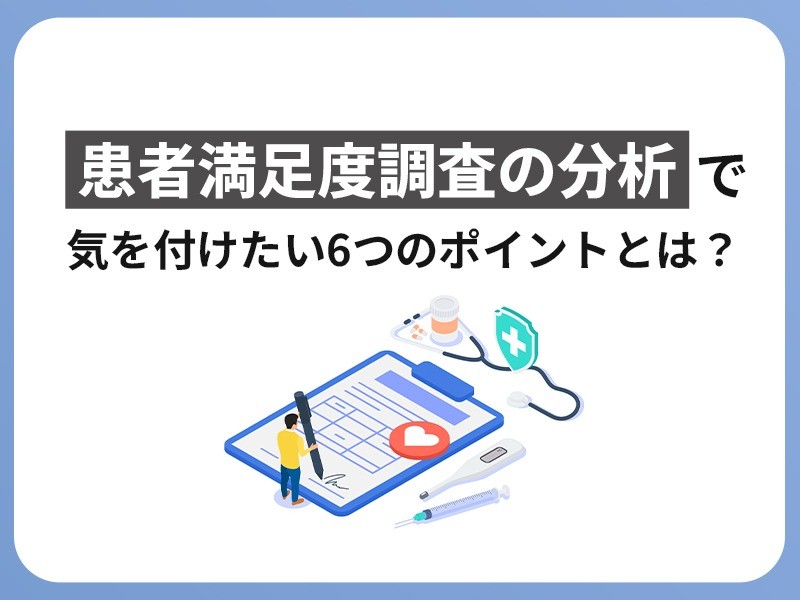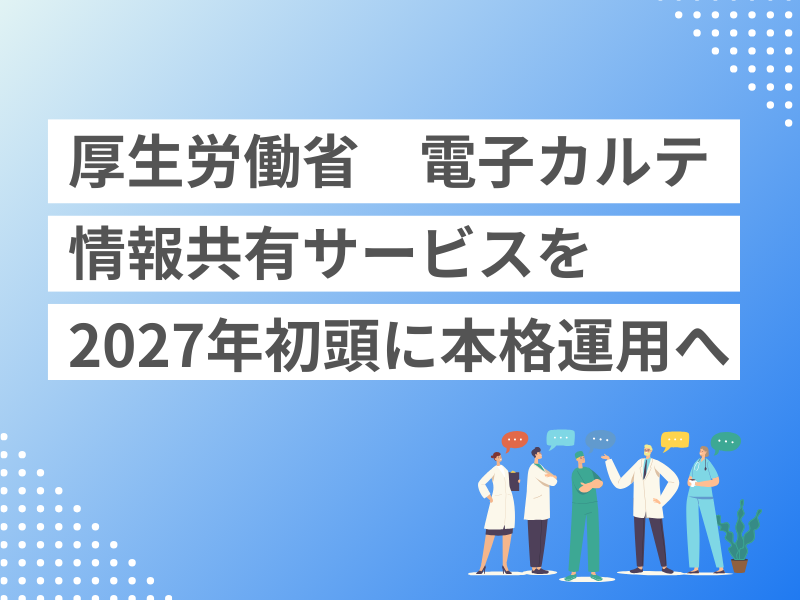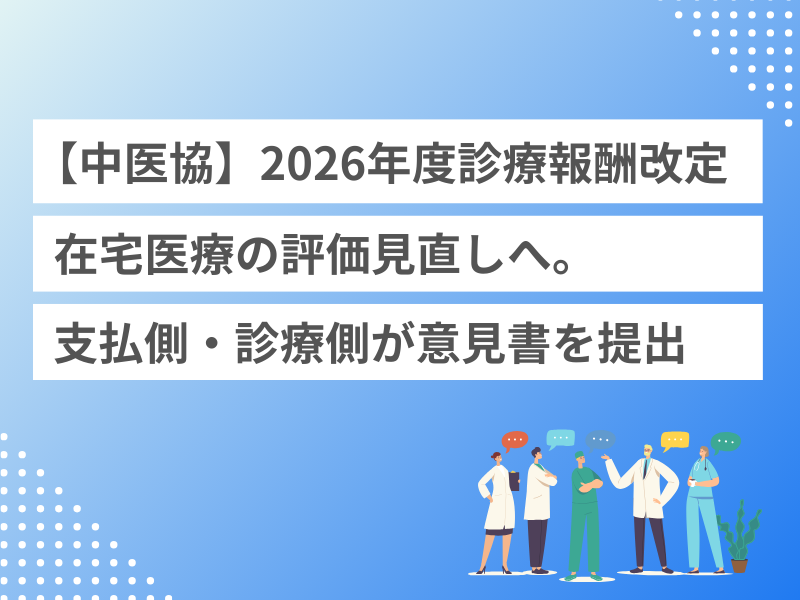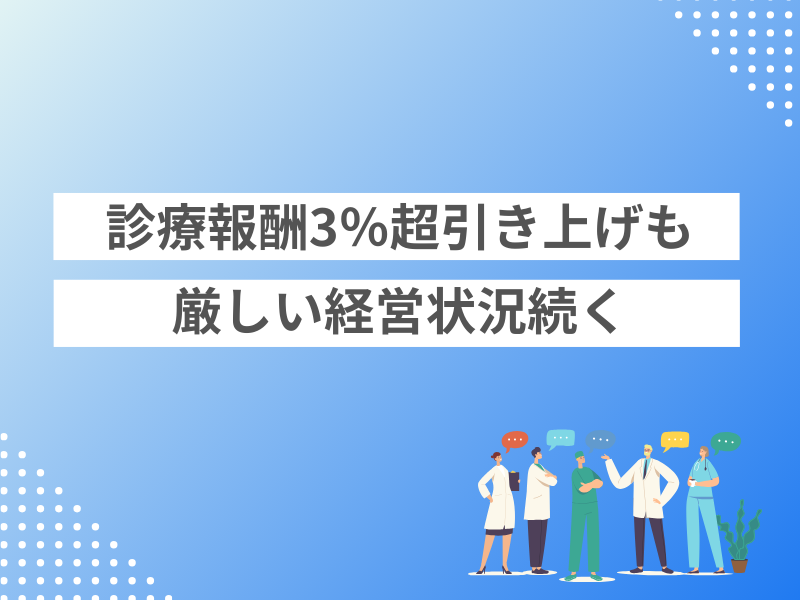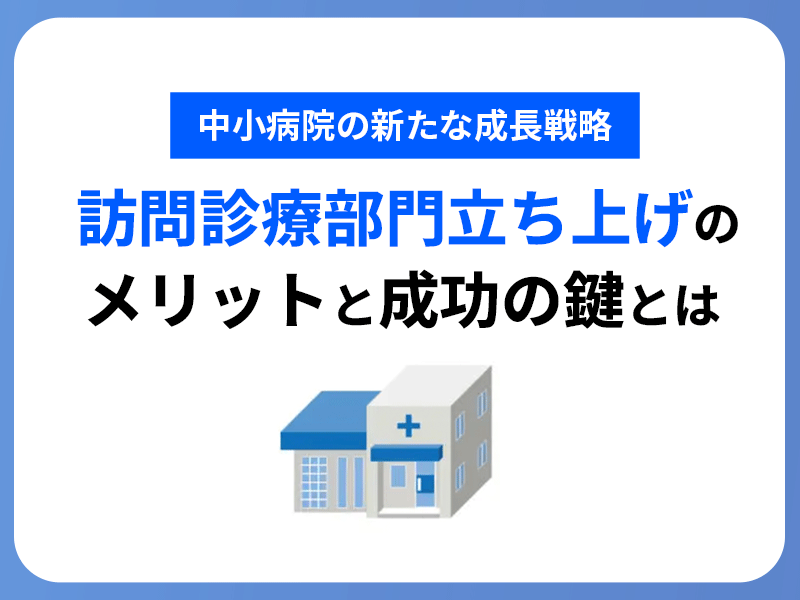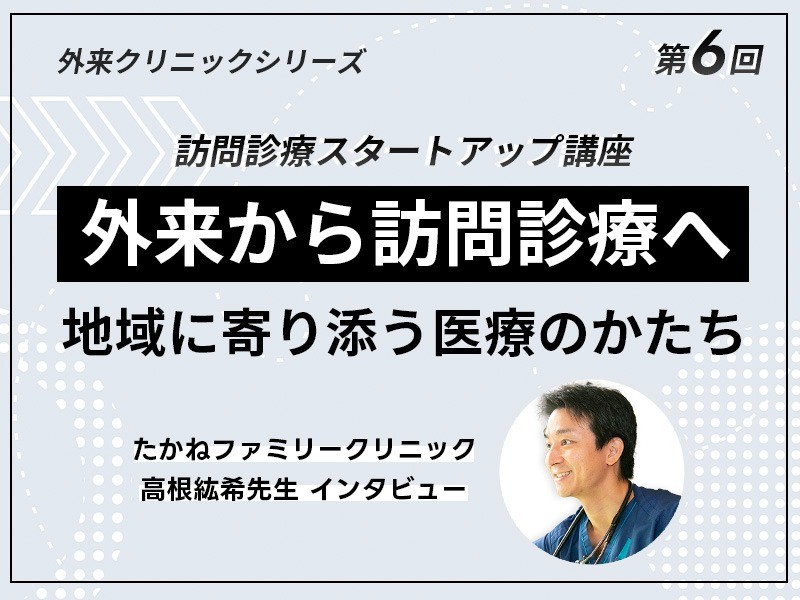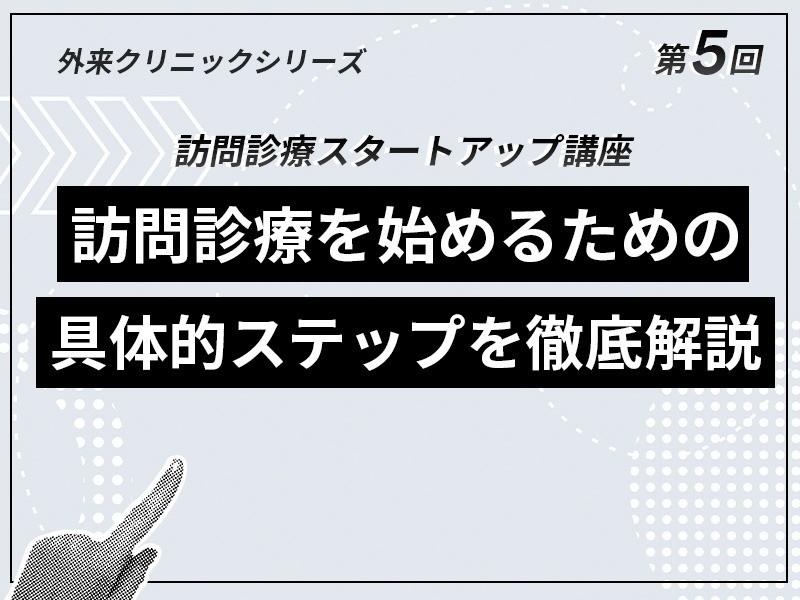- #運営
- #開業

自身の理想とする医療を実現するため、クリニックの開業を目指す医師は少なくありません。しかし、優れた医療技術や知識だけでは、クリニックを安定的に運営していくことは困難です。日々の診療はもちろん、スタッフの雇用、外部業者との契約、そして患者さんにクリニックを知ってもらうための広報活動まで、運営のあらゆる場面で法律が関わってきます。
本記事では、クリニックを開業・運営する医師が最低限押さえておくべき法律の知識を、「診療」「雇用」「契約」「広告」の4つのテーマに分け、具体的なポイントを平易に解説します。
【診療編】日々の医療行為と患者の権利を守る法律
まずは、医療の根幹である診療に関わる法律です。これらは医師としての責務や、クリニックという「場」のルールを定めています。
医師法
医師法は、医師の資格、業務内容、義務、罰則などを定めた法律です。国民の健康を守り、公衆衛生の向上に貢献することを目的としています。クリニック開業において特に重要なのが「応召義務」と「診療録の保存義務」です。
応召義務(第19条)
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」 応召義務は、医師の職業倫理の根幹をなす公法上の義務です。これは、患者が医師個人に対して診療を直接強制できる権利(私法上の権利)ではありません。しかし、正当な理由なく診療を拒否し、患者に損害を与えた場合、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があるため、極めて重要な義務であることに変わりはありません。
もっとも、常に無制限に応じなければならないわけではありません。厚生労働省は2019年に応召義務に関する考え方を整理し、現代の医療提供体制に合わせて、診療を行わないことが「正当な事由」にあたる場合や、正当化される場合があることを明確化しました。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 診療時間外・勤務時間外の対応
緊急対応が不要な患者から、診療時間外や勤務時間外に診療を求められた場合、即座の対応は必須ではなく、時間内の受診を勧めたり、他の医療機関を案内したりすることは正当化されます。
- 患者の迷惑行為
診療内容と関係のないクレームを繰り返したり、暴言・暴力行為に及んだりするなど、医師との信頼関係が喪失してしまった場合には、新たな診療を断ることが正当化されます。
- 悪質な医療費不払い
支払能力があるにもかかわらず、悪意を持って意図的に支払いを拒否する場合などは、診療を断ることが正当化されることがあります。ただし、単に過去に不払いがあったという事実だけでは、直ちに診療拒否の理由とはなりません。
- 専門性や設備の問題
自院の専門性や設備では対応が困難であり、地域の他の医療機関でより適切な医療が提供できる場合には、そちらを紹介・転院させることが正当化されます。
- 差別的扱いやコミュニケーション困難
患者の国籍、宗教、言語などを理由に診療を拒否することは正当化されません。ただし、言語が通じない、宗教上の理由で必要な医療行為が行えないなど、結果として診療そのものが著しく困難な場合はこの限りではありません。
ただし、どのような状況であっても、患者の生命や身体に重大な影響が及ぶおそれがある緊急の場合には、応急的に必要な処置を行うことが求められる点には注意が必要です。
診療録の保存義務(第24条)
医師には、診療録(カルテ)を5年間保存する義務があります。これは、患者の治療経過を正確に記録し、継続的な医療の質を担保するだけでなく、万が一医療過誤などが問われた際に、適切な医療を提供したことを証明する重要な証拠にもなります。
医療法
医療法は、病院、診療所、助産所といった医療提供施設の開設や管理、運営について定めた法律です。
クリニック(診療所)を開設するには、保健所への届出や許可が不可欠であり、その基準は医療法によって定められています。内装工事を始めてから「この構造では基準を満たせなかった」といった事態を避けるためにも、計画段階で必ず管轄の保健所に相談しましょう。
また、医療法は医療機関の信頼性を担保する役割も担っています。例えば、院内に掲示する診療科目名や、後述する広告のルールも医療法で定められており、患者が適切な医療選択をするための基盤となっています。
個人情報保護法:患者の信頼に応える情報管理
クリニックが扱うカルテやレセプトは、病名や治療歴といった極めてセンシティブな個人情報の塊です。これらの情報は、個人情報保護法において特に慎重な取り扱いが求められる「要配慮個人情報」に該当し、より厳格な保護措置が課されています。
- 取得に関する同意
要配慮個人情報を取得する際は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。
- 利用目的の特定と目的外利用の禁止
個人情報を取得する際は、その利用目的(例:診療、診療報酬の請求など)を通知・公表する必要があり、その利用目的以外で利用してはなりません。なお、利用目的の公表方法としては、院内掲示などで患者に分かりやすく示しておくことが考えられます。
- 同意なき第三者提供の禁止
原則として、患者本人の同意なく個人情報を第三者に提供してはなりません。
- 安全管理措置
情報の漏えい、紛失、改ざんなどを防ぐための物理的・技術的な安全対策が義務付けられています。電子カルテやクラウドサービスを利用する際は、セキュリティ対策が万全なシステムを選定する必要があります。
情報漏洩は、損害賠償といった金銭的なダメージだけでなく、長年かけて築いてきた患者や地域社会からの信頼を一瞬で失うことにも繋がりかねません。スタッフ全員で守秘義務を徹底し、情報管理体制を構築することが重要です。
【雇用編】スタッフが安心して働ける職場をつくる法律
看護師や医療事務など、スタッフの力なくしてクリニック運営は成り立ちません。スタッフが安心して働ける環境を整えることは、経営者である院長の重要な責務です。
労働基準法・労働契約法:労務トラブルを未然に防ぐ
スタッフを一人でも雇用すれば、労働基準法や労働契約法といった労働法のルールが適用されます。
- 労働基準法
労働時間、休憩、休日、有給休暇、残業代の支払いなど、労働条件の最低基準を定めています。特に、勤務時間が不規則になりがちなクリニックでは、労働時間管理が重要です。夜間のオンコール待機を手当で済ませていたつもりが、法的には労働時間とみなされ、後から高額な未払い残業代を請求されるケースもあり得ます。
- 労働契約法
雇用契約に関するルールが定められており、例えば、解雇に関するルール(客観的に合理的な理由なく解雇できない)や、有期雇用スタッフの無期雇用への転換ルールなどが定められています。
これらの法律を知らずにいると、「知らなかった」では済まされない労務トラブルに発展する可能性があります。開業前に就業規則や雇用契約書を整備し、弁護士などの専門家の助言を得ながら、コンプライアンス体制を整えることが、安定したクリニック運営の鍵となります。
【契約編】クリニックの経営を安定させる法律
クリニックの運営は、患者さんとの診療契約だけでなく、様々な外部パートナーとの契約関係の上に成り立っています。
民法:患者との診療契約と万一への備え
患者が診療を申し込み、医師がそれに応じた時点で、民法上の「診療契約」が成立します。医師は、この契約に基づき、患者に対して適切な医療を提供する義務(債務)を負います。
もし、この義務が果たされず、患者に損害が生じた場合には、債務不履行や不法行為として損害賠償責任を問われる可能性があります。賠償額が数千万円に及ぶケースもあり得ます。
こうしたリスクに備えるため、日々の診療では丁寧なインフォームド・コンセントを徹底し、その内容を診療録に詳細に記録することが何よりの防御策となります。それに加え、万一の事態に備えて医師賠償責任保険に加入することは、現代のクリニック経営において重要なポイントと言えるでしょう。
業務委託契約:外部パートナーとの適切な連携
医療事務(レセプト請求)や検査、医療廃棄物の処理など、院内業務の一部を外部の専門業者に委託するケースは多いでしょう。その際に重要になるのが「業務委託契約書」です。
契約書では、委託する業務の範囲や費用、責任の所在を明確にすることがトラブル防止に繋がります。特に、患者の個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、秘密保持契約(NDA)を締結し、委託先における情報管理体制まで確認することが求められます。
ただし、医師にしかできない「医業行為」そのものを外部に委託することは医師法で禁じられています。業務委託の範囲を正しく理解し、適切なパートナーシップを築きましょう。
【広告編】患者に正しく情報を届けるためのルール
どれだけ質の高い医療を提供していても、患者さんに知ってもらえなければ経営は成り立ちません。しかし、医療に関する広告は厳しく規制されています。
医療法・医療広告ガイドライン:ウェブサイトも対象
医療機関の広告は、医療法および厚生労働省の医療広告ガイドラインによって詳細に規制されています。かつては看板やチラシが主な対象でしたが、2018年の法改正でウェブサイトも広告規制の対象となり、より一層の注意が必要になりました。 具体的に、ガイドラインでは以下のような広告が禁止されています。
- 虚偽広告
医学的にあり得ない「絶対安全な手術」といった表現や、根拠のない「満足度○%」などの表示。
- 比較優良広告
「日本一」「No.1」といった最上級の表現や、他のクリニックと比較して自院が優れていると示す広告。
- 誇大広告
事実を不当に誇張したり、患者に誤認を与えたりする表現。例えば、当然の手続きである保健所の許可を「特別な許可」のように見せかけること。
- 患者の体験談
個人の感想に過ぎず、全ての患者に当てはまるわけではないため、治療内容や効果に関する体験談の掲載は禁止されています。
- 治療前後の写真
いわゆるビフォー・アフター写真も、適切な説明(治療内容、費用、リスク、副作用など)がなければ掲載できません。
- 品位を損ねる広告
「キャンペーン実施中!」といった費用を過度に強調する表現や、医療の内容と関係ないことで誘引する広告。
- 広告が認められていない事項
原則として法律で定められた事項(医師の経歴、診療時間、実施可能な保険診療など)しか広告できません。「専門外来」という表現や、未承認の医薬品による治療などは広告できません。
一方で、患者が自ら情報を求めて閲覧するウェブサイトなどでは、以下の要件をすべて満たすことで、広告可能な事項の限定が解除され、より詳細な情報(例:保険適用外の自由診療の内容など)を掲載できます。
- 患者が能動的に情報を得る場であること:クリニックのウェブサイトや、患者の求めに応じて送付するパンフレットなどが対象です(バナー広告や検索連動型広告は対象外)。
- 問い合わせ先が明記されていること:電話番号やメールアドレスなど、患者が容易に照会できる連絡先を記載する必要があります。
- 自由診療に関する情報提供(自由診療の場合):自由診療について掲載する場合は、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間や回数、そして主なリスクや副作用などを分かりやすく明記しなければなりません。
自院のウェブサイトやパンフレットを作成する際は、必ず医療広告ガイドラインに目を通し、「患者を誤認させる恐れがないか」という視点で厳しくチェックしましょう。
まとめ:法令遵守で築く、地域に根差したクリニック
本記事では、クリニックの開業・運営に関わる法律の要点を解説しました。医療制度や関連法規は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を収集し、知識をアップデートし続ける姿勢が求められます。
しかし、院長一人が全ての法律を完璧に把握するのは現実的ではありません。必要に応じて弁護士などの専門家の力を借り、相談できる体制を整えておくことも、リスク管理の重要な一環です。
法令を正しく遵守するクリーンなクリニック運営は、スタッフの安心感や定着率を高め、ひいては患者からの信頼獲得に繋がります。盤石なリーガル体制を築き、地域に根差したクリニックの実現を目指しましょう。