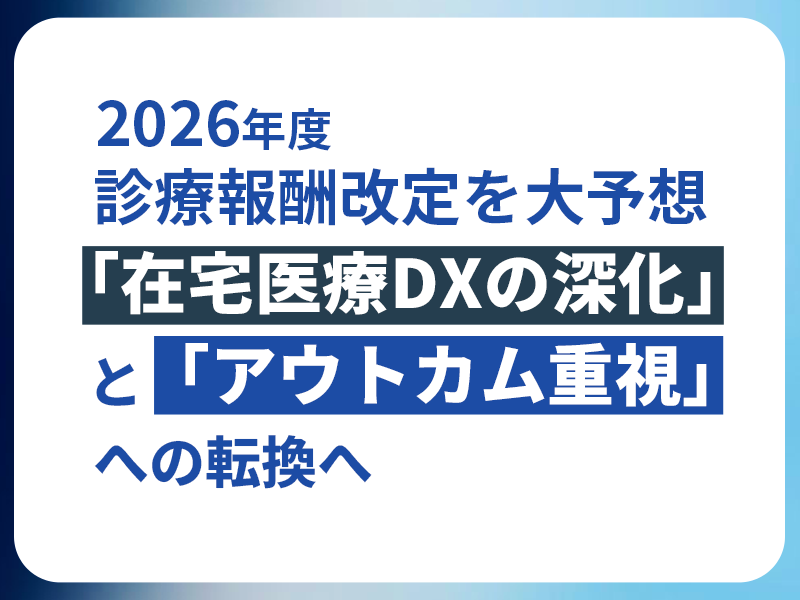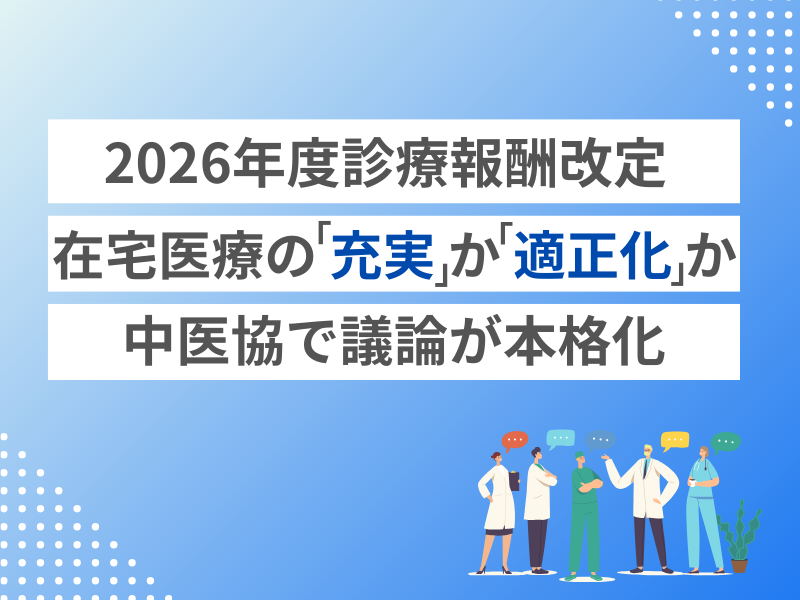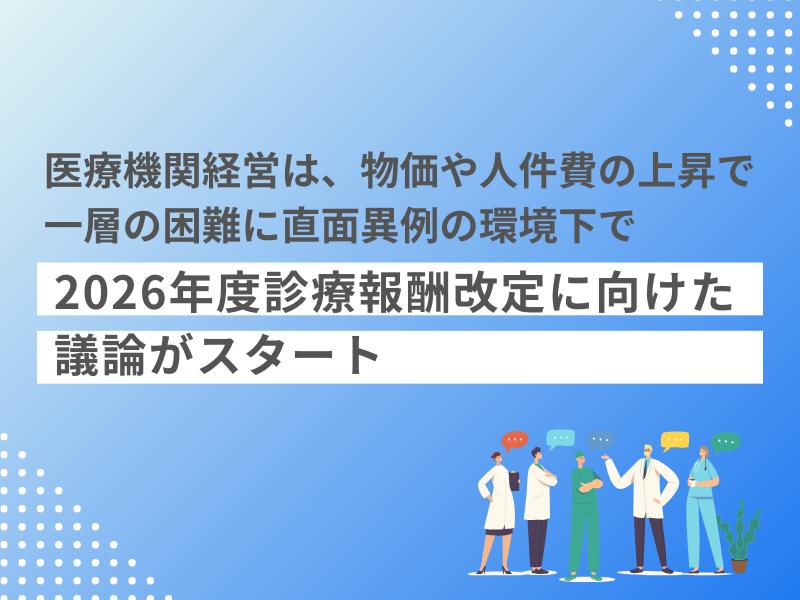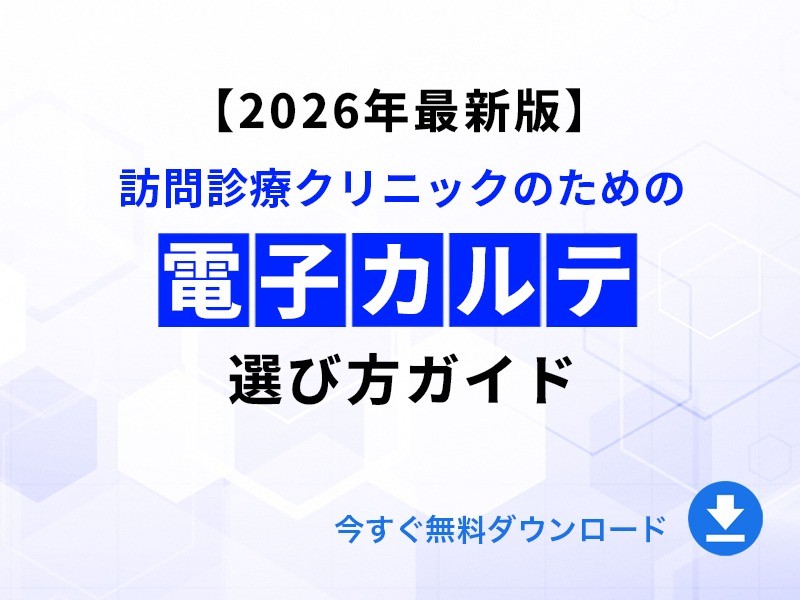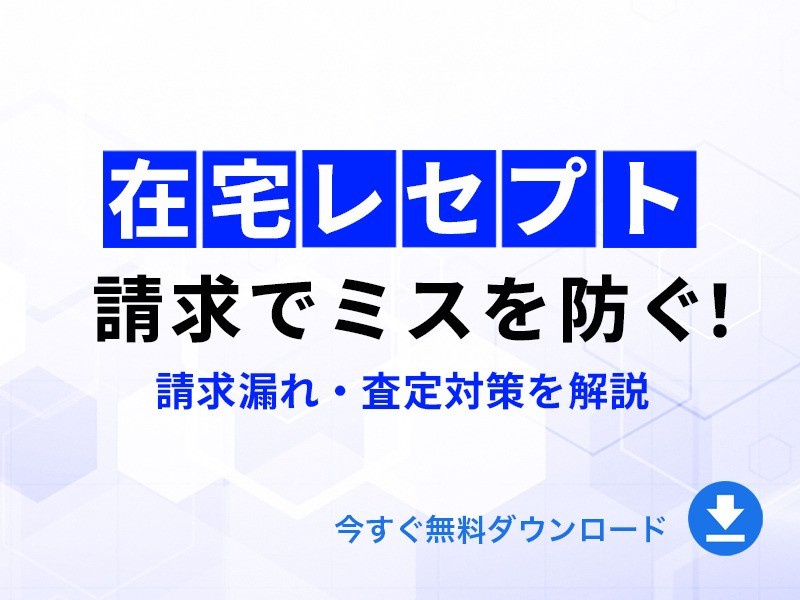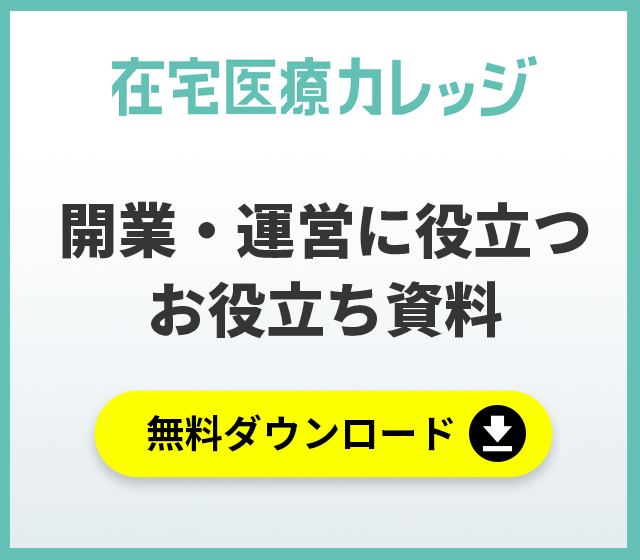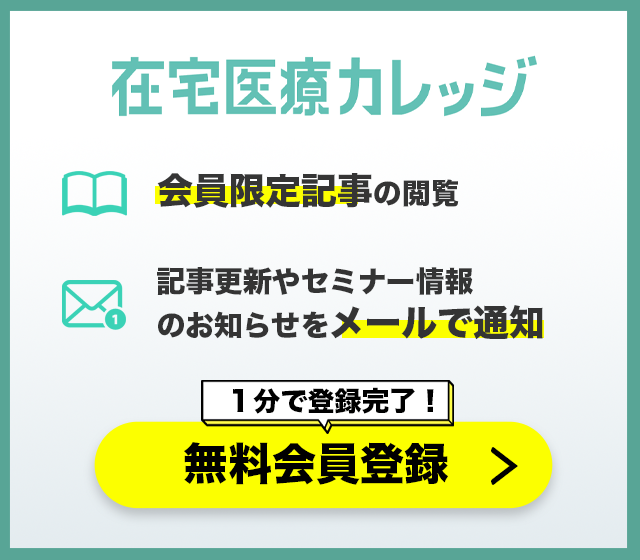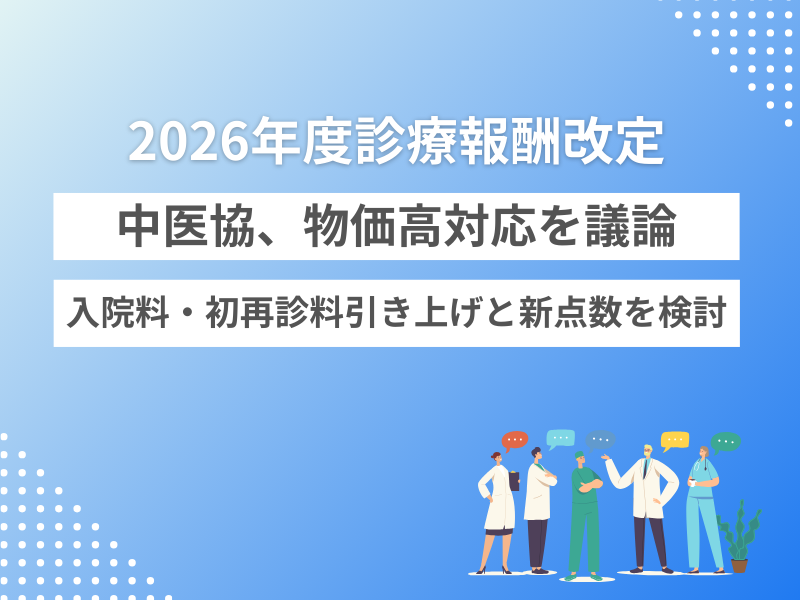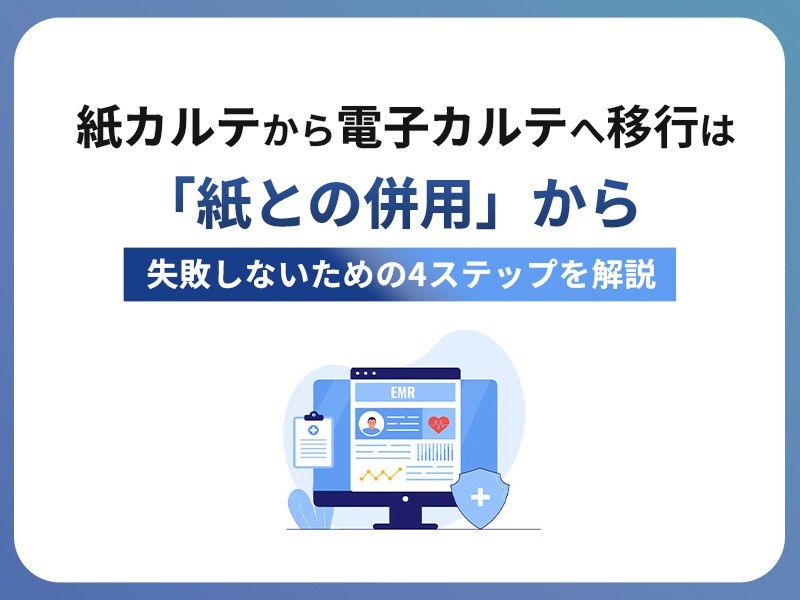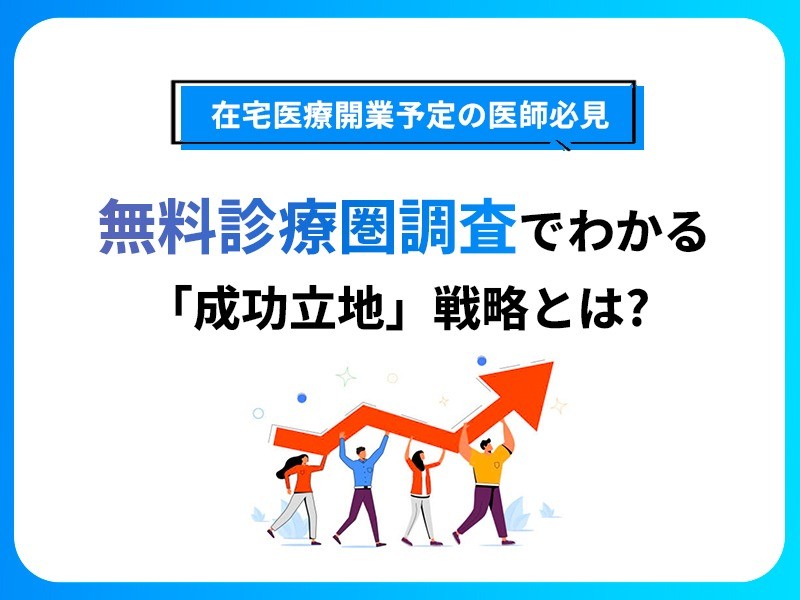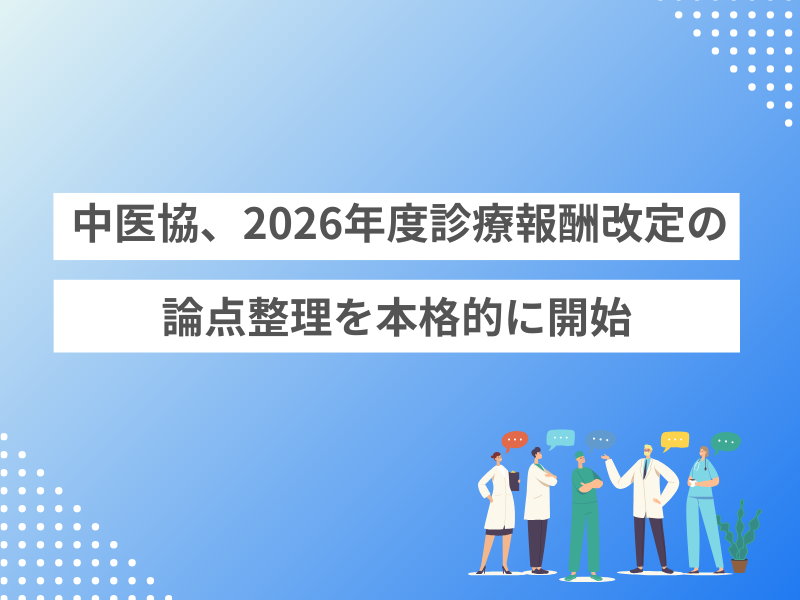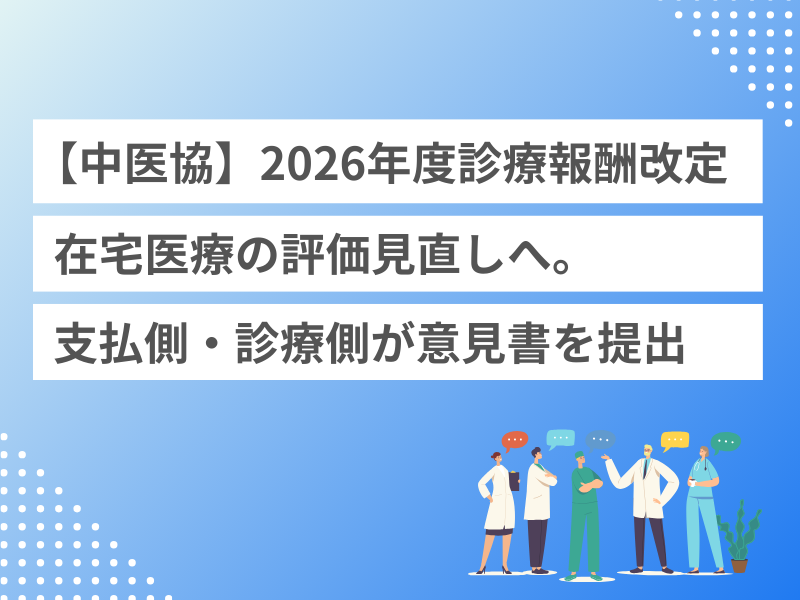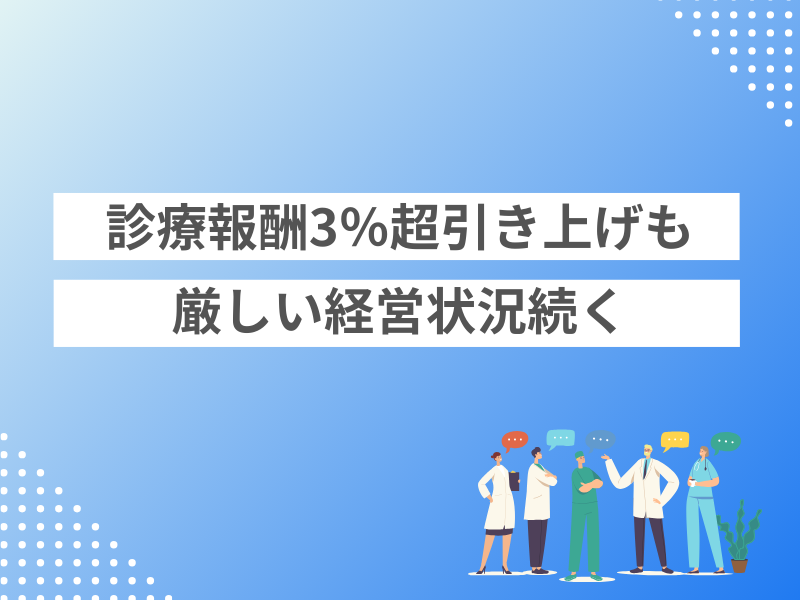- #制度
- #運営
- #診療報酬
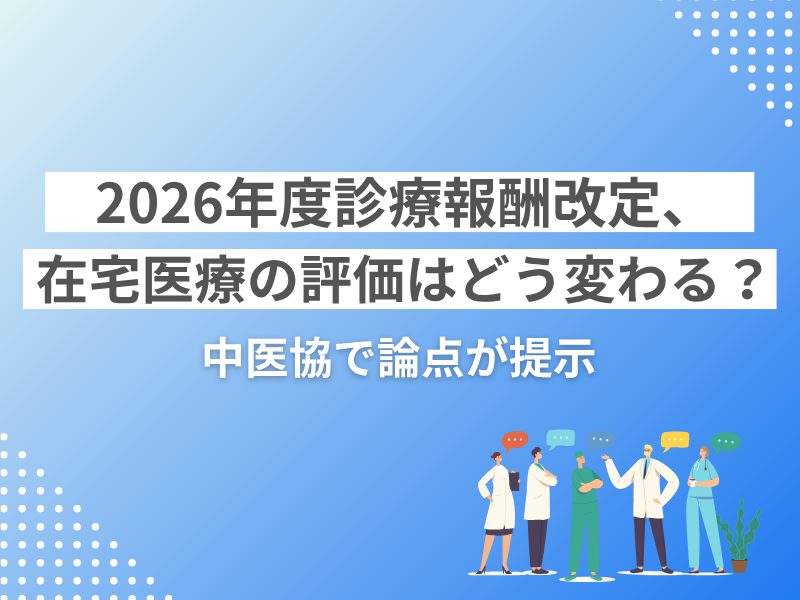
2025年10月1日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2026年度の次期診療報酬改定に向けた「在宅医療」および「訪問看護」の評価に関する踏み込んだ議論なされました。今後の在宅医療のあり方を大きく左右する可能性のある、注目すべき論点が複数提示されています。
在宅医療の役割を担う医療機関への「メリハリの利いた評価」
今回の議論の大きな柱の一つが、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関への評価」です。
厚生労働省は、地域の在宅医療提供の中核となる在宅療養支援診療所・病院(在支診・病)について、より手厚い評価を行う方向性を示しました。具体的には、機能強化型の在支診・病の中でも、「緊急往診や看取り、重症患者の訪問実績が豊富で、十分な数の医師を配置している医療機関、他の医療機関への支援機能、医育機能を持つ在宅医療機関」を高く評価する案を提示しました。
これに対し、健康保険組合連合会の松本真人委員は、実績・体制・機能に着目した「よりメリハリの利いた評価体系」に見直すことも「十分にあり得る」と述べ、積極的な医療機関を重点的に評価する考えに賛同を示しました。
一方で、日本医師会の江澤和彦委員は、評価要件の一つとして議論された「医育機能」について、直接的な医療提供とは異なるため、患者負担に影響する点数算定の要件とすることには慎重であるべきとの考えを示しており、評価のあり方については多角的な議論が求められそうです。
「患者の状態」に応じた適切な診療の評価
もう一つの重要な論点が、「患者の状態などに応じた適切な診療の評価」です。
特に、「在宅時医学総合管理料」や「施設入居時等医学総合管理料」の算定において、「要介護度が低いものの、在宅医療を継続している患者の割合」を評価に勘案する案が提示され、委員の間で意見が分かれました。
江澤委員は、「要介護度は医療の指標とは異なる」と指摘。要介護度が低くても医療的な必要性が高い患者は多く存在するのが現状であり、要介護度のみに着目した評価ではなく、個々の患者の医療必要度や通院困難な要因などを丁寧に検討する必要があると主張しています。
一方、松本委員は重症患者への診療や診療体制の効率化という視点を重視し、評価にメリハリをつけるべきだと主張。患者の状態を見ながら外来通院可能な患者は外来への移行を促す方向性が望ましいとの認識を示しました。
今後の展望
このほか、「同一建物に住む複数人への訪問看護」や「短時間・頻回の訪問看護」の評価のあり方なども今後の論点として挙げられています。
今後、より具体的な議論が進む中で、在宅医療の現場で働く皆様の診療や働き方に直結する評価体系が形作られていきます。在宅医療の質と持続可能性を両立させるための議論の行方を、引き続き注視していく必要があります。
■あわせて読みたい
【2026(令和8)年度診療報酬改定を大予想】 「在宅医療DXの深化」と「アウトカム重視」への転換へ
【2026年度診療報酬改定】在宅医療の「充実」か「適正化」か。中医協で議論が本格化
参考)厚生労働省|中央社会保険医療協議会 総会(第618回)|在宅(その2)(令和7年10月1日)