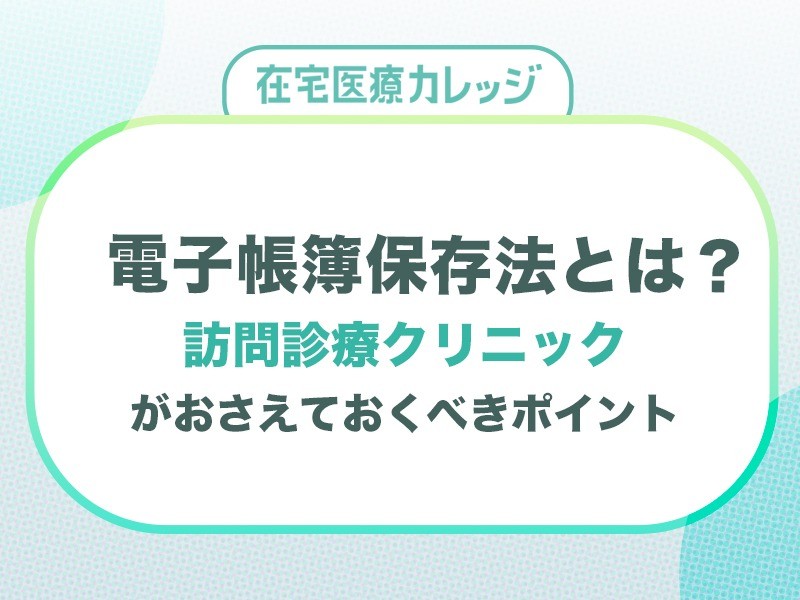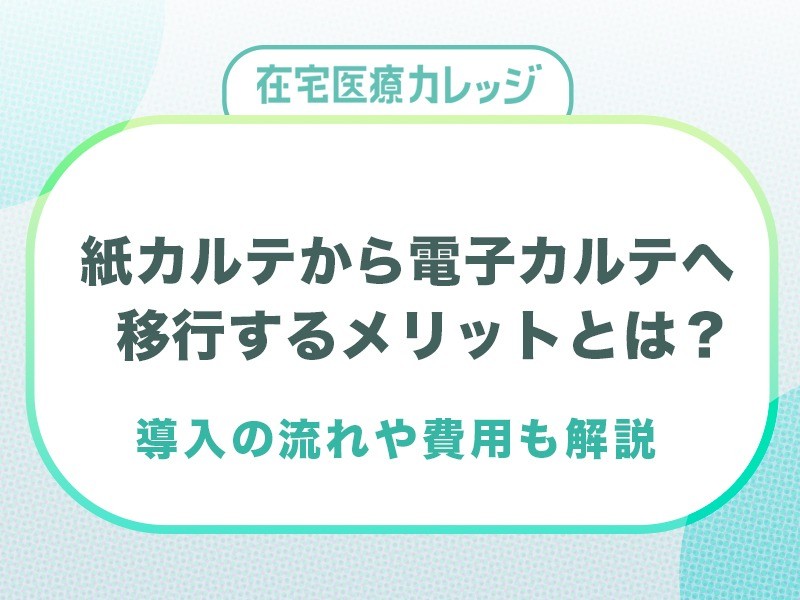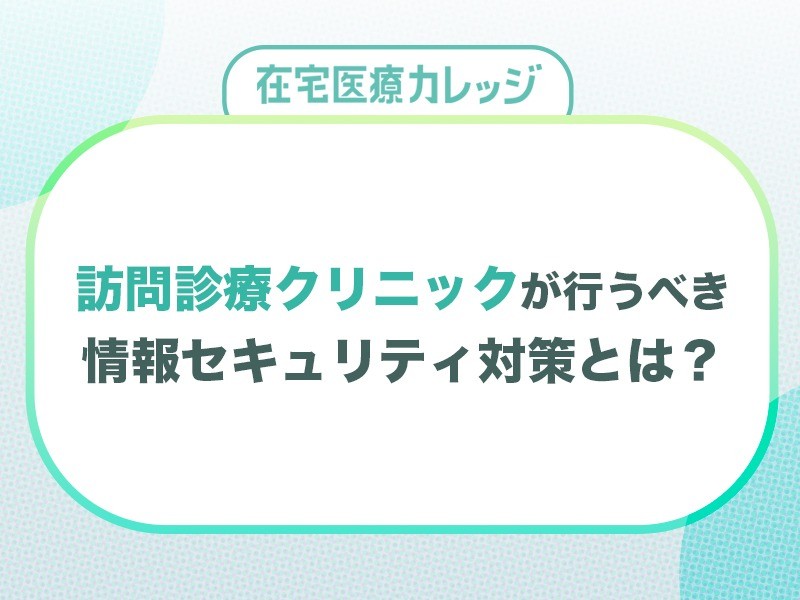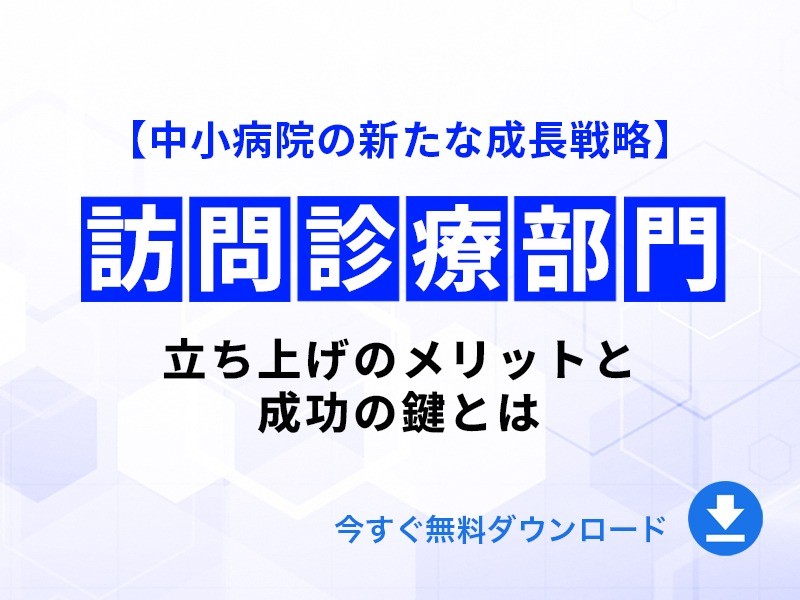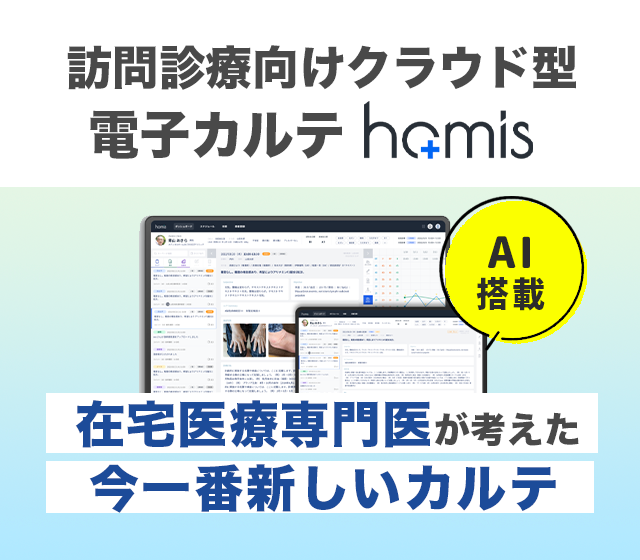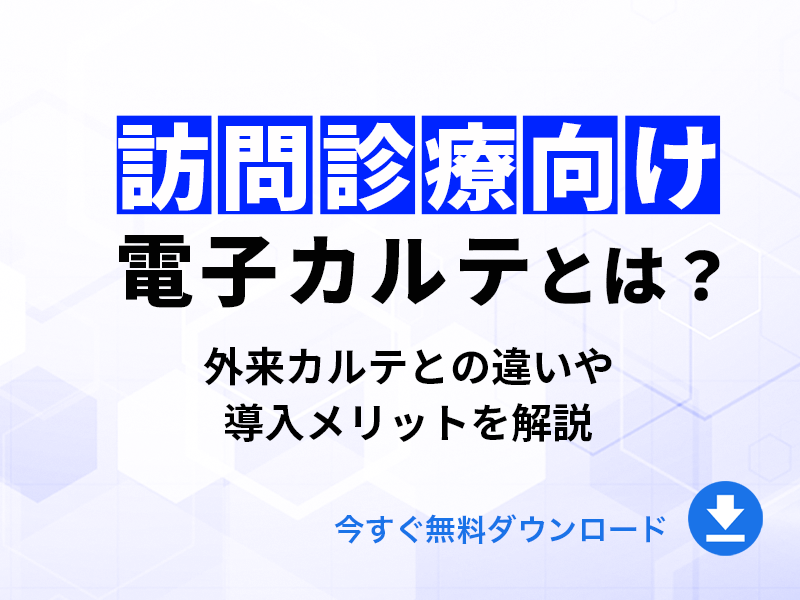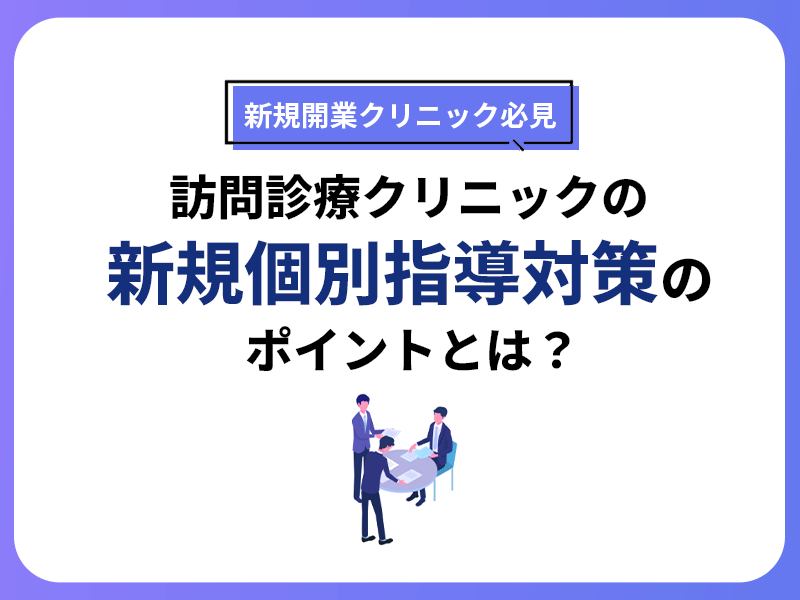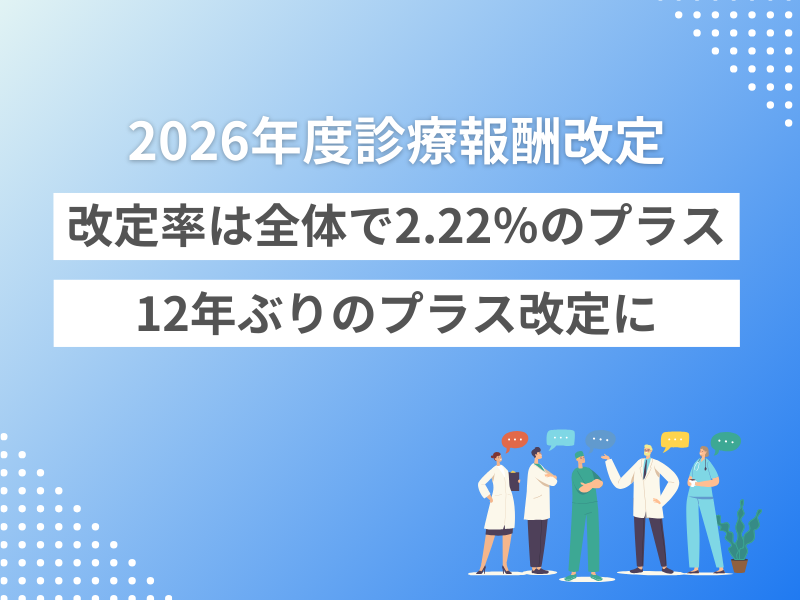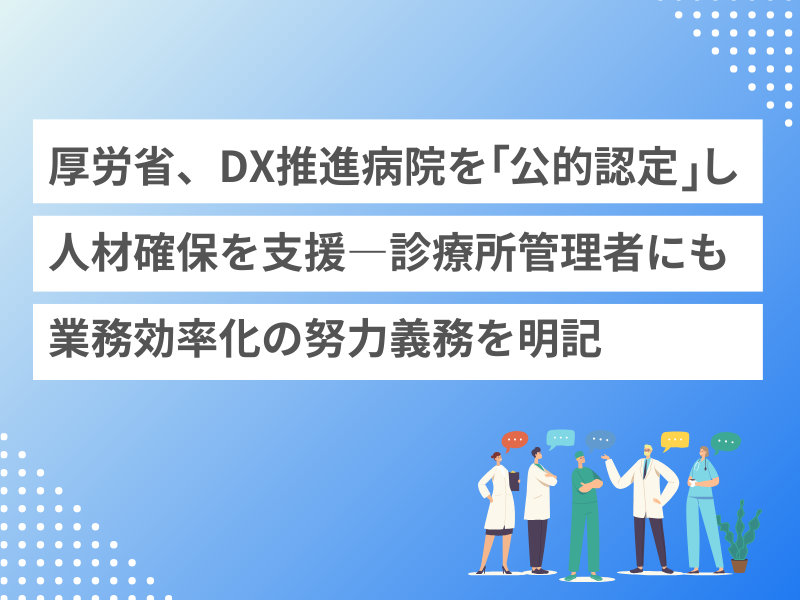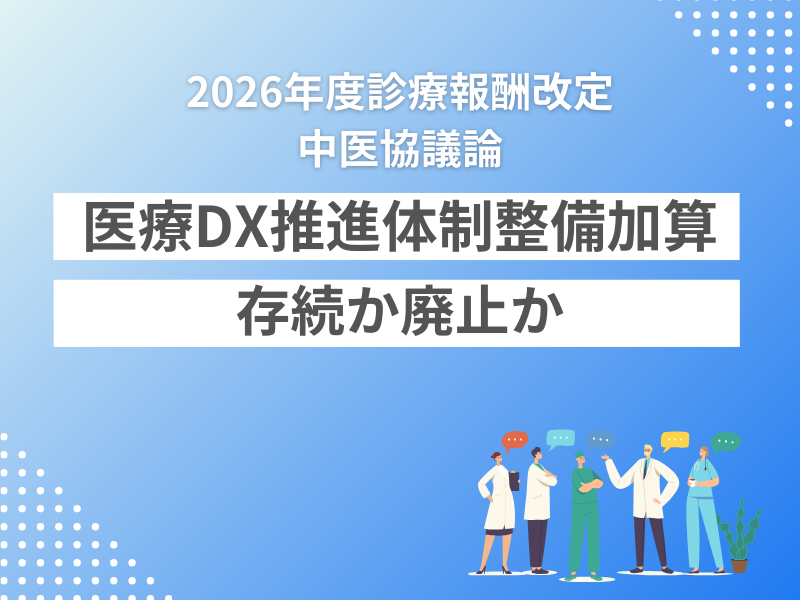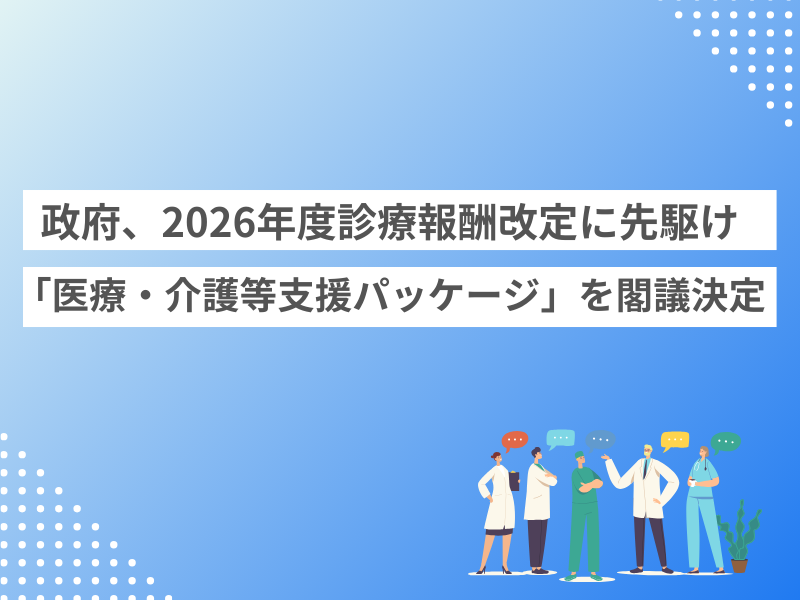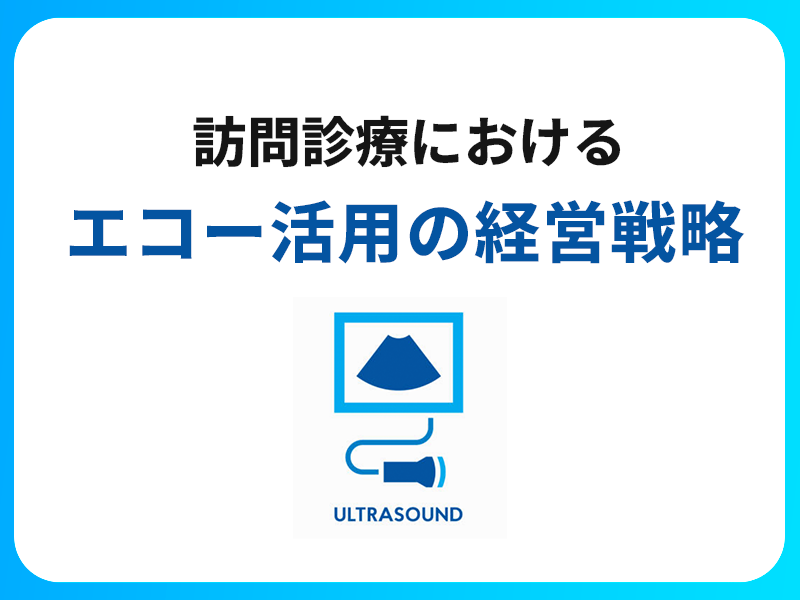- #運営
- #DX
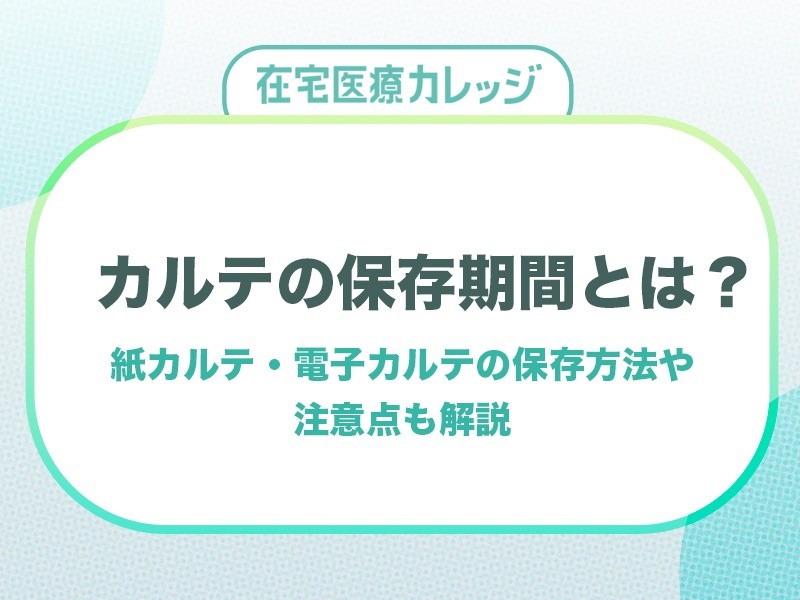
カルテの保存期間や適切な保存方法がわからず、管理にお困りではないでしょうか。紙カルテを適切に管理できないと、情報漏洩のリスクが高まり、法律で罰せられる可能性があります。
また、データの紛失や改ざんなどの問題に発展するリスクがあるため、適切に対策しなければなりません。
本記事では、カルテの保存期間や保存方法を解説します。紙カルテ・電子カルテを保管する際は、正しいルールに沿って管理していきましょう。
>>安心のセキュリティ!訪問診療向けクラウド型電子カルテhomisはこちら
カルテの保存期間は「5年間」が原則
カルテは、診療が完結した日を起点とし、5年間の保管が義務付けられています。もし、保存期間内に破棄すると、法律違反として罰則が与えられる可能性があります。カルテを含めた各種データの保存期間は以下のとおりです。
| 保存期間 | 項目 |
| 2年 |
|
|
|
| 5年 |
|
しかし、実際は「20年以上の保存」が推奨されるケースも多い
理由①:民法改正により損害賠償請求の時効が最大20年に
2020年の民法改正により、医療事故などの損害賠償請求の消滅時効は最長20年とされました。
そのため、万一の訴訟リスクを考慮して、カルテを20年間またはそれ以上保存する医療機関も増えています。
理由②:日本医師会は「電子化による永久保存」を推奨
日本医師会は、電子カルテ導入による情報の長期保存を重視しており、診療録の永久保存を推奨しています。
これは将来的な医療の質向上や、患者からの照会・訴訟対応の観点からも重要とされています。
日本医師会の見解:
「記録保存形式の主流が紙媒体から電子媒体に移行しつつある状況において、診療諸記録の保存期間は診療録の保存期間と同じになるべきである。わが国では5年という期間も最低限の法的義務として定められているが、永続的な保存が望ましい。」
引用)日本医師会|医師の職業倫理指針[第3版]
以上のような理由から、カルテを20年、あるいはそれ以上にわたって保存している医療機関も少なくありません。
とくに訴訟リスクへの備えや、診療情報の継続的な活用を目的として、実務上は長期保存がスタンダードになりつつあります。
そこで次に、紙カルテの場合にはどのように保存・管理されているのか、その方法や課題について解説していきます。
紙カルテの長期間の保存方法
紙カルテを保存するおもな方法は以下のとおりです。
- 院内で保管する
- 倉庫で保管する
- 電子化する
院内でカルテを保管するのが難しい場合、倉庫での保管や電子化の手段を取りましょう。
院内で保管する
カルテ保管用の棚を準備し、保存する方法です。クリニックの規模が小さく、患者さんの数が多い場合、カルテの収納場所を確保するのが難しくなるケースがあります。
そのため、収納スペースを確保するために、設備投資をおこなう必要があるでしょう。
倉庫で保管する
院内でカルテを保管するスペースが確保できない場合、倉庫を借りて保管する方法があります。
利用する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 必要に応じてすぐに利用できる体制を作ること
- 個人情報の保護がなされていること
- 保存する際は、保存の義務を有するクリニックの責任において実施すること
- 事故が発生した場合の責任の所在を明確にすること
電子化する
紙カルテをスキャナなどで電子化する方法です。実施する際は、実施計画書を作成する必要があります。
ただ、事前に対象となる患者さんにカルテを電子化して保存することを周知しなければなりません。
紙カルテをデータ化する際の注意点
紙カルテをデータ化する際のおもな注意点は以下のとおりです。
- 電子署名・スタンプを押す必要がある
- 紙カルテを廃棄する際はルールを遵守する
- 電子保存の3条件を遵守する
患者さんの大事なカルテを扱ううえで、適切な管理方法を守る必要があります。
電子署名・スタンプを押す必要がある
電子署名・スタンプは、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)で推奨されている保管方法です。
電子署名・スタンプを押すことで、電子的な保管が認められ、破棄できるようになります。
紙カルテを廃棄する際はルールを遵守する
データ化した後の紙カルテは、適切な方法で破棄する必要があります。正しく破棄できていないと、患者さんの氏名や住所、治療歴や家族歴などが流出し、医師法やプライバシーの人権侵害につながります。
紙カルテを破棄する際は、シュレッダーにかけて適切に処理しましょう。クリニック内で処理できない場合は、プライバシーマーク(「個人情報を適切に管理している」と評価された事業者が使用できるマーク)を保有した廃棄業者に依頼することをおすすめします。
電子保存の3原則を満たす
カルテを電子化する際は電子保存の3原則を守らなければなりません。電子保存の3原則とは、「診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関するガイドライン」で規定された以下3つの基準を指します。
- 真正性
- 見読性
- 保存性
カルテが正しいもので、かつ誰でも確実に読める状態が担保されつつ、適切に保存されていることが重要です。
真正性
真正性では、カルテの責任と所在が明確になっており、虚偽や改ざんなどがないことが必要になります。
真正性を担保するためのおもな対策は以下のとおりです。
- 不正入力を防止するためのセキュリティ対策を実行する
- 機器やソフトウェアの品質を管理する
- 更新履歴の保存する
- 識別情報の記録する
- 作成者の識別・認証をするためにID・パスワードを設定する
見読性
見読性では、誰が読んでも「確実に見て読めること」が必要になります。カルテは医師や看護師だけでなく、患者さんやその家族にも共有しなければなりません。
また、必要なタイミングで情報に対して適切にアクセスし、情報を抽出できる環境を整える必要があります。
保存性
保存性では、保存すべき期間を守りながら、真正性や見読性を確保した状態で保存することが求められます。
保存性を担保するためには、記憶媒体の劣化対策やウイルス対策を徹底し、バックアップをこまめにおこなうことが大切です。
訪問診療クリニックの情報セキュリティ対策に関するよくある質問
紙カルテ・電子カルテの保存方法に関するよくある質問は以下のとおりです。
カルテの保存に関するルールや今後の動き、罰則について把握し、適切に管理していきましょう。
-
Q
閉院する際のデータ保管義務はどうなる?
A以下の3つのパターンに応じて適切に対処する必要があります。
■ 管理者が死亡した場合
公的機関における保管が推奨されています。一方で、損害賠償責任は遺族に移るため、重要な書類は保管しておくとよいでしょう。
■ 他院へカルテを継承する場合
保管義務は継承先の医療機関の管理者に移行します。
■ カルテを継承せずに閉院する閉院する場合
カルテの保管期間である5年間は保管し続ける必要があります。 -
Q
いつから電子カルテは義務化される?
A政府により、遅くとも2030年には概ねすべての医療機関にて電子カルテの導入を目指すことが発表されています。
-
Q
電子保存の3原則が守られていない場合の罰則は?
A即座に罰則が課されるわけでないないものの、医師法や個人情報保護法に違反するおそれがあります。
カルテの長期保存ならクラウド型電子カルテがおすすめ
カルテの保管期間は5年です。この期間内では、院内や倉庫などを利用し、データを適切に管理する必要があります。
しかし、紙カルテの場合、保管スペースが必要になるため、クリニックによっては保管場所を確保するのが難しいケースがあります。また、セキュリティ面で紛失や改ざんのリスクがあることがデメリットといえます。
カルテの保管スペースやセキュリティ上の問題がある場合は、電子化をおこない、データを適切に管理しましょう。
カルテの長期保存の面からもクラウド型電子カルテはおすすめです。
クラウド型電子カルテは外部のクラウドサーバーにカルテ情報を保存する方法で、カルテ保存の観点からも以下のメリットがあります。
- 保管スペース不要・データ消失リスクを最小限に
- 法改正や制度変更に自動対応
- 訪問診療など遠隔地からもアクセス可能
- 自動バックアップと堅牢なセキュリティ体制
- 医療情報ガイドライン準拠の設計で安心
現在紙カルテやオンプレミス型のカルテをお使いの方は、セキュリティ面からもクラウド型カルテへの切り替えをおすすめします。
セキュリティ面も安心!訪問診療向けクラウド型電子カルテ「homis」
患者さんの個人情報が蓄積されるカルテは情報セキュリティ面も考慮して選ぶことが大切です。
訪問診療向けクラウド型電子カルテhomisは最新のセキュリティ技術で患者さんの大切な個人情報をしっかりと守ります。
>>訪問診療向け電子カルテhomisのくわしい機能はこちら
安心のセキュリティ
国内のデータセンターでデータを管理しています。また、インターネット通信時の伝送データはhttpsという技術を用いて暗号化を行なっています。最新の暗号化技術でデータのやり取りを保護しているので、情報の漏洩を防止しています。
また、運営会社のメディカルインフォマティクス株式会社は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO27001」を取得しております。
万全のバックアップ体制
データセンターのデータについても定期的にバックアップを取っているので、災害時等有事の際にも最新のデータが確保されております。
くわしい機能を知りたい、使い勝手を試してみたい、セキュリティ面をチェックしたい…という方、
まずはお気軽に無料デモでお試しください。
homisユーザー見学会や開業をお考えの方には無料診療圏調査も受け付けております。お気軽にご相談ください。