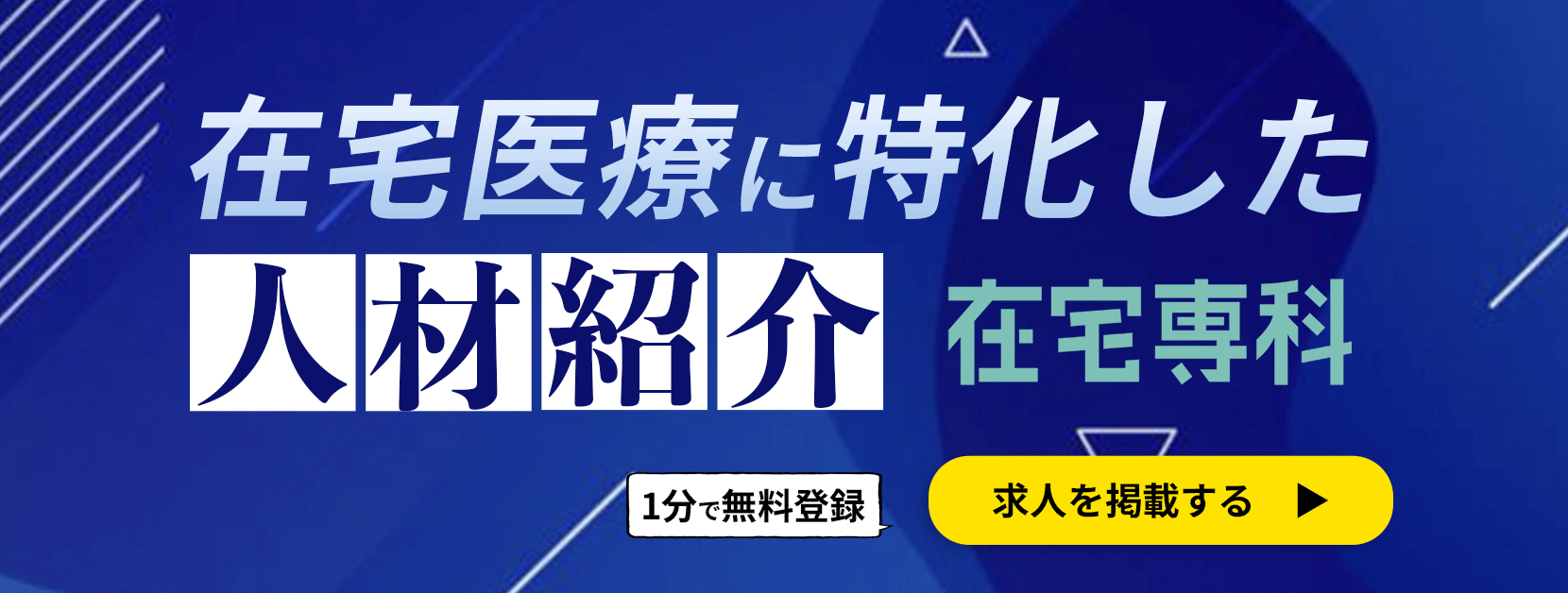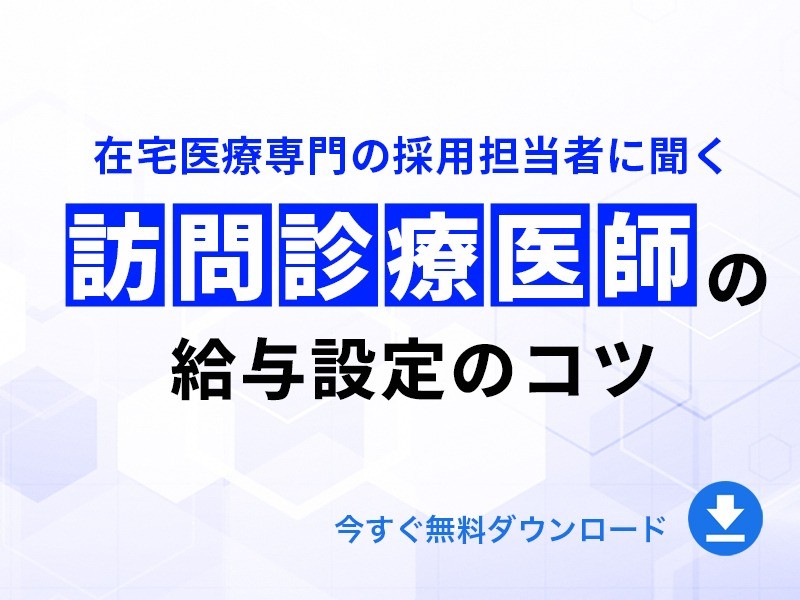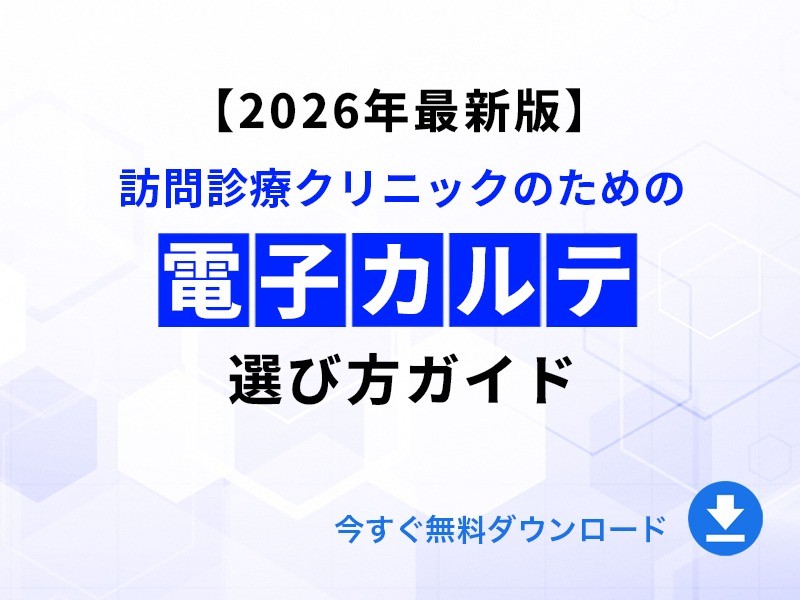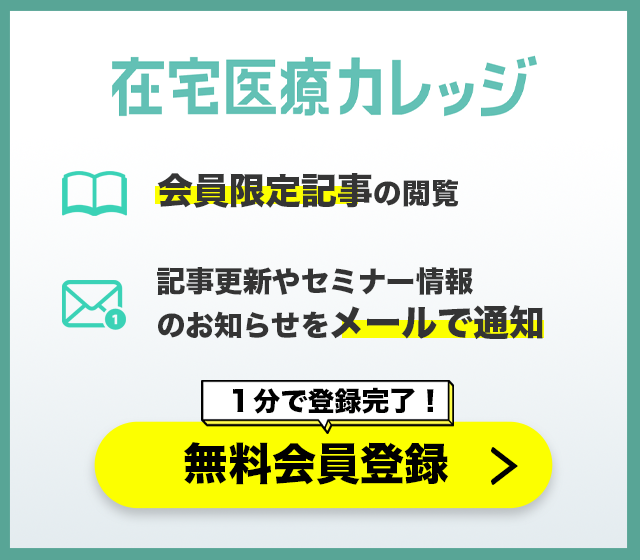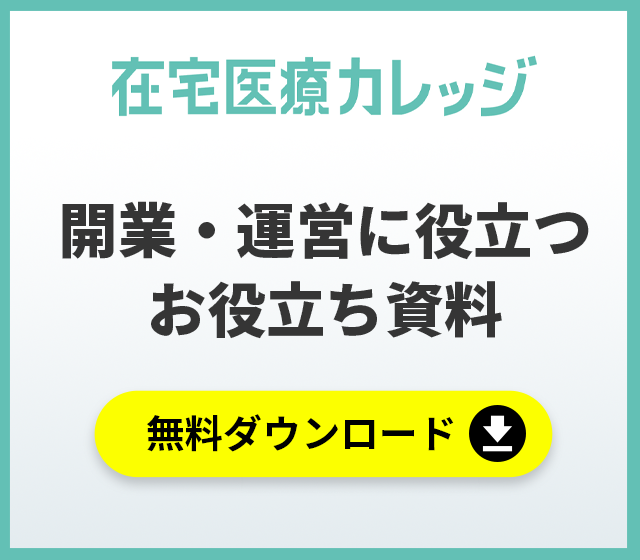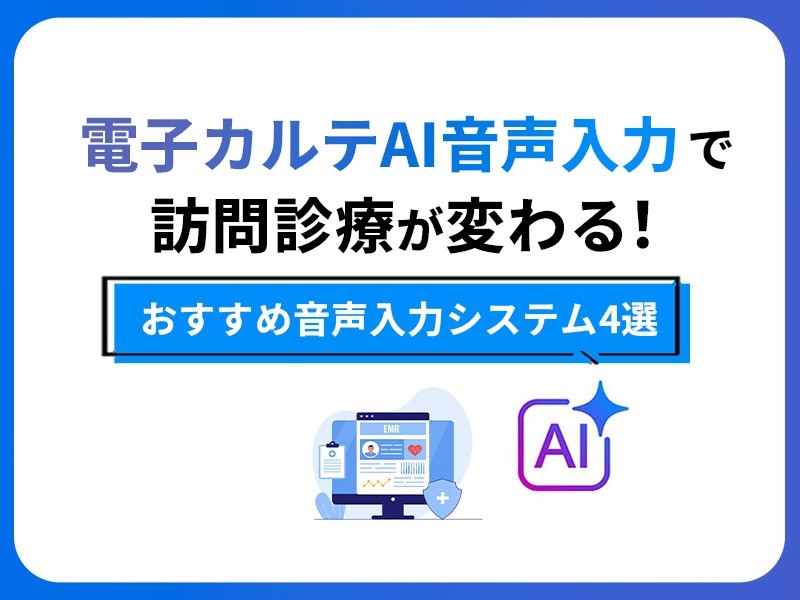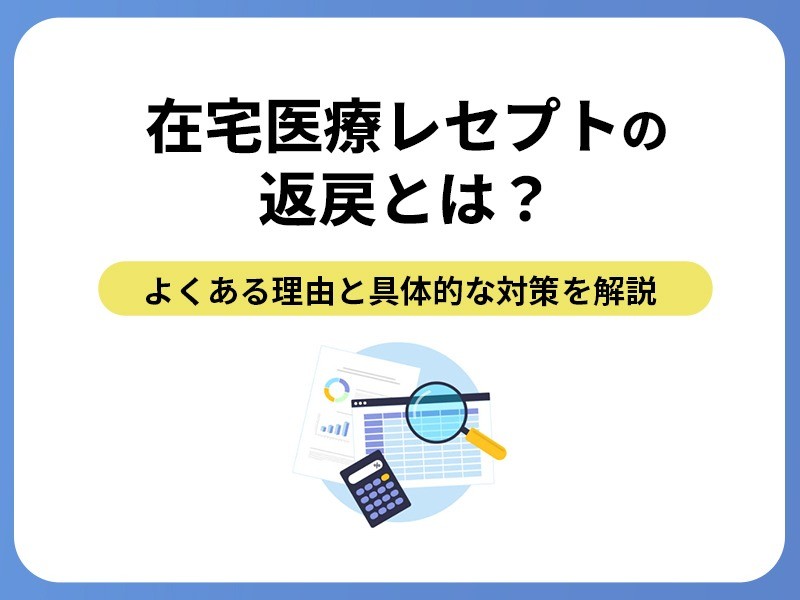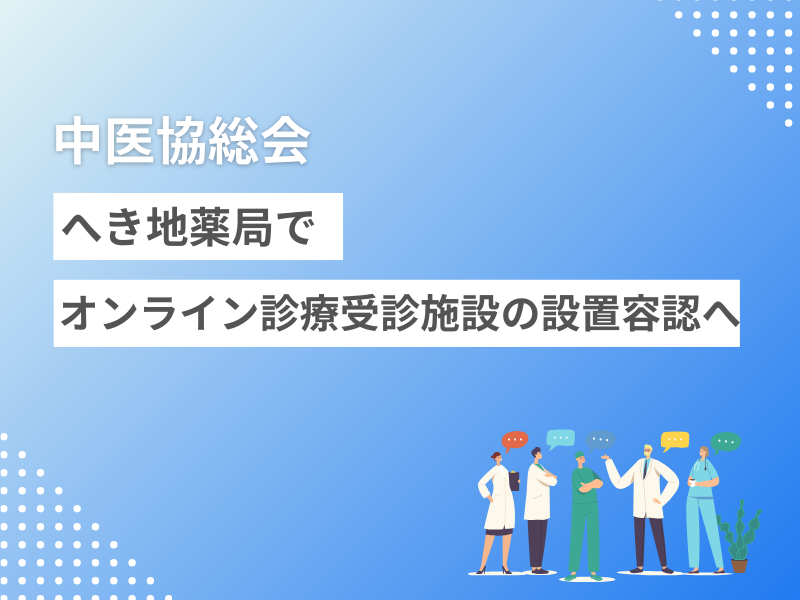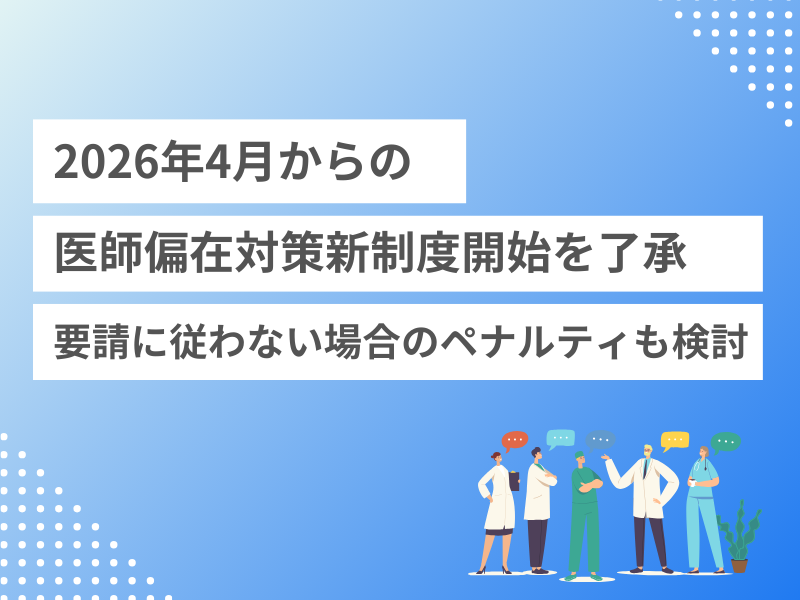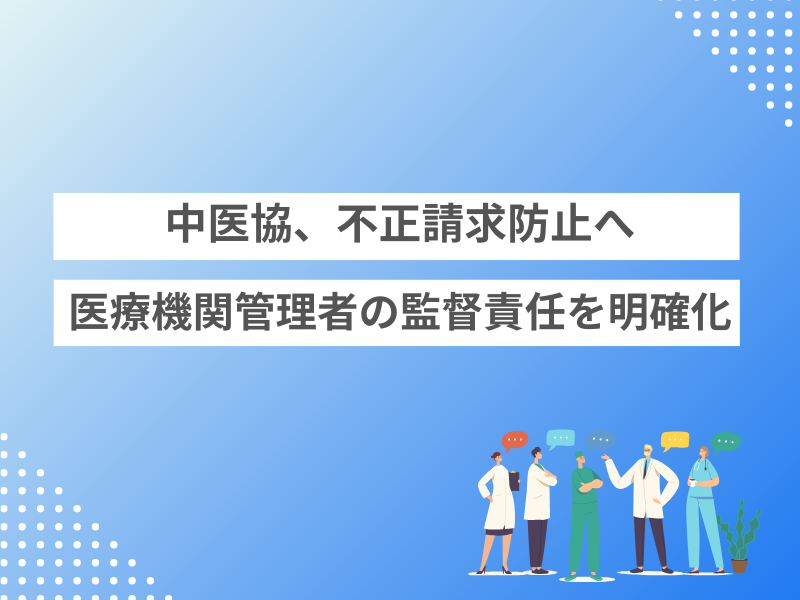- #制度
- #運営
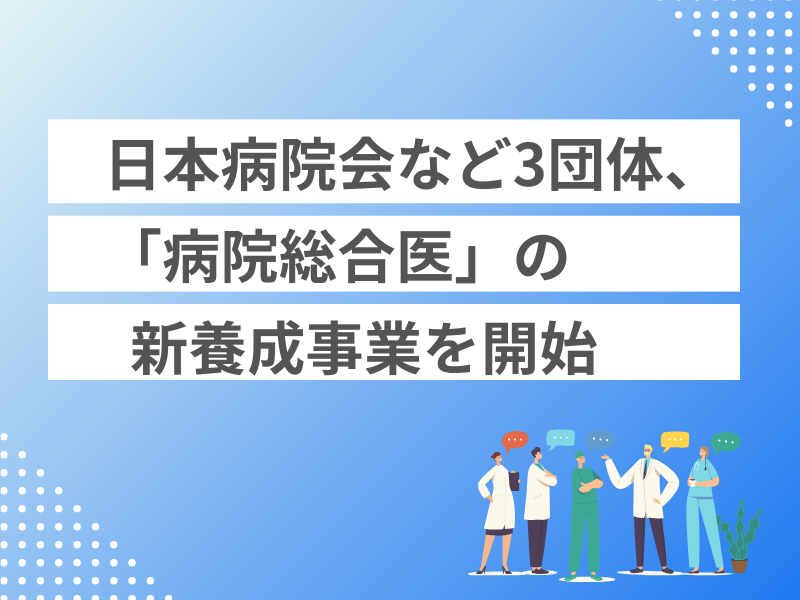
日本病院会、全国自治体病院協議会、全国国民健康保険診療施設協議会の3団体は、多様な疾病に総合的に対応できる「病院総合医」の養成と認定を目的とした共同事業を新たに開始しました。
高齢化の進展とそれに伴う患者の病態の複雑化を背景に、専門領域だけでなく、より広い視野で診療できる医師を育成し、地域医療の基盤強化と医師偏在の解消を目指します。
「病院総合医」養成事業とは
本事業は、特定の専門分野を持つ医師が、その経験を生かしつつ総合的な診療能力を習得し、新たなキャリアを形成することを支援するものです。
参加する医師は、原則として2年間の研修を受け、地域医療の最前線で「かかりつけ医機能」を実践的に学びます。
事業の主なポイント:
- 参加要件: 臨床経験6年以上で、3団体の会員施設に勤務する(またはその予定の)医師などが対象となります。
- 研修内容: 臨床能力、社会性、人間性、倫理観の4つの到達目標に基づき、多職種連携や地域包括ケアシステムに関する内容を含む研修が行われます。
- 認定: 研修修了後、委員会の審査を経て認定され、認定期間は5年です。既に十分な実績を持つ医師は、推薦により研修期間の短縮・免除も可能です。
在宅医療業界への影響
今回の「病院総合医」養成事業は、病院内にとどまらず、在宅医療の分野にも大きな影響を与えると考えられます。
- 地域包括ケアシステムの担い手が増加
本事業の理念には「地域住民とともに地域包括ケアシステム構築に貢献できる医師を養成する」ことが明確に掲げられています。
養成される病院総合医は、病院と地域をつなぐハブとしての役割が期待でき、在宅医療を支える中核的な人材となる可能性があります。 - 多職種連携の質の向上
研修の到達目標には、多職種チームとの連携やリーダー的役割を担う能力が含まれています。これにより、医師、看護師、ケアマネジャー、リハビリ専門職などがより円滑に連携できるようになり、在宅患者一人ひとりに対するケアの質が向上することが期待されます。 - 医師偏在の解消による在宅医の確保
3団体は、この事業が医師偏在問題の解決の糸口になるとしています。特に在宅医療の担い手が不足している地域において、総合的な診療能力を持つ医師が増えることは、新たな在宅医の確保に繋がり、地域医療の格差是正に貢献する可能性があります。
まとめ
この度の「病院総合医」養成事業は、単に病院内で活躍する総合医を増やすだけでなく、地域全体の医療提供体制、特に在宅医療を含む「地域包括ケアシステム」を強化するための重要な一手です。
養成された医師たちが、病院と在宅、医療と介護の架け橋としてどのように活躍していくのか。在宅医療業界としても、この新しい取り組みから生まれる人材に大きな期待を寄せ、今後の動向を注視していく必要があります。
引用元:
一般社団法人日本病院会, 公益社団法人全国自治体病院協議会, 公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会. (2025). 病院総合医養成事業のご案内.