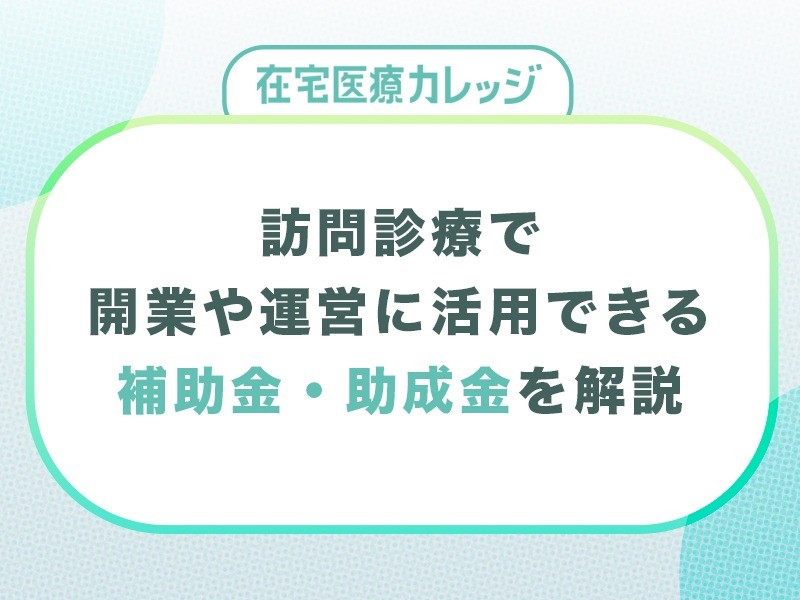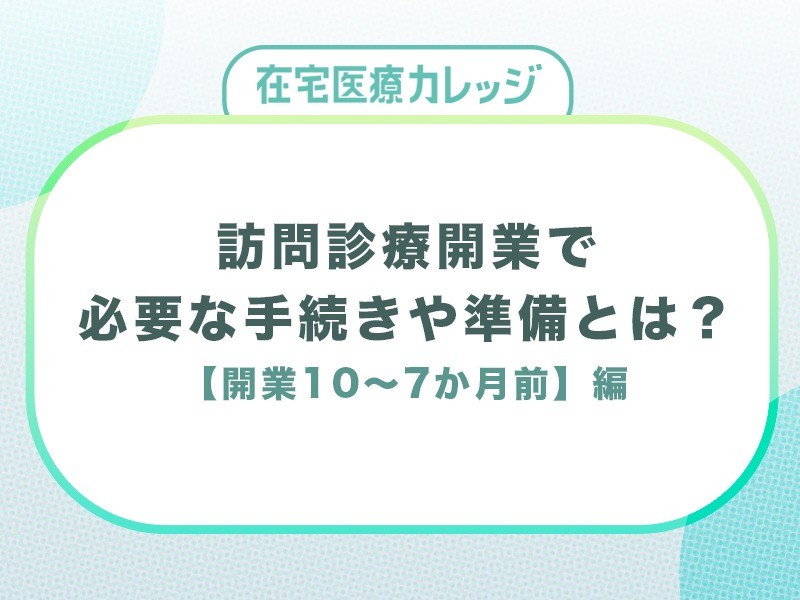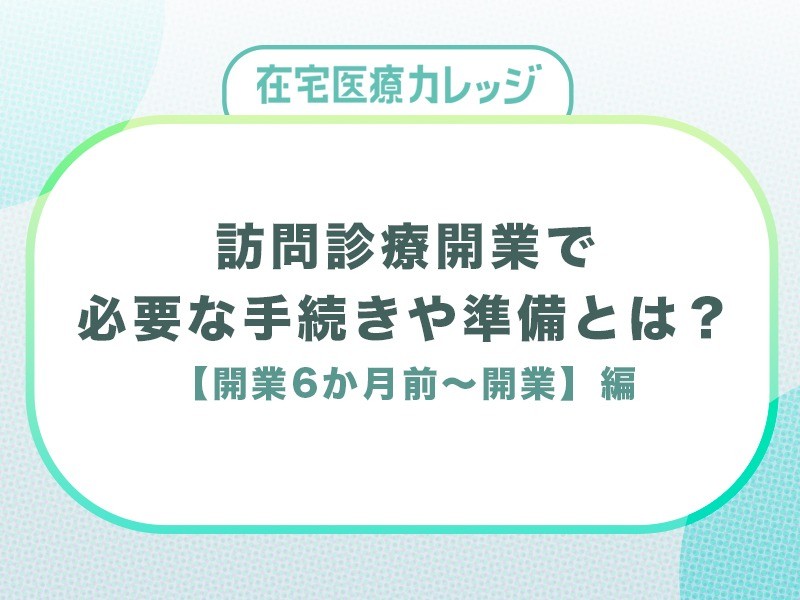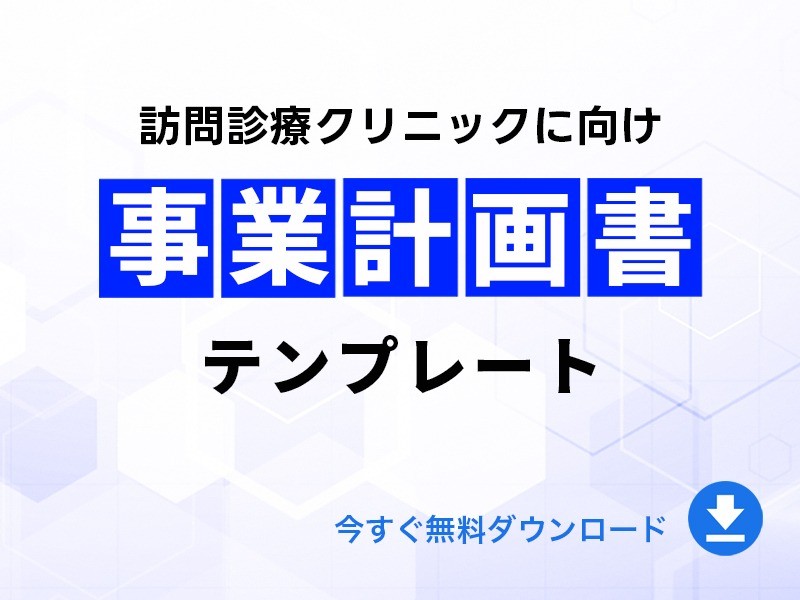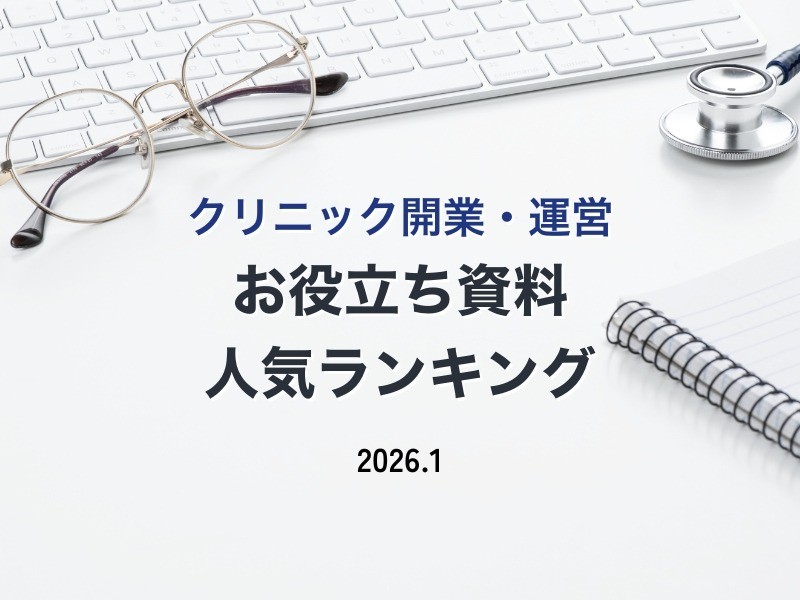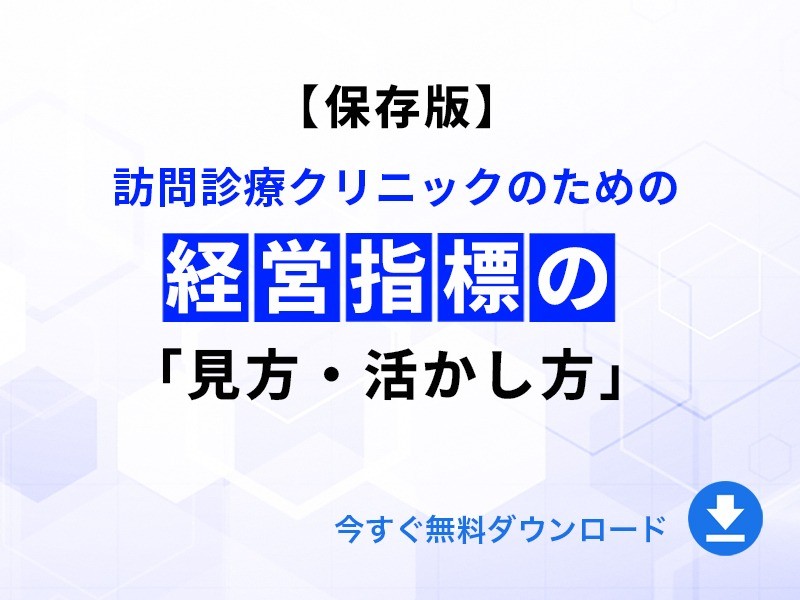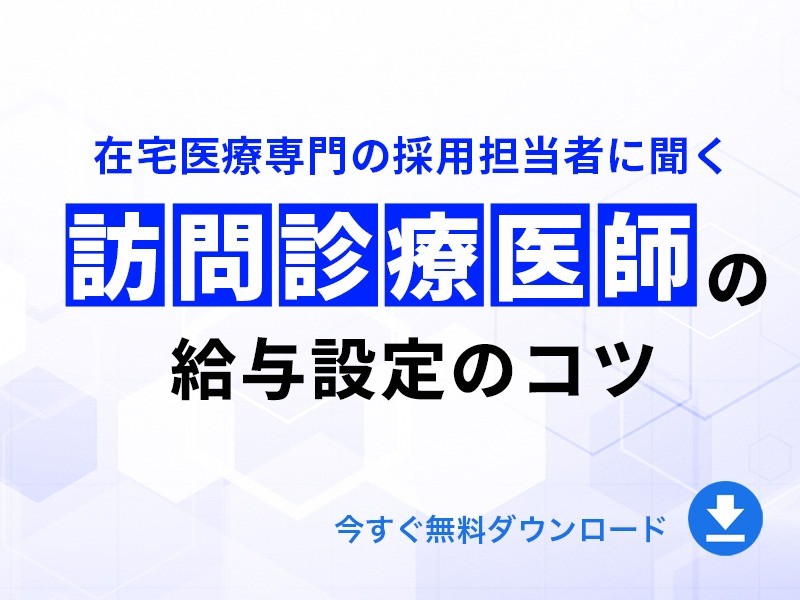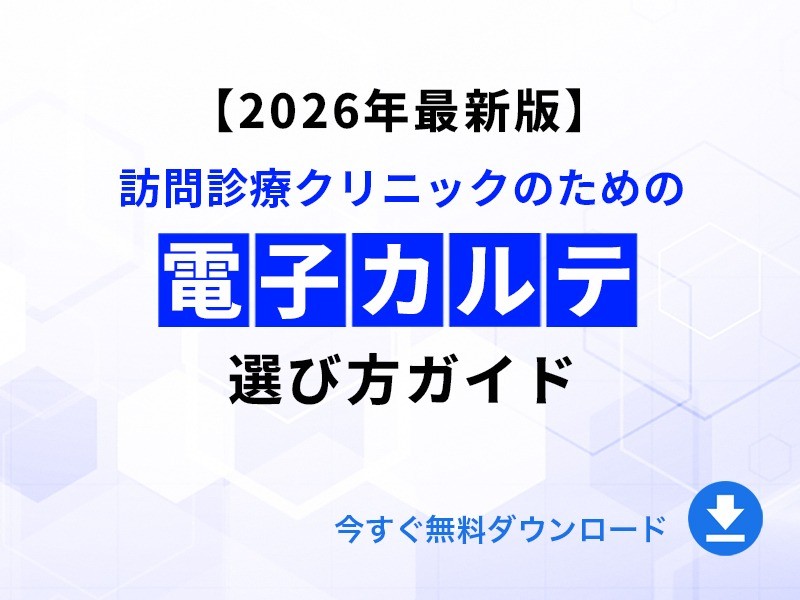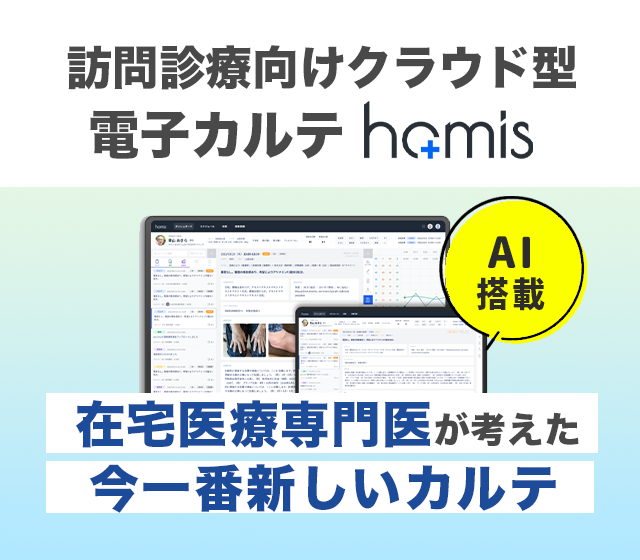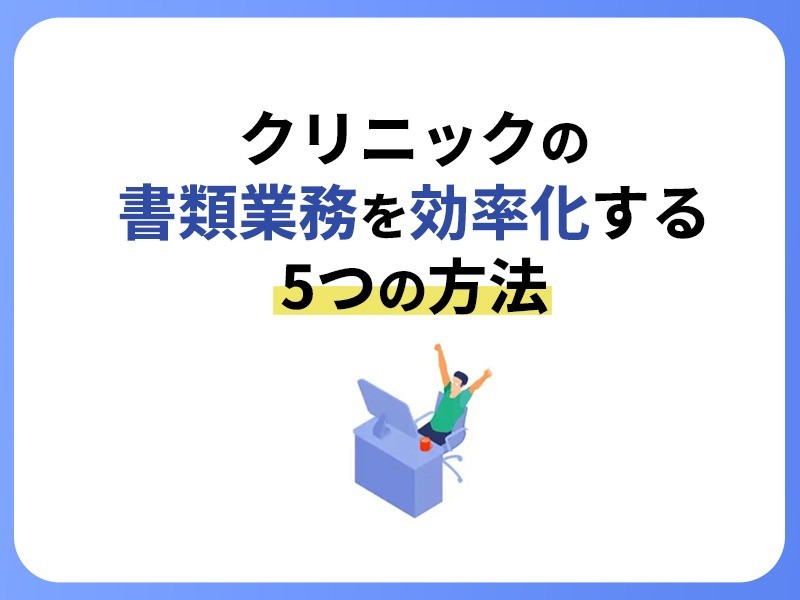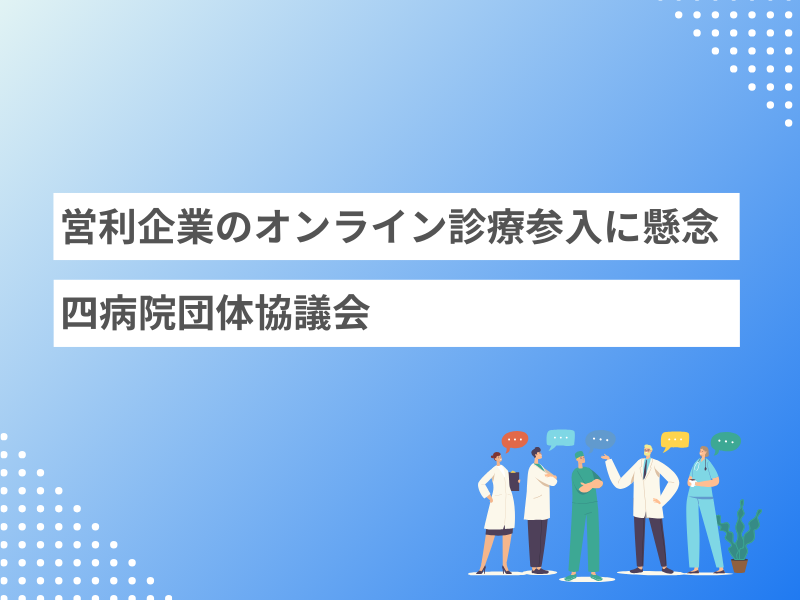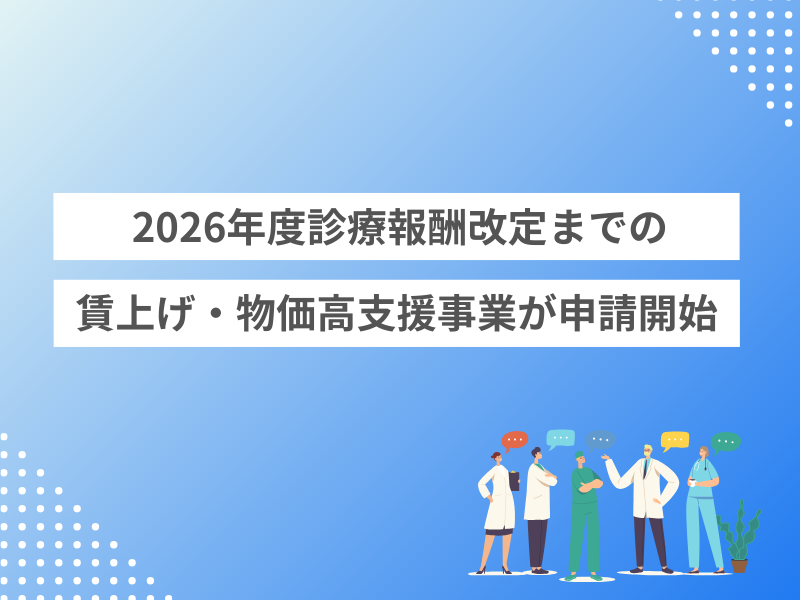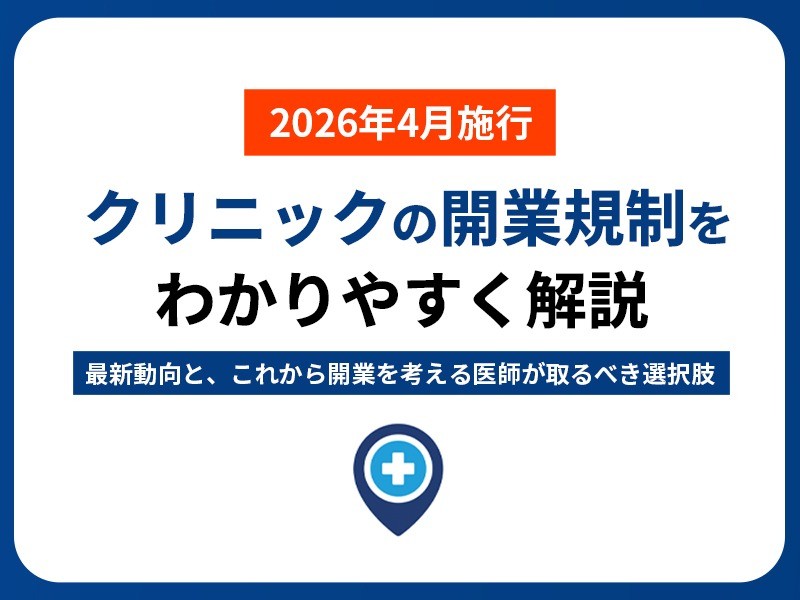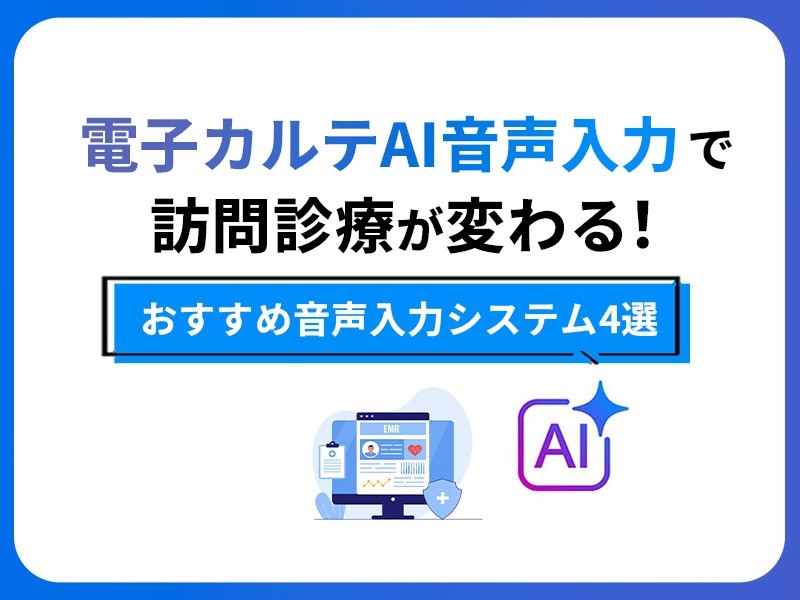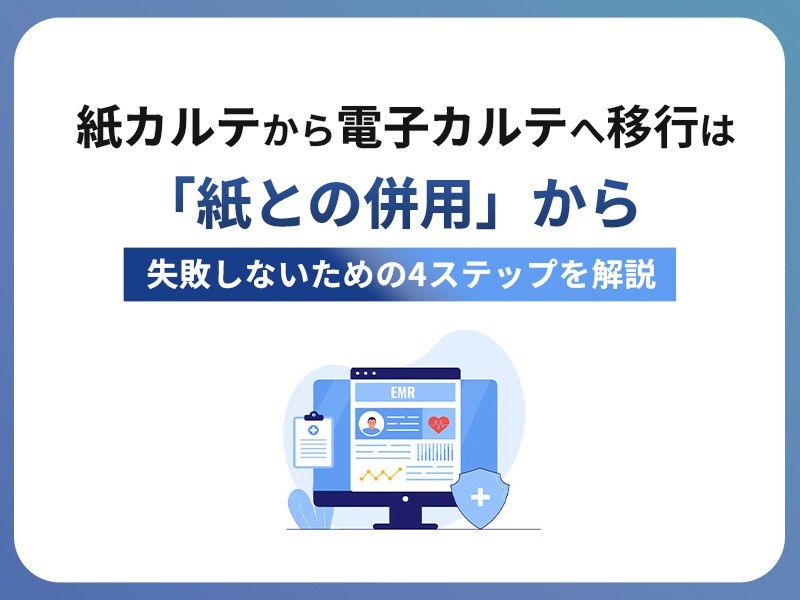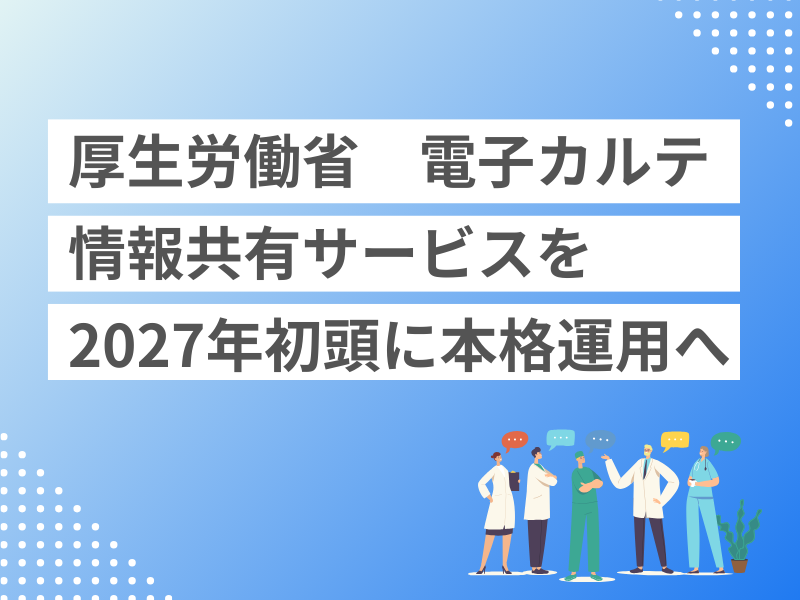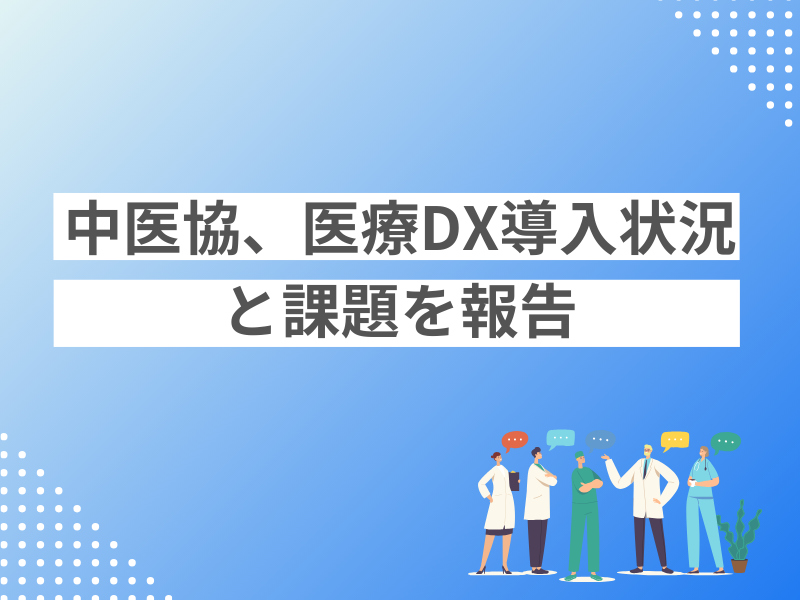- #DX
- #運営
- #開業
.jpg)
「電子カルテを導入したいが費用がかかりそうで躊躇してしまう」
「電子カルテの初期導入費用はなるべく抑えたい」
このようなお悩みを持つ訪問診療クリニックの院長・事務長の方、多いのではないでしょうか。
今回は電子カルテにかかる導入費用や運用コストについて解説していきます。
コストを抑えるポイントも解説していますので、電子カルテ導入の参考にしてみてください。
訪問診療向け電子カルテの導入費用の相場
電子カルテの導入費用は、「オンプレミス型」か「クラウド型」かによって大きく異なります。
それぞれの特徴と費用相場を見ていきましょう。
| クラウド型 | オンプレミス型 | レセプトコンピューター | |
| 初期導入費用 | 数十万~100万 | 250万~400万円 | 150万円前後 |
| 月額費用 | 2~5万円 | 2~3万円(保守費用) | 2万円程度 |
オンプレミス型
「オンプレミス型」とは、院内にサーバーや専用端末を設置して使用する従来型の電子カルテです。
初期導入時に大きな投資が必要となる一方で、カスタマイズ性が高く、セキュリティを自院で管理できる点が特徴です。
- 初期導入費用:250万~400万円程度
- 月額(保守)費用:2~3万円程度
クラウド型
「クラウド型」は、電子カルテを提供する企業側のサーバーを利用し、インターネット経由でサービスを利用する形態です。
初期コストが抑えられ、運用もシンプルなため、訪問診療クリニックで選ばれるケースが増えています。
- 初期導入費用:数十万~100万円程度
- 月額費用:2~5万円程度
クラウド型の場合、サーバー管理やバージョンアップなどの保守作業を事業者側が行うため、クリニック側の負担が少ない点がメリットです。
導入・運用に関わる費用の内容
初期費用・月額費用
カルテの導入時の「初期費用」と運用開始後の維持のための「月額費用」が発生します。
パソコンの買い替え費用
オンプレミス型の場合、電子カルテ・レセコンはメーカーによっては、約5年利用するとメーカーから指定されたパソコン一式の買い換えを求められます。その際には、初期導入と同等の費用(電子カルテ:300万円程度、レセコン:150万円程度)が発生します。
サポート費用
電子カルテによってサポートの有償/無償範囲が異なりますので事前にしっかり確認しておきましょう。
システムのカスタマイズ費用
オンプレミス型の場合は、機能をカスタマイズすることができますが、その場合カスタマイズ費用が発生します。
一方、クラウド型の場合、パッケージ化されたシステムのため、一般的には自院に合わせたカスタマイズは行うことができません。しかし機能のアップデートは自動更新のため、いつでも最新のカルテを使用できるという考え方もあります。
ライセンス数による従量課金制
メーカーによって、使用する端末台数、使用するスタッフのアカウント数、患者数などでの従量課金制となる場合があります。自院の規模に見合ったコストになるか検討しましょう。
診療報酬改定時などの手動更新作業(人的コスト)
オンプレミス型の場合は診療報酬改定や機能アップデートはクリニック側で手動で行う必要があり、更新業務が発生(人的コストが発生)します。いわゆる「見えないコスト」ですが忙しい診療の中での毎回の手間や時間を考慮するとトータルで大きなコストとなります。
一方でクラウド型の場合はカルテ事業者側で一括更新されますのでクリニックでの対応が必要ありません。
カルテ導入費用を抑える5つのポイント
① クラウド型カルテを検討する
オンプレミス型(自院サーバー設置)と比較して、クラウド型は初期費用が圧倒的に低く抑えられます。
- サーバー購入や設置工事が不要
- 保守費用が月額に含まれる場合が多い
- ソフトウェア更新も自動で対応可能
そのため、限られた予算で導入を検討したいクリニックにとって、クラウド型はコストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。
② カルテとレセコンの販売窓口が一本化できる業者を選ぶ
レセプトコンピュータ(レセコン)と電子カルテを別々に導入すると連携費用や運用負担がかかります。
レセコン一体型のカルテか、レセコンの販売窓口も一本化している業者を選べば、導入費用や連携の手間を押さえられ、運用コストと人的コストを同時に削減できます。
③ 必要最小限の機能で患者数に応じた料金設定ができるカルテを選ぶ
多機能な電子カルテは魅力的ですが、初期導入では必要な機能だけに絞ることで費用を抑えられます。
訪問診療なら「地図連携」「スケジュール管理」など、目的に合う最小機能で開始し、後から必要な機能をオプション追加できるシステムを選べば月額費用も抑えられます。
また、患者数に応じた従量課金制の料金設定であれば、新規開業や小規模クリニックも規模に応じた料金となるため安心です。
④ 導入から運用まで支援のある業者を選ぶ
一見、導入費用が安くても、導入後のサポートが不十分だと、結果的に対応コストがかさむことがあります。
初期設定やデータ移行、スタッフ研修、サポート対応などがどこまで基本料金に含まれており、どの範囲が追加費用となるのかを事前に確認することが重要です。
また、レセプト作成支援や事務業務の代行サービスとスムーズに連携できる体制が整っていれば、日常業務の負担軽減にもつながり、安心して運用をスタートできます。
⑤ 補助金・助成金の活用
地域によっては、医療IT化や在宅医療推進の一環として、カルテ導入に関する補助金が用意されていることがあります。
医師会や自治体窓口に相談してみるのもおすすめです。
導入費用だけでなく、月額費用、サポート体制、人件費の節約効果などを含めた総コストで比較することが重要です。
最小限のコストで始めて、必要に応じて拡張していくという考え方が、特に訪問診療や小規模クリニックにはマッチします。
「homis」は費用を抑えたい訪問診療クリニックに最適な選択肢
訪問診療向け電子カルテ「homis」はこれらのポイントをしっかり押さえており、初期費用や運用面で安心して導入いただけます。
以下に、それぞれの特長をご紹介します。
在宅医療向けクラウド型電子カルテ homisを詳しく見てみる
-
クラウド型だから初期費用を大幅に削減
「homis」はクラウド型電子カルテ。
・バージョンアップも自動対応で、更新作業も不要
・セキュリティもクラウド側で一元管理

-
カルテとレセコンの販売窓口一本化で相場の約⅓の導入費用
homisの運営元であるメディカルインフォマティクス株式会社は日医IT認定サポート事業所に登録されており、日本医師会が提供するレセコン「ORCA」の導入・サポートも行っております。電子カルテ+レセコンの導入費用の相場の約1/3程度の費用に抑えることができます。
・導入・保守の窓口が一本化されており、導入コストを削減
・面倒なレセコン連携設定もサポートに含まれており、すぐに運用可能
人的リソースが限られるクリニックにも非常に相性の良い構成です。
-
必要最小限の機能から導入可能、料金もスケール型
homisでは、訪問診療クリニックに必要な機能だけに絞ったミニマムなプランから導入が可能です。
・クリニックの運営体制に応じて必要な機能をオプションで選択可能
・患者数に応じた従量課金制なので、開業初期のコスト負担も安心
最初から“全部入り”にせず、必要に応じて拡張できる柔軟な設計が魅力です。
導入から運用まで一貫サポート
homisは、導入支援から運用フォローまで一貫して対応します。
・初期設定、データ移行、スタッフ向けの操作研修までトータルサポート
・カルテやレセコンで不明点があればすぐに対応できるカスタマーサポート体制あり
・レセプト作成や事務業務の代行サービスとも連携可能で、少人数体制のクリニックでも安心して運用できます
ただ「使える」だけでなく、「使いこなせる」までを見据えた支援体制が整っています。
導入事例インタビュー:ホームケアクリニック麻生 井尻学見院長
開業当初からhomisをご利用いただいているホームケアクリニック麻生様に、homis導入の決め手やおすすめのポイントについてお伺いしました。
>>詳しいインタビューはこちら
導入の決め手
- 導入コストが手頃で、複数クリニック運営や情報共有にも対応可能
- 大規模在宅医療クリニックでの導入実績があり、安心して使える
- クラウド型で既存のネット回線・パソコンを使えるため導入が簡単
導入後の効果
- 多職種間の情報が一元管理され、業務効率が大幅に改善
- どこからでもアクセスできるため業務の柔軟性が向上
- サポート対応が迅速で、不明点やトラブルも安心して解決できている。
費用を抑えて、安心して長く使えるカルテを選ぶなら「homis」
「導入費用をなるべく抑えたい」
「少人数で無理なく訪問診療を始めたい」
そんなクリニックにとって、homisは機能・コスト・支援体制のすべてにおいて、バランスの取れた最適な選択肢です。