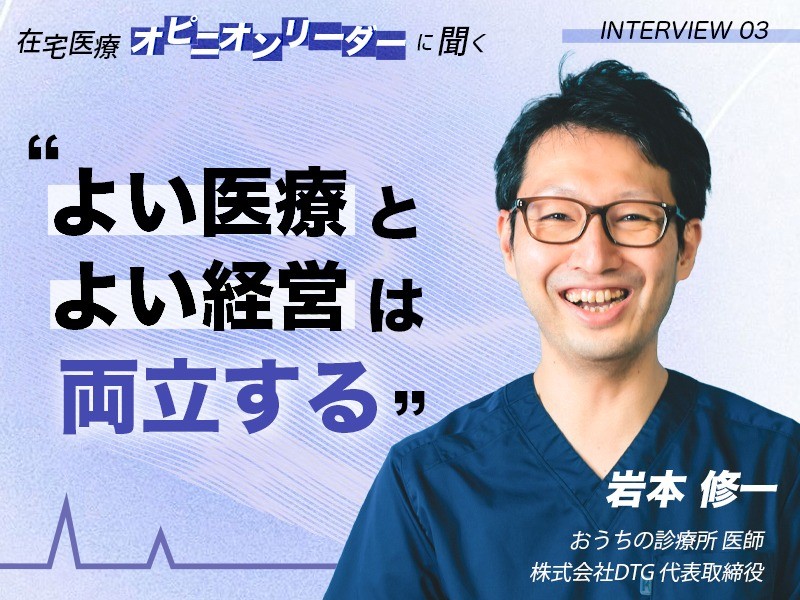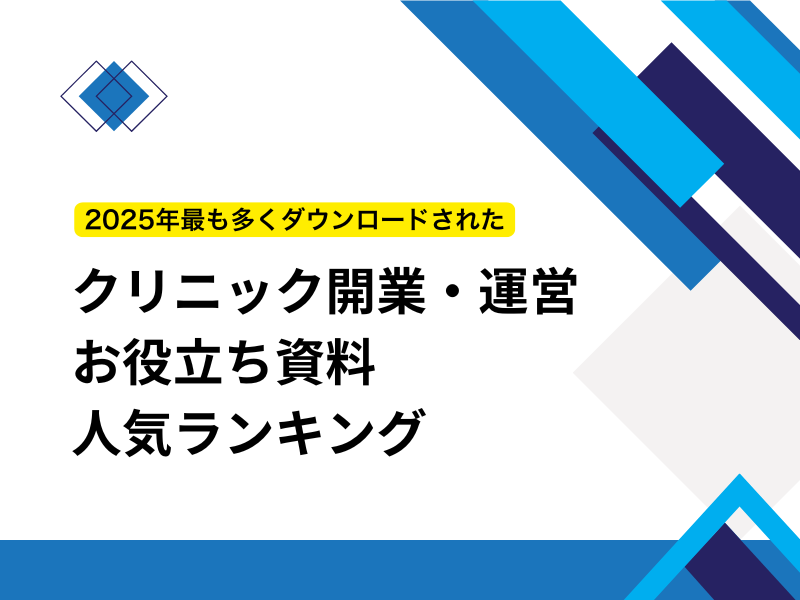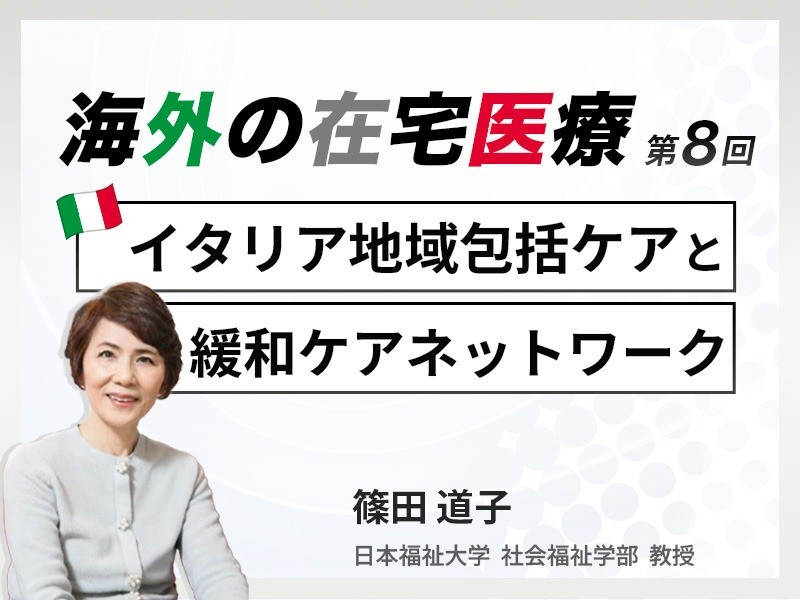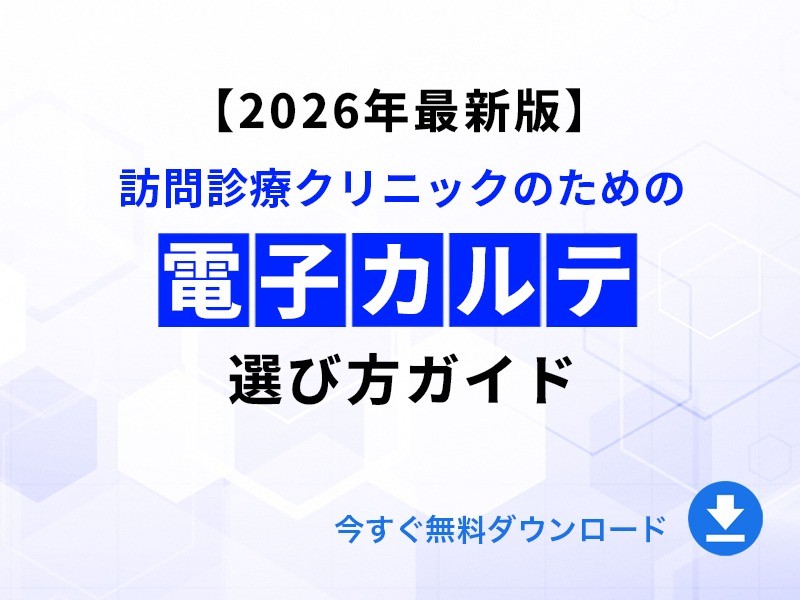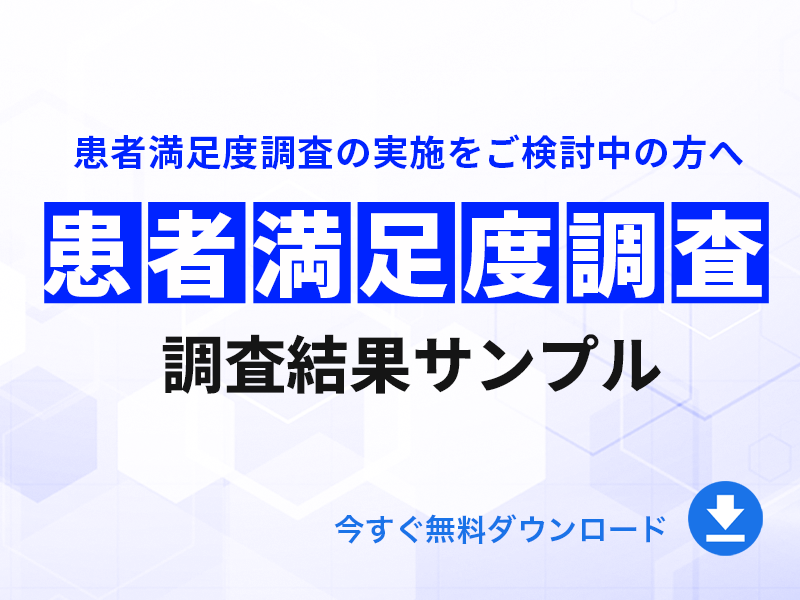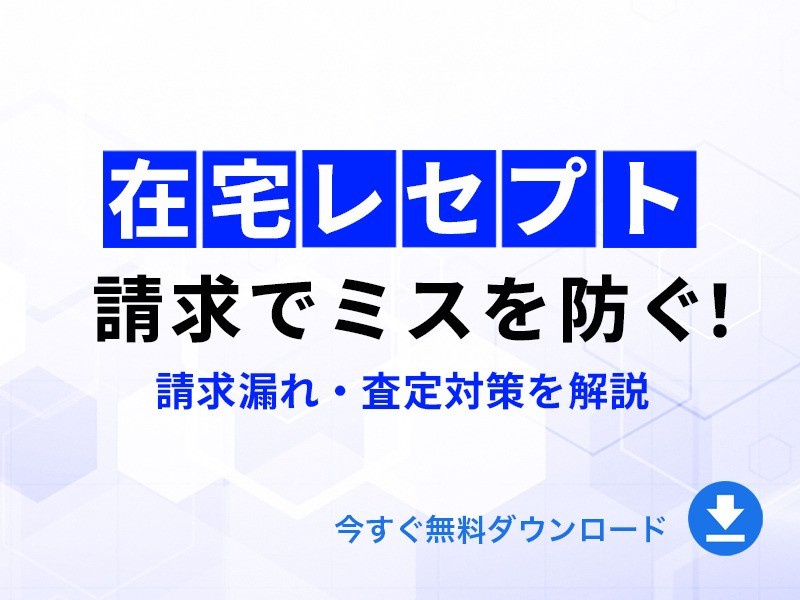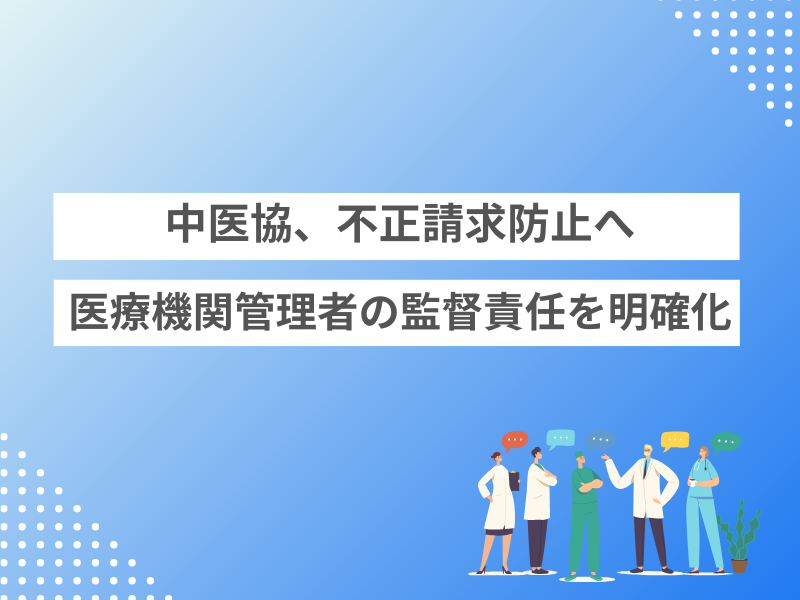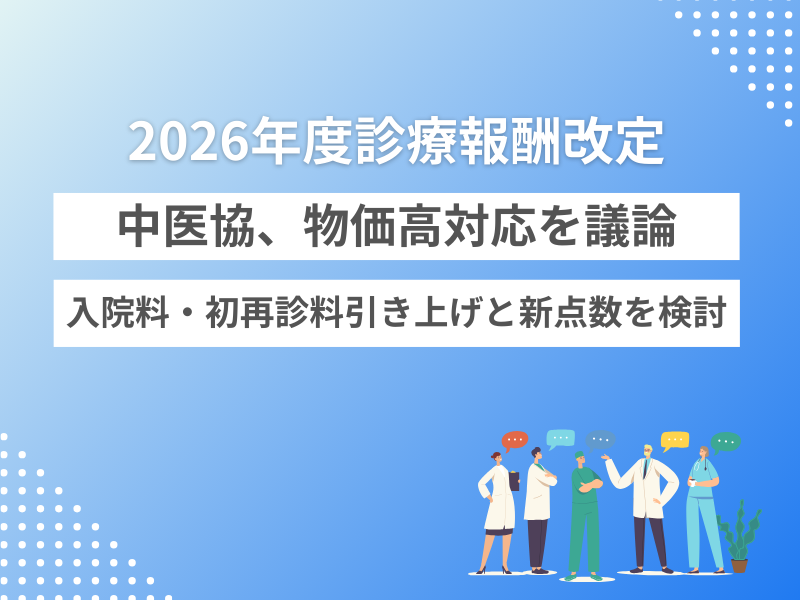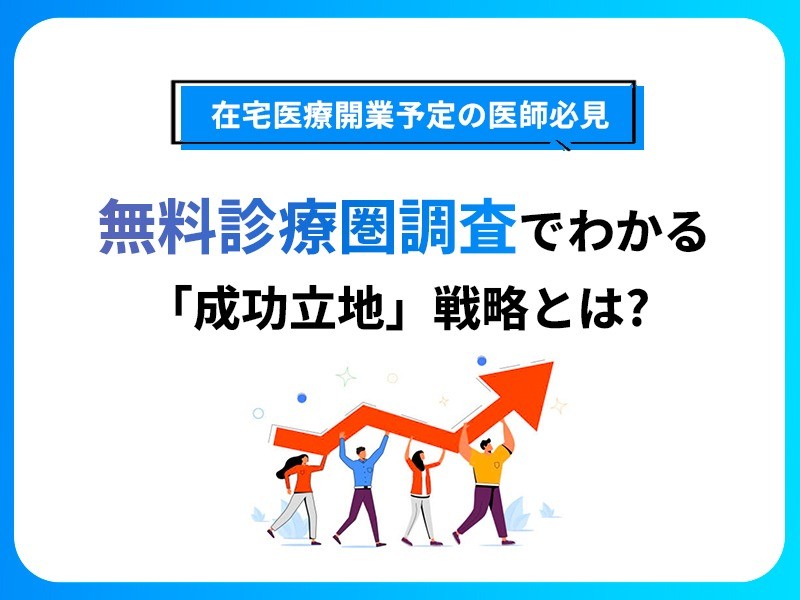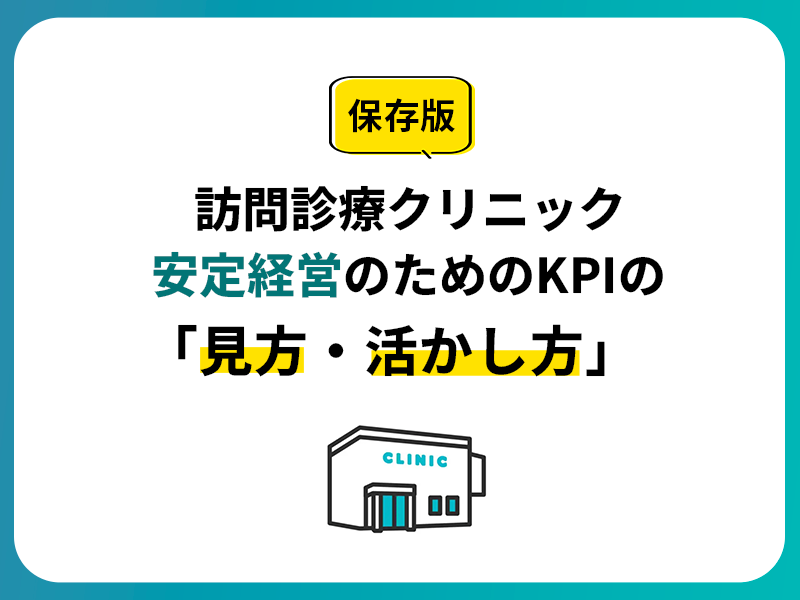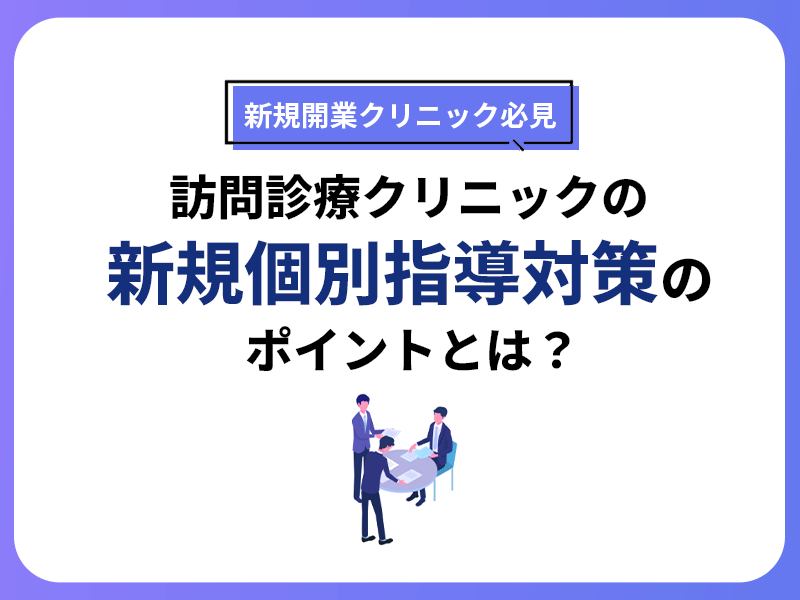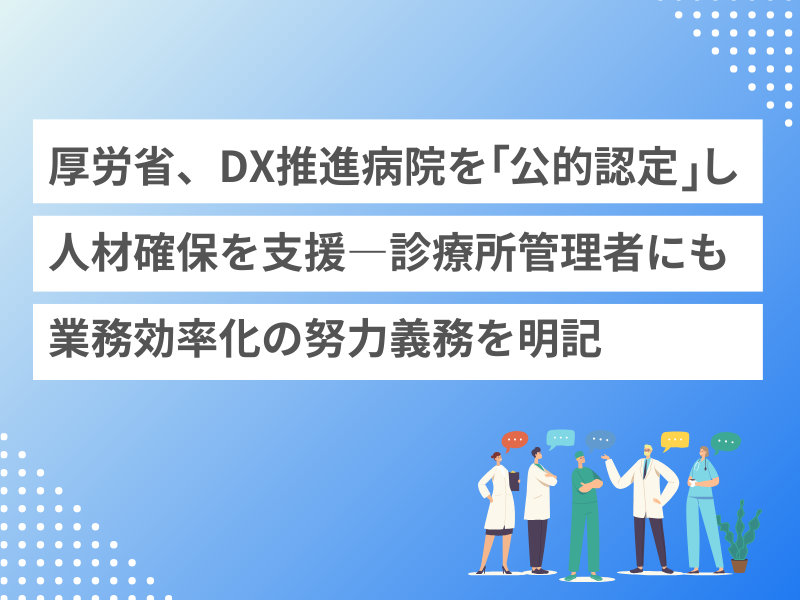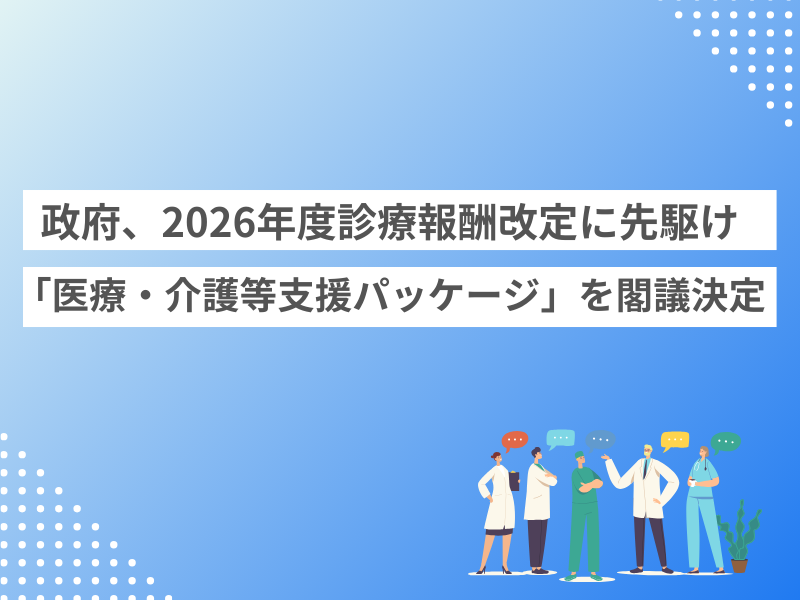- #運営
- #品質

こちらの記事は2025年10月22日に開催された「在宅医療カレッジ×PeerStudy共催セミナー『エコーを使った訪問診療の経営戦略 〜機器選定から活用事例まで教えます〜』(講師:株式会社BearMedi 取締役副社長 安藤雄太 氏)」の内容をもとに、編集部が再構成したものです。
在宅医療の現場では、限られた時間と人員の中で、いかに迅速かつ正確な診断とケアを提供し続けるかという課題に、多くの従事者が直面しています。特にその場での高度な判断力が求められる中、ポータブルエコーの導入が「診療の質」の向上と「クリニック経営の安定」に直結する重要な鍵として注目されています。
しかし、「どの機種を選べばいいのか?」「導入しても使いこなせるか不安だ」「本当に収益につながるのか?」といった疑問や懸念を抱える先生方も多いのではないでしょうか。
本記事では、検査技師としての臨床経験と医療機器メーカー勤務の経験を併せ持つ、株式会社BearMedi取締役副社長の安藤氏によるセミナー「エコーを使用した訪問診療と経営戦略」 の内容をもとに、在宅医療におけるエコー活用の具体的なメリットと、導入を成功させるための経営戦略について詳しく解説します。
なぜ今、在宅医療でエコーが求められるのか?
高齢化の進展に伴い、「最期まで自宅で過ごしたい」という患者ニーズは急速に高まっており、在宅医療・訪問診療の役割はますます重要になっています。
一方で、訪問診療の現場は「限られた時間」と「限られた設備」という制約の中で、迅速かつ安全な診療を求められます。病院のようにすぐにCTやMRI検査ができる環境ではないため、その場で正確な判断を下すための情報が不足しがちです。
患者さんやご家族が最も求めているのは、「安心できる診療」と「納得できる説明」です。診断の根拠が明確であれば、それは医療者と患者側の信頼関係の構築に直結します。
ここで大きな役割を果たすのがエコーです。
エコーを活用することで、訪問先の“その場”で迅速な診断と治療方針の決定が可能になります。まさしく「第3の聴診器」 として、在宅医療の質と安全性を両立させる強力なツールとなるのです。

ポータブルエコー「戦国時代」- 主な機種と特徴
近年のエコーは小型化が急速に進み、タブレットやスマートフォンに接続して使用するタイプも登場しています。各メーカーが競って多様な機種を市場に投入しており、まさに「ポータブルエコーの戦国時代」とも言える状況です。
重要なのは、自院の「現場のニーズ(誰が、どんな場面で、どのくらい使うか)」に合わせて、最適な機種を選択することです。


【具体例】訪問診療におけるエコー活用シーン
近年の技術進歩により、エコーはタブレットやスマートフォンに接続できるほど小型化し、訪問現場でも高度な画像診断が容易になりました。非侵襲的で放射線被ばくもなく、繰り返し安全に使用できる点も大きなメリットです。
現場では、以下のような多様なシーンで活用されています。
- 心不全患者のフォロー 心機能や胸水の有無をその場で定量的に評価できます。頸静脈の怒張や下肢浮腫といった身体所見とエコー所見を合わせることで、より正確な状態把握が可能となります。特に胸水貯留の早期発見は、心不全の急性増悪を未然に防ぎ、入院の回避にもつながります。
- 誤嚥性肺炎・呼吸器疾患 聴診だけでは捉えきれない少量の胸水や、肺の炎症を可視化できます。レントゲンやCTがすぐに使えない在宅の現場において、その場で判断材料を得られる利点は非常に大きいと言えます。
- 下肢静脈エコー(DVT評価) 寝たきりの患者さんや悪性腫瘍の患者さんは、深部静脈血栓症(DVT)のリスクが高い状態にあります。下肢の腫脹や疼痛が見られた際に訪問先で即時評価できれば、致死的な肺塞栓症などの重篤な合併症を未然に防ぐことにつながります。
- 皮下腫瘤・腹水の評価 皮下のしこりが嚢胞性か充実性かを判断したり、腹水の量を把握したりすることで、安全な穿刺・ドレナージのガイドにも活用できます。
- 緩和ケア 胸水や腹水のコントロール(ドレナージ)による呼吸苦や腹部膨満感の軽減など、患者さんのQOL(生活の質)向上サポートにも役立てられています。
このように、在宅医療の現場でエコーを活用することで、これまで病院でしか行えなかった画像診断や処置の判断がその場で可能となり、より迅速で質の高い医療を患者さんの生活の場で提供できるようになりました。
エコー導入を「経営戦略」として成功させる3つのポイント
エコーの導入は、「単に機器を買うこと」がゴールではありません。現場で確実に活用し、診療の質と経営の安定につなげるためには、「人の教育」と「仕組みづくり」が不可欠です。
安藤氏は、導入を成功させる戦略として3つのポイントを挙げています。

1. スタッフ教育と体制構築
まず重要なのは、現場でエコーを使いこなせる人材の育成です。検査プロトコルを標準化し、誰が行っても一定の質が担保できるような継続的な教育体制を構築することで、組織全体の医療レベルが底上げされます。
2. 収益インパクトの試算
算定可能な診療報酬と、機器導入にかかる投資コスト。このバランスをどう設計するかが経営の鍵となります。しっかりとした計画のもとで運用すれば、エコーは費用対効果の高い投資となり得ます。
3. 経営上の「差別化」
在宅医療において「その場で評価できる」という即応性は、他のクリニックとの明確な差別化要因となります。質の高い医療を提供できるという事実は、地域のケアマネジャーや連携病院からの信頼獲得、ひいてはクリニックのブランド力強化にも貢献します。
知っておきたい診療報酬と投資回収シミュレーション
エコー導入にあたり、具体的な収益イメージを持つことは重要です。
診療報酬のポイント
まず、「訪問診療」(計画的に訪問)と「往診」(臨時の要請で訪問)では、診療報酬の仕組みが異なる点を理解しておく必要があります。

- 訪問診療の場合
在宅患者訪問診療料(888点)や在宅時医学総合管理料(2700点以上)などがベースとなります。超音波検査は、心臓(880点)またはそれ以外の領域(400点)が、月1回に限り加算可能です。 - 往診の場合
初診/再診+往診料(720点)が加算されます。この場合、超音波検査は通常の「外来」と同様の診療報酬を算定でき、実施ごと(同月内に複数回でも)に加算が可能です。
主な超音波検査の診療報酬点数(外来・往診時)
主な超音波検査の点数は以下の通りです。


投資回収シミュレーション(一例)
では、実際にどのくらいの期間で投資を回収できるのでしょうか。
以下の試算が目安となります。

- 前提条件
- 機器投資額:130万円
- 運用:訪問診療で月20件のエコー検査を実施
- 平均診療報酬:540点/件(=約5,400円)
- 試算結果
- 月間収益:約10万円
- 年間収益:約130万円
この試算では、約1~2年で初期投資の回収が可能という結果になります。なお、これは訪問診療のみの試算であり、外来診療でも併用すれば、さらに早期の回収が見込めます。
【重要】導入を「コスト」で終わらせないための運用術
エコー導入を単なる「コスト」で終わらせず、継続的な「価値」に変えていくためには、日々の運用が最も重要です。
「導入して終わり」ではなく、「使うのが当たり前」という文化を醸成し、その質を高め続ける「仕組み」を構築する必要があります。

導入を成功に導く「5ステップ習慣化」
安藤氏は、機器を組織に根付かせるための5つのステップを紹介しています。
【Step 1】使う「機会」を作る
どんなに便利な機器でも、最初の「触ってみる」場がなければ使われません。導入後はメーカー担当者による使用説明会や研修会、OJT(実地研修)などを設定し、まずはスタッフ全員に機器の存在と可能性を認知してもらうことが第一歩です。
【Step 2】日常診療に「組み込む」
特別な検査として構えるのではなく、日常の診療フローの中に自然に組み込みます。例えば、「胸部症状(胸痛、呼吸苦など)のある患者さんには、聴診と同時に必ず心エコーも当てる」といったルールを設けることで、自然なルーチン化が進みます。
【Step 3】小さな「成功体験」を共有する
「エコーのおかげで診断がスムーズになった」「患者さんへの説明が視覚的になり、とても納得してもらえた」など、「使って良かった」という小さな成功体験を積み重ね、チーム内で共有することが次の使用へのモチベーションにつながります。
【Step 4】ナレッジを「チームの財産」にする
「こういう場面で使えた」「この設定の方が見やすかった」といった現場の知見や工夫を共有します。個人の経験をチーム全体の「財産」として蓄積していくことが重要です。
【Step 5】「当たり前」の文化にする
この段階まで来ると、スタッフが特別に意識しなくても、必要な場面でエコーが自然に使われるようになります。こうして「習慣」が「組織文化」として定着するのです。
診療の質を高め続ける「PDCAサイクル」
運用は「やりっぱなし」にせず、継続的に改善することが重要です。そのためのフレームワークが「PDCAサイクル」です。このサイクルは、「回すこと」自体が目的ではなく、「回すたびに診療の質を上げていく」ことが本質です。
P (Plan):計画
「今月は心不全フォローを〇件実施する」「まず心臓と頸動脈の領域から運用を開始する」といった具体的な数値目標や対象範囲を明確にします。併せて、スタッフの教育スケジュールなども計画に盛り込みます。
D (Do):実行
計画に沿って、まずは運用を開始します。この段階では完璧を目指すよりも、「小さく始めて、まず動かしてみる」という意識が大切です。
C (Check):評価
「計画した件数は達成できたか?」「検査に時間はかかりすぎていないか?」「画像の精度は十分か?」などを振り返ります。この時、件数などの「数値(定量的評価)」と、現場スタッフの「感覚(定性的評価)」の両面から評価することが改善のヒントにつながります。
A (Act):改善
評価で見えてきた課題(例:撮影プロトコルが煩雑、教育不足など)を整理し、マニュアルや教育内容を更新するなど、次の「P (計画)」に具体的に反映させます。
この改善の積み重ねこそが、エコー運用の質を着実に高めていきます。
チーム医療としての「情報共有」
エコー導入を成功させる上で、上記の習慣化やPDCAと並んで重要なのが「情報共有」です。
エコー所見を医師だけが把握している状態は非常にもったいないです。看護師やリハビリスタッフなどチーム全体で情報を共有することで、それぞれの専門職が患者さんに行う説明やフォローの質が格段に向上します。
エコー活用の将来展望:AIとクラウドが現場を変える
在宅医療におけるエコー活用は、AI(人工知能)やクラウド技術の進化によって、今後ますます発展していくでしょう。
訪問診療の現場では、医師が1人で判断する場面も多く、術者の経験によって診断の質にばらつきが出てしまう可能性があります。また、判断に迷った際に専門医に画像を送って助言を求めたくても、リアルタイムでの対応は難しいのが実情です。これらの課題は、新しい技術によって解決されつつあります。
AIによる自動解析・計測
AIが画像描出をサポートしたり、必要な計測を自動で行ってくれる機能がすでに登場しています。これにより、術者の経験によらず、一定の質の検査が可能になります。
クラウドによるリアルタイム遠隔診断
オンラインでエコー画像をリアルタイムに共有し、遠隔地にいる専門医と相談しながら検査を進められる技術も登場しています。判断に悩む症例でも、その場で専門的な助言を得る(テレ-エコー)ことが可能になりつつあります。
このように、テクノロジーの力で現場の課題が解決されることで、在宅エコーの需要は今後さらに高まっていくことが予想されます。
まとめ
在宅医療におけるエコーの導入は、単なる検査機器の追加ではなく、「診療の質」と「経営の安定」を両立させるための重要な経営戦略です。
その成功の鍵は、①適切な機器選定、②スタッフ教育、③収益化の仕組みづくり、そして④他院との差別化戦略にあります。
エコーの最大の強みである「その場で答えを出せる医療」 を最大限に活用することが、これからの在宅医療の現場を支え、その未来を切り開く力となるでしょう。