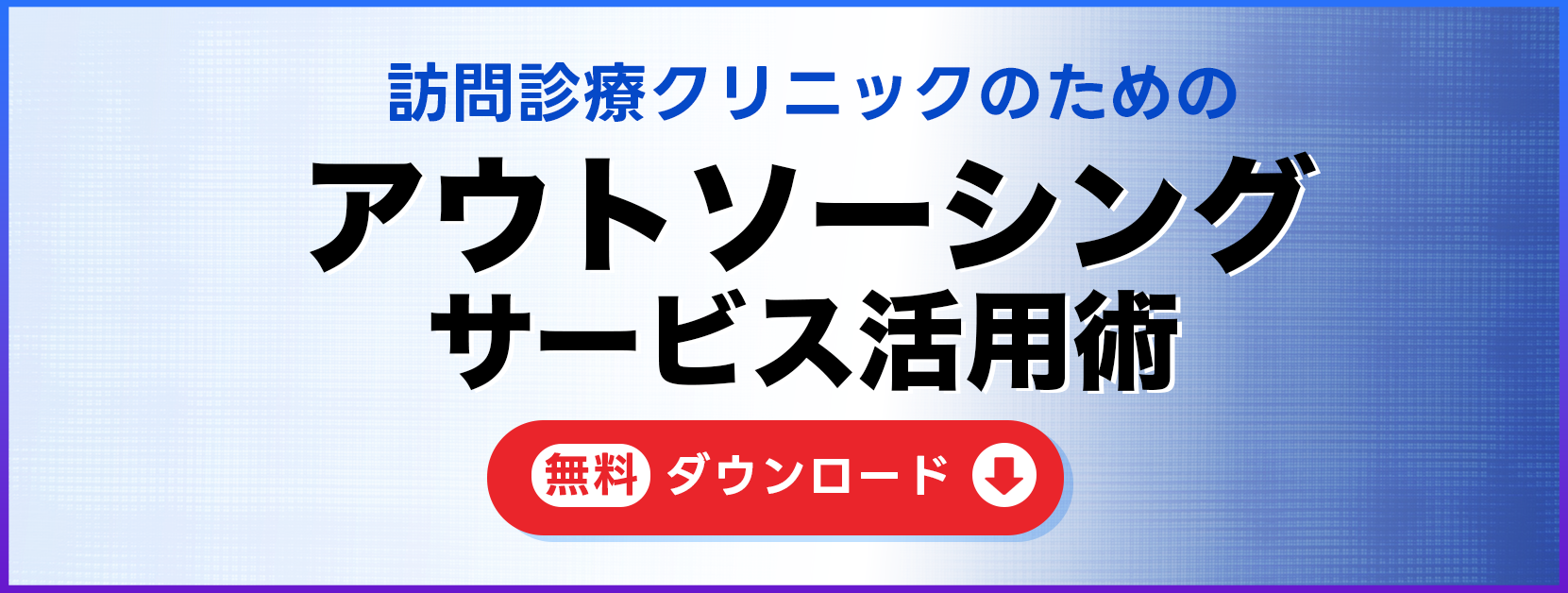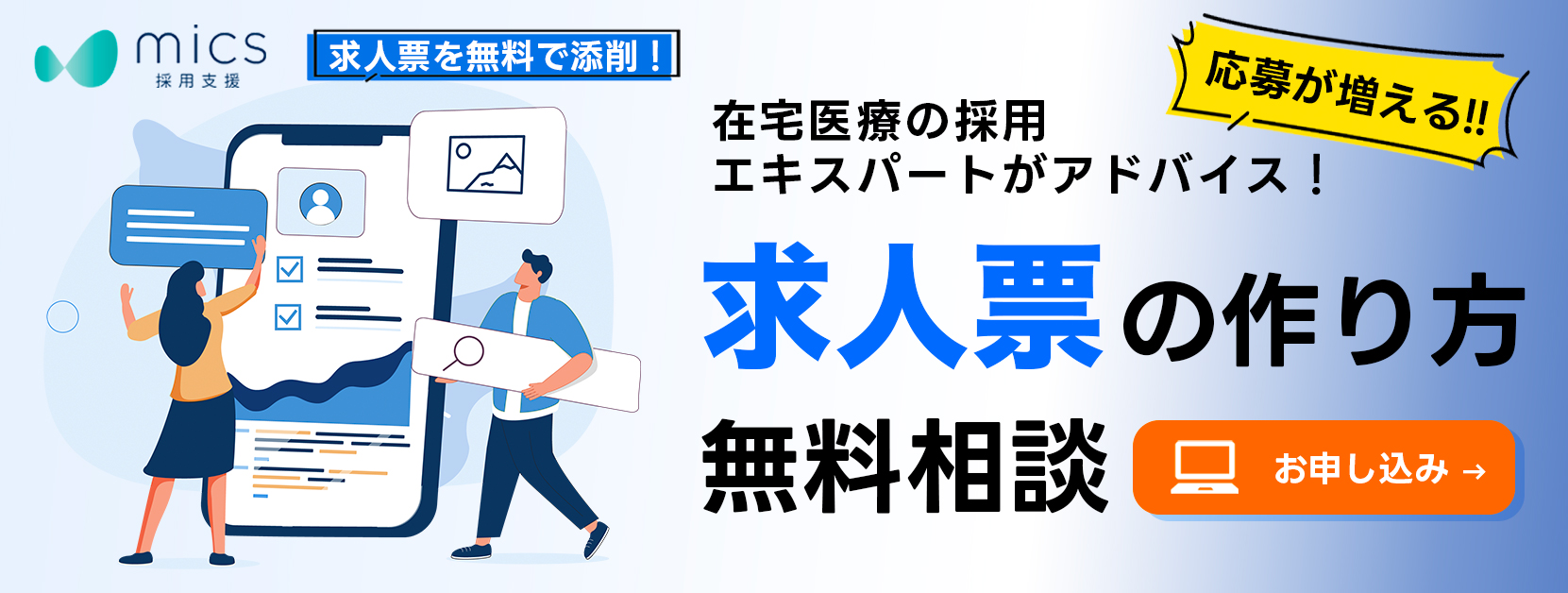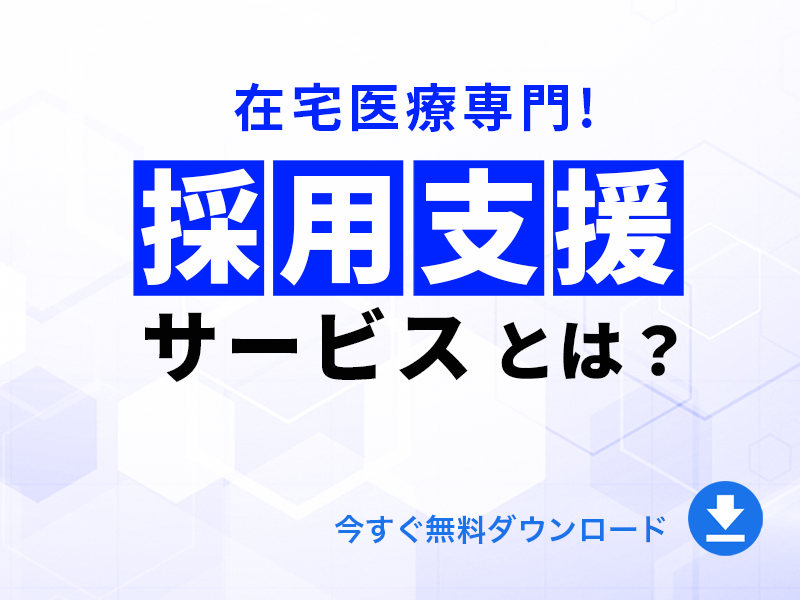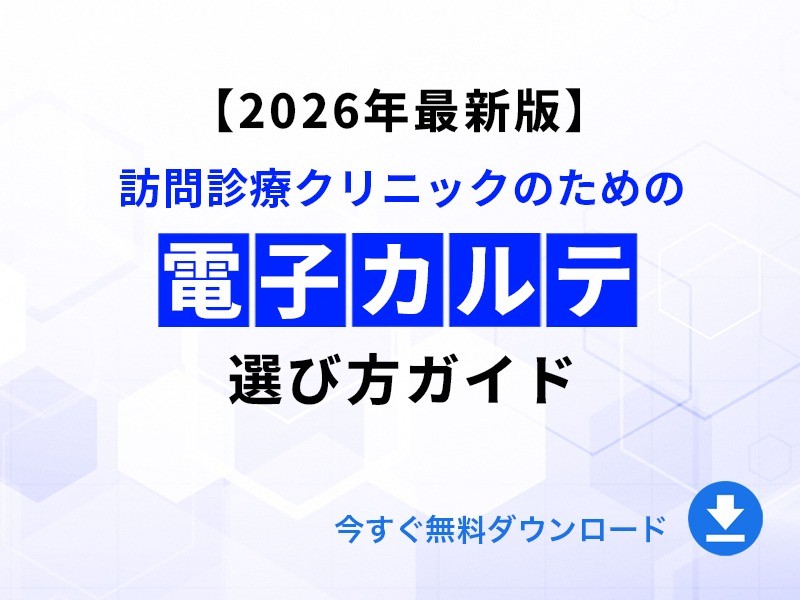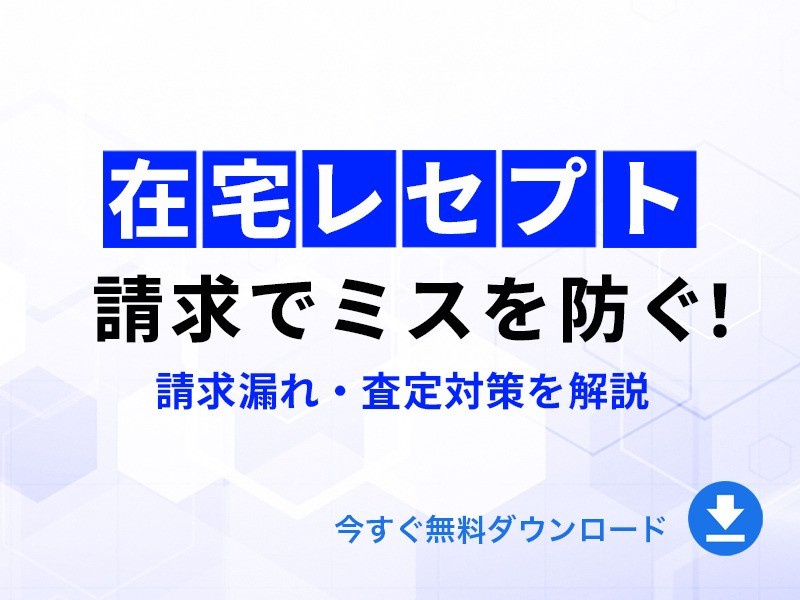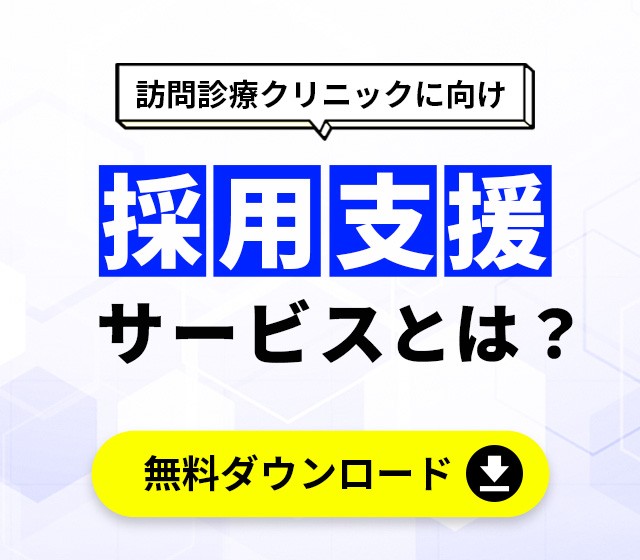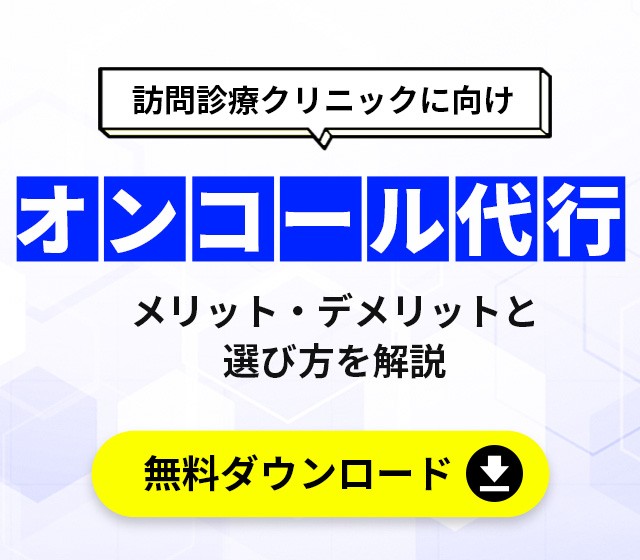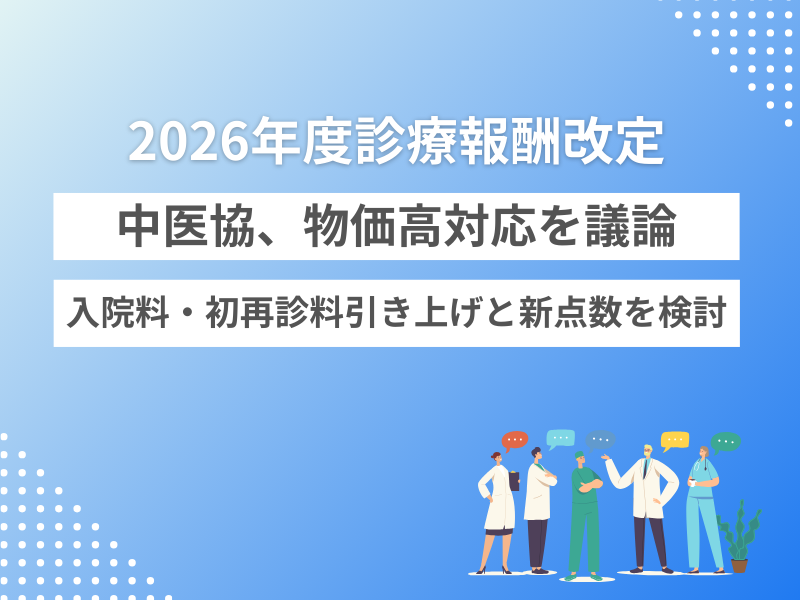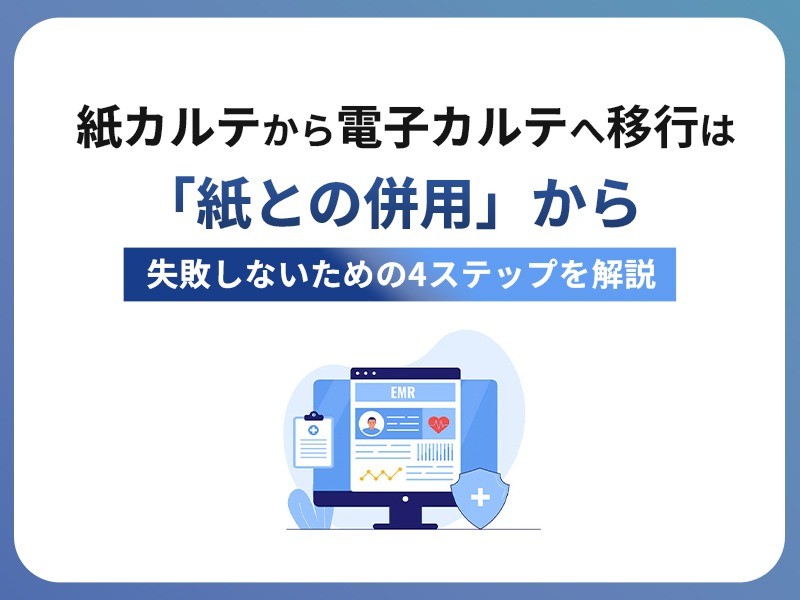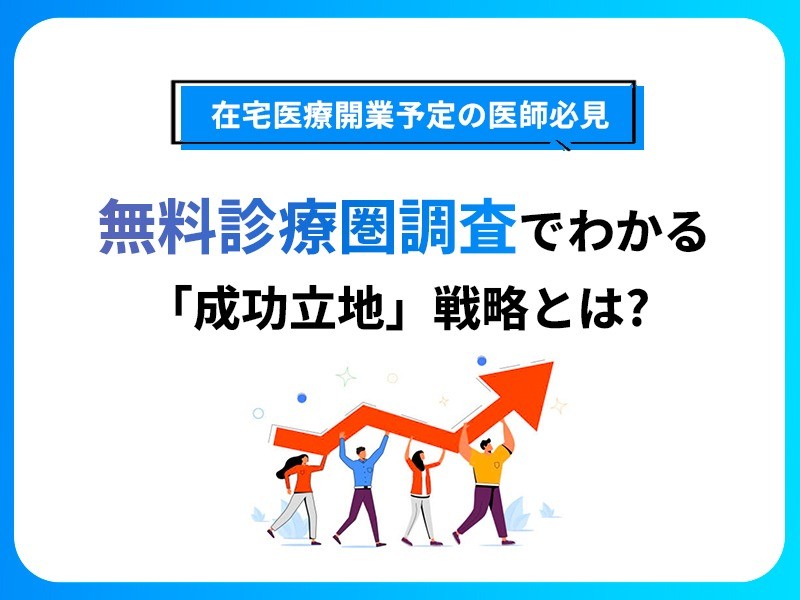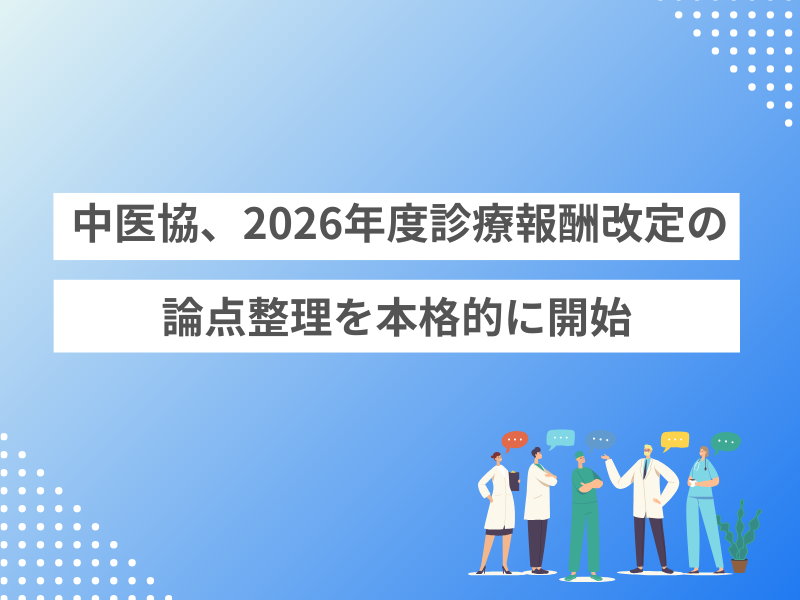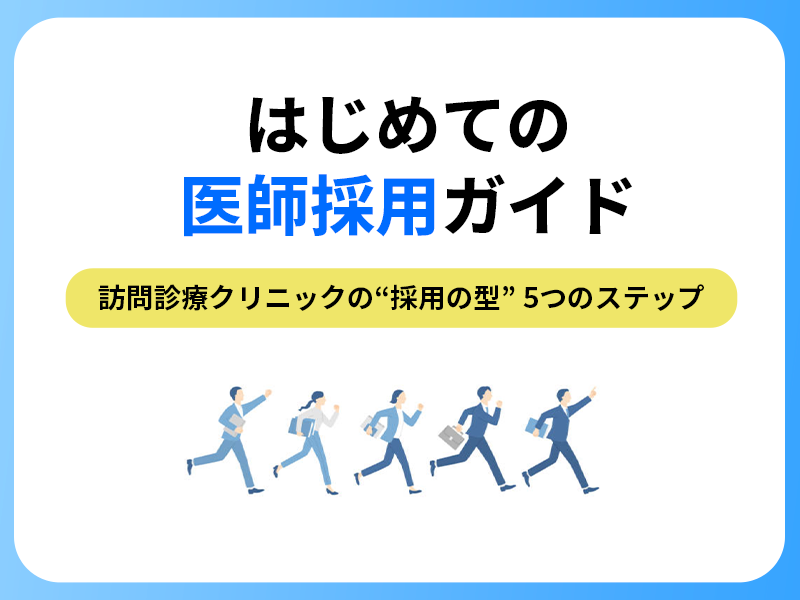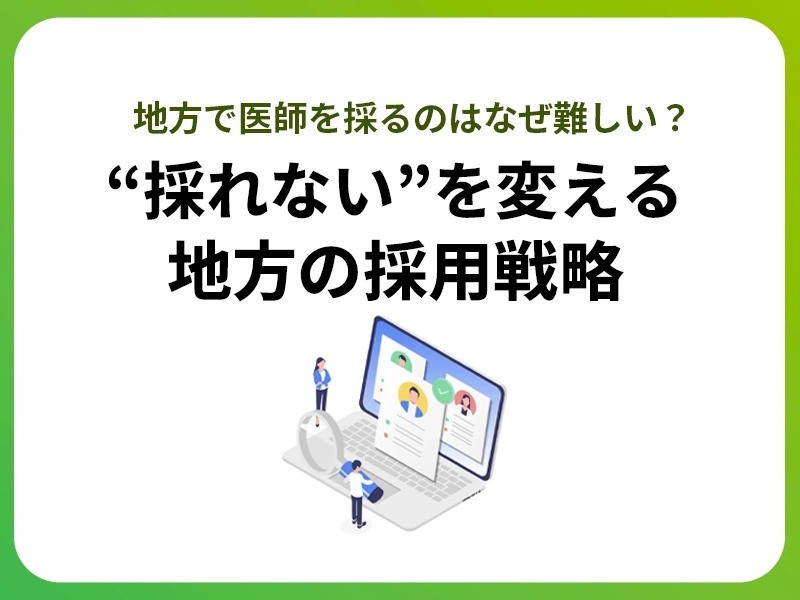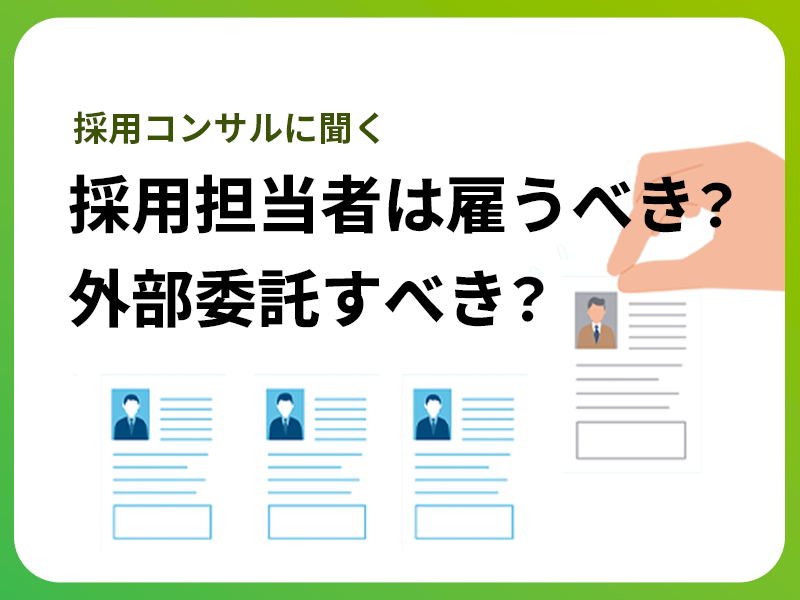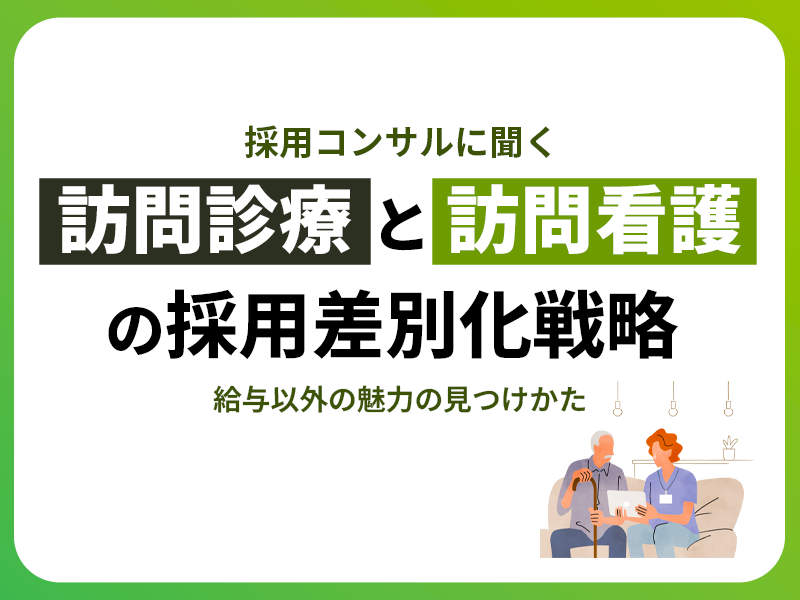- #運営
- #採用
- #人事
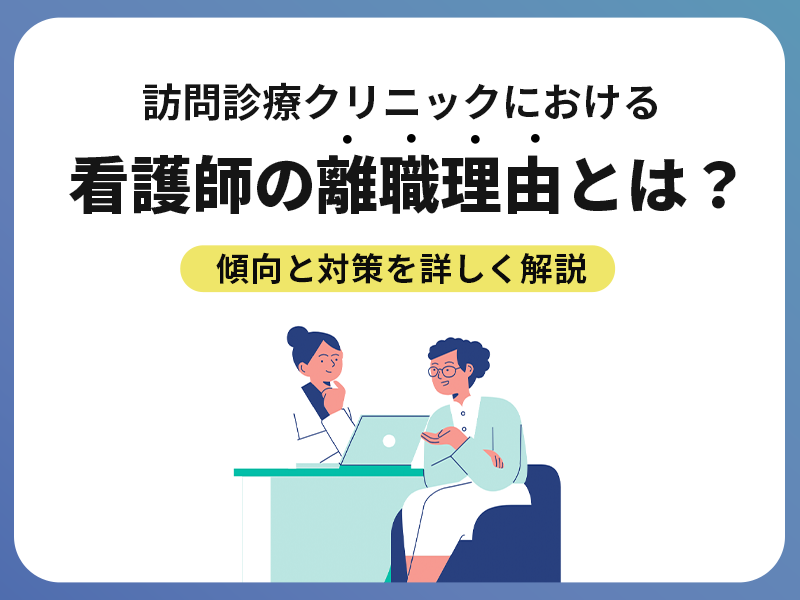
訪問診療クリニックにおける診療業務には、看護師の存在が欠かせません。
看護師は、医師の診療をサポートするだけでなく、患者さんとのコミュニケーションや、地域との連携を支える重要な役割を担っています。
しかし、現場では「看護師を採用してもなかなか定着しない」「採用してもすぐに辞めてしまう」という悩みを抱えるクリニックも少なくありません。
人手不足が深刻化する今、訪問診療クリニックにおける看護師の離職理由を正しく理解し、対策を立てることが大切です。
この記事では、訪問診療クリニックにおける看護師の離職理由の傾向と、それに対する有効な対策について詳しく解説します。
訪問診療クリニックにおける看護師の離職理由に見られる傾向
訪問診療クリニックで働く看護師の離職には、次のような理由が挙げられます。
- 訪問診療と訪問看護の役割のちがいによるミスマッチ
- オンコール対応や時間外業務の負担
- 人間関係や職場環境の課題
- 自己学習の必要性と教育体制の課題
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
訪問診療と訪問看護の役割のちがいによるミスマッチ
「在宅医療」とひとくくりにされがちですが、訪問診療と訪問看護では、看護師の役割が大きく異なります。
訪問看護では、看護師が主体的に動き、医療的ケアや生活支援を提供する場面が多くあります。
患者さんやご家族にとって、生活を支えてくれる身近な存在といえるでしょう。
一方、訪問診療の看護師は医師と2人1組で行動することが多く、看護師は診療のサポートに回ることが中心です。
そのため「もっとケアがしたい」という思いを持つ方にとっては、業務の内容にギャップを感じやすく、早期の離職につながるケースがあります。
訪問診療クリニックで働く看護師である「診療同行看護師」の仕事内容と役割については、こちらの記事をご参照ください。
(■あわせて読みたい:現役診療同行看護師が解説!診療同行看護師の仕事とは?)
オンコール対応や時間外業務の負担
訪問診療は24時間365日の対応を求められることが多く、看護師にオンコール業務を求めるクリニックもあります。
とくに、小規模なクリニックではオンコール対応が特定のスタッフに偏り、オンコール当番の頻度が高くなる傾向があります。
また、患者さんの体調不良や緊急時などで急な往診が入ると、時間外勤務になることも少なくありません。
「休日や夜も気が抜けない」「休息がしっかり取れない」といったストレスが蓄積され、離職の要因のひとつになるのです。
人間関係や職場環境の課題
訪問診療クリニックは少人数の体制であることが多く、職場の人間関係が業務のしやすさにつながります。
たとえば、医師との関係性が一方通行だったり、コミュニケーションが乏しい職場では、看護師が孤立を感じやすくなります。
閉鎖的な雰囲気や相談しにくい職場環境は、看護師のモチベーション低下や離職につながる大きなリスクです。
自己学習の必要性と教育体制の不足
在宅医療では、終末期ケア、認知症、在宅酸素など、幅広い知識と柔軟な対応力が求められます。
看護師自身がこれまで培った知識やスキルを活かしつつ、未経験の分野では自己学習が必要となるでしょう。
職場に教育体制が整っていないと「質問しづらい」「学ぶ環境がない」と感じ、業務についていけずに離職してしまうことがあります。
看護師の離職が訪問診療クリニックに与える3つの影響
看護師の離職は、単に人員が減るだけでなく、訪問診療クリニックにさまざまな影響を及ぼします。
たとえば、次の3つです。
- 既存スタッフへの業務負担の増加
- 診療体制の維持困難と質の低下
- 採用や教育にかかるコストと時間の増加
それぞれ詳しく解説します。
既存スタッフへの業務負担の増加
離職者が出ると、オンコール対応の回数や訪問に同行する件数の増加など、残ったスタッフにしわ寄せが及びます。
負担が大きくなった結果「もう続けられない」と感じるスタッフが連鎖的に退職するかもしれません。
診療体制の維持困難と質の低下
看護師が不足すると、訪問スケジュールの調整が難しくなったり、訪問件数が限られたりするなど、診療そのものの継続が困難になることも。
診療の質が低下すれば、患者さんやご家族からの不満につながり、契約の解除に発展する可能性もあります。
採用や教育にかかるコストと時間の増加
離職のたびに発生する求人広告費や教育コストは、クリニックの経営を圧迫するでしょう。
とくに、専門性が求められる訪問診療では、即戦力の人材を採用するのが難しく、育成には時間とリソースが必要です。
訪問診療クリニックにおける看護師の離職防止のための対策
看護師の離職を防ぎ、安定した診療体制を築くには、効果的な対策が不可欠です。
院内の取り組みと外部サービスの活用、両面からアプローチすることで、看護師の定着率を向上できる可能性があります。
ここからは、具体的な対策をみていきましょう。
離職を防ぐための院内での取り組み
看護師の離職を防ぐためには、まず院内の働きやすい環境づくりが欠かせません。
次のような取り組みをしてみてはいかがでしょうか。
| 院内でできる取り組み | 内容 |
|---|---|
| 業務の効率化 | 柔軟なシフト体制の構築やITツールの活用により、業務負担の軽減や働きやすさの向上を図る |
| 教育体制の整備 | スキルアップ研修や定期面談、プリセプター制度を導入し、経験の浅い看護師も安心して成長できる環境を整える |
| 職場の心理的安全性 | ランチミーティングの実施や感謝の言葉を伝える習慣づくりを通して、風通しの良い職場づくりを目指す |
こうした取り組みを積み重ねることで、看護師が安心して長く働ける職場環境を実現できるでしょう。
外部サービスの有効活用
オンコール対応の負担は、看護師の離職理由に挙げられる課題のひとつです。
そこで効果的な対策のひとつに「コール代行サービス」の導入があります。
在宅医療に特化したコール代行サービスの「Okitell365」は、夜間・休日の電話対応やトリアージを外部の専門スタッフが代行するため、スタッフが常に電話に気を張る必要がありません。心理的な負担が軽減され、結果として看護師の定着率の向上が期待できます。
コール代行サービス導入のメリットについては、こちらの記事を参考にしてみてください。
(■あわせて読みたい:訪問診療クリニックの電話クレーム対応)
定着しやすい看護師の採用に必要な戦略とは
看護師の離職防止には、採用の段階からミスマッチを防ぐ視点が重要です。
仕事内容や職場環境への理解が深い人材を採用できれば、早期離職のリスクも軽減されるでしょう。
ここからは、定着率を高める採用戦略についてご紹介します。
採用前のマッチング制度の向上
求人票や採用面接の段階で、訪問診療における看護師の業務内容やオンコール体制などを明確に伝え、求職者との認識のズレを防ぐことが大切です。
たとえば、次のような情報を伝えてみるのはいかがでしょうか。
- 看護師は医師の診療のサポートや、地域連携が主な仕事
- ケアを提供する機会は少ないが、多職種連携に重要な役割
- オンコール体制は医師・看護師で当番制
- このように、具体的な仕事内容を丁寧に伝えておくと、業務内容に対する納得感を高められるでしょう。
採用活動の効率化
訪問診療に特化した採用代行サービスを活用すると、求職者とのマッチング制度を高めつつ、採用にかかる業務負担を大幅に削減できます。
「mics採用支援」は、訪問診療クリニックにおける看護師の採用プロセスをまるごとサポート。
以下のようなサポートが受けられます。
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 採用市場の調査 | クリニックにおける強み・弱み分析、採用ターゲットの選定 |
| 採用戦略の提案 | 採用の目標設定、事業・人員計画に基づいた戦略立案 |
| 採用プロモーション | 採用サイト・資料作成で魅力を発信 |
| 候補者の獲得 | 求人媒体や人材エージェントの活用 |
| 採用成功まで伴走 | 面談・選考・入職まで丁寧にサポート |
看護師のキャリアや価値観を理解したプロが対応するため、定着しやすい人材の採用が可能です。
まとめ|看護師の離職を減らし、定着率を高めるための一歩を
訪問診療クリニックにおける看護師の離職には、業務内容のミスマッチやオンコールの負担、教育体制の不足など、さまざまな要因が関連しています。
これらの課題に対応するためには、院内の働きやすい環境づくりに加えて、オンコール代行や採用支援サービスといった外部サービスの活用も有効です。
まずは、看護師の離職の原因を正しく理解したうえで効果的な対策を立て、看護師が安心して働き続けられるクリニックづくりを進めていきましょう。